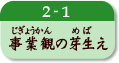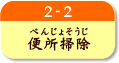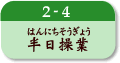大正12年の暮(く)れ。工場では従業員一同(じゅうぎょういんいちどう)が大掃除(おおそうじ)を行っていた。満足げに見回っていた幸之助は、従業員の便所だけが、なぜか汚(よご)れたままなのに気づいた。幸之助はしばし見守っていたが、だれも掃除しようとせず、上司も言いつけない。どうやら、職場(しょくば)でいさかいでもあった様子で、その余波(よは)で便所掃除にだれもが手をつけ難(がた)い状況(じょうきょう)になっているらしいのを、幸之助はその場の不穏(ふおん)な雰囲気(ふんいき)から察した。
「おい、所主が便所を掃除し始めたぞ」
「手伝おか?」
「今手伝ったらややこしいで」
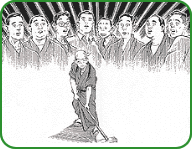
「事情(じじょう)がどうあれ、このままでは汚(きたな)い。このままで新しい年が迎(むか)えられるか」----。 幸之助はほうきを手に取り、バケツで水を流しながら踏(ふ)み板をゴシゴシこすり始めた。所主自らの行動にみかねて水くみを買って出た一人を除(のぞ)いて、多くの者は、ただ、見ているだけであった。
便所はみんなが使う、自分たちのものである。それを掃除するのに、何の理屈(りくつ)があるものか! 幸之助は激(はげ)しく憤(いきどお)りを感じ、そして考えた。「これではいかん。たとえ仕事ができても、常識的(じょうしきてき)なことや礼儀作法(れいぎさほう)がわからないままでは、社員にとって松下ではたらく意義(いぎ)は薄(うす)い。人間としての精神(せいしん)の持ち方を教えるのも工場主たる私(わたし)の責任(せきにん)だ。言いにくいことも言わねばならない」と。
便所掃除が終わったら、何と言われようが、みんなに強く注意をしよう。そう思いながら、幸之助は便所の踏み板を何度も何度もほうきでこすった。