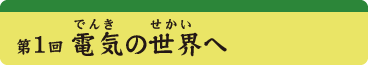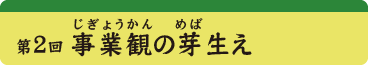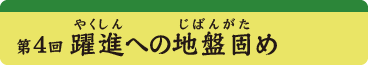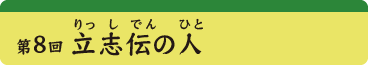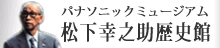
パナソニックをつくった松下幸之助をもっと詳(くわ)しく知りたいならここ!写真もいっぱい展示してあるよ。

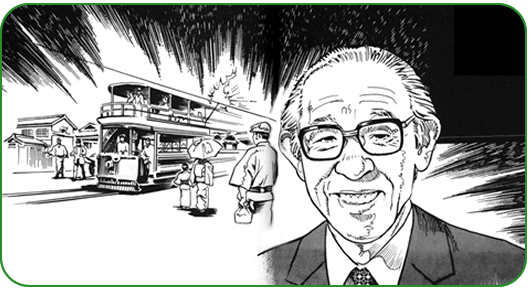
明治27年11月27日、松下幸之助は和歌山に生まれた。旧家(きゅうか)の末っ子に生まれ、なにひとつ不自由ない暮(く)らしが約束されているかに見えた幸之助の人生は、父が米相場(※1)に手を出し失敗したことで一変した。
小学校を中退(ちゅうたい)し、単身、親元を離(はな)れて大阪(おおさか)に丁稚奉公(でっちぼうこう)(※2)に出たとき、幸之助は満9歳(さい)。以後5年余(あま)り、幸之助は、もっとも多感な少年時代(しょうねんじだい)を丁稚として商家で暮らした。あまりにも大きな環境(かんきょう)の変化。しかし、幸之助はくじけることなく、子守から店の掃除(そうじ)・手伝いにいたる多くの経験(けいけん)を糧(かて)に、商売人としての心得を幼(おさな)い心に植えつけていった。同時に、その暮らしが幸之助生来の商才を目覚めさせた。ことに、子守のために三日分の給金でまんじゅうを買ったり、お客様に頼(たの)まれるタバコを買い置きして、おまけをもらったりと、お金を活かして使う才にすぐれた感覚を見せはじめていた。
少年時代を自分ではどうにもできない境遇(きょうぐう)(※3)の中で過(す)ごした幸之助だったが、今度は自分の志(こころざし)で人生を大きく変えていく。明治43年、開通したばかりの大阪の市電が「電気で走る」のを見て電気事業(でんきじぎょう)の将来(しょうらい)を予感した幸之助は、長年慣(な)れ親しみ、高い評価(ひょうか)もしてくれていた奉公先をあえて飛び出し、「大阪電燈(おおさかでんとう)」の内線係見習工になる。 このとき初めて、幸之助は「電気の世界」へ、その第一歩を踏(ふ)み出したのである。
※1 米相場(こめそうば):古い制度(せいど)の米の取引所で、米の売買でもうけを得ようとする取引
※2 丁稚奉公(でっちぼうこう):商店などに住み込んで、めし使われて勤(つと)めること
※3 境遇(きょうぐう):生きていくうえでの、めぐりあわせ

幸之助が異例(いれい)の若(わか)さで工事担当者(こうじたんとうしゃ)を経(へ)て検査員に昇進(しょうしん)したのは、大正6年のことである。検査員の主な仕事は、現場(げんば)の見回り検査。一日の仕事がほんの数時間でできた。仕事が楽で、しかも尊敬(そんけい)されるとあって、喜ぶ検査員が多い中、22歳(さい)の幸之助は充実感(じゅうじつかん)を味わえない生活に、ひとりゆううつを感じていた。
ゆううつのタネはほかにもあった。病気である。生まれつきの体の弱さを気力で支(ささ)えてきた 幸之助にとって、張(は)りのない生活はかえって災(わざわ)いとなった。医者の診断(しんだん)は「肺尖(はいせん)カタル」。ひと月ばかり療養(りょうよう)しろと勧(すす)められたが、日給暮(ぐ)らしの勤(つと)め人では、休めばその日から生活に行き詰(づ)まる。そんな日々(ひび)、思い出されるのは仕事の合間に自分で考えた「改良ソケット」だった。
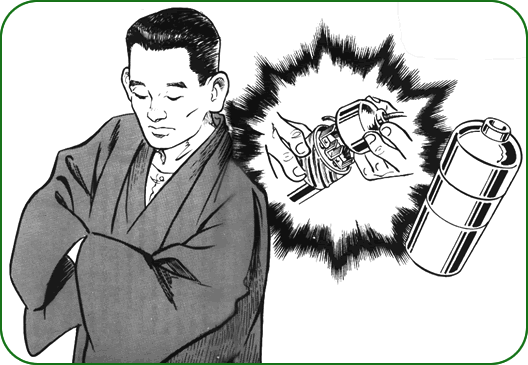
「前から、いちいちねじでとめなアカンのは不便やと思っとたんです」
「ふーん……」
「どうですやろ」
「うむ……あかんな、こらあかん」
「えっ!」
「工夫せなあかんとこがありすぎる。使い物にならんな」
まだ、工事担当者だったころ、高下駄(たかげた)の歯(※1)が抜(ぬ)けて困(こま)っていたおばあさんを助けてひらめいた改良ソケット。しかし、自信満々(じしんまんまん)で試作品を上司にみせたところ、答えは意外なことに完璧(かんぺき)な否定(ひてい)であった。幸之助はがく然とした。「絶対(ぜったい)に、この改良ソケットを作れば売れる……」―。あまりの悔(くや)しさに涙(なみだ)を流した幸之助の熱い思いは、しだいに胸(むね)のうちで確信(かくしん)となり、やがて、自分で作ってみたいという気持ちが心を離(はな)れなくなっていた。
※1 高下駄(たかげた)の歯(は):高い脚(あし)が付いた下駄(げた)の脚の部分


大正6年6月、幸之助は独立(どくりつ)を決心した。手元資金(てもとしきん)わずかに95円余(あま)り。生活していた4畳半(じょうはん)の2畳の借家に工場スペースを作るのも、みずからの手で行った。妻(つま)と妻の実弟、それに二人の知人を加えて始めた事業は、ソケットの胴(どう)に使う練物(※1)の製法(せいほう)も知らないというスタートだった。やがて何とか完成した改良ソケットだが、売れ行きは散々(さんざん)。うまくいかないことがはっきりしてきたころ、二人の知人は幸之助のもとを去っていった。しかし、幸之助は、まだまだ、あきらめる気にならなかった。きっと成功する。不思議とそんな自信があった。そして、そんな幸之助を支(ささ)えたのは、まだ若(わか)い、妻の「むめの」であった。
「さあ、そろそろ、風呂でも行こうか」
「あなた、これ、うまく動かんみたいなんやけど……」
「ん、どれ、かしてみ。おかしいな……。いっぺんバラしてみようか」
たった2銭(せん)の風呂代にもことかく日もあった。むめのはそんな生活の苦労を幸之助に感じさせまいと、風呂屋が閉(し)まる時間まで、なにかと話を持ち出しては気持ちをそらし、一方で行水(※2)の用意をしたという。むめのは指輪も替(か)えの着物も、幸之助に黙(だま)って、あらかた質屋(しちや)へ入れてしまった。それでも作った製品(せいひん)は売れないまま、ひと月余りが過(す)ぎ去った。
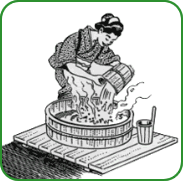
※1 練物(ねりもの):ねり固められたもの
※2 行水(ぎょうずい):たらいに湯や水を入れ、その中でからだのあせを洗(あら)い流すこと
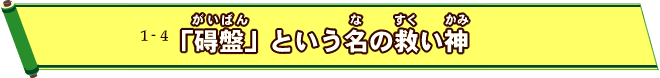
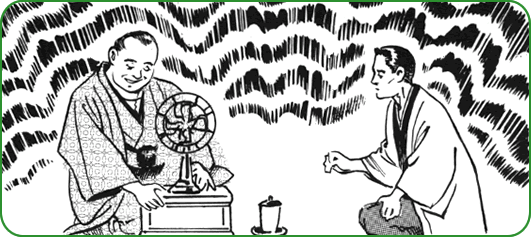
「おお、ここやここや。ごめん!おお松下君やな」
「へえ?」
「わしは、この間ソケット見せてもろた、阿部電気商会(あべでんきしょうかい)の者や。捜(さが)したで」
「ソケット、買うてくれはるんでっか!」
「いやいや、実はソケットやのうて、ガイバンや」
「ガイバン?」
意気は衰(おとろ)えないものの、進退(しんたい)きわまった大正6年の12月、思わぬところから“救いの神”はやってきた。当時、扇風機(せんぷうき)の碍盤(※1)は陶器製(とうきせい)で壊(こわ)れやすかった。そこで、扇風機の大手メーカー、川北電気が練物でつくってみようと練物を手がけるところをさがしていたのである。まずは見本注文であったが、試作品は好評(こうひょう)で、年内1000枚(まい)の注文を受けた。それを10日間で完納(かんのう)した幸之助は80円の利益(りえき)を手にし、年明けにはさらに2000枚の追加注文を受けた。
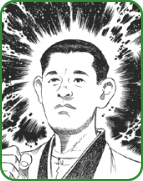
独立(どくりつ)から半年。幸之助はこうして事業での最初の試練を脱(だっ)したのである。碍盤の仕事が軌道(きどう)に乗るや、念願の電気器具製造(でんききぐせいぞう)・販売(はんばい)に本格的(ほんかくてき)に着手するため、大正7年3月7日、松下幸之助は大阪(おおさか)・大開町に「松下電気器具製作所(まつしたでんききぐせいさくしょ)」を創業(そうぎょう)した。
※1 碍盤(がいばん):絶縁体(ぜつえんたい)で電気を通さない板

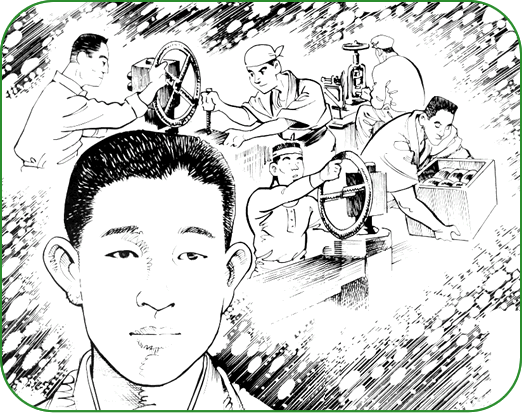
大正7年、松下幸之助は「松下電気器具製作所(まつしたでんききぐせいさくしょ)」を創業(そうぎょう)した。2階建ての借家の階下3室を改造(かいぞう)した作業場に小型のプレス機2台、人手は自分を含(ふく)めて家族3人。このささやかな体制(たいせい)を出発点に、幸之助は「アタッチメントプラグ」「二灯用差し込(こ)みプラグ」をはじめとして、便利で安い配線器具を次々(つぎつぎ)と生み出していった。一方で持ち前の商才も発揮(はっき)。日本経済全体(にほんけいざいぜんたい)が第1次世界大戦による好景気の反動で停滞(ていたい)していたこの時期に、関東方面へ販路(はんろ)を伸(の)ばしていった。
創業からわずか4年余(あま)り、幸之助は50名の従業員(じゅうぎょういん)を擁(よう)し、全国に販売(はんばい)される十数種類もの製品(せいひん)を生み出す中堅企業(ちゅうけんきぎょう)の所主となっていた。そして、事業が一応(いちおう)の成功を見せ始めた頃(ころ)、自分の事業のあり方について、目先の商売、損得(そんとく)という枠(わく)を超(こ)えて探(ふか)く、広い視野(しや)で考えるようになってきていた。
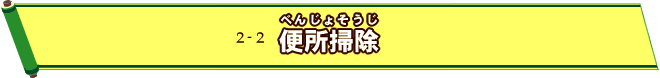
大正12年の暮(く)れ。工場では従業員一同(じゅうぎょういんいちどう)が大掃除(おおそうじ)を行っていた。満足げに見回っていた幸之助は、従業員の便所だけが、なぜか汚(よご)れたままなのに気づいた。幸之助はしばし見守っていたが、だれも掃除しようとせず、上司も言いつけない。どうやら、職場(しょくば)でいさかいでもあった様子で、その余波(よは)で便所掃除にだれもが手をつけ難(がた)い状況(じょうきょう)になっているらしいのを、幸之助はその場の不穏(ふおん)な雰囲気(ふんいき)から察した。
「おい、所主が便所を掃除し始めたぞ」
「手伝おか?」
「今手伝ったらややこしいで」
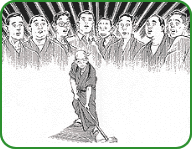
「事情(じじょう)がどうあれ、このままでは汚(きたな)い。このままで新しい年が迎(むか)えられるか」----。 幸之助はほうきを手に取り、バケツで水を流しながら踏(ふ)み板をゴシゴシこすり始めた。所主自らの行動にみかねて水くみを買って出た一人を除(のぞ)いて、多くの者は、ただ、見ているだけであった。
便所はみんなが使う、自分たちのものである。それを掃除するのに、何の理屈(りくつ)があるものか! 幸之助は激(はげ)しく憤(いきどお)りを感じ、そして考えた。「これではいかん。たとえ仕事ができても、常識的(じょうしきてき)なことや礼儀作法(れいぎさほう)がわからないままでは、社員にとって松下ではたらく意義(いぎ)は薄(うす)い。人間としての精神(せいしん)の持ち方を教えるのも工場主たる私(わたし)の責任(せきにん)だ。言いにくいことも言わねばならない」と。
便所掃除が終わったら、何と言われようが、みんなに強く注意をしよう。そう思いながら、幸之助は便所の踏み板を何度も何度もほうきでこすった。
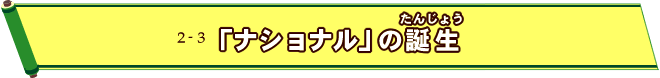
幸之助は頭をひねっていた。今度の新製品(しんせいひん)にどんな名前をつけるか、悩(なや)みに悩んでいたのである。新製品とは角型の自転車ランプ。大正12年に売り出した「砲弾型(ほうだんがた)ランプ(※1)」に続く第二弾(だいにだん)の商品である。幸之助にとって、この角型ランプの売り出しには特別の意味があった。それまで自転車ランプの販売(はんばい)を任(まか)せていた山本商店から販売権(はんばいけん)を買い戻(もど)し、自らリスクを背負(せお)って、自分で全国に売り出そうと決意した商品だからだ。10も20も紙の上に名前を連ねてみては、腕(うで)を組む日々(ひび)が続いた。ある日、新聞を見ていた幸之助は一つの言葉に目をひかれた。
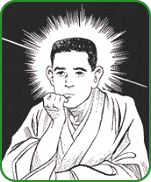
「おい、"インターナショナル“ってなんちゅう意味や?ロシアの革命(かくめい)と関係あるんやろか?」
「ん-、辞書では"国際的(こくさいてき)"ちゅうような意味ですな。"ナショナル"だけでは、"国民の"、ですなあ」
「国民……ナショナル……。」

「ナショナルランプ」即(すなわ)ち、「国民のランプ」や。国民の必需品(ひつじゅひん)になっていくにふさわしい、いい名前ではないかと幸之助は思った。
幸之助は全生命をこの「ナショナルランプ」に打ち込(こ)んだ。販促宣伝(はんそくせんでん)のため1万個(こ)も市場に無料提供(むりょうていきょう)し、初めて新聞広告も出した。ホーロー製の看板(かんばん)も用意した。
このランプなら全国民を相手に商売ができうる。そう信じて企業規模(きぎょうきぼ)から考えれば桁外(けたはず)れの大さな手を打ったのだ。昭和2年4月に売り出したこのランプは、予想をはるかに超(こ)えるほどの大ヒット商品となった。
※1 砲弾型(ほうだんがた)ランプ:電池寿命(じゅみょう)が従来(じゅうらい)の10倍以上もある画期的な新製品だったことから、市場の人気を博(はく)した
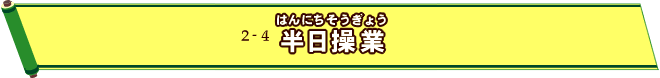
昭和4年の暮(く)れ、「松下電器製作所(まつしたでんきせいさくしょ)」の倉庫は、入りきれないほどの在庫(ざいこ)を抱(かか)え込(こ)んで悲鳴をあげていた。日本中がかつてない大不況(だいふきょう)にあえいでいるのをよそに伸展(しんてん)し続けていた事業も、ついに11月頃(ころ)から急速に悪化、製品(せいひん)の売れ行きが半数以下になってしまったのである。しかも、500人に達する人員を抱える所主たる幸之助は病床(びょうしょう)に伏(ふ)せていた。打開策(だかいさく)に思い悩(なや)む幸之助のもとに、現場(げんば)を預(あず)けられていた幹部(かんぶ)が、訪(おとず)れた。こうなったら、ひとまず従業員(じゅうぎょういん)を半減(はんげん)するより仕方がない。そう報告(ほうこく)する幹部を目の前にして、幸之助には一つの決断(けつだん)がひらめいた。
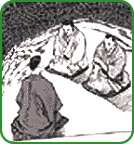
「決めた、ひとは一人もへらさん。日給も全額(ぜんがく)払(はら)うで」
「えっ」
「生産半減(せいさんはんげん)のため、工場は半日操業や。けど、そのかわり、休日も返上して全員で全力で在庫を売るんや!」
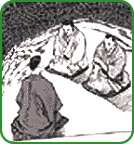
自分は、将来(しょうらい)ますます発展(はってん)するつもりで事業をしている。ならば、せっかく松下に入ってもらった人たちを一時の事情(じじょう)で手放すのは間違(まちが)った判断(はんだん)だ----。こう考えた幸之助に迷(まよ)いはなかった。解雇(かいこ)も覚悟(かくご)していた従業員たちはその心意気に感激(かんげき)し、燃(も)えた。その結果、翌年(よくねん)2月には倉庫を埋(う)めつくしていた在庫はきれいになくなり、一日中操業しなくては生産が追いつかないまでに回復(かいふく)したのである。
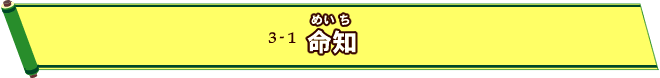
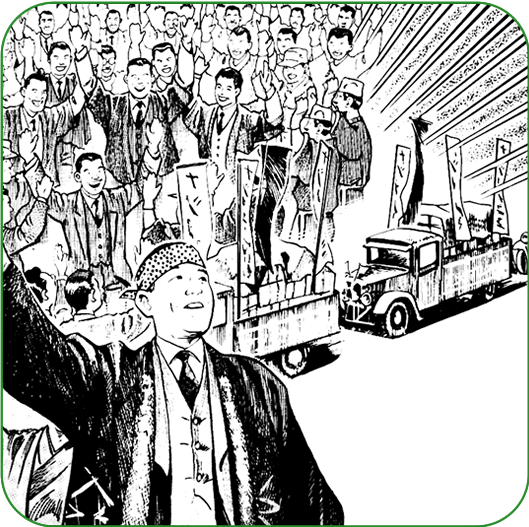
「松下電器製作所(まつしたでんきせいさくしょ)」が昭和4年の売れゆき不振(ふしん)を半日操業(はんにちそうぎょう)で脱(だっ)したあとも、日本中を不況(ふきょう)がおおっていた。産業界では閉鎖縮小(へいさしゅくしょう)が常識(じょうしき)で、多くの企業(きぎょう)が倒産(とうさん)。電機業界(でんきぎょうかい)も例外ではなく、姿(すがた)を消す大手メーカーがいくつもあったが、工夫をこらした製品(せいひん)を手に、積極的に展開(てんかい)を続ける幸之助の事業は逆風(ぎゃくふう)に負けず成長し続けた。昭和4年、採用(さいよう)を控(ひか)える企業が続出するなか、学卒者の採用を開始。昭和6年正月には、初めて初荷(※1)を挙行し、静まりかえった世間に威勢(いせい)のいい声がこだました。
昭和6年末、配線器具(はいせんきぐ)、電熱、ラジオ、ランプ乾電池(かんでんち)の4部門に200余(あま)りの製品をもち、本店、各支店(かくしてん)、出張所(しゅっちょうじょ)および8つの工場で働く従業員数(じゅうぎょういんすう)は1000人に達する企業のトップとして幸之助は忙(いそが)しい日々(ひび)を送っていた。そんなある日、幸之助は取引先の某氏(ぼうし)(※2)の勧(すす)めで、とある宗教団体(しゅうきょうだんたい)の本部に参詣(さんけい)(※3)する機会を得た。
※1 初荷(はつに):正月の初商いの日に荷を送り出す行事
※2 某氏(ぼうし):名をはっきりさせたくないときに使う、ある人
※3 参詣(さんけい):神社や寺にお参りすること
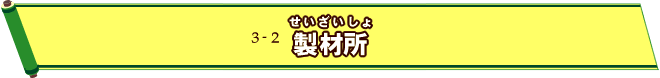
昭和7年春、幸之助は某氏(ぼうし)に連れられて、とある宗教団体(しゅうきょうだんたい)の本部を訪(おとず)れていた。広大な敷地(しきち)を順に案内されるうち、二人は製材所にたどり着いた。
「製材所? 製材所って何をするとこでっか?」
「もちろん材木の製材所です。 全国の信者から献(けん)じられた木を使うて、教祖殿(きょうそでん)などの建築(けんちく)を進めてるんですわ」
「これ、みな、献木(けんぼく)ですか!」
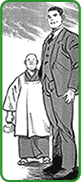
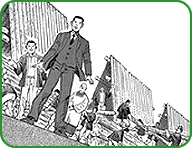
不況(ふきょう)のど真ん中というのに、信者から献木が山のようにやってくる。奉仕(ほうし)によって作業は進められているというのに、作業をする信者の人たちの顔は喜びに満ちている。この様子を見て、幸之助は心を打たれた。
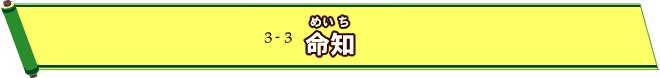
宗教団体(しゅうきょうだんたい)の見学を終え、ひとり電車に揺(ゆ)られながら幸之助はもの思いにふけっていた。宗教は精神(せいしん)の安定をもたらすことで人を幸せにしている。崇高(すうこう)(※1)な使命に立つ聖(せい)なる事業だ。そこに携(たずさ)わる人たちは喜びにあふれて活躍(かつやく)し、真剣(しんけん)に努力している。これは、なんとすぐれた経営(けいえい)ではないか。
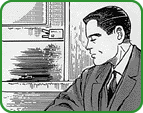
「正義(せいぎ)の経営、経営の正義……」
帰宅(きたく)して後も考え続ける幸之助の頭に、いつしか一つの諺(ことわざ)が浮(う)かんでいた。「四百四病(しひゃくしびょう)の病より貧(ひん)ほどつらいものはない」---- 人間の幸せにとって精神的安定(せいしんてきあんてい)と物質(ぶっしつ)の豊(ゆた)かさは車の両輪のような存在(そんざい)である。となれば、貧を除(のぞ)き富(とみ)をつくるわれわれの仕事は、人生(じんせい)至高(しこう)(※2)の尊(とうと)き聖業(せいぎょう)(※3)と言えるのではないか。
「そうや! 生産につぐ生産で貧を無くす営(いとな)みこそ、われわれの尊き使命やったんや! ああ、わしはそんなことも知らんかったんや」
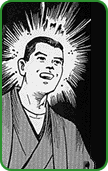
われらこそは、自己(じこ)にとらわれた経営、単なる商道としての経営の殻(から)を破(やぶ)らねばならない使命を自覚すべきだったのだ----。いつしか夜も更(ふ)けていた。漆黒(しっこく)の闇(やみ)(※4)のなかで、初めて自らの事業の真の使命に目覚めた幸之助は、ひとり、震(ふる)えるような感激(かんげき)を覚えていた。
※1 崇高(すうこう):気高くとうといこと
※2 至高(しこう):この上もなく高くすぐれていること
※3 聖業(せいぎょう):とうとくけがれのない事業
※4 漆黒(しっこく)の闇(やみ):うるしの黒びかりのような、ぼんやりと認められるほどの暗さ
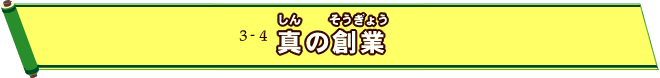
真の使命を知った以上、一刻(いっこく)も早く使命に基(もと)づく経営(けいえい)に入らなければならない。そのためには全店員に松下電器(まつしたでんき)の真の使命を心から自覚してほしい----。そう考えた幸之助が大阪(おおさか)の中央電気倶楽部(ちゅうおうでんきくらぶ)に全店員168名を招集(しょうしゅう)したのは昭和7年5月5日のことである。幸之助は、宗教団体(しゅうきょうだんたい)の見学で、その繁栄(はんえい)ぶりに感嘆(かんたん)し、宗教の使命の聖(ひじり)なるを痛感(つうかん)したこと、ひるがえって自分たち生産人の使命について深く考えたことを順を追って話した。そして、水道の水のごとく、すべての物質(ぶっしつ)を無尽蔵(むじんぞう)(※1)たらしめようではないかと訴(うった)えた。創業者(そうぎょうしゃ)は、使命達成(しめいたっせい)のための、250年にも及(およ)ぶ壮大(そうだい)な事業計画(じぎょうけいかく)を語りながら、限(かぎ)りない喜びを感じていた。ついに事業の究極の目的を確信(かくしん)した喜びであった。
「思えば過去十五年間(かこじゅうごねんかん)は胎児(たいじ)(※2)の時代であった。
それが今日ここに、呱々(ここ)(※3)の声を上げ、世にまかり出たのである」
幸之助が話を終えたとき、会場は言いようのない感動に包まれていた。その後行われた所感発表(しょかんはっぴょう)では、上席店員(かみせきてんいん)も新入の者も、老いも若(わか)きも壇上(だんじょう)に上がろうと列をなした。感きわまって、しばし無言の者。武者震(むしゃぶる)い(※4)する者。制限時間(せいげんじかん)が3分から2分、2分から1分となっても店員たちの興奮(こうふん)は、とどまるところを知らなかった。幸之助は自分の考えが正しかったことを確信した。そしてこの日、真の松下電器が誕生(たんじょう)したのである。
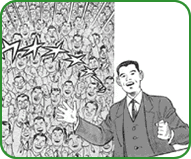
※1 無尽蔵(むじんぞう):かぎりないほどたくさんあること
※2 胎児(たいじ):母親のおなかの中にあってまだ出生してない子
※3 呱々(ここ):赤ん坊の泣き声
※4 武者震(むしゃぶる)い:興奮(こうふん)や緊張(きんちょう)でからだがふるえること
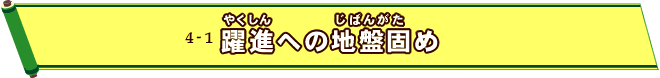
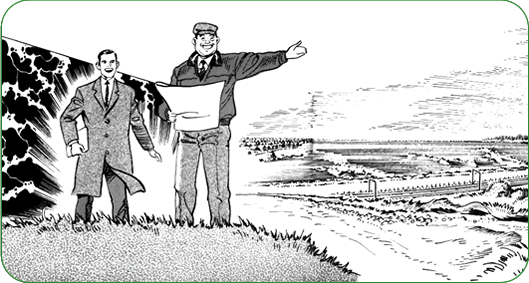
命知以来、強い使命感で一段(いちだん)と社員の団結(だんけつ)が深まった松下電器製作所(まつしたでんきせいさくしょ)の勢(いきお)いは、とどまるところを知らなかった。しかしその一方で、事業が規模(きぼ)においても社会的責任(しゃかいてきせきにん)においても今までのレベルを超(こ)え、一人ですべてを切り盛(も)りする限界(げんかい)を超えつつあることを幸之助は肌(はだ)で感じはじめていた。これ以上大きくなると一人では細かく注意を配ることができなくなる。それに、社会の公器(※1)として、松下電器製作所には、もし病弱な自分が倒(たお)れようとも運営(うんえい)されていく義務(ぎむ)もある。幸之助は新しい段階(だんかい)に入った事業に合った新しい体制(たいせい)の必要を考えていた。もっといい人材を育て、もっと任(まか)せていきたい----。幸之助は前から温めていた一つの構想(こうそう)である「店員養成所(てんいんようせいじょ)」の開設(かいせつ)や生産増加(せいさんぞうか)のための新工場建設(しんこうじょうけんせつ)に適(てき)した土地をいつしか探(さが)し始めていた。
昭和6年末のある日、一人の松下店員が門真駅に降(お)り立った。松下の新天地を探す命を受けて枚方(ひらかた)に出向いた帰りがけであった。一面に広がる広大な田園風景。京阪電車(けいはんでんしゃ)の駅は近く、広い道路にも面している。枚方での調査(ちょうさ)がいまひとつだったこともある。彼(かれ)は、ここは結構(けっこう)いいのではないかと思った。その足で耕地整理組合長(こうちせいりくみあいちょう)を訪(たず)ねたところ、組合長も誘致(ゆうち)(※2)に乗り気のようである。その話を聞いて、幸之助は様子を見に門真に足を運んだ。
※1 公器(こうき):おおやけのもの
※2 誘致(ゆうち):積極的にまねくこと

さっそく検分(けんぶん)(※1)に行き、すっかり気に入った幸之助は門真の土地を買収(ばいしゅう)した。ところが、土地を手にしたにもかかわらず、あることが気になって本格的(ほんかくてき)な移転(いてん)を決めかねていた。方角のことである。
「松下はん、門真ゆうたら大阪(おおさか)の鬼門(※2)やで。
別のところで考えはったらどうです」
「鬼門……だっか」
北東の方角は「鬼門」といって縁起(えんぎ)がよくないといわれる。門真は大阪から見て北東にある。幸之助はそれが気になっていたのである。迷信(めいしん)と思いつつなかなか踏(ふ)ん切りがつかない。ある日、悩(なや)んでいるうちに日本地図(にほんちず)が頭に浮(う)かび、はたと気づいた。
「まてよ、鬼門ゆうたら、日本じゅうが鬼門やないか」

日本の国は南西から北東に伸(の)びている。ならば日本中が鬼門だらけである。「よし、ほんなら気にせんとこやないか」----。幸之助の気持ちは晴れた。それどころか、鬼門で大成功して迷信を打ち破(やぶ)ってやろうという気持ちが沸(わ)き上がるのを感じていた。
昭和7年も暮(く)れのころ、幸之助は門真への大投資(だいとうし)を決意した。世間からは「放漫(ほうまん)(※3)経営(けいえい)だ」との声も聞こえたが、いったん決意した幸之助は意に介(かい)さなかった。
※1 検分(けんぶん):見たり調べたりすること
※2 鬼門(きもん):よくないことが起こりそうな方角
※3 放漫(ほうまん):気ままでしまりのないこと
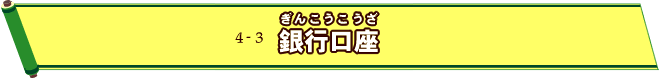
同じ頃(ころ)、幸之助は一つの組織改革(そしきかいかく)を考えていた。それは、昭和2年の電熱部設立(でんねつぶせつりつ)のとき、まったく新しい事業なのに忙(いそが)しくて手が回らない幸之助が「ならば、いっそのこと」とばかりに製造(せいぞう)から販売(はんばい)までの全部をある幹部(かんぶ)に任(まか)せたことがヒントとなっていた。
「実はな、君に事業部長(じぎょうぶちょう)をやってもらおと思てるんや」
「事業部長? 部長と違(ちが)いまんのか」
「違う。もっとえらいで」
幸之助は、事業を製品群別(せいひんぐんべつ)に「事業部」に分け、その一つひとつを独立(どくりつ)した事業体として経営(けいえい)したいと考えた。それぞれの事業部のトップに人、物、金に関する権限(けんげん)と責任(せきにん)を大幅(おおはば)に任せることで、自分一人ではすべてを見ることができなくなっていく事業の拡大(かくだい)に対応(たいおう)し、同時に真の経営者(けいえいしゃ)を育てたい。どういう意味なのか、ピンと来ない幹部たちに幸之助は、小さな帳簿(ちょうぼ)(※1)を見せた。
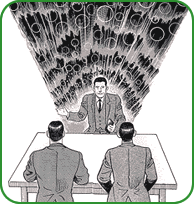
「これは……」
「きみ名義(めいぎ)の口座を一つ開いたんや。この口座のやり繰(く)りはきみの責任やで。しっかりやってや」
幸之助は任せる覚悟(かくご)を、事業部長に銀行口座をもたせることで示(しめ)してみせたのだった。通帳を手にした事業部長も、責任の重さを感じていた。昭和8年5月、日本で初めての事業部長が誕生(たんじょう)した。
※1 帳簿(ちょうぼ):お金や品物の出し入れを記入する帳面
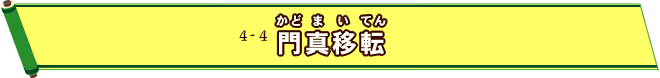
昭和8年7月、ついに、門真に本店工場(ほんてんこうじょう)が完成した。念願の店員養成所(てんいんようせいじょ)も同じ敷地内(しきちない)につくられ、近日開校(きんじつかいこう)の見通しであった。広大な敷地に立ち並(なら)んだ立派(りっぱ)な工場群(こうじょうぐん)に所員たちは大喜びであったが、移転を期して朝会の壇上(だんじょう)に立った幸之助の言葉は意外なものだった。
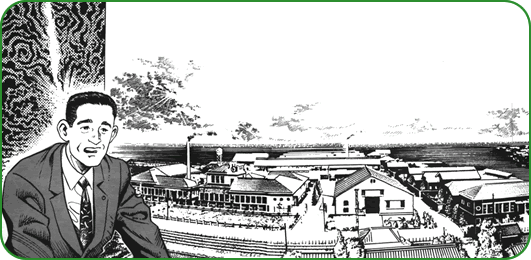
「松下電器は、今躍進と崩壊(ほうかい)の分岐点(ぶんきてん)(※1)に立っている。本所将来(ほんじょしょうらい)の発展(はってん)、衰亡(すいぼう)(※2)は、諸君(しょくん)の双肩(そうけん)(※3)にあることを考え、一事一物(いちじいちもつ)にも "最慎(さいしん)"の注意を怠(おこた)らないよう、この際(さい)特に一言しておく」
華(はな)やかさに幻惑(げんわく)(※4)され、浮(うわ)ついた気持ちから経費(けいひ)がかさみ、生産原価(せいさんげんか)も上がる----。社内に安易感(あんいかん)が生まれ、放漫(ほうまん)の気風が生じて衰亡への道につながる危険(きけん)を幸之助は見抜(みぬ)いていた。さし当たっての緊急方針(きんきゅうほうしん)として、半年間の徹底的(てっていてき)な経費節減(けいひせつげん)の断行(だんこう)を命じた幸之助の気持ちは所員一人ひとりに伝わり、皆(みな)が気を引き締(し)めた。
松下電器製作所(まつしたでんきせいさくしょ)は、さらなる躍進に見合った器と組織(そしき)と人、そして気風を門真の地で手にした。
※1 分岐点(ぶんきてん):物事の分かれ目
※2 衰亡(すいぼう):おとろえてほろびること
※3 双肩(そうけん):重い責任(せきにん)や義務(ぎむ)を負うもののたとえ
※4 幻惑(げんわく):目をくらまし、まよわすこと
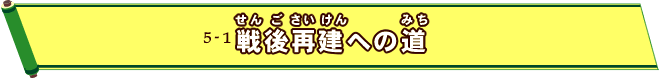
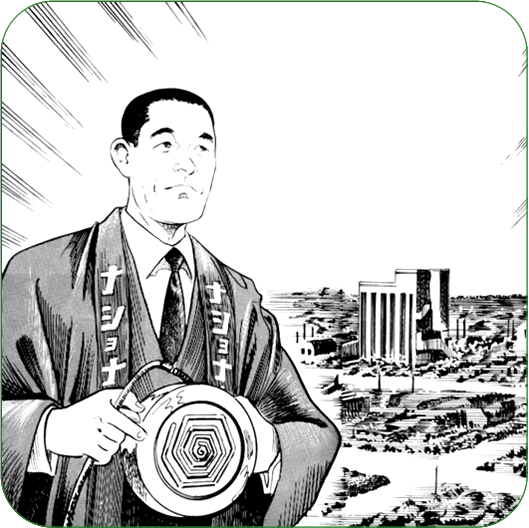
昭和20年8月15日、幸之助は松下電器(まつしたでんき)の幹部(かんぶ)たちとともに終戦を告げるラジオ放送を聞いた。虚脱感(きょだつかん)(※1)に包まれた社員たちをとにかく家に帰した幸之助は、自分自身(じぶんじしん)も力が抜(ぬ)けていくのを感じていた。しかし、今後のことは、自分で考えなければいけない。「無条件(むじょうけん)降伏(こうふく)(※2)は残念だ。でも、終わった以上は今後のことを考えねばならない」。幸之助は2万の従業員(じゅうぎょういん)と60の工場のことを思い、生かす道を探(さぐ)った。ことに社員たちの動揺(どうよう)(※3)は計り知れない。眠(ねむ)れぬ一夜が過(す)ぎ一つの結論(けつろん)が出た。「生産こそ復興(ふっこう)(※4)の基盤(きばん)、今こそ松下電器は民需(みんじゅ)(※5)生産(せいさん)の先陣(せんじん)を切り、物資欠乏(ぶっしけつぼう)をなくし、失業をなくす産業人の使命を果たしていこう」----。気持ちを固めた幸之助は、翌(よく)16日、経営幹部(けいえいかんぶ)を本社講堂(ほんしゃこうどう)に集め、決意を述(の)べた。日本人の誰(だれ)もが先行きの不安を感じていたとき、すでに松下電器には進むべき道が示(しめ)されていたのである。
※1 虚脱感(きょだつかん):やる気がなくなり何も手につかなくなる感じ
※2 降伏(こうふく):戦いに負けて、相手にしたがうこと
※3 動揺(どうよう):平静さを失うこと
※4 復興(ふっこう):ふたたびさかんにすること
※5 民需(みんじゅ):一般(いっぱん)の人が求めようとするもの
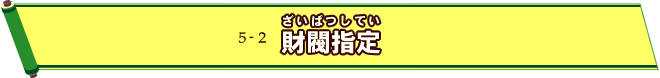
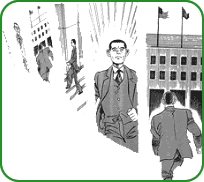
9月にはGHQ(※1)から生産中止命令(せいさんちゅうしめいれい)が出るなど、再出発(さいしゅっぱつ)に当たって困難(こんなん)はあったが、その命令も10月にはすべて解(と)け、全事業場(ぜんじぎょうじょう)で生産が再開(さいかい)された。しかし、すぐ大きな壁(かべ)が立ちはだかった。GHQによって「松下は財閥(※2)」と判定(はんてい)され、松下電器(まつしたでんき)が「制限会社(せいげんがいしゃ)」に、松下家が「財閥家族(ざいばつかぞく)」に指定されたのである。
社史から見ても、規模(きぼ)から見ても、業容(ぎょうよう)から見ても、財界(ざいかい)での位置から見ても、どこから見ても松下は「財閥」ではない。GHQは間違(まちが)っている。間違いはただすべきだ----。こう考えた幸之助は自ら東京のGHQ本部・財閥課(ざいばつか)に何度も足を運んだ。
「松下は財閥やない。この資料(しりょう)を見てください」
「マツシタさん、また来ましたか。何度来たってだめですよ」
「いいや。間違いがただされるまで、わしは何度でも足を運ばしてもらいます」
間違いは間違い----。指定を受けたほかの会社の社長が次々(つぎつぎ)と辞任(じにん)する中、幸之助は頑(がん)としてやめなかった。粘(ねば)り強い説明が功を奏(そう)したのか、GHQは昭和24年に松下家への「財閥家族」指定を、昭和25年に松下電器への「制限会社」指定を解除(かいじょ)した。その間、4年の歳月(さいげつ)が流れ、幸之助自身がGHQを訪(おとず)れた回数は50回を数えていた。
※1 GHQ:連合国軍が日本を占領(せんりょう)中にもうけた総(そう)司令部
※2 財閥(ざいばつ):一族の家族的関係のもとに結合した会社の連合体
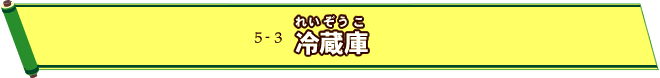
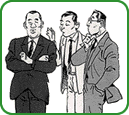
「おい、驚(おどろ)いたで。社長の家に冷蔵庫の具合をみにいってきてんけどな、中に何入ってたと思う」
「そんなにええもん入ってたんか」
「逆(ぎゃく)や。何と芋(いも)のつるや。丼(どんぶり)がひとつと、そこに芋のつるが入ってるだけやった」
GHQの指令で、給料までも制限(せいげん)されていた幸之助の生活は窮乏(きゅうぼう)(※1)していた。松下電器(まつしたでんき)の再建(さいけん)に心血を注いできた幸之助にとって会社は赤字、自分は食うにも困(こま)るという非常(ひじょう)に苦しい日々(ひび)であった。昭和24年には松下電器の物品税(ぶっぴんぜい)滞納(たいのう)(※2)が世間の話題になり、幸之助は新聞に「滞納王(たいのうおう)」と報(ほう)じられるほど行き詰(づ)まった状況(じょうきょう)の中にいた。
※1 窮乏(きゅうぼう):お金や物が不足して、生活にこまること
※2 滞納(たいのう):期日がすぎても、おかねや品物をおさめないこと

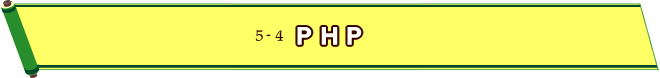
製品(せいひん)の公定価格(こうていかかく)(※1)が低く抑(おさ)えられている一方で、驚異的(きょういてき)なインフレ(※2)に見舞(みま)われ、松下電器(まつしたでんき)は製品を作れば作るほど赤字が増(ふ)える状態(じょうたい)にあった。幸之助にとって自分の会社が赤字を出し続けることは耐(た)え難(がた)い苦痛(くつう)であった。「正しく法を守り、誠意(せいい)を尽(つ)くして働いているものがみんな苦しみ、悪徳(あくとく)(※3)が栄えている」と、幸之助は戦後の混乱(こんらん)した社会を憂(うれ)えた。
「どうしたら人間の苦しみをなくし、正しい、平和な社会が築(きず)けるだろうか」
考えた末、幸之助が出した結論(けつろん)は「繁栄(はんえい)こそが幸福で平和な生活をもたらすものである。今の日本ではその繁栄をもたらす理念が認識(にんしき)されていないから平和な社会が築けないのだ」という考えであった。
「繁栄によって平和と幸福を(Peace and Happiness through Prosperity = PHP)」。この考えを実現(じつげん)しなければ国家の安定もなく、ましてや会社の安定もない。昭和21年11月3日、幸之助はPHPの実現方法(じつげんほうほう)を研究し、その考えを世間に広める機関として「PHP研究所」を設立(せつりつ)した。幸之助は一産業人としての立場を超(こ)える決心をしたのである。事業活動(じぎょうかつどう)が制限(せいげん)されていたことも手伝って、勉強会や講演会(こうえんかい)の開催(かいさい)、機関誌(きかんし)「PHP」の創刊(そうかん)、そして街頭でのビラ配りと、幸之助はPHP運動に精力(せいりょく)を傾(かたむ)けた。人生最大の苦難(くなん)の時期に、思想家(※4)、そして著述家(ちょじゅつか)(※5)としての幸之助が誕生(たんじょう)したのである。
※1 公定価格(こうていかかく):公に定められたねだん
※2 インフレ:物のねだんが続けて上がり、お金のねうちが下がっていくこと
※3 悪徳(あくとく):人の道から外れた悪いおこない
※4 思想家(しそうか):あるものごとに対して、まとまった考えを持っている人
※5 著述家(ちょじゅつか):書物を書きあらわすことを仕事にする人
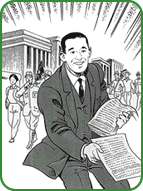
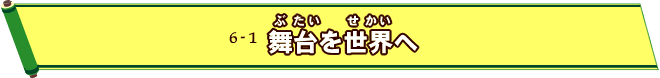
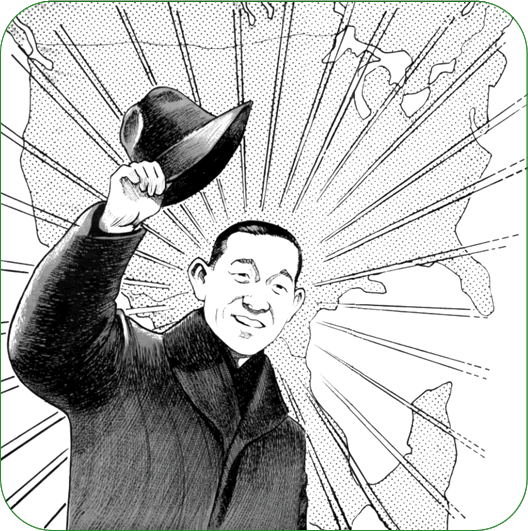
昭和25年、戦後の疲弊(ひへい)(※1)した日本経済(にほんけいざい)に変化が起こった。世界的な景気回復(けいきかいふく)の波に加え、6月に朝鮮戦争(ちょうせんせんそう)がぼっ発(※2)。参戦したアメリカが、軍需品(ぐんじゅひん)の調達を日本に求めたのである。世に言う「特需(とくじゅ)(※3)」が日本経済界(にほんけいざいかい)を刺激(しげき)した。
民需生産(みんじゅせいさん)で再建(さいけん)に取り組んでいた松下電器(まつしたでんき)にとって、特需そのものよりも、人々(ひとびと)の暮(く)らしに余裕(よゆう)が生まれてきたことが喜ばしかった。数年来の苦難(くなん)の時代を乗り越(こ)え、わずか半年のうちに松下電器は経営収支(けいえいしゅうし)を大幅(おおはば)に改善(かいぜん)。事業は軌道(きどう)に乗り始めた。
恒例(こうれい)の経営方針発表会(けいえいほうしんはっぴょうかい)を迎(むか)えた昭和26年正月、幸之助は事業の回復ぶりに深い感慨(かんがい)を覚えていた。しかし、その心はさらに前を、広く世界を見つめていた。これまでの経営をいったん白紙にして世界的視野(せかいてきしや)で事業を再構築(さいこうちく)したい。幸之助はその必要を痛感(つうかん)していた。壇上(だんじょう)で幸之助は今日の回復に甘(あま)んじる事なく「松下電器は、今日から再(ふたた)び開業する」という心構(こころがま)えで経営に当たることを宣言(せんげん)。初のアメリカ視察(しさつ)(※4)を発表した。旅行も英語も不得手な社長のこの発表に社員たちは一様に驚(おどろ)いた。このとき、幸之助は56歳(さい)。
※1 疲弊(ひへい):つかれ弱ること
※2 ぼっ発(ぱつ):急に起こること
※3 特需(とくじゅ):米軍が日本で調達する物や労力などを求めること
※4 視察(しさつ):ほんとのことを知るために実地を見ること
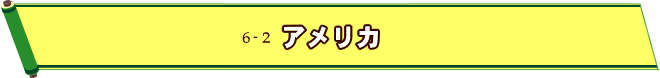
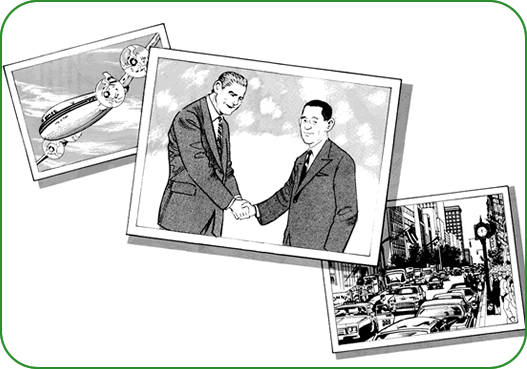
発表した2週間後にはもう、幸之助は機上の人(※1)となっていた。1月25日、ニューヨークに無事到着(ぶじとうちゃく)。日本とあまりに違(ちが)うアメリカは、強く幸之助の心を揺(ゆ)さぶった。人々(ひとびと)の合理的で気さくな考え方、工場の規模(きぼ)の大きさや専門細分化(せんもんさいぶんか)による効率(こうりつ)のよさ、街角や映画(えいが)の中に見る人々の暮(く)らしの、夢(ゆめ)のような豊(ゆた)かさ。なによりスケールとスピードの違いが幸之助の心をとらえた。
ある日、1台の工作機械(こうさくきかい)に興味(きょうみ)を持った幸之助は、製造元(せいぞうもと)の社長に話を聞きたいと思った。本社はカナダにある。国際電話(こくさいでんわ)が日常的(にちじょうてき)に交わされる風景にも驚(おどろ)いたが、会話の中身を知って、幸之助は開いた口がふさがらなかった。
「社長さんに話を伺(うかが)いたいのですが」
「社長はいま出張中(しゅっちょうちゅう)ですが、ビジネスの話なら現地(げんち)から飛行機でそちらに向かいます」
次の日、実際(じっさい)に目の前に現(あらわ)れたその社長と握手(あくしゅ)を交わしながら、幸之助は事業スケールの大きさと、そのスケールに負けない機動性(きどうせい)に感銘(かんめい)(※2)を受けていた。
※1 機上(きじょう)の人(ひと):飛行機に乗ってる人
※2 感銘(かんめい):心に深く感じてわすれないこと
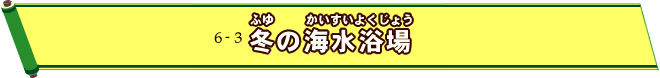

アメリカ滞在中(たいざいちゅう)のある日、幸之助は海水浴場を見に行く機会があった。しかし季節は冬である。しばらくして、寒さのあまりトイレに行きたくなった。人影(ひとかげ)のない海水浴場の公衆(こうしゅう)トイレに向かった幸之助は、思うともなしに、落書きだらけの汚(よご)れたトイレを予想していた。
「これは……!だれか掃除(そうじ)してるんやろか」
「何言ってるんですか、ミスター・マツシタ。当然、役所がやってるんですよ」
「お役所が……」
「そのために我々(われわれ)は税金(ぜいきん)を払(はら)っているんじやないですか
冬の海水浴場 幸之助は考え込(こ)んだ。日本では役所や役人は「お上」と奉(たてまつ)り(※1)、税金は「納(おさ)める」ものである。しかし、なんとアメリカは逆(ぎゃく)ではないか。役所をサービス機関ととらえ、目的をしっかり自覚して税金を払うアメリカ人の姿(すがた)は、後々(あとあと)までも幸之助の脳裏(のうり)に焼きつくことになった。
※1 奉(たてまつ)り:まつりあげる
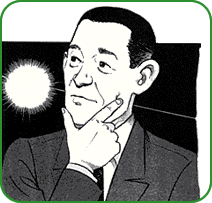
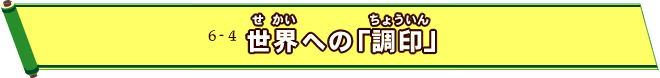
昭和27年10月、幸之助はオランダにいた。アメリカ視察(しさつ)を敢行(かんこう)(※1)してから2年足らず。すでに三度目の海外旅行(かいがいりょこう)であった。すぐに世界中に電化の時代が来る、そのとき世界を相手にするには、飛躍的(ひやくてき)な技術(ぎじゅつ)の向上と合理化が不可欠(ふかけつ)だ----。初渡米(はつとべい)以来、幸之助には並々(なみなみ)ならぬ危機感(ききかん)があった。常(つね)に、自分に足りないことは素直(すなお)に教えを請(こ)うてきた幸之助である。今は世界に教えを請うときだ。しかもことは一刻(いっこく)を争うと幸之助は感じていた。
世界への「調印」 幸之助が選んだ "先生" はオランダのフィリップス社。しかし、松下にとって、これは大きな賭(か)けでもあった。提携(ていけい)(※2)の条件(じょうけん)として、自社の資本金(しほんきん)(※3)よりも多い資本金を持つ子会社を設立(せつりつ)することになったからである。本当にこれでいいのか----。調印を目前にして幸之助は最後の自問自答(じもんじとう)をくり返していた。ペンを持つ手が震(ふる)えた。幸之助は、迷(まよ)いが晴れない自分を、しかり続けた。
「ええい、ここまで来て迷うやつがあるか」
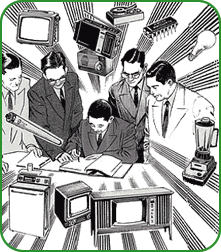
迷いに迷った幸之助の決断(けつだん)の是非(ぜひ)(※4)は、数年後に明らかになる。この提携で誕生(たんじょう)した「松下電子工業株式会社(まつしたでんしこうぎょうかぶしきがいしゃ)」は、しばらくしてあらゆる松下商品(まつしたしょうひん)の品質(ひんしつ)を支(ささ)える電子管や半導体(はんどうたい)を生み出していった。景気回復期(けいきかいふくき)にいち早く "世界" をめざした幸之助の志(こころざし)の高さが、高度成長(こうどせいちょう)の波に乗って「家電の松下」の世評(せひょう)(※5)を揺(ゆ)るぎないものに育てていったのである。
※1 敢行(かんこう):思い切って実行すること
※2 提携(ていけい):協同で仕事をすること
※3 資本金(しほんきん):事業を行う上で、もとでとなるお金のこと
※4 是非(ぜひ):正しいか、正しくないか
※5 世評(せひょう):世間によく知られて話題になること
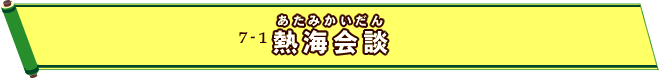
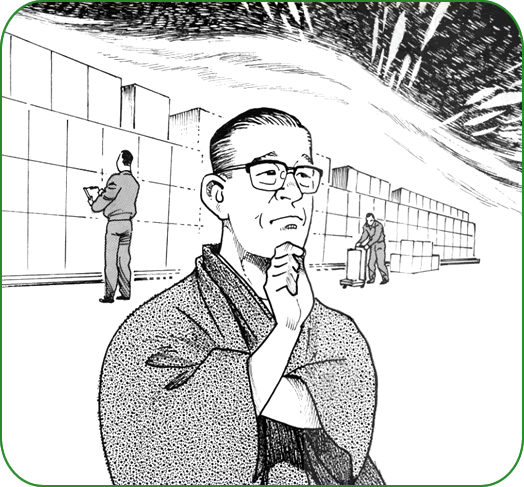
昭和36年、会長に退(しりぞ)いた幸之助は、活動拠点(かつどうきょてん)を京都の別邸(べってい)「真々庵(しんしんあん)」に移(うつ)し、会社運営(かいしゃうんえい)の日常業務(にちじょうぎょうむ)から離(はな)れた。ただし、社業の第一線から身を引いたといっても、「立志伝(りっしでん)(※1)中の人」として講演(こうえん)や取材の依頼(いらい)が殺到(さっとう)。相変わらず多忙(たぼう)な日々(ひび)を過ごしていた。しかし、空前の家電ブームも需要一巡(じゅよういちじゅん)で成長鈍化(せいちょうどんか)の時期を迎(むか)える。
昭和39年初夏、幸之助は報告書(ほうこくしょ)を眺(なが)めながら考え込(こ)んでいた。高度成長(こうどせいちょう)からくる業界の過熱投資(かねつとうし)や過当競争(かとうきょうそう)を少なからず憂(うれ)いていた幸之助は、長年の経験(けいけん)で、数字に表れた減収減益(げんしゅうげんえき)の兆しに、数字以上の事態(じたい)の深刻(しんこく)さ、構造的(こうぞうてき)行き詰(づ)まりを感じ取っていたのである。
やがて、営業所長(えいぎょうしょちょう)たちは会長からの突然(とつぜん)の号令を聞く。「営業所長が同道(※2)し、販売会社(はんばいがいしゃ)、代理店の社長さんに、一人残らずお集りいただきたい」----。場所は熱海である。
※1 立志伝(りっしでん):こころざしを立てて努力し、成功した人の伝記
※2 同道(どうどう):いっしょに行くこと
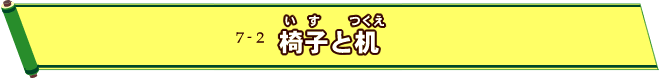
会議の前日、会場のチェックをしている幸之助が立ち止まった。
「これでは、出席していただく方全員のお顔が見えへんやないか」
「人数も多いことですし…」
「しかし今回は、ぜひ、皆(みな)さん一人ひとりとお話する気持ちで臨(のぞ)みたいんや」
椅子と机 会場にぎっしりならべられた椅子は、前列の人と人の間から後ろの人の顔が見えるようにならべ直されることになった。さらに、壇上(だんじょう)からチェックしていた幸之助は、もっとよく見えるようにと、壇を高くするようにと指示(しじ)を飛ばした。
案内状(あんないじょう)を出す前から、「今回の会合は日にちを切らない」「議題はあえて用意しない」と幸之助は事務局(じむきょく)に告げていた。そして自分自身(じぶんじしん)は当日一人ひとりにお渡(わた)ししたいと、合計200枚(まい)もの「共存共栄(きょうぞんきょうえい)」の色紙を毎日少しずつ気持ちを込(こ)めて、書き溜(た)めていたのである。「策(さく)はないが、とにかく徹底的(てっていてき)に話し合う」----。幸之助には並々(なみなみ)ならぬ決意があった。
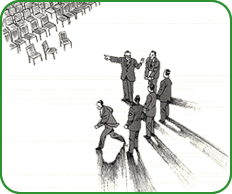
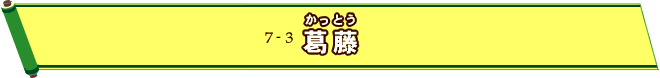
「結論(けつろん)が出るまで何日でもやる」
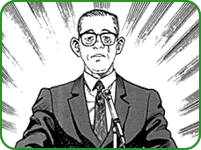
幸之助はこう切り出した。事態(じたい)に対する幸之助の漠然(ばくぜん)(※1)とした不安は的中していた。何と大半の販売会社(はんばいがいしゃ)・代理店が赤字に苦しんでいる。販売会社・代理店、ひいてはお店の努力不足(どりょくぶそく)なのではないか----。幸之助はそんな思いが抑(おさ)えられず、出席者の発言に激(はげ)しい反論(はんろん)をせずにはいられなかった。しかし松下に対する不満は思いのほか強かった。会場の声に耳を傾(かたむ)け、自らの意見を述(の)べながら、幸之助は葛藤(※2)のなかにいた。激論(げきろん)は平行線をたどり、いつ終わるとも知れない様相を呈(てい)していた。会議は3日目に入り、誰(だれ)もが結論は出ないのではと感じていた。
「皆(みな)さんの言い分はよく分かった。松下が悪かった」
突如(とつじょ)(※3)、頭を下げ、話を始めた幸之助に驚(おどろ)き、騒然(そうぜん)(※4)としていた会場はしんとなった。幸之助はもう誰が悪いと言い合っているときではないと思った。誰の言い分にもそれなりに理があり、どこが悪いといっても始まらない。現状(げんじょう)は分かった。この現状を突破(とっぱ)するために、そしてお得意先のこれまでの信頼(しんらい)に応(こた)えるために、今は松下が頑張(がんば)るときなのだ。葛藤は消え、一言ごとに、これまでのご愛顧(あいこ)(※5)に応えられていない現状への悔(くや)しさと、現状打破(げんじょうだは)への決意をかみしめていた。思いは一筋(ひとすじ)の涙(なみだ)となり、非難(ひなん)で埋(う)めつくされていた会場を団結(だんけつ)に変えた。
※1 漠然(ばくぜん):ぼんやりとしてはっきりしない様子
※2 葛藤(かっとう):入りくんだもめごと
※3 突如(とつじょ):なんの前ぶれもなしに
※4 騒然(そうぜん):さわがしい様子
※5 愛顧(あいこ):ひいきにしてもらうこと
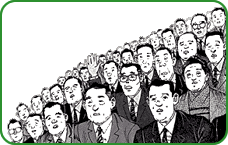
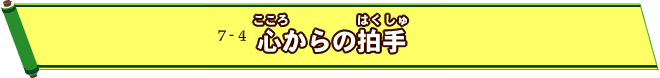
熱海での会議が終わった約3週間後、幸之助は自ら営業本部長代行(えいぎょうほんぶちょうだいこう)となった。"会長の第一線返り咲(ざ)き" に世間は一様に驚(おどろ)いたが、「非常時(ひじょうじ)には非常時のやり方がある」と幸之助は意に介(かい)さなかった。病気療養中(びょうきりょうようちゅう)の営業本部長の机の横に自分の机を置き、毎日のように出社した。幸之助が打ち出した改革構想(かいかくこうぞう)は「一地域(ちいき)一販社(はんしゃ)(※1)制(せい)」「事業部、販社間(はんしゃかん)の直取引」「新月販制度(しんげっぱんせいど)(※2)」の三つ。大改革(だいかいかく)だけに利害の対立が各方面で起こったが、幸之助は先頭に立って、理解(りかい)を得るため奔走(ほんそう)(※3)する日々(ひび)が続いた。
「松下さんがそこまで言うなら……」
「待ってください。そんなんではまだ十分とはいえまへん」
「やってみようというのに何が不服なんです?」
「心からの賛同(さんどう)(※4)をいただくまで、説明を続けさせてもらいます」

言うは易(やす)く行うは難(かた)し----。この改革(かいかく)は、関係者全員(かんけいしゃぜんいん)の強い意思統一(いしとういつ)のもとでなければなし得ない。幸之助はそう思い、販売会社(はんばいがいしゃ)や代理店、販売店(はんばいてん)での説明でも満場一致(まんじょういっち)(※5)の拍手で積極的な賛同を全員から得るまでやめなかった。
文字通りの "ヒザ詰(づ)め" での懇談(こんだん)(※6)も重ねた。やがて、新販売制度(しんはんばいせいど)は軌道(きどう)に乗り、苦しかった販売会社・代理店の経営(けいえい)も回復(かいふく)し始めた。
昭和40年、「勲二等旭日重光章(くんにとうきょくじつじゅうこうしょう)」を受章した幸之助に、全国の販売会社・代理店から「天馬往空之像(てんばおうくうのぞう)」が贈(おく)られた。「共存共栄(きょうぞんきょうえい)」の信念で改革を断行(だんこう)した幸之助への感謝(かんしゃ)、そして心からの信頼(しんらい)の表れであった。
※1 立志伝(りっしでん):こころざしを立てて努力し、成功した人の伝記
※2 同道(どうどう):いっしょに行くこと

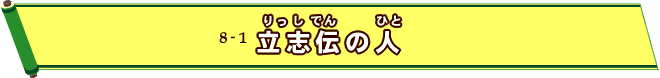
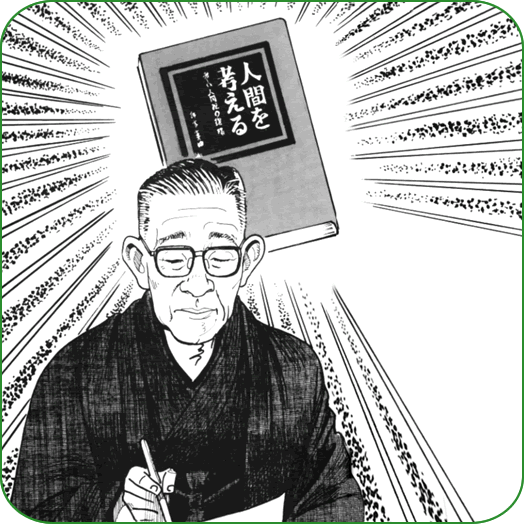
幾度(いくど)もの困難(こんなん)を見事に克服(こくふく)し、経営者(けいえいしゃ)としてまれに見る成功を収(おさ)めてきた松下幸之助を、いつしか世間は「経営の神様」と呼(よ)ぶようになっていた。 しかし、飽(あ)くなき向上心が身上である幸之助には、まだまだ満足という気持ちはなかった。
経営活動(けいえいかつどう)を通し、そしてPHP研究を通して、いつしか幸之助は、「人間とは何か」という根源的(こんげんてき)なテーマと向き合っていた。 これこそ、経営活動を通して半世紀もの間、追い求めてきたものではないか。 経営者としての成功が揺(ゆ)るぎないものになればなるほど、探求心(たんきゅうしん)は募(つの)った。 そして昭和47年、長年、思索(しさく)してきた「新しい人間観」について、一つの答えを一冊(いっさつ)の本にまとめた。 書き終えたとき「自分は結局このことが言いたかったのだ。自分の考え方の根本はこれに尽(つ)きる」とさえ思った著書(ちょしょ)、「人間を考える----新しい人間観の提唱(ていしょう)(※1)」である。
※1 提唱(ていしょう):人に先立って新しい考えかたを言いはること
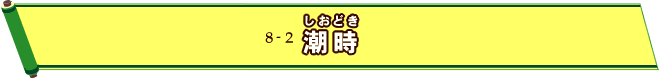
昭和48年7月、幸之助はふと「松下電器(まつしたでんき)も今年で創業(そうぎょう)55年。自分も人生80年の区切り目や」と思った。 するとその瞬間(しゅんかん)、日ごろ漠然(ばくぜん)と考えていた”引退(いんたい)”の二文字が急速に現実感(げんじつかん)を持ってきたのである。そや、そろそろ潮時(※1)や----。 幸之助は素直(すなお)にそう思った。
「どない思う?」
「どない、って言われましても…」
「私(わたし)も数えで80歳、ここらが潮時やと思う。 君はええと思うか?」
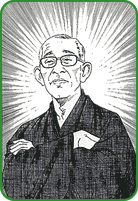
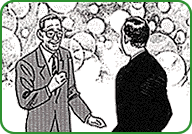
次の日、在阪(ざいはん)の役員たちを訪(たず)ね、自分の引退が経営陣(けいえいじん)にどれほどの影響(えいきょう)を与(あた)えるかを推(お)し量る幸之助の姿(すがた)があった。 突然(とつぜん)の話に、はじめは一様に驚(おどろ)くものの、「幸之助のいない松下」を支(ささ)える覚悟(かくご)を囲めていく役員たちの姿を見て、幸之助は安堵(あんど)(※2)した。
思い立ってわずか3日、幸之助は取締役会(とりしまりやくかい)の席上で、会長から相談役へ身を引く決意を表明した。 続く記者会見で「自分で自分の頭をなでてやりたい心境(しんきょう)です」と、所信を淡々(たんたん)と語る姿は、やるべきことはやったというすがすがしさに満ちていた。
※1 潮時(しおどき):物事をするのにちょうどよい時
※2 安堵(あんど):安心すること
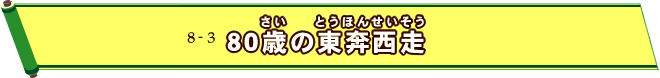

かつて知人から「商売人が政治(せいじ)に手を出したらあかん」と戒(いまし)め(※1)られ、自分自身(じぶんじしん)でも積極的な活動は控(ひか)えてきた幸之助だが相談役に退(しりぞ)いて経営(けいえい)に一線を画して以来、日に日に、日本の将来(しょうらい)を案じる気持ちが強くなっていくのを抑(おさ)えることはできなかった。
世界の繁栄(はんえい)の中心は時代と共に移(うつ)り変わってきた。来るべき21世紀はアジアが世界の繁栄をリードする時代になるだろう。 そのとき、日本は中心的役割(ちゅうしんてきやくわり)を果たすべき立場にあるのではないか----。 こう考えると、政治も経済(けいざい)も社会も、新しい世紀にふさわしい新しい国に変わる必要があると、幸之助は切実に感じていた。 案じるあまり、頭が冴(さ)えてきて一睡(いっすい)もできない日もあるほどだった。
「日本が輝(かがや)かしい21世紀を迎(むか)えるために、やりたいことがたくさんあるんや」
80歳の東奔西走 憂国(ゆうこく)(※2)の情(じょう)から、幸之助は『崩(くず)れゆく日本をどう救うか』『新国土創成論(しんこくどそうせいろん)』『無税国家論(むぜいこっかろん)』などを発表し、「松下政経塾(まつしたせいけいじゅく)」を設立(せつりつ)した。 常(つね)に世界の中の日本という観点に立つ幸之助は、一方で積極的に世界に働きかけた。 国際科学技術財団(こくさいかがくぎじゅつざいだん)をつくり、日本国際賞(にほんこくさいしょう)を設置(せっち)。大きな視野(しや)に立って中国の近代化に協力しなければならないと、中国訪問(ちゅうごくほうもん)も果たした。
21世紀に日本が果たすべき役割を大きなスケールで描(えが)き、世に問い、実行に東奔西走する幸之助は80歳を越(こ)えてなお、果てしない未来を見据(みす)えていた。
昭和62年、92歳の幸之助は勲一等旭日桐花大綬章(くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう)を受章した。 民間人として異例(いれい)の受章は、社会への役立ちを第一に考えて活動してきた証(あか)しであった。
※1 戒(いまし)め:あやまちがないように前もってあたえる注意
※2 憂国(ゆうこく):国のことを心配すること
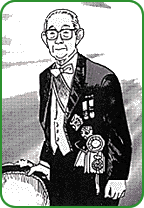
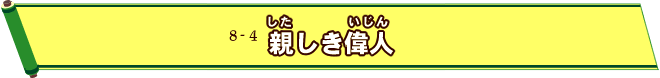
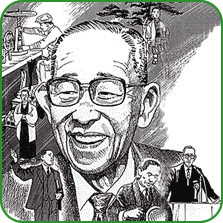
昭和が終わりを告げた春、風邪(かぜ)をひいた幸之助はそのまま気管支肺炎(きかんしはいえん)を起こし、94年5ヶ月にわたる生涯(しょうがい)を閉(と)じた。 平成元年4月27日午前10時6分。 波乱(はらん)に富(と)んだ人生とは対照的な、安らかな顔で迎(むか)えた最期であった。 国内外のマスコミが大きく報(ほう)じ、訃報(ふほう)(※1)は世界を駆(か)け巡(めぐ)った。 密葬(みっそう)(※2)に1万2千人、松下グルーブ各社の合同葬には約2万人が参列。 アメリカ合衆国大統領(がっしゅうこくだいとうりょう)をはじめ、世界中から多数の弔電(ちょうでん)(※3)が寄(よ)せられた。
まだ電灯さえ普及(ふきゅう)の途(と)にあった明治の終わりに電気の世界に身を投じ、マルチメディア時代を目前にした昭和の終わりに幕(まく)を引いた幸之助の生涯は、日本の電化時代を象徴(しょうちょう)する立志伝であった。 世界の繁栄(はんえい)という大きな願いを、あくまで追い求める高邁(こうまい)(※4)な精神(せいしん)と同時に、常(つね)に世間の人々(ひとびと)と同じ立場に立つ庶民性(しょみんせい)を併(あわ)せ持つ不思議な魅力(みりょく)。 そして、火鉢屋(ひばちや)の丁稚(でっち)を振(ふ)り出しに、幾多(いくた)の困難(こんなん)を強い信念で乗り越(こ)え、自らの「道」を切り拓(ひら)き続けた生き方は、今もなお、多くの人の心に生き続けている。
心を定め
希望をもって歩むならば
必ず道はひらけてくる
※1 訃報(ふほう):人が死んだことの知らせ
※2 密葬(みっそう):うちうちでする葬式(そうしき)のこと
※3 弔電(ちょうでん):死者をくやむ電報(でんぽう)
※4 高邁(こうまい):気高くすぐれていること