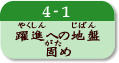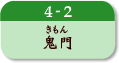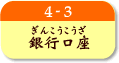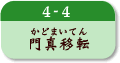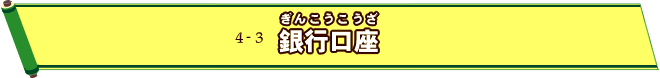
同じ頃(ころ)、幸之助は一つの組織改革(そしきかいかく)を考えていた。それは、昭和2年の電熱部設立(でんねつぶせつりつ)のとき、まったく新しい事業なのに忙(いそが)しくて手が回らない幸之助が「ならば、いっそのこと」とばかりに製造(せいぞう)から販売(はんばい)までの全部をある幹部(かんぶ)に任(まか)せたことがヒントとなっていた。
「実はな、君に事業部長(じぎょうぶちょう)をやってもらおと思てるんや」
「事業部長? 部長と違(ちが)いまんのか」
「違う。もっとえらいで」
幸之助は、事業を製品群別(せいひんぐんべつ)に「事業部」に分け、その一つひとつを独立(どくりつ)した事業体として経営(けいえい)したいと考えた。それぞれの事業部のトップに人、物、金に関する権限(けんげん)と責任(せきにん)を大幅(おおはば)に任せることで、自分一人ではすべてを見ることができなくなっていく事業の拡大(かくだい)に対応(たいおう)し、同時に真の経営者(けいえいしゃ)を育てたい。どういう意味なのか、ピンと来ない幹部たちに幸之助は、小さな帳簿(ちょうぼ)(※1)を見せた。
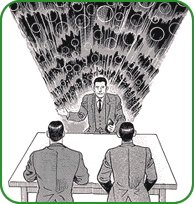
「これは……」
「きみ名義(めいぎ)の口座を一つ開いたんや。この口座のやり繰(く)りはきみの責任やで。しっかりやってや」
幸之助は任せる覚悟(かくご)を、事業部長に銀行口座をもたせることで示(しめ)してみせたのだった。通帳を手にした事業部長も、責任の重さを感じていた。昭和8年5月、日本で初めての事業部長が誕生(たんじょう)した。
※1 帳簿(ちょうぼ):お金や品物の出し入れを記入する帳面