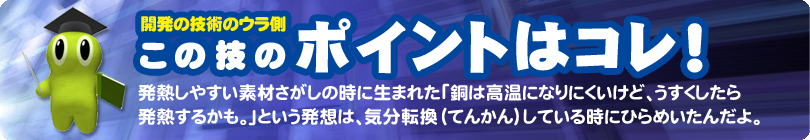002「銅釜(どうがま)を使った炊飯器(すいはんき)」開発の技術のウラ側

「もっとおいしいご飯が食べたい」そんな追究から生まれた「銅釜(どうがま)炊飯器(すいはんき)」。
「まんべんなく高温」にすることがおいしいご飯をたくために必要。
そのために発熱しやすい素材(そざい)は何か。
炊飯器の開発者 大橋秀行(おおはしひでゆき)が素材さがしで苦労する毎日の合間に家族との休日に目にしたのが、奈良(なら)の銅像(どうぞう)。
その美しさにひきつけられると共に新たな発想が生まれたんだ。
「銅は電気抵抗(ていこう)が低くて高温になりにくいからさがしてる素材に不向きだけど、金ぱくみたいにうすくしたら電気抵抗が高まって発熱するかもしれない」。それからが新しいスタートの始まり。
銅をどのくらいうすくするかの問題、量産する設備(せつび)の問題などをクリアして、
ついに発売!そして成功!
その後も開発者は次々に新たな炊飯器づくりに情熱(じょうねつ)をもやし続けている。
おいしいご飯を食べたら、炊飯器を開発した人の想いを考えてみるのもいいね。