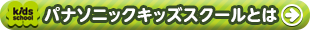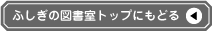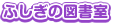

天気のことわざはほんとうにあたる?
天気のことわざは、風の吹(ふ)き方や雲などを見て、昔の人の経験(けいけん)から伝わってきたものが多い。迷信(めいしん)ではなく、科学的に根拠(こんきょ)があるものも多いんだ。その中のいくつかを紹介(しょうかい)しよう。
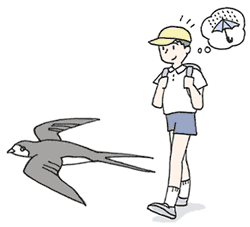
「日がさ月がさは雨のきざし」
太陽や月のまわりに、きれいな輪がかかっているように見えることがある。これは低気圧(ていきあつ)や前線の前面で見られるうす雲のせい。この雲が出ると、時間がたつにつれて雨が降(ふ)りやすくなる。
「ツバメが低く飛ぶと雨」
空気中の水分が多くなると、蚊(か)などの羽が水分をおびて、下の方を飛ぶようになる。すると、蚊をえさにするツバメも低く飛ぶようになる。空気中の水分が多いということは、雨になりやすいということだ。
「高い山(ふじさん)にかさ雲がかかると雨」
富士山などの高い山では、かさをかぶったような雲が見られる。山の近くで上昇気流(じょうしょうきりゅう)が起こり、水分を含(ふく)んだ空気が山をはい上がって、山頂(さんちょう)近くに雲を作るためだ。このため、かさ雲が出ると雨が降(ふ)ることが多い。