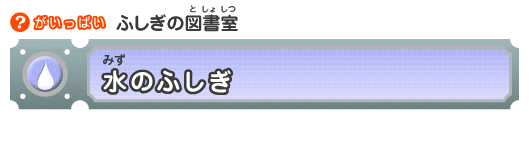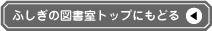サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
川はどうやってできる?
川の水はどこから来るのかな?川になるまで、水はいろいろ姿(すがた)を変えて冒険(ぼうけん)しているぞ。まずは海からスタート。広い広い海からたくさんの水が蒸発(じょうはつ)して水蒸気になり、空の上で雲を作る。その雲から降(ふ)った雨がたくさんたくさん集まって川になるんだ。雨粒(つぶ)の一つ一つは小さいけれど、集まったらあんなに大きな川を作るんだね。
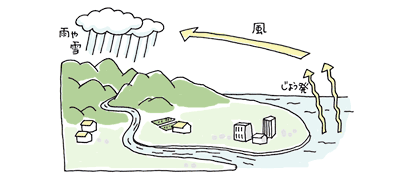
川がどこから流れ始めているかというと、ほとんどの出発点は山の中。山に降った雨や、雪が解(と)けて流れ出した水が、土や岩の中に染(し)み込(こ)んで溜(た)まって、わき水として山のあちこちから出て来るんだよ。ちょろちょろ流れ出したわき水は少しずつ集まって、だんだんと大きくなり、やっとみんなのよく知っている川の姿になるんだ。
水はほかの星にもある?
地球以外の星からは、今のところまだ、水は見つかっていない。どうしてだと思う? 水は、すごく寒い星では氷になっちゃうし、逆(ぎゃく)にすごく暑い星では水蒸気(すいじょうき)になってしまう。今までに人が調べた星の中で、水が液体(えきたい)のままである温度の星はないんだ。地球ってすごいんだね。広い宇宙(うちゅう)でたった一つだけ、水のある星なんだから。
地球って宇宙から見ると青と白のとってもきれいな星。青は海の色、白は海から沸(わ)き上がってくる水蒸気でできる雲の色。動物や植物が地球で暮(く)らせるのも、このたくさんの水があるからなんだよ。
川はみんな青色だろうか?
絵の具の「水色」は薄(うす)い青。だから川の色はみんな青? 実は青じゃない川もたくさんある。外国に行くといろんな色の川が流れているよ。中国の黄河(こうが)という大きな川は黄色の砂(すな)が降(ふ)ってくるから黄色いし、いつも泥(どろ)が混(ま)じっていて茶色いままの川もある。

日本でも、山の方に行くと、水の深さの違(ちが)いで緑色に見える川があるって知ってた? それに汚(よご)れた水も緑色になっちゃう。汚れた水には植物性(しょくぶつせい)プランクトンという緑色の小さな生き物の好きな栄養が入っているから、植物性プランクトンがどんどん増(ふ)えて、水を緑色にしてしまうんだ。流れにくくなった川の水ほど、すぐに汚れて緑色に変わってしまう。同じ川なのに、不思議だね。
地面の下に、きれいな水がある
地面の下に流れている水、それは地下水だ。土や岩に染(し)み込(こ)んだ水が、地下に溜(た)まって地下水になる。地下を流れる水は川に比(くら)べてとてもゆっくりなので、すぐには海に流れ込まないから、雨が少なくてぼくたちが困(こま)っている時にも助けてくれるんだ。
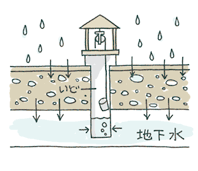
そんな地下水を上手に利用するために、地下水に海の水が混(ま)ざらないようにする地下ダムっていう仕組みもあるよ。地下で溜めた水は井戸(いど)という穴(あな)からすくい上げて、おいしく飲むこともできる。地下ダムには、地下水を飲み水などに利用するためだけじゃなく、雨がいっぱい降(ふ)り過(す)ぎた時に洪水(こうずい)を防(ふせ)ぐという大切な役割(やくわり)もあるんだよ。
硬(かた)い水と軟(やわ)らかい水があるって本当?
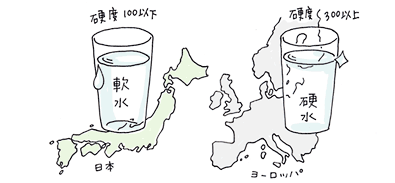
本当。でも、触(さわ)っただけじゃ分からないよ。水には主にカルシウムとマグネシウムという成分でできているミネラル分というものが溶(と)け込(こ)んでいる。そのカルシウムとマグネシウムがいっぱい入った水のことを「硬水」(こうすい=硬い水)、少ない水を「軟水」(なんすい=軟らかい水)と呼(よ)んでいるんだ。
硬さが違(ちが)うと、特徴(とくちょう)も全然違(ちが)う。もし、ふっくらとしたおいしいご飯を炊(た)きたいなら、軟水がぴったりだ。反対に硬水を使うとご飯がぱさぱさになっちゃう。世界には硬水が多い国と軟水が多い国があるんだけど、日本には軟水が多いから、お米もおいしく炊けるんだよ。
海はどうやってできたの?
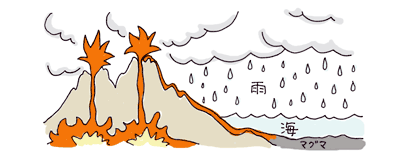
海は、ずっと大昔にたくさんたくさん降(ふ)った雨が地上に溜(た)まってできたもの。今から46億年も前の地球には、まだ熱いマグマの海しかなくて、空も、水蒸気(すいじょうき)や二酸化炭素(にさんかたんそ)で覆(おお)われていたんだ。その内地球の、表面の温度がだんだん下がり始め、水蒸気が雲になってそこから雨が降ってきた。雨はさらに地表の温度を下げて、下げればまた新しい雨が降るという繰(く)り返しがずっと続いた。海ができるほどなんだから、すごいたくさんの雨だったんだね。
そうやってでき上がった海は、鉄やアルミニウム、ナトリウムなど、地球上のほとんどの元素(げんそ)を含(ふく)んでいて、もう今の海と同じくらい塩辛(から)かったんだって。
花はどうやって水を吸(す)っているの?
花は土の中の根から水を吸い込(こ)んでいるんだよ。植物の中の水分の多さと、土の中の水分の多さを比(くら)べてみると、土の中の水分の方が多い。だから、水の分子が植物の中へ入っていくんだ。水は多い方から少ない方へ染(し)み込(こ)んでいく。この仕組みは浸透圧(しんとうあつ)と呼(よ)ばれているよ。根から入った水は、茎(くき)を通って花全体に行き渡(わた)っていく。
じゃあ、根がない花瓶(かびん)の花は水を吸うことができないのかな? 心配いらないよ。切った茎の一番下から同じことができるんだ。だから、茎を切る時は斜(なな)めに切ってあげると、水を吸う面が広くなって、たくさんの水が吸えるから、長生きできるんだよ。
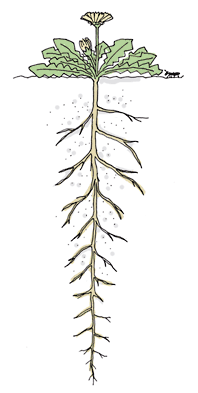
地球上は海だらけ
宇宙(うちゅう)から見た地球は青く見える。それは表面がほとんど海だから。陸の部分は地球上でおよそ、たった10分の3しかなくて、残りのおよそ10分の7は海なんだって。海が陸より2倍以上も広いなんて、ちょっとびっくりだね。
そんなに広いから、地球上の水のほとんどが海にある。地球にある水は大きく分けると、塩からい海水と、川や湖なんかの塩からくない淡水(たんすい)の2種類。淡水は、南極や北極のすごく大きな氷も含(ふく)まれるのに、地球上の水のほんの100分の2.5くらいにしかならないんだ。地球には本当にたくさんの海水があるんだね。
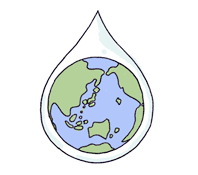
どうしてダムを作るの?
どうしてダムを作るの? さて、ここで問題。どうしてダムを作るんだと思う?
A 水を溜(た)めて使うため
B 川をなくすため
C 魚を飼(か)うた
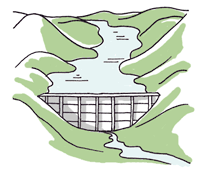
正解(せいかい)はA。たくさん雨が降(ふ)った時に水を溜めておいて、欲(ほ)しい分だけ使うためだ。もしダムがなかったら、どうなるだろう? たくさん降った雨は川からすぐ海に流れ込(こ)んでしまうし、川があふれてしまうこともあるんだ。ちなみに日本はとってもダムの多い国。なぜかというと、日本では、梅雨(つゆ)や台風などで雨がたくさん降ることもあれば、ずっと雨が降らないこともあるから。だから水が足りなくならないように、溜めておく必要があるんだよ。
ただ、心配なのは魚たち。ダムで川をせき止められて大丈夫(だいじょうぶ)なのかな?大丈夫。ダムの中には、魚が通るための道もちゃんと作られているから安心して。でも、大きなダムはどうしても貴重(きちょう)な自然を壊(こわ)して作るから、これからは作るのが難(むずか)しいということも考えておいてね。
歯磨(みが)きの時に使う水の量は?
さて、問題だよ。歯磨きには1回どれ位の水を使っていると思う?
A コップ3杯(ぱい)分
B コップ10杯分
C コップ30杯分
正解(せいかい)はC。歯磨きの時水を出しっ放しにしていると、たった30秒でコップ30杯分(約6リットル)も水を使っちゃうんだよ。歯ブラシでごしごししている間は水道の水を止めて、うがいをする水はコップにくんで使うといいね。

実は、暮(く)らしの中では意外とたくさんの水が使われているんだ。例えば、おふろでシャワーを10分間出しっ放しにしたら、約120リットル(2リットルのペットボトル60本分)もの水を使う。さらに、ホースから水を流して車を洗(あら)うと、1回の洗車(せんしゃ)で約240リットルもの水を使っちゃうんだよ。水道は出しっ放しにせず、水を大事に使おうね。
おふろの底の水は表面よりなぜぬるい?
いつもおふろに入った時に思うでしょ? どうしておふろの底の方は、上の方よりぬるいんだろう。
A 火から遠いから
B 熱いお湯は軽いから
C 地面が冷たいから
正解(せいかい)はB。温かい水は冷たい水よりも軽いんだ。水が一番重くなる温度は4度。それより温度が高くなればなるほど、軽くなっていく。下の方から温めるおふろの水も、温まって軽くなると上へあがっていくし、冷たくて重い水ほど下に沈(しず)む、というわけ。表面は熱くても、下にいくほど温度が下がって、一番ぬるい水が底に溜(た)まっていくよ。
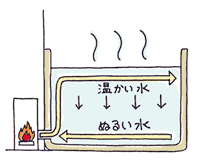
水を温める時には、ぐるぐる回ることで少しずつ全体を温めていく。こういう水の動きを対流という。やかんなどで水を沸(わ)かしている時も、同じような動きをしているんだ。
水をもっとおいしく飲む方ほうあるの?
毎日使ってる水道の水。もっとおいしく飲む方法があったら、きっともっと好きになるよね。それにはこんな方法があるよ。水の温度を10度位まで冷やして飲む。どうしてかというと、水道の水の中には、汚(よご)れなんかをきれいにする塩素(えんそ)が含(ふく)まれている。でも、水の温度が低ければ、塩素の臭(にお)いを感じなくなって、おいしく感じるんだ。反対に名水でも、ぬるいとおいしくなくなってしまう。
冷たくする以外にも方法がある。レモンの汁(しる)やお茶の葉っぱを少しだけ入れてみよう。やっぱり塩素の臭いを消してくれて、水道水でも名水に負けないおいしさで飲めるんだよ。
水道の水はどこから来て、どこに行くの
水道をひねれば、水はいつでも出てきてくれる。あの水は一体どこから来ているんだろう。洗面所(せんめんじょ)で流した水は、どこへ行くんだと思う?
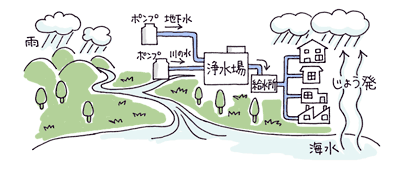
みんなが普段(ふだん)飲んだり手を洗(あら)ったりする水は、元々(もともと)川の水や地下水だ。海の水は塩辛(から)くて飲めないので、雨が溜(た)まってできる真水だけを使っている。真水は浄水場(じょうすいじょう)に集められて、ゴミやばい菌(きん)を取ってきれいになってから、ぼくらの家まで届(とど)けられているんだよ。家で使った水は、川に流れて海へ行く。海へ行った水は蒸発(じょうはつ)して雨になって、また水道に戻(もど)ってくる。 水の大冒険(だいぼうけん)は毎日続いているんだね。
人の体はほとんど水って本当?
人の体にどの位の水分があるかというと、なんと60%(パーセント)、体重の3分の2位にもなるんだ。体の全体に、いっぱい水が入っている。だから人間にとって水はとっても大切。もしも水がなかったら、人は一週間位で死んでしまう。怖(こわ)いね。反対に、何も食べなくても、水だけあれば3週間は生きられるっていうから、やっぱり水ってすごい。
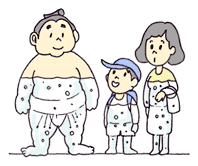
人の体からは毎日2.5リットルもの水分が、汗(あせ)やおしっことして出て行く。でも、飲み水や食べ物からまた同じ量の水分が入ってくるんだ。だから、地球にある水が汚(よご)されていくと、人はすぐに病気になってしまう。水はとっても大切なんだよ。
はじめの生き物は海から生まれたって本当?
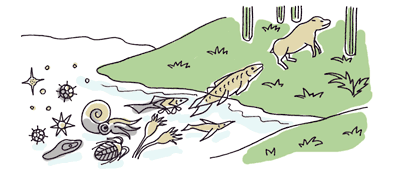
ずっと大昔、最初の生き物は海の中で生まれたんだよ。生き物は太陽の紫外線(しがいせん)をいっぱい浴びると生きられないから、紫外線があまり届(とど)かない深い海で少しずつ進化していったんだ。そのころ地上には生き物は一匹(いっぴき)もいなくて、海の中でゆっくり進化した生き物が、やがて地球にとどく紫外線が少なくなって、生き物は海を出て地上に上がり始めた。
でも、地上に上がる時にちゃんとおなかの中に、海の水を入れておいたんだよ。お母さんのお腹の中の羊水(ようすい)でみんなは生まれるのを待っていたんだけど、その羊水は海の水と同じ成分なんだって。だから、今でも、生き物はみんな海の中で生命をもらって生まれてくるんだよ。