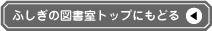サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
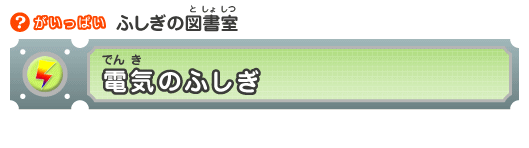
-
電気はどこからやってくるの?
-
電車ってどうやって動かしてるの?
-
LED照明(しょうめい)はどうやって光るの?
-
電話で話ができるのはなぜ?
-
電子レンジはどうやってたべものを温めているの?
-
トースターやアイロンはどうしてあつくなるのかな?
-
セーターをぬぐときパチパチいってるのはなに?
-
雷(かみなり)はどうして起こるの?
-
鳥は電線にとまってもしびれないの?
-
太陽の光で電気ができるって本当?
-
人間の体に電気が流れているって本当?
-
テレビはどうしてうつるの?
-
けいたい電話で話ができるのはなぜ?
-
電球(でんきゅう)はどうやって発明されたの?
-
電気が流れるものと、流れないものがある
-
電気っていったい何?
-
発電の仕組みを詳(くわ)しく知りたい!
-
自分でも発電できますか?
電気はどこからやってくるの?
みんなの家のテレビやエアコンなどを動かしている電気って、一体どこから来てるんだろう。実は、みんなの家から遠く離(はな)れた発電所から、長い長い電線を通ってはるばるやって来ているんだよ。
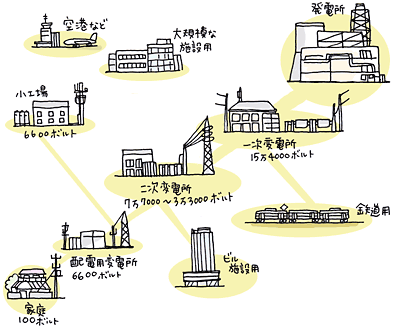
でも、そこで作られた電気はとても力が強い。だから、みんなの家に届(とど)ける前に、変電所(へんでんしょ)で強さを調節しているんだ。だからみんなの家に届くころには、安全に使える100ボルトの力になっているんだよ。
電車ってどうやって動かしてるの?
電車って大きいね。電気で動かすから電車という名前なんだけど、一体どうやって動かしているんだろう?
電車の屋根の上をよく見ると、電線があるはずだ。電車はここから電気を取り入れているんだ。でも、この電線だけでは走らないんだよ。電気には、流そうとする力が強い方から弱い方に流れるという特徴(とくちょう)がある。電車の上にある電線のほうが、流そうとする力が強く、流そうとする力が弱い電線と同じ役割をするのが、線路なんだ。その流れる道筋(みちすじ)にあるモーターに電気が通ることで、車輪を回して電車を動かしているんだよ。
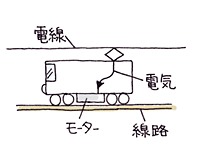
LED照明(しょうめい)はどうやって光るの?
みんなの家の部屋や教室を照らしている、LED 照明。小さいけれど、スイッチを入れるとすぐに明るく光るし、色も変えられたりする。でも、どうしてそんなに便利なの?どんな仕組みで光るのかな?
LEDは「発光ダイオード(はっこうダイオード)」の略で、電気を流すと光る特別な素材でできているんだよ。
LEDの中には、電気を流すと光を出す性質を持った物質が入っているんだ。スイッチを入れて電気を流すと、この物質が光り出すんだよ。LED は、使う物質の種類によって、赤や青、緑など、いろいろな色の光を出すことができるんだよ。白い光を出すLED は、青い光を出すLED に黄色い蛍光物質を組み合わせているんだ。
LED照明のいいところは、電気が少なくても、とても明るく光らせることができるということ。それに、長持ちするし、熱をあまり出さないから環境にもやさしいんだ。蛍光灯(けいこうとう)や白熱灯(はくねつとう)と比べて、電気のエネルギーを無駄なく光に変えることができるんだよ。
電話で話ができるのはなぜ?
みんなは糸電話で遊んだこと、あるかな? 紙コップと紙コップの間を糸でつないで、片方(かたほう)のコップを口に当てて話すと、もう片方のコップから声が聞こえる。でもずっと遠くの人とのお話は無理だ。壁(かべ)だってあるし、糸もそんなに長くできないからね。
なのに家の電話だったら、遠くにいる人とでも話ができるのはなぜだろう? これは音を電気に変えて運ぶからなんだ。電話で話ができるのはなぜ?
話器の中にある振動板(しんどうばん)は、糸電話の紙コップが声の震(ふる)えを糸に伝えるような役目をしている。そして糸の代わりが電話線というわけ。電話線の中では音が電気の波に変わって、遠くの人まですぐに届(とど)いちゃう。届いた電気の波は、また振動板に伝わって声になるんだよ。
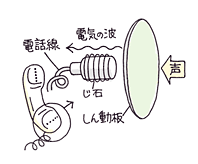
電子レンジはどうやって食べ物を温めているの?
電子レンジはどうやって食べ物を温めているの? 火も使わないのに、どうして電子レンジの中の食べ物はアツアツになるのかな? ちょっと難(むずか)しいから、順番に説明するよ。まず、食べ物の中には水がたくさん含(ふく)まれている。水は水分子というすごく小さな粒(つぶ)の集まりなんだ。
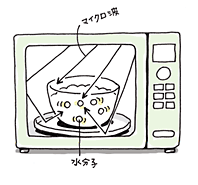
冷たい水の時は水分子がゆっくり動いているけど、お湯の時は激(はげ)しくぶつかり合って、ぶつかったエネルギーで熱を出す。ということは、食べ物を温めるには、中の水分子を激しく揺(ゆ)らすといいんだよ。
ここで電子レンジの出番。電子レンジはマイクロ波という電気と磁気(じき)の波を出すんだ。このマイクロ波が食べ物に当たると中の水分子はお互(たが)いにぶつかりあう。だから温かくなるんだね。
トースターやアイロンはどうして熱くなるのかな?
トースター、アイロン、こたつ、ドライヤーなど。熱を出す道具は、一体どうやって熱を出しているんだろう?
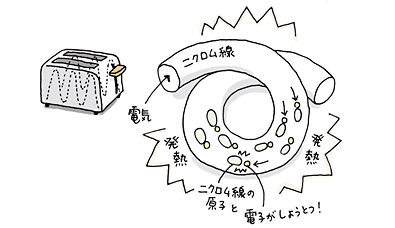
まず、ものに電気が流れる仕組みから説明するね。そのためには、原子や自由電子というものの話から。
あらゆる物質は原子という小さい粒でできているんだよ。原子の中心にはプラスの電気を持つ原子核があり、原子核のまわりにはマイナスの電気を持つ電子があって、原子核と電子の数は等しいので、原子全体としては中性で電気を帯びていない状態なんだ。ところが金属の場合は原子が金属結晶という密な結晶をつくっていて、原子の一番外側の電子が一つの原子にしばられることなく金属全体の中を移動することができるんだ。これらの電子を自由電子と呼んでいるよ。金属に電圧をかけると自由電子が移動して電流となる。金属に電流が流れるのは、この自由電子が存在するからなんだ。
そして、トースターやアイロンなど熱を出す電気製品には、ニクロム線という電気を流しにくい金属の線が入っている。ニクロム線に電圧を加えると、ニクロム線内部で自由電子と原子がぶつかることによって生じる振動で、ニクロム線が発熱する。それで、トースターの熱でパンを焼けたり、アイロンの熱でシャツの生地のシワをまっすぐにのばしたりできるんだよ。
セーターを脱(ぬ)ぐ時パチパチいってるのは何?
セーターを着て体を動かしていると、セーターとその内側の服が擦(こす)れ合うよね。すると片方(かたほう)がプラスの電気を持ち、もう片方がマイナスの電気を持つようになるんだ。そうなってからセーターを脱ぐと、マイナスの電気はプラスの方に引き寄(よ)せられ、電気が流れている状態(じょうたい)になってしまう。パチパチというのは電気が流れる音、チクチクするのは電気に触(ふ)れたからなんだ。こういう電気のことを静電気と呼(よ)んでいるよ。

雷(かみなり)はどうして起こるの?
雲の中には大小様々(さまざま)な氷のかけらがある。かけら同士が激(はげ)しくぶつかり合うと、電気ができる。この電気は少しずつ雲の中に溜(た)まっていくんだ。でも、抱(かか)えきれなくなると地面に向かっていきなり電気が一気に流れていっちゃう。これが雷の正体なんだよ。
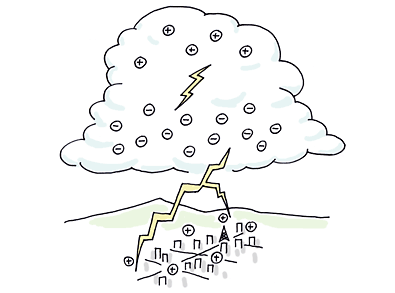
ではどうしてピカッと光ったりゴロゴロと音がするのだろう? 地面に向かって電気が流れた瞬間(しゅんかん)、1万℃(度)以上の高温になった空気の分子が激(はげ)しく運動する。それが光や、激しい音の原因(げんいん)になるんだ。普通(ふつう)、空気は電気を通さない物なんだけど、雷の時は電気を流そうとする力がおよそ1億ボルトにもなるから、無理やり空気の中をかき分けて進んでいく。だからまっすぐ進めずにギザギザに見えるんだって。
鳥は電線に止まってもしびれないの?
電気には、流そうとする力の強い所から弱い所に流れるという性質(せいしつ)があるんだ。でも、1本の電線なら、力はどこでもほとんど一緒(いっしょ)だよね。だから電気が鳥の体を流れることはないんだ。
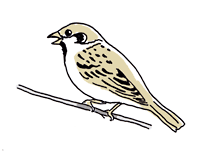
もし、電気を流す力が違(ちが)う2本の電線にまたがって止まったら、どうなると思う?体の中を強い電気が通ったショックで命を落としてしまう。体の中を電気が通ることを感電っていうんだ。同じように、みんなが上げたたこが電線にぶつかると、電圧(でんあつ)の強い電線と弱い地面との間に電気が流れて感電してしまうよ。絶対(ぜったい)しないでね。
太陽の光で電気ができるって本当?
みんなが使っている電気は、火や風などの力で作られているんだけど、いつも空から顔をのぞかせている太陽の光で電気ができたら便利だよね。実は太陽で電気を作る機械があるんだ。それが太陽電池だ。
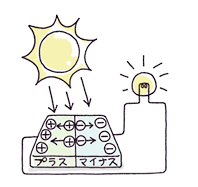
太陽電池の中には、不思議な部品があるんだよ。その部品は太陽の光が当たると、そこでできた電気を、プラスの電気を集める部品とマイナスの電気を集める部品に分けてくれる。電気はマイナスの電気がプラスの方に引き寄(よ)せられれば流れるから、そんな不思議な部品を発明できたんだね。
人間の体に電気が流れているって本当?
本当だよ。みんなの体の中には、いつも弱い電気が流れているんだ。例えば野球をしている時、転がってきたボールを目で見たら、体の中で何が起こると思う? 見たことやしたいことを弱い電気の信号にして、神経(しんけい)が脳(のう)に伝えてるんだ。例えば「ボールが来たぞ」と伝える。そして「ボールを取れ」という脳からの電気信号を神経が手や足の筋肉(きんにく)に伝えれば、ボールが取れるというわけだ。
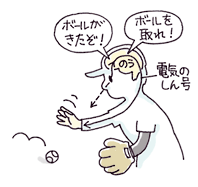
そんな風に体を流れる電気の状態(じょうたい)で、体の具合が分かったりもするんだ。例えば、脳波という脳の電気信号や、心臓(しんぞう)の動きでできる電気信号で心電図という図を描(えが)くことができる。そうした図を見ることで、病気を調べることができるから便利なんだ。
テレビはどうして映(うつ)るの?
毎日楽しい番組を画面に映して見せてくれるテレビって不思議だよね。遠くで撮影(さつえい)した映像(がぞう)が、どうやってみんなのテレビに運ばれてくるんだろう?
昔はアナログ信号を使っていたけど、今では地上デジタル放送(ちじょうデジタルほうそう)やBS/CS デジタル放送という形で、映像や音声をデジタルデータに変換(へんかん)して送るんだ。これによって、もっとクリアできれいな映像を見ることができるようになったんだ。
地上デジタル放送は、テレビ局から送られる電波を、テレビのアンテナで受信(じゅしん)して見るんだよ。画質(がしつ)や音質(おんしつ)がアナログ放送よりもきれいで、たくさんのチャンネルを楽しめるんだ。
BS/CS放送は、人工衛星(じんこうえいせい)を使って放送されているんだよ。地上デジタル放送よりもさらにたくさんのチャンネルがあって、専門的な番組も見られるんだ。
そして、4K や8K といった超高解像度(ちょうこうかいぞうど)放送というのもあるよ。4Kは、地デジの4 倍の解像度(かいぞうど)で、とてもリアルで迫力のある映像を見ることができるよ。8K になると、地デジの16 倍の解像度になるんだよ!
テレビ局では、映像や音声をデジタルデータに変換(へんかん)して、電波や人工衛星に乗せて送信(そうしん)するんだ。みんなのテレビでは、そのデータを受信して、元の映像や音声に戻して番組を映し出すんだよ。
携帯電話(けいたいでんわ)で話ができるのはなぜ?
携帯電話は声を電気の信号に変えて、相手に伝えているんだよ。でも、携帯電話から直接相手に電気信号を飛ばしているわけじゃないんだ。携帯電話の電気信号が届(とど)く範囲(はんい)は、せいぜい2km位。だからまずはその範囲の基地局(きちきょく)に信号を送るんだ。
そこからは、普通(ふつう)の電話と同じように相手に近い基地局へと電話回線やインターネットを介して信号が送られ、またそこから電気信号を飛ばして相手の携帯電話につながるというわけ。
声を電気信号で飛ばすにはアナログ方式とデジタル方式があって、以前はアナログ方式も使われていたけど、今の携帯電話はデジタル方式だけを使っているんだ。デジタル方式では、声を出す時の空気の振動(しんどう)を0 と1 の数字に置き換(か)えて伝える方法で、雑音に強く、天気が悪い時でも相手に正確(せいかく)に声を届けることができるんだ。

声を電気信号で飛ばすにはアナログ方式とデジタル方式があって、携帯電話はデジタル方式。これは声として出た空気の揺(ゆ)れを数字に置き換(か)える方法で、天気が悪い時でも正確(せいかく)に届けられるんだ。
電球はどうやって発明されたの?
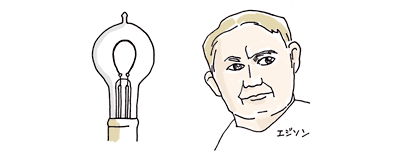
昔は夜の明かりとして油を燃(も)やすランプ、ろうそく、ガス灯などが使われていたけど、あんまり明るくならないよね。そこで登場したのが電気で強い明かりを作る電球。この電球を発明したのは、アメリカの発明王エジソンだよ。
電気を通しにくい物に無理やり電気を流すと、その部分が熱を出して光る。電球はこの仕組みを利用しているんだ。でもこの電気を通しにくい物を見つけるのがとっても大変だった。熱くて焼けちゃったらダメだもんね。エジソンは何千回も実験をして、日本で育った竹が焼けにくく、光るのに一番いいと気付いたんだよ。こうして1879年、ついに電球が完成!できるまで決してあきらめない、強い気持ちが実を結んだんだね。イギリスのスワンという人も電球の研究をしていて、スワンの方が先に発明したという説もあるけど、やがてエジソンとスワンは共同の電球会社を設立(せつりつ)して電球を世の中に広めたんだよ。
電気が流れる物と、流れない物がある
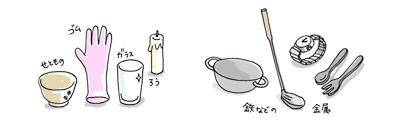
電気をよく通すのは、例えば鉄や銅(どう)などの金属(きんぞく)。通さないのは木、ゴム、ガラスなどだ。電気が流れる、流れないっていうのは、一体何がどう違(ちが)うんだろう。
電気が銅線などの金属に流れるのは、金属が、その中を自由に動き回る自由電子を持っているから。金属の線に電池をつないだとすると、電池には電気を流そうとする力があるから、その力で金属の中の自由電子が一斉(いっせい)に動く。電池のマイナスからプラスの方に動くんだよ。この動きが電気の流れになっているんだ。一方で、木やゴムには自由電子が一つもない。だから電気が流れないんだね。
電気っていったい何?
物体は、原子や分子と言われる小さな粒(つぶ)が組み合わさってできている。原子と原子を結びつけているのが、電子というもっと小さな部品。
絵のように、原子の周りでは、いくつかの電子がぐるぐる回っている。地球のまわりを回る月みたいだね。原子と原子が並(なら)んで分子になると、今度は花の間を飛び回るハチみたいに電子が動き始める。
電子には、分子のまわりをぐるぐる回るだけのものと、自由に飛び回れるものがあるんだ。水などでは、図のように、分子がいっぱいあるだけで、全部が1つにつながっているわけではない。だから水は器の形に合わせて形を変えるんだね。
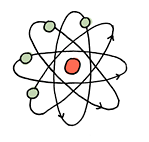
ところが金属(きんぞく)では全部がもっと強くつながっているから硬(かた)い。電子はその中を自由に飛び回ることができるんだ。これを「自由電子」と呼(よ)んでいる。
この自由電子は、普段(ふだん)はバラバラの方向に動いているけど、これが決まった方向に動いて流れができると、それが電気となる。電気って何?って聞かれたら、金属の線の中を飛び回る電子という小さな粒の流れのこと、と答えたらいいだろう。
この流れは自然にできることもある。例えば、ドアを開けようとした時にバチバチッと音がしてびっくりすることがあるでしょう。あれは「静電気」といって、電気の一種。でも、物の一部分だけに起こる、ほんの短い時間のでき事なので、電球を光らせたりするのには使いにくいね。
私達(わたしたち)がいつも使っている電気は、静電気ではなく、動電気。つまりいつも決まった方向に一定に近い強さで流れる電気でないと、使えない。それを生み出すのが発電なんだ。
発電の仕組みを詳(くわ)しく知りたい!
「電気っていったい何?」のページは読んだかな?ここでは、そこで見たような、決まった方向にいつも一定の強さで流れる電気をとりだす方法、つまり発電の仕方を考えていこう。
電気が起きる仕組みは、1831年に、ファラデーというイギリスの学者によって発見された。
図のように、金属(きんぞく)の線をぐるぐる巻(ま)いたものを「コイル」と言う。この中に磁石(じしゃく)を通してやると、その磁力で、金属の線の中で自由電子が決まった向きに流れ始めることが分かった。
磁石の動きを速くすると、それだけ強い流れができて、電気が強くなる。だけど、磁石をすごい速さで何度も動かすのは大変だ。じゃあ、どうすればいいと思う?
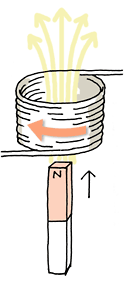
磁石を動かすのではなく、コイルの方を回したらどうだろう? やってみると同じように電気が生まれた! 回す方が簡単(かんたん)だ! いろいろ試して、もっと良い方法はないか? と世界中の人がいつも考えているから人間はいろんな物を作りだすことができるんだね。
今、大きな発電機はほとんど、磁石の中でコイルを回して電気を取り出す方式になっているよ。
例えば、山に行くと見られるダムにある水力発電所。これは川をダムで一度せき止めて、高いところから下に落とし、その勢いでタービンという水車を回して、それでコイルを回しているんだ。火力発電所では、石炭や石油を燃(も)やしてお湯を沸(わ)かし、吹(ふ)き出す蒸気(じょうき)の力でタービンを回している。
もちろん、このごろ山でよく見かける風力発電の大きなプロペラも、その回転がコイルに伝えられて、発電されているんだ。
言ってみれば、コイルを回転させる力があれば、どんなやり方でも発電ができるわけだ。
自分でも発電できますか?
もちろんできる。発電の仕組みのページで見たように、金属(きんぞく)の線をぐるぐる巻いたコイルの回りで、磁石(じしゃく)を回してやると電気が起こるんだから。
考え方は図のような形。磁石をコイルにかぶせて、これをぐるぐる回すんだ。手で回すと電気が起こる。速く回すと強い電気になる。だけどずっと回しておくのは大変だね。
みんなが毎日ぐるぐる回しているものって何かないかな? たとえば、自転車のタイヤとかだね。夜に自転車で走る時、タイヤの回転を利用してライトをつける。あれがちょうどこの発電になっているんだ。
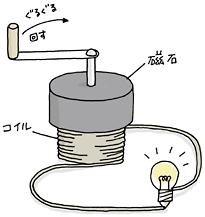
タイヤに発電機のローラーをくっつけると、タイヤの回転がローラーを通してコイルに伝えられる。それで生まれた電気でライトが光るんだね。タイヤにローラーがくっついているから、いつもよりペダルをこぐのが重く感じられる。一生懸命(けんめい)にこぐと、より電気が強くなって、ライトも明るくなる。分かりやすいね! こういう仕組みで発電する小さな装置(そうち)は「ダイナモ」と呼ばれている。
ダイナモを使った発電が身近なところに使われているもう1つの例として、ダイナモ式の懐中電灯(かいちゅうでんとう)がある。これはハンドルをぎゅっぎゅっと何度もにぎると、それで回転が生まれてライトがつく仕組みだ。ずっと明るくしておくには手がくたびれるけど、地震などで電気が止まってしまった時にはとても便利なものだね。
家庭用の風力発電機も売り出されているから、だんだん見かけるようになるだろう。
また、夜店や屋台などでは、自動車のエンジンみたいな機械でコイルを回して発電し、電気をつけたりしているよ。今度お祭りの時に見てみよう。