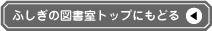サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
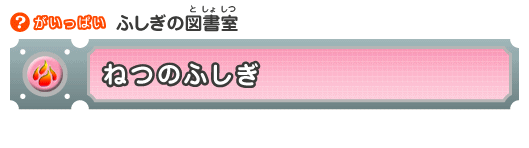
-
熱って何?
-
どうして風邪(かぜ)をひくと熱が出るんだろう?
-
地球の中心はと~っても熱い
-
ろうそくの火とコンロの火、色が違(ちが)うのはどうして?
-
太陽がなければ地球も凍(こお)る?
-
一番熱い温度と一番冷たい温度って何度?
-
火に近付けたら、1円玉と10円玉、どちらが先に熱くなる?
-
どうして熱い日には汗(あせ)が出るの?
-
使い切りのカイロはどうして温かくなるの?
-
空気だって凍(こお)ることがある!
-
どうして食べ物を冷蔵庫(れいぞうこ)に入れるの?
-
お湯に手を入れると「痛(いた)い」と感じるのはなぜ?
-
どうしてマッチは擦(こす)っただけで火が付くの?
-
体温計に42度までしか目盛(も)りがないのはどうして?
-
南極の海はどうして凍(こお)らない?
-
手足がすぐに冷えるのはどうして?
-
ストーブでタンクまで燃(も)えないのはどうして?
熱って何?
熱は分子の運動エネルギーだ。分子っていうのは目では見えない程(ほど)小さな粒(つぶ)で、物体は何でもみんな、この分子や原子が集まってできてるんだよ。分子や原子はいつも動き続けて物体の形を保(たも)っているんだ。その動くエネルギーが熱、という訳(わけ)。分子が動く量によって熱は熱かったり冷たかったりするし、物の形も変わったりするんだよ。
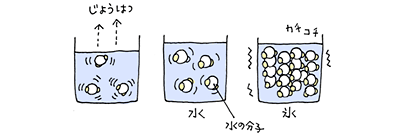
例えば、水。水を作っている分子が、ほとんど動いていなければ氷の状態(じょうたい)。運動を始めると少し温度が高くなって液体(えきたい)の状態の水になる。もっと強く運動をすると、今度は液体じゃいられなくて水蒸気(すいじょうき)になるんだ。
どうして風邪(かぜ)をひくと熱が出るんだろう?
風邪をひくと、頭が痛(いた)くなったりせきが出たり、遊びにも行けないし、嫌(いや)だよね。それに、熱が出て体がだるくなる。でも、どうして風邪をひくと熱が出て体が熱くなるんだろう?
風邪をひくのは、体の中に風邪のウイルスが入ってくるから。ウイルスというのは、小さな小さな生物。生物なのに自分だけでは生きられなくて、動物の体の細胞(さいぼう)に入らないといけないんだ。
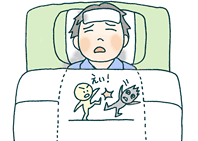
ウイルスが入ってくるとやっつけようとして、体の中の白血球が出動して戦う。この時、熱が出るんだ。風邪のウイルスは温度が高いとあまり動けなくなるんだけど、反対に白血球たちは元気になる。だから体は熱を出して、悪いウイルスをやっつけやすくするってわけ。体の中では白血球たちが、みんなが元気になるように頑(がん)張(ば)ってくれているんだよ。
地球の中心はと~っても熱い
地球のずっとずっと中の方は、何と6000度っていう、すごい熱さなんだ。どうしてそうなったと思う?
大昔の地球は、小さな星同士がたくさんぶつかってできた、ドロドロの熱い塊(かたまり)だった。そのうち重い鉄(てつ)を含(ふく)んだ部分は沈(しず)んでいって、軽い物だけが浮(う)いてきた。地球の熱が冷めてくると、表面が固まって、岩や土の地面ができて、熱いドロドロは地球の中だけに残ったというわけ。
中がそんなに熱いのに、地面はどうして熱くないんだろう? それは、地面の下にはマントルという土や岩のとても分厚(あつ)い壁(かべ)があって、熱を伝えにくくしているからなんだよ。
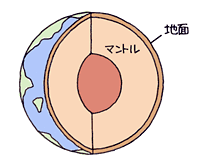
ろうそくの火とコンロの火、色が違(ちが)うのはどうして?
ろうそくの火は赤い色、台所にあるコンロの火は青い色。同じ火なのに、どうして違う色になるんだろう。
それは、火の中に「すす」という炭素の粒(つぶ)がどれだけ交ざっているかで色が違ってくるからだ。ろうそくの火が赤いのは、すすがたくさん交ざっていて、それが高い温度に熱せられてキラキラして見えるから。コンロのようなガスの火にはすすがほとんど交ざってなくて、空気がたくさん入ってよく燃え(も)えているから青く見えるんだ。
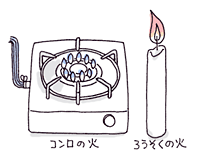
温度を比(くら)べると、ろうそくの火は1000度位なのに、コンロの火は約1700度もある。たき火などの赤い火よりも、見えにくい青白い火の方が温度が高いことが多いから覚えておこうね。
太陽がなければ地球も凍(こお)る?
太陽がなければ地球も凍(こお)る? 太陽はず~っと遠くにあるのに、地球まで温かくしてくれている。もしも太陽がなければ地球は全部凍っちゃうんだよ。太陽の温度はというと、表面の温度が約6000度。太陽の周りにあるガスはコロナといって、何と100万度以上! 人の体温が約36度だから、すごい差だよね。こんなに熱いから、遠い地球まで温かくなるんだね。
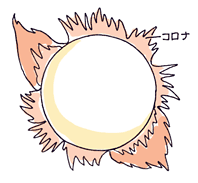
さらに、夏は暑くて冬に寒くなるのは、太陽が地面に当たる時間が違(ちが)うから。日本の場合、冬に太陽が地面を温める時間は夏に比(くら)べて何と約4時間も短いんだって。そういえば、冬はすぐ夜になっちゃうもんね。
一番熱い温度と一番冷たい温度って何度?
一番熱い温度っていうのは、はっきり言って分からないんだ。例えば、太陽の中心はなんと数千万度以上あるとも言われている。とてもとても計りきれないよね。
でも、冷たい温度には限界(げんかい)がある。それは、マイナス273度。絶対零度(ぜったいれいど)と呼(よ)ばれる温度だ。熱っていうのは、いろんな物体を作っている分子という小さな粒(つぶ)が動いているエネルギーのこと。この分子が、完全に動かなくなるとマイナス273度だ。エネルギーがなくなるから、熱もなくなって、もうそれより下げることができない。
火に近付けたら、どちらのお金が先に熱くなる?
さて、問題です。1円玉と10円玉、火に近付けたらどちらが先に熱くなると思う?
A 1円玉
B 10円玉
正解(せいかい)はBの10円玉。物によって、熱の伝わりやすさは全然違(ちが)うんだ。まず、それぞれのお金が何からできているのか調べてみよう。1円玉はアルミニウム、10円玉は銅(どう)でできている。銅はアルミニウムより熱を伝えやすい。熱の伝えやすさのことを熱伝導率(ねつでんどうりつ)というんだけど、銅はアルミと比(くら)べて熱伝導率は約2倍。ということは、約半分の時間で熱くなるというわけだ。
だから、銅のなべやフライパンは、料理に大活躍(だいかつやく)だ。強火にしなくても熱くなるし、火の当たっていない所にも熱が伝わりやすいから、料理がおいしくできるんだよ。
どうして暑い日には汗(あせ)が出るの?
夏って暑い。汗がいっぱい出て、かゆくなったりするね。でもどうして汗なんか出るんだろう? 実は汗には体温を調節してくれるという大切な役目があるんだ。
夏みたいに暑い日には、体温も上がってしまう。風邪(かぜ)をひいて熱が出たときもそうだね。体温が上がると体が辛(つら)く感じる。そんな時、汗は、皮膚(ひふ)に開いた小さな穴(あな)から出てきて、蒸発(じょうはつ)する時に体の熱を奪(うば)っていってくれるんだ。そうして体温を大体36.5度前後に保(たも)ってくれている。夏には1日で5~10リットル(2リットルのペットボトル2~5本分)もの汗が流れることもあるんだって。
つかいきりのカイロはどうして温かくなるの?
寒い冬の味方、カイロ。手でもんだらすぐに温かくなってとっても便利だ。でもどうしてあんなに簡単(かんたん)に温かくすることができるのだろう?つかいきりのカイロはどうして温かくなるの?
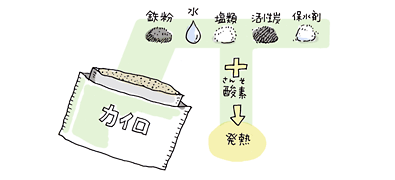
答えはもちろんあの袋(ふくろ)の中。触(さわ)ってみるとさらさらしてる。これは、塩水を染(し)み込(こ)ませた石の粉、鉄の粉、木の粉、活性炭(かっせいたん)などを交ぜた物。その中で熱を出すのは鉄(てつ)の粉。鉄は空気に触(ふ)れるとその中の水分などのためにさびて、その時に酸化熱(さんかねつ)を出す。だから温かくなるんだ。普通(ふつう)なら鉄はゆっくりさびるけど、速くさびるように、石や木の粉などを交ぜている。カイロは小さいけどすごい仕組みになっているんだね。
空気だって凍(こお)ることがある!
例えば水が温度によって、水蒸気(すいじょうき)になったり氷になった りするように、空気も、温度を下げていくと液体(えきたい)や固体になる んだ。水が凍る温度は0度。でも、空気を作っている窒素(ちっそ)や酸素 (さんそ)が凍る温度はもっともっと低いんだよ。
温度は0度より低いとマイナス何度という呼(よ)び方をするんだけど、 空気をどんどん冷やしていって、温度が約マイナス190度以下になると、 わずかに青みをおびた液体になる。さらに温度を下げていくと、マイナス 219度で空気の中の窒素や酸素が凍って固体になるんだ。地球上で一番 低い気温は南極のマイナス88.3度。吸(す)おうとしたら空気が凍って た…、なんてことはないから安心して。
どうして食べ物を冷蔵庫(れいぞうこ)に入れるの?
買い物をして帰ったら、すぐに食べ物を冷蔵庫に入れるよね。肉や卵(たまご)など、温めて食べる物でも入れておくでしょう。どうして食べ物は冷蔵庫に入れておくのかな? もし入れなかったら、どうなるんだろう?
冷蔵庫の役目は、食べ物を冷やして、長持ちさせること。冷蔵庫の中は、食べ物を腐(くさ)らせてしまう悪い細菌(さいきん)が住みにくい温度になっている。冷たくして細菌が増(ふ)えるのを防(ふせ)げば、おいしいままで食べ物を入れておける。もし外に置っ放しにしてしまったら、肉や魚はたちまち腐ってしまうから、注意が必要だ。特に6月、昼が1年で一番長くなる「夏至(げし)」のころには、湿気(しっけ)の多い梅雨(つゆ)でもあり、物が腐りやすくなる。だから夏至の日は「電気冷蔵庫の日」。傷(いた)みが早いから、冷蔵庫の中をよく整理しておきましょう、という日なんだよ。
お湯に手を入れると「痛(いた)い」と感じるのはなぜ?
熱湯に手を入れるとすごく熱い。熱いと感じたらすぐに手を引っこめないと、やけどしてしまう。ところで、皮フが痛いと感じるのはどうしてなんだろう。
人の体には「痛み」を感じるセンサーがあるんだよ。 「痛み」を感じるセンサーは、様々な刺激(しげき)や分泌(ぶんぴ)されるホルモンに反応(はんのう)するんだ。
例えば、熱すぎるものや冷たすぎるものにさわった時。また、熱湯にさわってやけどしかけたり寒いところで凍傷(とうしょう)になりかけたりして、皮フの細胞(さいぼう)が傷(きず)ついた時。そのような時、センサーがそれを「刺激」としてとらえて「痛み」を感じるんだよ。
熱いお湯だけじゃなくて、冷たい氷をずっとさわったりすることも、注意!だよ。
どうしてマッチは擦(こす)っただけで火が付くの?
マッチ棒(ぼう)の頭をマッチ箱の横に擦りつけると、箱の赤リン(せきりん)が少しはがれてマッチの頭に付く。この赤リンが、擦った時に起きる熱、摩擦熱(まさつねつ)で燃(も)え出すと、マッチ棒の頭に交ざった硫黄(いおう)なども燃えて、ボッと火が付くんだよ。
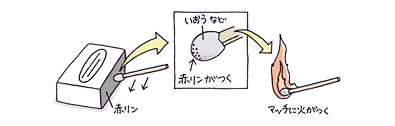
物が燃える温度はそれぞれ違(ちが)う。燃え出す温度を発火点と言って、紙の発火点は450度、木の発火点は400~470度位。マッチに使われている赤リンは発火点がとても低くて260度位。擦った時の温度で、赤リンは十分燃え始めることができる。燃え始めは低い温度だけど、火が付いた瞬間(しゅんかん)のマッチの温度は何と2500度もあるんだ!
体温計に42度までしか目盛(も)りがないのはどうして?
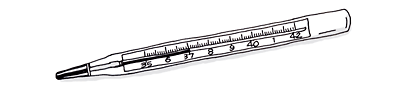
体温計の目盛りって、そういえば42度までだね。どうしてだか分かる?
A・人の体温は42度より上がらないから
B・41度になると熱は自然に下がっていくから
C・42度以上の熱が続くと命の危険があるから
正解(せいかい)はC。人は42度よりも高い熱が出ると命の危険があるんだ。だから体温計には42度以上の目盛りが書いていないんだよ。 以前よく使われていた、測るのに時間はかかるけど正確な実測式の水銀体温計に代わって、今は短時間で測れる予測式の電子体温計を使う人が多いよね。これは温度の変化を感知し予測して体温として表示するしくみだよ。このほか時間をかけて測る実測式電子体温計、水銀に代わる安全な液体金属を使った実測式アナログ体温計、そしてさわらないでもすぐに測れる非接触式体温計など、いろいろあるよ。 体温計の種類や測り方、測る場所によって誤差が出ることもあるから、その時必要な体温計を正しく選んで、正しく測るといいね。
南極の海はどうして凍(こお)らない?
それは海に塩が入っているから。普通(ふつう)の水は0度で凍るけど、塩分を含(ふく)んだ物質(ぶっしつ)は凍りにくくなるという性質(せいしつ)があるんだ。だから、南極の海水は、マイナス20度にならないと凍らない。
それじゃあ、南極の海に浮(う)かんでいる氷山は、どうやってできたんだろう。答は、何十万年も前から降(ふ)り積もった雪。南極の海に浮かぶ氷の山は、雪の塊(かたまり)が大陸から押(お)し出されてできたもので、0度で凍る普通の水でできているんだよ。その氷の厚(あつ)さは、何と平均(へいきん)で2450メートルあるんだって。本当に氷の「山」なんだね。

手足がすぐに冷えるのはどうして?
冬の寒い日、口で温かい息をかけてもなかなか手や指が温かくならないことってあるよね。部屋にいても、足先や手先はすごく冷えてしまう。どうしてだろう。
人の体で、命を保(たも)つためにどうしても必要な部分ってどこだと思う? それは頭(=脳(のう))と心臓(しんぞう)、胃腸(いちょう)などだ。これを温め、元気にしているのは血の流れ。温かい血が送られると温かくなるし、脳や筋肉(きんにく)が生きるためには、血が運んでくる酸素(さんそ)がどうしても必要なんだ。

寒さから生き延(の)びるために長年苦労してきた地球の生き物にとって、寒いというのは一大事。だから人の体も、手足は後回しにしてでも、頭や胴体(どうたい)に血を送り込んで命を守ろうとするんだ。手足の先の方では細い血管(けっかん)が縮(ちぢ)んで、あまり血を流さないようにする。その分、脳や胴体に血が回るんだね。
だから本当は、手足を一生懸命(いっしょうけんめい)カイロで温めようとすると、「あ、手足が温かい。じゃあ手足は大丈夫(だいじょうぶ)だから、もっと血を脳に回そう」とか脳が思って、ますます血が手足に回らなくなるんだよ。
じゃあどうすればいい? そう、逆(ぎゃく)にやってみよう。腹(はら)巻(ま)きをしたりして、腰(こし)やお腹(なか)を温めてみよう。そうすれば脳は、胃腸などの心配をせずに、手足に血を回してくれる。おへそを出していると、手足が冷たくなるって、人の体はほんとにうまくできているね!
ストーブでタンクまで燃(も)えないのはどうして?
灯油のストーブが赤々と燃えていると、目で見るだけでも暖かそうで、冬にはついつい離(はな)れられなくなってしまうね。だけど、タンクにいっぱい灯油が入っているのに、どうしてタンクごと燃えてしまわないんだろうね。
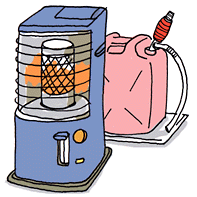
ロウソクだって、上から燃えていく。時計代わりにできるぐらい、時間をかけて静かに燃えていく。火を付けた途端(とたん)に全部燃えちゃうロウソクなんてない。それは芯(しん)の所に火を付けると、その近くのロウが溶(と)けて気体になり、酸素(さんそ)と結び付きやすくなってやっと燃えるからなんだ。上のロウがなくなると、次第に火が下へ降(お)りていって、だんだん溶けて燃え進んでいく。燃えるっていうのは、普通(ふつう)は何かが空気にふれて、酸素と結びつくことなんだ。
灯油のストーブにもちゃんと火を付ける芯がある。タンクから流れてきた灯油は芯にしみ込んで、芯から蒸発(じょうはつ)して気体になる。それで酸素と結びつきやすくなって燃えるんだね。芯とタンクの間の細いパイプのところでは、灯油は灯油のまま。蒸発してたまったりしていないから、酸素と結びつけないので燃えることはないんだ。
灯油をつぎ足す時は、ちゃんと火を消して、タンクを外してから入れようね。火を付けたままでつぎ足すと、こぼれたりして、蒸発して酸素と結びつきやすくなる。パイプでも灯油が少なくなると隙間(すきま)ができて、蒸発した灯油が溜(た)まることになる。とても燃えやすい、危(あぶ)ない状態(じょうたい)になるんだ。「消すと臭(くさ)いにおいがするから」なんて言ってないで、絶対(ぜったい)守ってね。