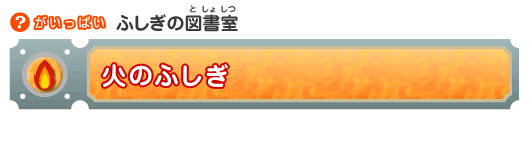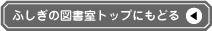サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
そもそも火とは何だろう?
赤く光って、めらめらと燃(も)える火。火のそばに近づくと、熱く感じるね。そもそも、火って何だろう。火は、ものが燃えている時のようすだ。ろうそくやライターの火のように、炎(ほのお)を出しているものを火とよんでいるけど、炭火や電熱線のように、赤くなるだけで炎が出ないものも火だよ。
「燃える」っていうのは、ものから熱と光が出ているようすだ。火が明るく光るのは、燃えているものが高温になっているからだよ。ものはすべて小さな粒子(りゅうし)でできていて、ものが燃えると粒子が振動(しんどう)して熱くなる。その振動は大きくなるほど、温度が高くなるんだ。

枯(か)れ木に火をつけると、火は燃え広がる。木が燃えると熱が出て、木の中にある燃える物質が気体になり、その気体が燃えるとまた大きな炎になるよ。燃え残った粒子は煙(けむり)になり、あとには灰(はい)が残る。灰は、木の中の燃えない物質(ぶっしつ)からできた「燃えかす」ってわけだよ。
ものが燃(も)えるには酸素(さんそ)が必要なの?
なぜ火が燃えるのか、火の正体とは何なのかを、人は長い間つきとめることができなかった。火をつけたろうそくにコップをかぶせると、しばらくすると火が消えてしまう。これは、ろうそくが燃えて、コップの中の空気が少なくなったせいだ。このことから、ものが燃えるには空気が必要だと考えられた。正確(せいかく)にいうと、空気が必要なのではなく、空気の中に含(ふく)まれる酸素が必要なんだ。
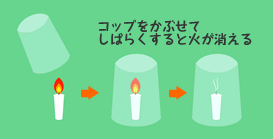
つまり、燃えるというのは、「何かが高い温度で、酸素と結びつくこと」だよ。たとえば木に火を近づけると、木に火が燃え広がるよね。これは、火に近づけると木が熱くなって、燃えやすい気体(つまりガス)が出てくる。その気体が、空中の酸素と結びついて燃えているんだ。だから本当は、木そのものが燃えているのではなく、木から出た気体が燃えているってことだよ。
太陽は燃(も)えているの?
宇宙(うちゅう)には、燃えている星があることを知っているかな。そう、太陽だ。太陽は、熱を出しているガスの球だよ。太陽はほとんどが水素(すいそ)という粒子(りゅうし)でできていて、球の中心では水素が特別な反応(はんのう)を起こしている。この反応は核反応(かくはんのう)とよばれ、すごい熱と光を出しているんだ。
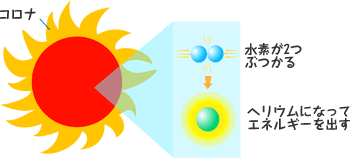
核反応は、酸素(さんそ)が何かと結(むす)びついてものが燃えるのとは、まったく違(ちが)う燃え方をするよ。水素の粒子が激(はげ)しくぶつかってひとつになり、ヘリウムというまったく別の粒子に変身する。この時に、すごいエネルギーを出すんだ。
太陽が核反応を起こして燃えると、大きな炎(ほのお)が立ちのぼる。この炎はコロナといわれていて、コロナは数百万度という、とてつもなく高い温度になっている。だから遠く離(はな)れた地球にも、太陽の熱がしっかり届(とど)けられるんだね。
ろうそくはどうして燃(も)えるのかな?
酸素(さんそ)が燃える気体と結びつくと、火がつくことはわかったかな。では、ろうそくはどうやって燃えるんだと思う?ろうそくは燃えるとだんだん溶(と)けて、小さくなってしまうよね。これは、ろうそくのかたまりが、そのまま燃えているのではないよ。ろうそくから燃えやすい気体が出て、それが空気中の酸素と結びついて燃えているんだ。
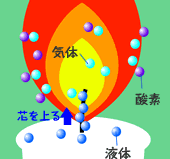
もう少しくわしく説明しよう。ろうそくの芯(しん)に火をつけると、熱によって、火の近くのろうそくが溶けて液体(えきたい)になる。溶けた液体は、ろうそくの芯を伝わって上がっていく。この間に液体は、火に熱せられて気体となり、この気体が空気中の酸素と結びついて燃えるんだ。一度ろうそくの芯に火がつくと、ろうそくの先は高い温度になっているから、ろうそくがどんどん溶けて液体から気体になり続ける。こうして、ろうそくは長い時間、燃え続けるというわけだよ。
炭を燃(も)やしても煙(けむり)や炎(ほのお)は出ないの?
木炭と石炭 炭ってどんなものか、知っているかな。炭は木から作られたもので、昔はよく燃料(ねんりょう)などに使われていたんだよ。木を並(なら)べて、その上に小枝(こえだ)や土をかぶせて火をつけ、むし焼きにすると、黒い炭ができる。木にはもともと、タールという油のような物質(ぶっしつ)や水分などが含(ふく)まれているけれど、むし焼きにすると出ていってしまい、炭になる。木が炭になると、ほとんどが炭素(たんそ)という物質(ぶっしつ)だけになってしまうので、その分だけ、軽くなっているよ。
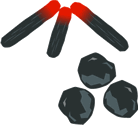
炭素には、数百度という高い温度で燃えるという性質(せいしつ)がある。炭素が酸素(さんそ)と結びつくと、炭全体がまっ赤になって燃える。だけど燃える気体が出ず、めらめらとした炎はほとんど出ないんだ。煙もほとんど出ないから、家の中が煙たくなったり、すすでまっ黒になったりすることがあまりない。そこで昔は、家で煮炊(にた)きものをしたり、部屋を暖(あたた)めたりするのによく使われていたよ。
石炭は、大昔の植物が地中の深くに埋(う)まって炭化したものだ。石油が使われるようになる前は、蒸気機関車(じょうききかんしゃ)やストーブの暖房(だんぼう)などに、よく使われていたんだよ。
火の色によって熱さがちがうの?
ろうそくの炎(ほのお)を、よく見てみよう。炎の部分によって、色や明るさが違(ちが)っているのがわかるはずだよ。ろうそくの炎の中には、炭素(たんそ)の粒子(りゅうし)、つまりすすが含(ふく)まれている。そのすすが熱くなって、明るい光を出しているんだ。
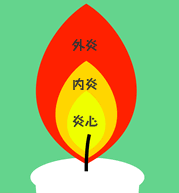
炎の色 芯(しん)に近いところは、炎心(えんしん)という。とけたろうが気体に変わっているところで、温度がもっとも低い。炎心の外側は内炎といって、オレンジ色に光って見えるよ。ここは空気が少ないので、ろうの気体は完全には燃(も)えていない。炎の一番外側は外炎といって、温度がもっとも高いところだ。外炎は空気によくふれているので、酸素(さんそ)とろうの気体が結びついて、完全に燃えているよ。
このように、ろうそくの炎はもちろん、炭火も温度によって色が変わるよ。まっ黒の炭に火をつけると、熱くなるにつれてだんだん赤くなる。500度くらいだと暗い赤色をしていて、900度くらいになると明るい赤色になる。さらに1000度を超(こ)えると、もっと明るい黄色に光るよ。
火が消えるのはなぜ?
火をつけるには、燃(も)える気体と酸素(さんそ)が必要だということはわかったね。その反対に火を消すには、どうしたらいいのかな。ものが燃えないように、熱や酸素、燃えるものを取りのぞくことが必要だ。火を消すには、水をかけることがあるよね。水をかけると、燃えているものが水で冷やされて温度が下がる。そして、燃えているものが、水におおわれて酸素が送られなくなってしまう。こうして、火が消えるんだ。
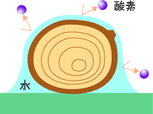
だけど、水をかけるのはよくない時もあるよ。天ぷら油の火に水をかけると、かえって油が飛びちって危険(きけん)だ。また、ガソリンのように激(はげ)しく燃えるものは、水をかけるだけでは追いつかない。そこで使われているのが、消火器だ。消火器の中には、液体炭酸(えきたいたんさん)ガスなどの、燃えない液体や気体が入っている。これをホースから吹(ふ)きかけると、燃えているものをつつみこんでしまう。すると酸素を取りこめなくなって、火が消えるというわけだよ。
火をおこすにはどうしたらいいの?
火おこし 今は、ライターなどを使えば、かんたんに火をつけることができる。だけど大昔は、火をおこすのはとても大変なことだった。昔ながらのやり方で火をおこしてみると、どれだけ難(むずか)しいかわかるよ。木の板に細長い木の棒(ぼう)をあてて、ぐるぐるまわしてこする。こすり続けているとやがて熱くなって、白い煙(けむり)が立ちのぼる。それを消さないように、草や葉っぱをまわりに置いて、少しずつ火をつけていくんだ。これには途方(とほう)もない根気が必要だよ。
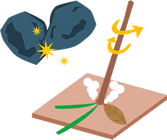
ほかには、火打ち石を使って火をおこす方法もある。火打ち石を両手に持って、カチカチとこするようにたたくと、火花が飛びちって火がつくんだ。この方法は古くから知られていて、720年に完成した歴史書「日本書紀」にも登場するよ。江戸(えど)時代には庶民(しょみん)にも火打ち石は広く伝わって、火をつけるのにはもちろん、厄(やく)よけのおまじないにも石を打っていたそうだ。
人はいつから火を使うようになったの?
火を使う動物は、人しかいない。火の発見が、文明の始まりになったといわれているよ。大昔の人は、山火事や火山の爆発(ばくはつ)で、火を知ったといわれている。始めのうちは、山火事などで自然に発生した火を、木の枝(えだ)に移(うつ)して住みかまで持っていった。そして、火を消さないように、とても大切にしていたんだ。

人が、自分で火をおこす方法を知ったのは、およそ45万年前だと考えられている。これは、あらゆる発見の中でも、特に重要なことだよ。火が必要な時に自分でおこせるようになったおかげで、寒い時にも凍(こご)え死なずに生きのびることができた。動物が襲(おそ)って来た時にも、火を使って追いはらうことができた。そんな火のふしぎな働きを、神様として敬(うやま)い、恐(おそ)れていたんだ。火の神様にまつわる伝説は世界中にあり、火をたいてお祈(いの)りをする火祭りは、古くから今でもあちこちで続いているよ。
昔の人は火をどう利用したのかな?
人が火を使うようになってから、人はほかの動物たちとはまったく違(ちが)う生活をするようになった。火は、暗い夜を明るく照らして、体を暖(あたた)めてくれる。人を動物から守ってくれる。火で食べ物を焼くと、やわらかくて食べやすいことも発見した。ひとつの火が、暖房(だんぼう)になり、照明になり、料理用にもなったんだね。

時代がすすむと、人は食べ物を煮炊(にた)きする土器を発明する。その土器を使ってお湯を沸(わ)かし、獲物(えもの)を煮て食べることを知った。 日本では5世紀後半の古墳(こふん)時代になると、農業とともに料理を作るためのかまどが伝わってきたといわれているよ。
こうして時代がすすむにつれて、それぞれの使い道に応(おう)じて火を使う道具が分かれていったよ。料理をするには、かまどやいろり。暖房と料理用を兼(か)ねて、寒いヨーロッパでは暖炉(だんろ)が作られた。日本では江戸(えど)時代に、炭火で暖まる七輪が広まった。おふろを沸かすのにも、薪(まき)を使って火で沸かしていたよ。
コンロの火はどうしてつくのかな?
今のくらしにも、火は欠かせないものだ。きみの家でも、都市ガスやプロパンガスのコンロで火を使っているよね。都市ガスやプロパンガスのコンロの栓(せん)をひねると、ガスが出てくる。ガスは燃(も)える気体でできていて、その気体が燃えて炎(ほのお)になるんだ。ガスは、石油や天然ガスなどからできているよ。
酸素(さんそ)がたくさんあると、ガスの炎は内側が透(す)き通った水色で、外側が薄(うす)い紫(むらさき)色をしている。だけど酸素が足りなくなると、炎が赤っぽく大きな形になって、ゆらゆらと燃える。この時は、不完全燃焼(ねんしょう)といって有毒なガスを出すので、窓(まど)を開けて空気を入れかえたり、換気扇(かんきせん)をまわしたりして、きれいな空気を取り入れよう。
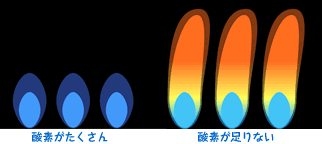
それから、気付いていないかもしれないけど、コンロ以外でも家でガス火を使っているところがあるかもしれないよ。おふろを沸(わ)かすのに、ガスの火を使っているんじゃないかな。ガスを使った暖房器具(だんぼうきぐ)を、知らずに使っているかもしれない。いろいろ探(さが)してみるといいね。
火を使って金属(きんぞく)が作れるの?
金属の取り出し方 鉄や銅(どう)などの金属(きんぞく)は、火を使って作るって知っていたかな。金属は石と違(ちが)って、たたいても壊(こわ)れないし、かたい石でたたくと薄(うす)くのびていろいろな形にできる。鉄や銅などの金属を作るには、原料となる鉱石(こうせき)が必要だ。鉱山などから鉱石をとってきて、炉(ろ)の中で木炭を燃やし続ける。そうして鉱石を溶(と)かし、金属を取り出しているよ。
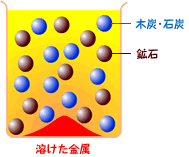
日本では、今から2000年ほど前、金属の作り方が伝わったといわれているよ。ちょうどこの時代は、弥生(やよい)時代の終わりごろで、農業が行われるようになっていた。そこで、鉄でくわや鎌(かま)などを作り、田畑をたがやしたんだね。また、武器(ぶき)や仏像(ぶつぞう)を作るのにも、金属を使ったんだ。
金属は現代(げんだい)のわたしたちのくらしにも、欠かせないものだよ。さまざまな種類の金属をまぜて、それぞれの性質(せいしつ)をいかした合金を作っている。鍋や電気製品(せいひん)など、いろんな製品に用いられているよね。高温になってもとけたり壊れたりしないから、飛行機やロケットにも使われているよ。
火にまつわるものをさがしてみよう!
火がつくものをさがしてみると、いろいろあるよ。キャンプファイアーや、オリンピックの聖火(せいか)など、今でも火はあちこちで使われているね。漁火(いさりび)は、見たことがあるかな。日が暮(く)れた海に、船の上から明かりをともして、集まってくる魚を網(あみ)でとる漁だ。まっ暗な海に、漁火の明かりがともるときれいだよ。
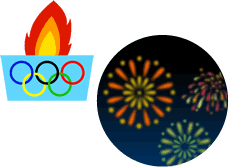
夏になるとよく見かける、打ち上げ花火。それは、花火玉という丸い玉に、火薬で火をつけて花火を打ち上げている。花火玉の中には、爆発(ばくはつ)する火薬や、花のように見せる薬剤(やくざい)などが入っている。それが空高く上がったところで、爆発するようにできているんだ。
たき火は、童謡(どうよう)でも知られているよね。秋になると落ち葉を集めて火をつけて、中でさつまいもを焼いたりしたんだ。今は、火事を防止(ぼうし)するためや、有毒なガスを出さないために、たき火はしないように決めている町も多い。めったに見られなくなったけど、昔は季節を感じる風景だったんだよ。