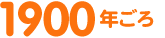
今とはどこが違うか調べてみよう
1900年ごろの「リビングにある家電」は?

日本で初めて、一般(いっぱん)の家に電気が送られるようになったのは、1887年のこと。それから10年くらいたったこの時代でも、家で電気を使っているのはお金持ちなど、ごくわずかの家だけだった。使うといっても、せいぜい電球で明かりをつけるくらい。その電球も今のものとはちがってすぐに切れてしまうものだった。ほかには発売されたばかりの扇風機(せんぷうき)。などもあったけど、どちらもぜいたく品だったんだ。
電気のない暮(く)らしは、どんなだったのかな? まず明かりは、石油を使ったランプが使われていた。すすがつくので、ランプを毎日みがくのが子どもの仕事だったんだ。学校の宿題は暗くなる前にすませてしまったんじゃないかな。テレビなんかはもちろんなかったから、みんなで話をしたり新聞を読んだりするのが一家のたのしみだった。電気がなかったから、そうじや洗濯(せんたく)、食事のしたくにもずいぶん時間がかかり、みんなで話をするような時間はあまりとれなかったんだよ。寒いときは火鉢(ひばち)に炭を入れて手を温め、暑いときはまどを開けて風を通したりうちわであおいだりしていたんだ。
今の時代とくらべると、家電製品(せいひん)だけじゃなくて、そのほかのものも工場でたくさん作ることが少なかった時代。お店に行けば何でも売っているわけではないので、一つ一つ手作りのものを買ってきたり、自分で作ったりしていたんだ。















