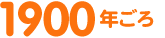
今とはどこが違うか調べてみよう
1900年ごろの「身の回りにある家電」は?
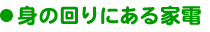
洗濯(せんたく)は洗濯機ではなく、洗濯板とたらいで行なっていた。洗濯板って知っているかな? 板にでこぼこがついていて、洗濯物をそこにこすりつけてよごれを落とすんだ。たらいは水を入れるおけのようなもので、そこに水をためておいて洗濯をしたんだ。
洗濯をする水は、もちろん外の井戸(いど)からくみ上げる。今みたいに水道から自動で出てくるわけけじゃないから、それは大変だったんだ。でも、長屋(今のアパートのようなところ)では、井戸にみんなが集まって話をしながら洗濯をするので、井戸端会議(いどばたかいぎ)と言って、女の人たちのおしゃべりの場にもなっていたんだよ。
たらいは洗濯に使うだけじゃなくて、いろいろな使い方があったよ。夏の暑いとき、たらいに水をくんで庭で水浴びをする行水(ぎょうずい)に使ったり、お風呂に行くかわりに体をふいたり。お風呂がある家は少なかったから、毎日お風呂屋さんへ行くのじゃなく、こうして節約していたんだね。使い終わった水は、まだ砂利道(じゃりみち)だった道にほこりがたたないようにまいたり、庭の木や草花に水やりをしたり、大切に使われていたんだ。















