2024年2月。今年もパナソニック スカラシップ アジアのアルムナイを対象にしたオンラインの交流会が開催されました。
パナソニック スカラシップ アジアには大きく3つの「支援」があります。
「学びの支援」「フィロソフィー研修」、そして「つながり支援」です。
「学びの支援」は留学時に、学業に専念できるように経済的なサポートすること。
「フィロソフィー研修」は創業者 松下幸之助の経営思想を学ぶ研修です。2023年度からスタートした初めての取り組みです。
「つながり支援」は在学中の経済支援に加え、卒業後も卒業生同士の交流の支援です。年代、国を超えて、優秀な人材ネットワークの構築につなげていただくことが大きな目的です。私たちは、留学中の支援に留まらず、アルムナイの皆さまに寄り添い、その後の活躍もしっかりと見続けていきたいと考えています。
これらは他のスカラシップにはない、パナソニック スカラシップ アジア独自の支援です。
今回の交流会は「つながり支援」の一環として年に1回オンラインで開催しています。
今回も日本やアジア諸国のほか、イギリス、オーストラリアなど、世界13カ国から34人が参加しました。皆さんの現職は、通信、IT、人材教育、AI関連企業や、大学や政府の研究機関など、職種も立場も様々。中にはスカラシップを卒業後、数々の国、複数の企業を渡り歩いた方、自分の夢を達成すべく、起業された方もいるなど、活躍の場は益々広がっています。

乾杯のショット。手にはグラス、マグカップ、ペットボトルなど、それぞれの環境と「都合」が見え、これもオンライン交流会ならではの楽しいシーンでした。
その後、参加されている皆さんに、認定年別に登場してもらい、それぞれ近況報告をお願いしました。そこでも皆さまの活躍ぶりを垣間見ることが出来ました。
1998年認定のモウさんは今回参加されたアルムナイの中で最古参。今回が初参加でした。
現在は上海で特許関連の事務所を起業。中国のパナソニック知的財産センターの顧問にも就任しているそうです。
「こちらでは、新人研修も受け入れるなど、今でもパナソニックの皆さまとビジネスで繋がりがあります」
2000年認定のキンさんは、神奈川の大学の医学分野で研究のサポートに就いているそうです。
「私にとってスカラシップの仲間は家族です」というキンさんは、皆さんとシェアしたい松下幸之助の言葉を披露しました。
「『青春とは心の若さである。
信念と希望にあふれ、勇気にみちて
日に新たな活動を続けるかぎり、
青春は永遠にその人のものである。』
私はこの言葉を知ったことで、自分の信念に従い、積極的に生きることを大切にしています」
「私たちは青春のまっただ中」と、伝えていました。
2005年認定のビンさんは、スカラシップを終えたあと、母国のベトナムへ戻ったものの、日本が忘れられず、再び来日。さらに勉強を重ね、現在はスコットランドの大学で、AIの研究に注力しているそうです。
中には自分の目標を目指し、再就職先を模索中というアルムナイもいます。
2012年認定のティファニーさんは、東京大学で学び、その後、イギリス、オーストラリアと移動。しかし、今はよりサスティナビリティの関連事業に就きたいという希望を持っていました。
「今日は先輩の皆さまのお話も参考にしたいです」
その言葉に、事務局の多田さんから、「どうか皆さんとチャットで相談にのってあげてください。この交流会は情報交換だけでなく、転職にも積極的に活用してください」と参加者に呼びかけました。
交流会はそれぞれの業務や、環境、時差もありながら、オンラインとはいえ、これほど多くの方が、一堂に会せたこと、そしてそれぞれの想いを発せられたことは、驚きでもありました。中には、現在所属している会社の送別会を抜け出して参加された方、帰宅途中に屋外で参加された方もいます。
またスカラシップの卒業以来の再会という方々も多く、互いの成長ぶりに歓声と驚きの声も上がっていました。
楽しい時間は本当に短く感じます。全員の近況報告を終えるころには、予定の2時間を優に超え、2時間30分も続き、エンディングへ。
最後に、アルムナイ代表として、マレーシアのムザファルさんに閉会の挨拶をお願いたしました。
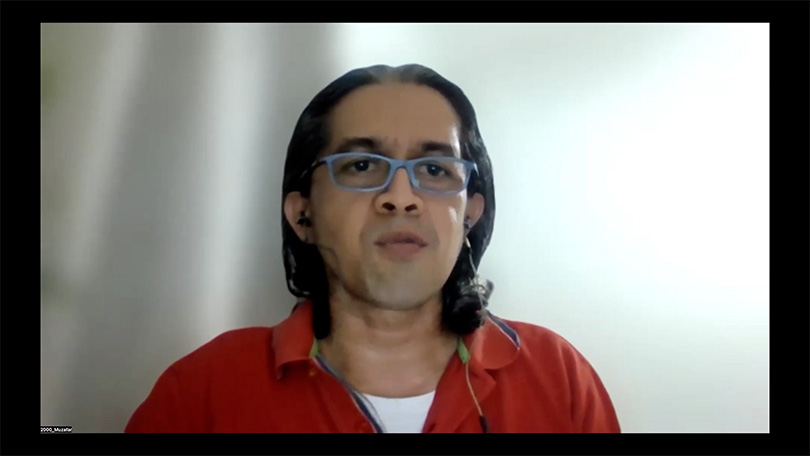
「本日、この時間に、世界中にいる皆さんと過ごし、お会いできたことは、光栄で幸せなことでした。この時間がもう終わると思うと非常に寂しい気持ちになります。
私たちにはできること、実現したいことが無限大にあります。そのために、みんなで力をあわせて、成果を出せるように、今後もこのつながりを大切にしていきましょう。
私たちには、これまでの経験を、社会貢献に活かすという責任があります。
これからも一人ひとりがそのチャレンジをしていきましょう」
この交流会は、これからも開催を続ける予定です。今回参加された方は次回も、そして残念ながら参加出来なかった方は次回こそ、お会いしましょう。

参加者による集合写真。
