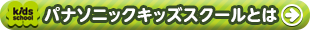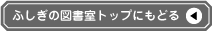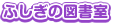

日本では今までどんな地震が起きたの?
日本で記録に残る最も古い地震は、416 年だそうだ。その後も日本では、大きな地震が何度も起きている。古い書物や絵でも、そのようすが描(えが)かれているよ。今までに起きた大きな地震を地図にしてみると、同じようなところで繰り返し起きているものもあれば、そうでないものもある。

よく知られているのが、1923 年(大正12 年)に起きた関東大震災(かんとうだいしんさい)だ。関東地方南部で大きな地震が起きて、14 万人以上もの人が命を落とした。その犠牲者(ぎせいしゃ)の多くは、地震の後に起きた火事が原因(げんいん)だったと言われているよ。東京の下町は、火事で一面の焼け野原になった。このことをきっかけに、地震が起きた9 月1 日を「防災(ぼうさい)の日」と定め、さまざまな防災の取り組みが行われているよ。
1995年には、阪神・淡路大震災(はんしん・あわじだいしんさい)が起こり、震源(しんげん)は淡路島の北の端(はし)で、神戸(こうべ)、芦屋(あしや)、西宮(にしのみや)、淡路島などが大きな被害(ひがい)を受けた。多くの建物がたおれ、高速道路がくずれ、6,400 人以上が亡(な)くなった。
2004年に新潟(にいがた)で中越(ちゅうえつ)地震、そして2011 年には東日本大震災が発生した。この地震は、巨大な津波を引き起こし、大きな被害をもたらしたよ。毎年地震が発生した日が近づくと、ニュースでも取り上げられるから、知っている人も多いかもしれないね。
2016年には、熊本(くまもと)地震が発生した。4 月14 日と16 日にマグニチュード6.5 と7.3 の地震が連続して起こり、熊本県を中心に大きな被害が出た。
最近では、2024 年1 月に石川県の能登(のと)地方を震源(しんげん)とする地震が発生し、多くの建物が倒れ、大規模(だいきぼ)な火災が発生した。