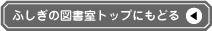サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
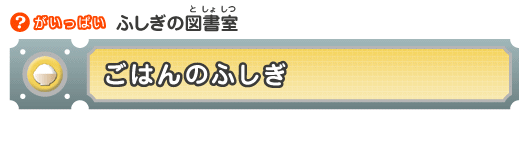
-
日本でお米が作られるようになったのはいつ?
-
ご飯はどうして白いの?
-
1日1食だとどうなる?
-
病気の時、なぜおかゆを食べるの?
-
どうしておかずが必要なの?
-
ご飯を食べると、頭が良くなる?
-
茶色いお米があるってホント?
-
カレーはどうして辛(から)いの?
-
ウンチはなぜ出るの?
-
草を食べる動物と肉を食べる動物の違(ちが)いは?
-
虫歯菌(きん)は甘い物大好き
-
ご飯にはどんな栄養があるの?
-
カルシウムってどんな働きがあるの?
-
お腹(なか)いっぱい食べてもどうしてまたお腹がすくの?
-
日本のお米と外国のお米、どこが違う?
-
おせち料理にはどんな意味があるの?
-
外国には正月料理ってあるの?
-
おもちってどうして膨(ふく)れるの?
日本でお米が作られるようになったのはいつ?
お米は稲(いね)の実から採(と)れた物。最初に生まれた場所は、まだはっきりとは分からないんだけど、今から6000年前、インドのアッサム地方の人たちが、稲の栽培(さいばい)を始めたのが最初だと考えられている。それが、西南アジア、西アジア、アフリカと広まって、中国に伝わったのが5000年程(ほど)前。日本には縄文時代(じょうもんじだい)の終わりに中国から伝わったんだ。
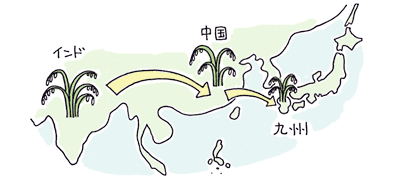
ずっとずっと昔の人たちが暮(く)らしていた縄文時代の終わりごろ、2000年前に海を渡(わた)って日本にやって来たお米。最初にやって来た場所は、今の北九州辺りだと言われている。それまで日本では、アワやヒエといった別の穀物(こくもつ)を食べていたんだって。
ご飯はどうして白いの?
日本人はお米が大好き。でも、お米って昔から真っ白だったの? 実はそうじゃないんだ。白いご飯を食べるようになったのは、お侍(さむらい)さんのいた江戸時代(えどじだい)のなかごろ。それまでは、稲(いね)からもみ殻(がら)を取っただけの茶色い玄米(げんまい)と呼(よ)ばれる状態(じょうたい)の物を煮(に)たり、蒸(む)したりして食べていたんだって。
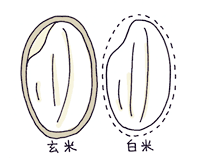
その玄米の周りの茶色い部分を取ると白いお米になる。これを使って水分の少ない固めのおかゆを食べるようになった。つまりそれが“白いご飯”の始まりって訳(わけ)。
それからもっともっと経(た)って、「炊(た)く」という料理方法ができて、今のようなふっくらしたご飯ができたんだよ。
1日1食だとどうなる?
太ることと食事の回数とは、深い関係があるって知ってる? 食べ物は、体を動かすエネルギー。そしてエネルギーが余(あま)ると、脂肪(しぼう)になって体に蓄(たくわ)えられるんだ。これが太る原因(げんいん)なんだね。じゃあ、回数が少ない程(ほど)太らない? 実は逆(ぎゃく)で、1日に食べる量が同じなら、まとめて食べる方が蓄えられる脂肪は増(ふ)えるんだ。
それは、食事を抜(ぬ)くと食事と食事の間が長くなって、体がエネルギーを蓄えようとするから。だから食べた物が脂肪になりやすくなってしまうんだ。太り過(す)ぎると、いろんな病気になりやすいんだよ。だから1日3食食べた方がいいってこと。まずは朝食から、しっかり食べよう!
病気のとき、なぜおかゆを食べるの?
たっぷりの水で炊(た)いたおかゆは、軟(やわ)らかくって胃に優(やさ)しい食べ物。消化吸収(しょうかきゅうしゅう)抜群(ばつぐん)だし、栄養が体全体に届(とど)きやすいんだ。
病気の時は治すためのエネルギーが必要だけど、そのために食べ物をたっぷり食べても、病気で胃が弱っていたら、栄養は吸収されにくいよね。もしかしたら、胃を悪くしちゃうかもしれない。おかゆは、栄養がしっかり取れる上に、弱っている胃をいたわってくれるという、すご~い食べ物なのだ。
どうしておかずが必要なの?
ご飯だけ、パンだけ、お肉だけ毎日食べたい! そんな子いるかな? 日本では、ご飯と一緒(いっしょ)にいろんなおかずを食べるよね。でもどうしてだろう? それはご飯だけだと栄養が偏(かたよ)るから。魚、肉、野菜などと組み合わせることで、栄養のバランスが良くなるんだ。
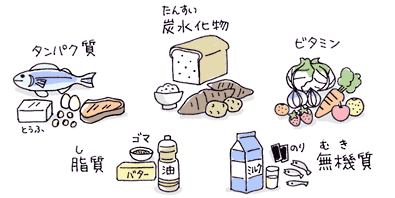
ご飯と一緒に魚、肉、野菜などをバランスよく食べてると、大人になっても健康にいい食生活ができるんだよ。外国では、肉などの脂肪(しぼう)の多い食事を取る人が多いから、大人になって太り過(す)ぎたり病気になりがちになったりする。好き嫌(きら)いをしないで、いろんな物を食べておこう。
ごはんを食べると、頭がよくなる?
脳(のう)を働かせるエネルギーの素(もと)はブドウ糖(とう)。お米に含(ふく)まれているでん粉は、体の中で消化されるとすぐにブドウ糖に変わって脳のエネルギーになってくれるんだ。もし朝ご飯を抜(ぬ)いたら、血液(けつえき)の中のブドウ糖が減(へ)って、考える力が鈍(にぶ)くなったり、集中力が長続きしなくなったりする。脳をしっかり働かせるためには、ご飯が大切なんだね。
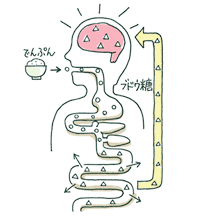
ご飯と一緒(いっしょ)にビタミンB1を取ると、脳の働きがもっと良くなるよ。ビタミンB1は大豆、卵(たまご)などに含まれている。よくかんで食べれば血液の流れが良くなるということも忘(わす)れないでね。
茶色いお米があるってホント?
お米は最初から白いわけじゃないんだ。田んぼからとれた稲(いね)から、外側のもみ殻(がら)を取り除(のぞ)くと、中からお米が出てくるんだ。これは玄米(げんまい)って呼(よ)ばれていて、この玄米からさらに、薄(うす)い皮を取ると白いお米になるってわけ。
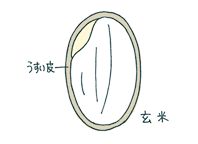
お米の栄養は、薄い皮の部分にもいっぱいある。何と、薄い皮がくっ付いた玄米は、白いお米の3倍も栄養があるんだって! 体を動かすエネルギーの素(もと)になる炭水化物や脂肪(しぼう)、脳(のう)の働きを良くするビタミンB1、細胞(さいぼう)や血管を若(わか)返らせるビタミンEなど、栄養がぎっしり。だから、玄米は、お茶やパンにも使われているんだ。
カレーはどうして辛(から)いの?
みんなが大好きなカレー。カレーの素(もと)になるカレー粉やカレールウは、たくさんのスパイスを混(ま)ぜ合わせて作っているんだ。スパイスっていうのは、植物の実や葉、根をすりつぶした物。色を付けるスパイス、香(かお)りを出すスパイス、辛さを出すスパイスなど、とてもたくさんの種類がある。カレーが辛いのは、辛さを出すスパイスが入っているからなんだね。
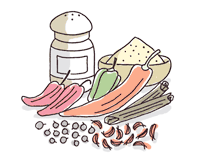
インドやタイなどの暑い国では、カレーを始めいろんな料理にこのスパイスを使っている。スパイスには、食欲(しょくよく)がない時に胃腸(いちょう)の働きを活発にして、おいしく食べられるようにする働きやばい菌(きん)を殺す働きもあるんだって。
ウンチはなぜ出るの?
おいしく食べたごはんやおかず。でも食べるとウンチがでるのはどうしてだろう。体の中では何がおこっているんだろう。
食べものは体を動かすエネルギーのもと。だからみんなのおなかの中の胃(い)や腸(ちょう)は、入ってきた食べものをエネルギーにするために、いろんなはたらきをしているんだ。口から入った食べものは、胃や腸におくられて消化される。消化っていうのは、食べものをくだいたりして、栄養(えいよう)をとりいれやすくすること。とけた食べものの中から栄養が吸収(きゅうしゅう)されるけど、いらないものは外に出る。それがウンチ。つまり食べものを食べると、かならずウンチやおしっこがでるってわけだね。
草を食べる動物と肉を食べる動物の違(ちが)いは?
動物を捕(つか)まえて食べるのは肉食動物、草を食べて生きるのは草食動物だ。肉食動物と草食動物では、体の仕組みが違うって知ってた? 特に歯は、全然違うんだ。それには理由があるんだよ。
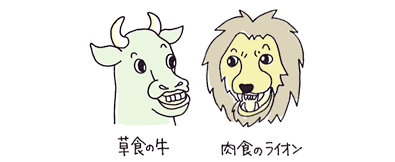
肉食動物の門歯(もんし)や犬歯(けんし)は鋭(するど)い。門歯っていうのは人間でいうと前歯の辺り。犬歯は牙(きば)として、草食動物を倒(たお)すのに役立っている。一方、柔(やわ)らかい草が大好きなシカなどの草食動物には、門歯と呼(よ)ばれる歯がないんだ。ゾウは上の門歯が長~く伸(の)びて象牙(ぞうげ)になっていて、犬歯がない。食べ物の違いで、歯はこんなに違うんだね。
虫歯菌(きん)は甘(あま)い物大好き
甘い物ばかり食べていると虫歯になるのはどうしてだろう。虫歯の原因(げんいん)は、口の中の細菌・虫歯菌(むしばきん)。虫歯菌たちは甘い物が大好きで、食べ物の中の砂糖(さとう)を食べてネバネバした液体(えきたい)を作るんだ。そして、そのネバネバの中にほかの細菌たちと一緒(いっしょ)に住みついてどんどん増(ふ)えてしまう。
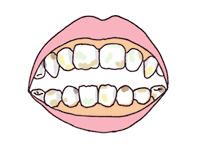
この、たくさんの細菌が住みついたネバネバが、歯を溶(と)かして虫歯になる。だから、ケーキやチョコレート、キャンディーみたいに、砂糖がいっぱいの甘い食べ物は虫歯になりやすいんだ。歯を強くする食べ物は、牛乳(ぎゅうにゅう)、小魚、チーズなど。しっかり食べて虫歯菌を倒(たお)してしまおう。もちろん歯磨(はみが)きも大切だよ。
ご飯にはどんな栄養があるの?
ご飯やおすし、おにぎりには、炭水化物、脂肪(しぼう)と呼(よ)ばれる栄養がたくさん入っている。炭水化物や脂肪は、体を動かすエネルギーの素(もと)や体温を作る熱などになる。みんなの体の体温をいつも同じに保(たも)って、元気よく動き回れるようにしてくれる、大切な栄養なんだ。
お米のほかにも、体を動かすエネルギーの素や、体温を作る熱になる食べ物はいろいろある。例えばうどんやラーメン、パンやスパゲティの素になる小麦、さつまいもやじゃがいも、それに、クッキーやキャンディなど砂糖(さとう)の入った物にも、同じような働きがあるんだって。
カルシウムってどんな働きがあるの?
カルシウムは、タンパク質(しつ)という栄養と一緒(いっしょ)になって、骨(ほね)と歯を作っている。それに、体を健康に保(たも)つ大切な働きをしているんだ。カルシウムは、血液(けつえき)や細胞(さいぼう)の中にいつも同じ量だけ溶(と)け込(こ)んでいる。もしカルシウムが足りなくなると、骨からカルシウムが溶け出してしまうから、骨が弱ってしまうんだ。だから、カルシウムはたっぷり取らなくちゃいけないんだね。

カルシウムが多く入っている食べ物は、牛乳(ぎゅうにゅう)、チーズ、ヨーグルト、わかめ、のり、ひじきなどの海藻(かいそう)、それに小魚。強くて丈夫(じょうぶ)な骨や歯を作ってくれるよ。
お腹(なか)いっぱい食べてもどうしてまたお腹がすくの?
お腹いっぱい食べてもまたお腹がすくのは、脳(のう)のなかに胃や血液(けつえき)の情報(じょうほう)を読み取る部分、空腹中枢(くうふくちゅうすう)があるからなんだ。食べた物はまず胃に入る。胃に入った食べ物は、消化されてこんどは小腸(しょうちょう)に運ばれるんだ。胃のなかに食べ物が入っている時間は、食べ物の種類によって違(ちが)う。ご飯やパンが1番早くて、2番目が肉や魚。食事をした後、2~3時間すると食べた物のほとんどが胃から出ていくんだって。
血液の中の糖分(とうぶん)が減(へ)っても、お腹がすいたと感じる。空腹中枢は、糖分などを情報として読み取っているんだよ。
日本のお米と外国のお米、どこが違(ちが)う?
土があるのにお米が作られていないのは、何と南極だけ。世界で作られているお米には、大きく分けるとジャポニカ種とインディカ種がある。ジャポニカ種とインディカ種では、葉の形や米の形のほかに、ご飯になった時にも違いがあるんだ。
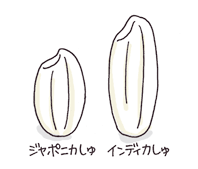
ジャポニカ種は、米の粒(つぶ)が短くて、ご飯になるとお互(たが)いがくっ付きやすく、粘(ねば)りが出て軟(やわ)らかい。日本や朝鮮半島で作られている。そして、インディカ種は、米の粒が長くて、お互いがくっ付かずパサパサしている物が多い。インドなどの暑い国で作られている。
おせち料理にはどんな意味があるの?
「おせち」っていうのは「お節句(せっく)」が短くなったもの。5月5日の子どもの日のことを「端午(たんご)の節句」とも言うけど、あの節句だ。節句とは、神様と人が一緒(いっしょ)に食べる、という意味。田畑で取れた物を神様にお供(そな)えしたことから始まったんだ。こうした節句は1年に5回もあって、おせち料理って最初はお正月だけのことじゃなかったんだね。
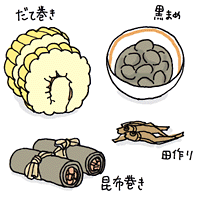
おせち料理ができてきたのは江戸時代(えどじだい)。神様にお供えするだけじゃなく、いつも料理している人が正月三が日ぐらい休めるように、という優(やさ)しい意味もあって、それで年末に作ってお重に入れるようになったんだね。たくさんの神様や縁起(えんぎ)の良さを大切にしてきた日本人。おせち料理の一つ一つにもちゃんと意味があるんだよ。
● こぶ巻(ま)きは「喜ぶ」に通じるから“こぶ”巻きっていうんだ。
● みんなが大好きな栗(くり)きんとんは、お金が集まりますように、という意味なんだ。
● 黒豆は、マメに(こつこつと)働くことができるように、という意味があるんだ。
● 数の子は、たくさんの魚の卵(たまご)が集まったものだから、子孫がたくさんできて栄えるように、という意味を持っているんだよ。
● 田作りはカタクチイワシって魚を干(ほ)して作るけど、昔カタクチイワシは田んぼの肥料(ひりょう)として使われていたから、豊作(ほうさく)を祈(いの)っておせち料理の一つにしたんだ。
● 田作りは「ごまめ」とも呼(よ)ぶんだけど、「五万米」と当て字をして、縁起を担(かつ)いだんだよ。
● えびは、腰(こし)が曲がるまで仲良く暮らす、長寿(ちょうじゅ)の願いが込(こ)められているんだ。
● かまぼこやなますは紅白にして、これも縁起がいいようにという意味があるんだ。
なんかダジャレみたいなのもあるけど、家族が1年間、元気で幸せに暮(く)らせるように、いろいろと考えたんだね。
外国には正月料理ってあるの?
ある国とない国がある。
イギリスやフランスなどのヨーロッパと、アメリカなどの国ではキリスト教が信じられている。キリスト教では、イエス=キリストが生まれた日、つまりクリスマスがとても大切なんだ。だからクリスマスには七面鳥やケーキなどのごちそうを食べて盛大(せいだい)に祝う。その後すぐのお正月には、騒(さわ)いだ後のお休みみたいに、静かに過(す)ごすことが多いようだね。
キリスト教の国とは違(ちが)い、アフリカやアジア、南アメリカなどの国では、日本と同じように田畑を耕(たがや)して食べ物を育ててきた人が多かった。食べ物を育ててくれるいろいろな神様に祈(いの)る気持ちが強かったんだね。そういう国では昔からの料理を食べてお正月を祝うところが多いようだ。
例えば...
フィリピンでは、お正月にはココナッツ風味のおもちを食べます。日本みたいに焼かないで、おなべで煮(に)て食べるんだ。最初、おもちはなべの底に沈(しず)むんだけど、煮えると浮(う)き上がってくる。だから縁起(えんぎ)がいいと考えられたんだね。
韓国(かんこく)のお正月のごちそうは「マンドゥク」。刻(きざ)んだキムチと肉に豆腐(とうふ)、もやしを混(ま)ぜたギョウサのようなのをスープで煮て食べるんだ。ぴりっと辛(から)くておいしそう!
台湾(たいわん)では、日本と同じように、普段(ふだん)離(はな)れている家族も集まって、にぎやかにごちそうを食べます。でも、お正月というより、大みそかの方が大切なんだって。
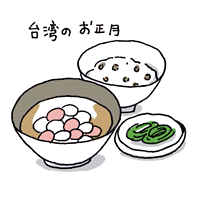
食べるのは、ほうれん草をゆでた長年菜(ツァンニェンツァイ)。その名の通り、長寿(ちょうじゅ)を祈り、包丁(ほうちょう)で切らずに長いまま口に運びます。紅白湯圓(ホンパイタンユェン)は甘(あま)いお吸(す)い物。紅白の白玉が入ってとてもおめでたい感じです。もう1つ、ヌォミィーティェンツォという、もち米のおかゆに果物を入れたものの3品を、仏様(ほとけさま)にお供(そな)えしてから食べるのです。
シンガポールやタイなど、アジアには「旧正月」という、今のお正月とは別の日にお祝いをする国が多い。そんな昔の風習を守るところに、先祖(せんぞ)を大切にする気持ちが表れているね。
南米ペルーでは、1月6日に3人の人が星を探しに行って、星を見つけた時に神様が生まれたとされます。だからお正月には、小麦粉や牛乳(ぎゅうにゅう)、卵、鳥の胸肉(むねにく)を入れて焼いたごちそう「トールタ・デ・フランゴ」を食べて朝まで祝います。1月6日には子どもたちはお小遣(づか)いをもらえるんだって。日本のお年玉と似(に)てる?
ちょっと変わった所では...
ケニアでは牛肉が安くて鶏(にわとり)が高いので、クリスマスにもお正月にも高い方の鶏を食べるんだって。
ロシアもお正月を盛大に祝う国。シベリア風の水ギョウザ「ペリメニ」をたくさん作って楽しみます。家族でギョウザを作るって日本でもよく行われてきたことだね。
ヨーロッパのチェコでは、クリスマスの方が大切であまりお正月を祝ったりしないけど、鳥肉は食べちゃいけないことになってる。幸せに羽根がはえて逃(に)げちゃう、っていうことみたい。
日本だけでも地方や町、家によって、いろいろ違う料理や祝い方がある。お雑煮(ぞうに)の作り方なんて何種類あるか分からないぐらい! あなたが毎年、普通のように食べている物も、友達に聞いてみると、珍(めずら)しい物かもしれないよ。
おもちってどうして膨(ふく)れるの?
おもちも、「力持ち」や「お金持ち」に通じるということや、よく粘(ねば)ることなど、いろいろな意味でお正月にぴったり。暮(く)れにおもちをついてお正月に食べる習慣(しゅうかん)は、平安時代に始まったというから1000年以上も前から行われているんだよ。
うまく焼けたおもちはおいしいね! 消化もいいから、ごちそうで疲(つか)れた胃や腸(ちょう)にも優(やさ)しい。でもどうしておもちは焼くと膨らむんだろう。
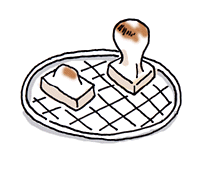
おもちというのは作る時、洗ったもち米を蒸(む)し器に入れて、お湯いっぱいのなべにかけて蒸し上げます。それを杵(きね)でつくと粘りが出ておもちのでき上がり。こういう作り方だから、おもちの中には水分がいっぱい入っている。
焼くと、もちの中の水分が熱せられて水蒸気(すいじょうき)になる。水が水蒸気になると、体積が大きくなるんだって。水蒸気はおもちの外に出ようとするけど、もちの表面は粘って水蒸気を外に逃(に)がさない。それでおもちは膨れてくるというわけ。
きな粉とかあんことか、いろいろ食べ方を工夫しておもちをいっぱい食べたいね。