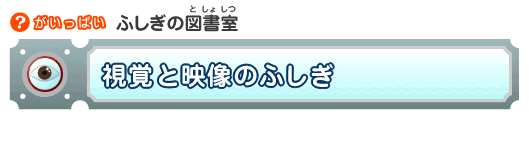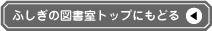サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
どうして物が見えるのかな?
目を使って、わたしたちは物を見ている。これは、どういうしくみで見えるのかな。目は丸いボールのような形をしていて、中には水晶体(すいしょうたい)というレンズがある。目に光が入ると、光は水晶体を通って進み、網膜(もうまく)の上で像(ぞう)を作るよ。これを視神経(ししんけい)が感じ取って、脳(のう)に伝えることで、わたしたちは「見える」とわかるんだ。
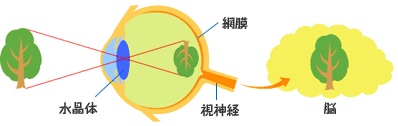
網膜に像をうつす時、実は上下がさかさまになっている。ところが脳に伝わると、うまくそれを正しい向きに読みとっているため、正しい向きに見えるんだよ。また、はっきりと見えるように、水晶体は厚(あつ)くなったり薄(うす)くなったりして、焦点(しょうてん)を合わせている。水晶体を通った光が網膜にうまく集まらないと、ぼんやりと見えてしまうからだ。こんなことが自動的にできるって、すごいよね。
光と影(かげ)ってふしぎだね
光は、まっすぐに進む性質(せいしつ)がある。光の一部をさえぎると、光が進んでいくところと、じゃまされて光が届(とど)かないところができる。光が届かずに黒くなったところ、それが影(かげ)だよ。
光と影は、わたしたちにふしぎな現象(げんしょう)を見せてくれるよ。そのひとつに、日食というものがある。日食は、宇宙(うちゅう)にできる大きな影だ。太陽と地球の間に月があって、太陽の光をさえぎるから、太陽が欠けたように見えるわけだね。
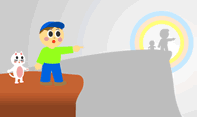
それから、「ブロッケンの妖怪(ようかい)」って知っているかな。高い山に登ると、雲に人のようなものが見えることがある。これは太陽が低いところにあって、背中(せなか)から光があたると、登山者の影が雲にうつって見えるからなんだ。影のまわりに、色つきの輪(わ)があらわれることもある。このふしぎな光と影は、ドイツのブロッケン山でよく見られるよ。
影を使って、いろんな遊びや実験(じっけん)ができるよ。用意するのは、照明(しょうめい)スタンド。白い壁(かべ)などに手をうつして、スタンドに、手やボールなどを近づけたり、遠ざけたりしてみよう。影の輪郭(りんかく)がはっきり見えたり、ぼやけたりするはずだよ。白熱電灯(はくねつでんとう)や蛍光灯(けいこうとう)など光るものを変えても、輪郭のできかたが違(ちが)ってくるだろう。薄(うす)くぼやけた影は、完全にさえぎられずに光の一部が届いているから、ぼんやりと見えるんだ。
目がかんちがいするってどういうこと?
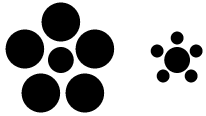
左の図形を見てみよう。まん中にある円は、どちらが大きいと思う?ちがう大きさに見えるかもしれないけど、実は同じ大きさだよ。こうした目のかんちがいは、錯視(さくし)とよばれている。目で見た物は、脳(のう)で理解(りかい)するから、脳のかんちがいと言ってもいいかもしれないね。まわりにある円の大きさがちがうから、脳がまちがえてしまうんだ。
次は、下の2本並(なら)んだ線を見てごらん。ゆがんで見えるかもしれないけれど、実はどちらもまっすぐな平行線なんだよ。2本の平行線にななめの線が入ると、その影響(えいきょう)を受けてゆがんで見えてしまうんだ。おもしろいね。
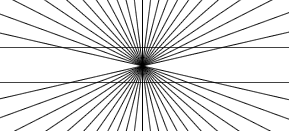
もうひとつ、実験をしてみよう。まず、新聞紙や雑誌(ざっし)を丸めて、筒(つつ)を作る。そして片目(かため)を閉(と)じて、あいている目で筒をのぞいてみる。そして閉じている目の前に、少し離(はな)して手のひらを出してみよう。そして閉じている目を開くと、あらふしぎ!手に穴(あな)があいて見えるよ。
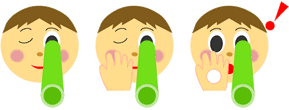
人は、両目で見たものを、脳の中でひとつに合成している。筒を使った実験では、右目と左目でまったくちがうものを見ているから、ひとつに合成した時に画像(がぞう)が重なって見えたってわけだね。
どうして鏡に物がうつるのかな?
鏡って、どうして物をうつすことができるんだろう。鏡にはガラスの表面に、銀(ぎん)やすずなど銀色の金属(きんぞく)が塗(ぬ)られているよ。銀色は、光をよくはねかえす色だ。光をはねかえす、つまり反射(はんしゃ)することによって、物をうつして見ることができるんだ。鏡にうつっている自分は、こちらからの光がいったん鏡にぶつかって、もどってきたものだよ。
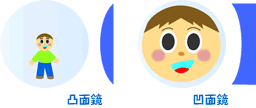
まっすぐ平らな鏡は、ゆがめずに物をうつすことができる。いっぽう、外側にふくらんだ凸面鏡(とつめんきょう)や、内側にへこんだ凹面鏡(おうめんきょう)というかわったものもあるよ。凸面鏡は広い景色(けしき)をうつすので、車のミラーによく使われる。曲がり道に立っている、カーブミラーも凸面鏡だ。凹面鏡は反射した光を内側に集めるため、近くの物を大きくうつすことができるよ。
鏡を使うとこんなこともできるよ!
鏡を反射(はんしゃ)させると、いろんなことができるのでいくつか紹介するよ。太陽の光をはねかえらせて、リレーをしてみよう。まず、太陽のあたるところに鏡をおいて、その光をはねかえす。さらに、その光の道に別の鏡を置くと、太陽のあたらない場所へ光をあてることができるよ。
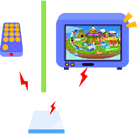
鏡を使うと、見えないところからテレビのリモコンをつけることだってできるよ。鏡の中に、テレビが見えるようにうつして、鏡に向かってスイッチを押(お)してみよう。リモコンからは、赤外線という目に見えない光線を出している。目に見えない光線も鏡ははねかえすから、テレビをつけることができるんだ。
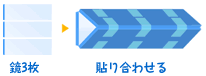
3枚の鏡を使うと、きれいな万華鏡(まんげきょう)を作ることができる。同じ大きさの鏡を貼(は)り合わせて3角すいを作り、いろんなものをのぞいてみよう。3枚の鏡にうつった像(ぞう)が、それぞれ別の鏡にうつし出され、その像がまた別の鏡に反射する。そうして像がいくつも反射して、たくさんの像がうつって見えるよ。
レンズを通して見てみよう!
コップの水をすかして物を見ると、ゆがんで見えたり、さかさまに見えたりするよね。これはコップの水がレンズのはたらきをして、光線を曲げているからなんだ。望遠鏡(ぼうえんきょう)など、物を見る道具にはレンズがついている。レンズには凸(とつ)レンズと凹(おう)レンズがあり、どちらも光の向きを変えるはたらきをしているよ。
凸レンズはまん中がふくらんだ形をしていて、光を通すと内側に折れ曲がる性質(せいしつ)がある。凸レンズを近づけて見ると、物が大きくうつって見えるよ。脳(のう)は目に入った光線が折(お)れ曲(ま)がってるとはわからず、まっすぐきていると思いこむ。それで実際(じっさい)よりも大きい姿(すがた)に見えるんだ。
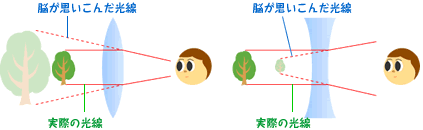
凹レンズは、まん中がへこんだ形をしている。凹レンズを通すと、光は外側へ折れ曲がり、光は広がるように進む。すると目は広がった光線を見て、実際の物よりも小さくうつって見える。光が折れ曲がっているせいで、脳がかんちがいしてしまうんだね。
メガネをかけるとよく見えるのはなぜ?
物を見る時、目の中にある水晶体(すいしょうたい)は自動的に厚(あつ)くなったり薄(うす)くなったりして、光をうまく網膜(もうまく)に集めている。ところが近視(きんし)や遠視(えんし)になると、うまく網膜に集めることができなくなってしまうんだ。これではぼやけて見えてしまうから、メガネをかける。メガネのレンズは、目に入る光の道すじを変えて、光がうまく網膜に集まるのを助けてくれるよ。
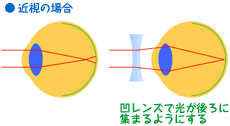
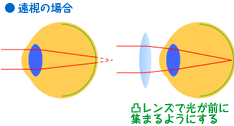
近視になると、近くの物は見えるけれど、遠くの物がぼやけてしまう。近視は網膜よりも手前のところで、光が集まっている状態(じょうたい)だ。そこで、近視の目には凹レンズのメガネを使う。すると凹レンズが光を後ろに集めるので、うまく網膜にうつるようになるんだ。
遠視になると、遠くの物はよく見えるのに、近くの物が見えにくくなる。遠視では網膜より後ろに、光が集まっているためだ。そこで凸レンズのメガネを使って見ると、前に光を集めて網膜にうつしてくれる。きれいに網膜に像(ぞう)がうつると、はっきり物が見えるようになるよ。
小さな物を大きく見るにはどうする?
小さな物を拡大(かくだい)して見る道具が、顕微鏡(けんびきょう)だ。顕微鏡で見ると、細胞(さいぼう)やアメーバなど、目に見えない物も見ることができるよ。
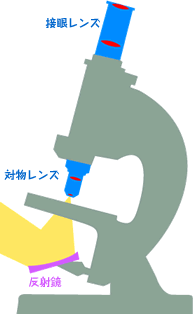
顕微鏡には、対物(たいぶつ)レンズと接眼(せつがん)レンズという2つの凸(とつ)レンズが使われているよ。まず、対物レンズのそばに見たい物を置(お)いて、拡大した像(ぞう)を作る。この像を、接眼レンズを通して見ると、さらに大きく見えるしくみだ。顕微鏡の下からは、外からの光を取り入れる反射鏡(はんしゃきょう)がついていて、明るく照(て)らしているよ。
学校などでよく使われる顕微鏡は、光学顕微鏡とよばれていて、物を2,000倍まで拡大して見ることができる。これより、もっと拡大して見ることができるのが、電子顕微鏡だよ。電子顕微鏡は、光のかわりに電子線を使って拡大している。電子顕微鏡を使うと、なんと100万倍まで拡大することができるよ。
遠くの物を近くに見るにはどうする?
遠くにある物を、近くではっきり見るための道具が、望遠鏡(ぼうえんきょう)だ。望遠鏡は、対物(たいぶつ)レンズと接眼(せつがん)レンズの2つのレンズを使って、遠くにある物を拡大して見ている。顕微鏡としくみがよく似(に)ているね。
望遠鏡には大きく分けて、屈折(くっせつ)望遠鏡と、反射(はんしゃ)望遠鏡の2種類があるよ。屈折望遠鏡では、筒(つつ)の先に取りつけられた対物レンズで、遠くにあるものの像(ぞう)を作る。さらに近くなった像を、接眼レンズで拡大して見るというしくみだ。反射望遠鏡は、凹(おう)面になった大きな反射鏡(はんしゃきょう)を使って像を作り、それを接眼レンズで拡大して見る。反射鏡を使うと光をたくさん集めることができるから、より遠いものを見ることができるんだよ。
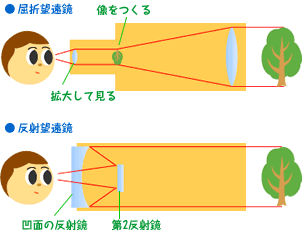
遠くを見るものには、双眼鏡(そうがんきょう)もあるよね。双眼鏡は、2つの望遠鏡を組み合わせて、両方の目で遠くを見ることができる。左右の望遠鏡にはそれぞれ、対物レンズと接眼レンズがつけられているよ。両方の目を使うことで、立体的に見ることができるのが特徴だ。
カメラのしくみはどうなっているの?
けしきや人をうつすカメラは、どんなしくみになっているのかな。一眼(いちがん)レフカメラで見てみよう。一眼レフカメラは、フィルムに画像(がぞう)を焼きつける機械だ。レンズとフィルムの間には鏡(かがみ)があって、ファインダーから画像が見える。レンズを使ってピントを合わせ、シャッターを切ると鏡が上がって、光がフィルムに焼きつけられるしくみだ。フィルムを現像(げんぞう)すると、写真ができるよ。
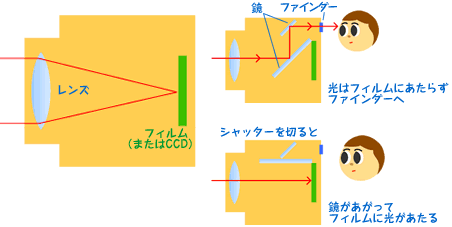
このごろは、デジタルカメラを使う人が多くなったね。デジタルカメラは、フィルムを使わず、画像をデジタルデータにするカメラだ。光を感知するCCDとよばれるものが入っていて、レンズからの画像を受けると信号に変えて、画像データとして記録(きろく)する。画像のデータはパソコンに取りこむができる。もちろんプリンターを使ったり、写真屋さんにデータを持ちこんだりして、写真プリントにすることもできるよ。
体の中を見るカメラがあるってほんと?
体の中など、目で見えないものを見るカメラがあるって知っているかな。身体検査(しんたいけんさ)で、レントゲン写真をとったことがあるよね。レントゲンは、X線を使って体の中を撮影(さつえい)する機械(きかい)だ。X線を発生させるX線管とフィルムの間に人が立って、X線をあてる。すると内臓(ないぞう)によってX線の吸収(きゅうしゅう)ぐあいが違(ちが)うため、フィルムに白黒の像(ぞう)になってうつるんだ。X線のほかにも、磁気(じき)を利用したMRIは、体を輪(わ)切りにした状態(じょうたい)で撮影(さつえい)することができるよ。
体の中をもっとはっきり見るためには、内視鏡(ないしきょう)が使われるよ。これは、光ファイバーケーブルの入った細いくだを、のどなどから体の中へ入れて、体の中を見る機械だ。くだの中には、照明(しょうめい)ケーブルや画像ケーブルなどが入っている。そして、照明ケーブルが体の中を照(て)らし、ケーブルから中のようすが画像で送られるしくみだ。接眼(せつがん)レンズやモニターを通して見ると、体の中がきれいにうつって見えるよ。
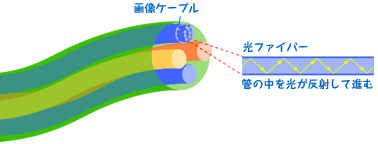
映画のカメラってどういうもの?
映写機(えいしゃき)はフィルムの像(ぞう)をレンズによって拡大(かくだい)し、大きなスクリーンに映画をうつし出す機械(きかい)だ。1コマごとにシャッターを切りながら、1秒(びょう)間にたくさんのフィルムを送る。するとパラパラまんがみたいに、連続して動く画像として見ることができるよ。
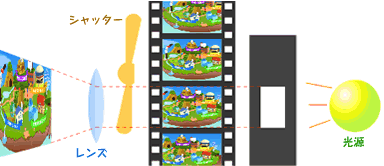
これは画像を速(はや)く送ると、目と脳(のう)が速さについていけなくて、前の画像が頭に残ったまま次の画像を見てしまうからだ。すると、画像はまとまったつながりに見える。自然に動いて見えるには、1秒間に16枚(まい)以上の画像を送ることが必要だ。映画のフィルムではふつう、1秒間に24枚の速さでフィルムを送っているよ。
映写機は、フィルムのサイズによって、8ミリ、16ミリ、35ミリ、70ミリの種類がある。16ミリ映写機は、持ち運びやすいので学校などでよく使われる機械だ。映画館では、35ミリの映写機がよく使われているよ。
テレビとビデオのカメラって似(に)ている?
テレビカメラは、映画としくみが似(に)ている。毎秒(まいびょう)30コマの画像(がぞう)を、次々と連続でうつしているよ。カラーの画面を作るには、1つの画像のために、赤と緑と青の3枚の画像を作っている。赤・緑・青の3色は、「光の3原色」とよばれている。この3つの色を組み合わせることで、さまざまな色を作り出すことができるんだ。
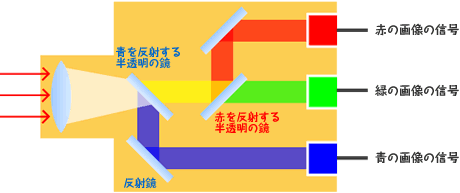
これからは、デジタルテレビの時代だ。テレビカメラには、光を感知するCCDとよばれるものが入っている。デジタルカメラに入っているものと、同じようなものだ。画像はデジタル変換器(へんかんき)で、デジタル信号に変換される。今までより、画質がぐんときれいなのが特徴だね。
手軽な大きさのビデオカメラは、お父さんが運動会の撮影(さつえい)をするなど、家庭でよく使っているね。ビデオカメラにも、光を電気信号に変えるCCDを内蔵(ないぞう)し、それを磁気(じき)の強弱としてビデオテープに記録(きろく)している。最近ではビデオも、デジタルの物が増(ふ)えているね。デジタルビデオカメラは、DVDなどに保存(ほぞん)できるよ。