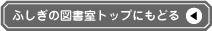サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
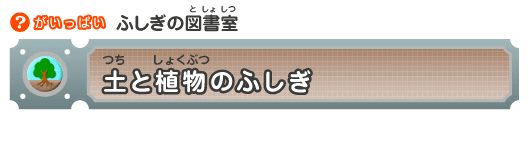
土はどうやってできたの?
私(わたし)たちがすむ地球の表面は、土でおおわれている。土は植物を育て、動物のすみかにもなっている。だけど土はいつ、どうやってできたんだろう。
地球ができたばかりのころ、地球は熱くどろどろにとけたマグマのかたまりだった。それが長い時間をかけて冷えたものが、岩石だ。岩石は太陽の光や熱を受け、風や雨によって細かくくだけて、砂(すな)になる。ねばり気のある性質(せいしつ)にかわって、粘土(ねんど)になったものもある。
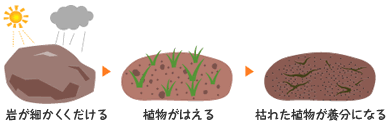
やがて地球に、植物の祖先(そせん)が生まれた。植物は枯(か)れて腐(くさ)ると、溶(と)けずにのこって養分になる。細かな砂に、しだいに植物の養分がたくわえられ、土になった。植物が生まれた4億年くらい前から、少しずつ土は作られて、地球は今のような土におおわれる大地になったんだ。
つまり、岩石が養分をふくんだ土になるには、植物のはたらきがなくてはならないんだ。土をくわしく調べてみると、砂と粘土のほかに黒いものがまじっているよ。これは、草や木や根っこが腐ったものだ。これを「腐植(ふしょく)」とよんでいるよ。
土にはどんな種類があるの?
土にはいろんな種類があって、色や性質(せいしつ)が違(ちが)うのを知っているかな。中国の黄河流域(こうがりゅういき)にある土は、黄土と呼(よ)ばれる黄色い土だ。アフリカの大地は、赤い土でおおわれている。私(わたし)たちがすんでいる日本の土にも、たくさんの種類の土があって、それぞれの土に適(てき)した草や木が生えているよ。日本の土は酸性(さんせい)が強く、やわらかいのが特徴(とくちょう)だ。
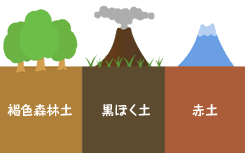
日本の山に多くある土は、褐色(かっしょく)森林土という種類の土だ。シイやカシなどの落ち葉や枯(か)れ枝(えだ)が、腐(くさ)ってできたものだよ。色は黒みがかった茶色をしていて、雨水をためこみやすいのが特徴だ。
人がくらしている平野(へいや)や丘(おか)に多いのが、黒ぼく土と呼ばれる黒土だ。火山灰(かざんばい)に草が生えて、腐った枯れ葉とまざってできたもの。水はけがよく、肥料(ひりょう)を混(ま)ぜると作物を育てるのにいい土になるよ。
赤色の土は、鉄から出る赤さびによって色がついていて、粘土(ねんど)分が多い。富士山の火山灰からできた関東ローム層(そう)の赤土が、よく知られているよ。
土の色は、その中にどんな成分がふくまれているかを知る手がかりになるんだね。きみも、家のまわりの土や、校庭の土や、花壇(かだん)の土などを集めて、色や水はけなどの性質をしらべてみるといいよ。
土はどんなはたらきをしているの?
土は、空気や水と同じようになくてはならないものだ。土がないと、地球上の生物は生きていけない。では、土がどんなはたらきをしているのか、調べてみよう。
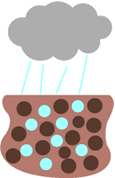
土の粒(つぶ)と粒の間にはすきまがあって、そこには空気や水がふくまれている。たくさん雨が降(ふ)ると、土には雨水がしみこんで、ゆっくりと流れていく。このため、少しくらいの雨では、洪水(こうずい)にならないんだ。また、汚(よご)れた水が流れてくると土にしみこみ、細かいゴミなどは土に残って、水をきれいにするんだよ。
土は、生き物にとっては栄養の宝庫(ほうこ)であり、すみかにもなっている。植物は、土の中の養分を吸(す)って生長している。動物のフンや死がい、枯(か)れた植物などは、土の中にすんでいる微生物(びせいぶつ)によって分解(ぶんかい)される。そして土の栄養となって、植物を育てるんだ。
土を水でこねて焼くと、お皿や茶碗を作ることもできる。レンガを作って、家を作ることだってできる。土は人のくらしにも、役に立っているんだよ。
土の中には生き物がいっぱい?
土の中には、昆虫(こんちゅう)、動物など、たくさんの生き物がすんでいる。土を掘(ほ)りおこしてみると、モグラやねずみなどの動物や、トカゲなどのは虫類、小さいミミズや虫の幼虫(ようちゅう)などの生き物が見つかるはずだ。さらに目には見えないカビや細菌(さいきん)などの微生物(びせいぶつ)も、土の中にはたくさんいるんだよ。

土の中では生き物が、それぞれおたがいに食べたり、助け合ったりしてくらしている。生き物が土の中で動きまわる時、通り道をあけてたくさんのトンネルを作る。このトンネルは空気の通る道にもなって、ほかの生き物や植物の根が、呼吸(こきゅう)しやすいようにしてくれているよ。植物が枯(か)れると、その落ち葉を虫が食べ、残りはもっと小さな生物が食べる。虫や動物が死ぬと、植物が育つための養分になる。土の中は、たくさんの生き物がすみやすい場所なんだね。
どうして土で植物が育つの?
植物は、どうやって成長するのかな。植物は光合成(こうごうせい)によって、養分を作っている。光合成に必要なのは、空気中の二酸化炭素(にさんかたんそ)と土の中にある水だ。葉からは二酸化炭素を吸(す)い、そして根から土の中の水を吸って、植物は成長するんだ。
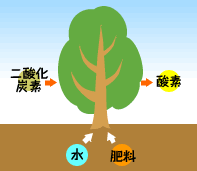
土には窒素(ちっそ)やカリウム、リンなどの肥料(ひりょう)がふくまれていて、それが水に溶(と)けた状態(じょうたい)で根から吸収(きゅうしゅう)される。たとえば、窒素には葉を大きくさせるなど、それぞれにはたらきがあるんだ。土の中にどんな肥料が含(ふく)まれているかで、作物のできがかわってくる。また、根から水をしっかり吸い上げて、植物は茎(くき)や葉のすみずみまでイキイキと育(そだ)つんだよ。
畑の中ではミミズが大活躍(だいかつやく)?
畑で作物を育(そだ)てるのには、土が大切だ。では、作物が育ついい土を作るのに、ある生き物が活躍(かつやく)しているのを知っているかな?それは、なんとミミズだよ。
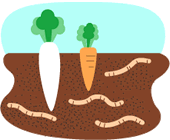
ミミズは土に穴(あな)を掘(ほ)って、巣を作っている。昼間は土の中に隠(かく)れているけど、夜になると巣から出てきて、腐(くさ)りかけた落ち葉を食べているんだ。そして、泥(どろ)のようなフンを穴のまわりに積み上げる。ミミズのフンは、土の粒(つぶ)や落ち葉のかけらがまじって、栄養たっぷりの黒土になるんだよ。
ミミズのフンからできた黒土は、植物が育つのに適(てき)している。黒土のほとんどは、ミミズのおなかを通ったものだといわれているんだって。植物の肥料(ひりょう)を作ってくれているミミズ。これからは畑などでミミズを見つけたら、感謝(かんしゃ)したいね。
野菜(やさい)がおいしいのは土のおかげ?
きみは野菜が好き?毎日、たくさん食べているかな?おいしい野菜を作るためには、土がとても大切だよ。たとえば、食べた時にしゃきしゃきとした歯ごたえがあるのは、野菜がみずみずしい証拠(しょうこ)。そんな新鮮(しんせん)な野菜は、土から水をたっぷり吸(す)い上げて育ったものだ。それには水はけがよく、水もちのいい土でなければならないんだよ。
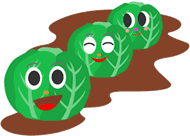
食べ物がおいしいと感じるのは、うまみ成分のアミノ酸(さん)が含(ふく)まれているからだ。野菜は根っこから肥料(ひりょう)の窒素(ちっそ)を吸(す)い上げ、自分でアミノ酸を作り出す。だから土の中には、窒素が十分にあることが必要だ。ほかにも肥料がバランス良く含まれていると、野菜の成長を助けて、もっとおいしくしてくれる。また、野菜が病気にならないように、そして虫に食べられにくくするためにも、野菜が健康に育つ土作りが大切だよ。
人や動物は、植物のように光合成を行って栄養を作ることができない。だから、野菜や果物などを食べて、その栄養をもらっている。そのことを忘(わす)れないでね。
土も呼吸(こきゅう)をしているの?
土の中には、空気がたくさんふくまれている。土は空気から酸素(さんそ)を吸(す)って、二酸化炭素(にさんかたんそ)を出しているんだ。つまり、呼吸(こきゅう)しているってわけだね。

でも本当は、土自体が呼吸しているのではないよ。土の中の細菌(さいきん)や小さなカビなどの微生物(びせいぶつ)が、呼吸しているんだ。植物も土の中の微生物なども、土の中に新鮮(しんせん)な空気があるから元気に生きていける。作物を植える時、土をたがやすよね。これは、土の中に新鮮な空気をたくさん送りこむためにやっていることだよ。
そう考えてみると、地上の空気も新鮮でないと、いい土を作ることができないね。工場や車から出る排気(はいき)ガスなどの大気汚染物質(たいきおせんぶっしつ)は、いったん上空に立ちのぼり、やがて雨となって地上にふってくる。そして雨にとけた大気汚染物質は、土にしみこむ。土には物質を吸(す)いつけるはたらきがあるから、これらの汚染物質は土の中にどんどんたくわえられてしまうんだ。
作物を作ると土はやせてしまうの?
植物は、土の中の養分を吸(す)って成長する。そのため、野菜などの作物を作ったあとには、土の養分がなくなってしまう。そのままの土でまた新しく作物を植えると、養分が足りないために、作物のできは悪くなってしまうんだよ。

東南アジアなど熱帯雨林の地域(ちいき)では、古くから焼き焼き畑農業(やきはたのうぎょう)が行われている。焼き畑農業とは、森林や原っぱを焼いて、その焼いた土地に作物を育てる方法だ。土の養分がなくなると別の土地に移(うつ)って、あらたに木や草を焼いて畑にする。これをくり返していると、森がどんどん少なくなっていると心配されている。
昔の日本では、今ほどたくさんの食料が必要ではなかったから、自然の肥料(ひりょう)だけで作物を育てていた。養分がなくなった畑はしばらく休ませておくと、やがて土は養分をたくわえて肥(こ)えた土に戻(もど)るんだ。だけど、現代(げんだい)は人口も多く、たくさんの食料が必要だ。生産がまに合わないから、化学肥料を使って手間や時間をかけずに野菜を育てることが多くなっている。だけど化学肥料を使うと、かえって土が悪くなってしまうんだよ。土が悪くなるのは困(こま)るけど、野菜はたくさん作らなくてはならない。難(むずか)しい問題だね。
土がよごれるってどういうこと?
野菜などの作物をたくさん、早く、じょうぶに育てるために、化学肥料(かがくひりょう)や農薬(のうやく)が使われている。でも、これらは土を汚(よご)している原因(げんいん)になっているんだよ。たくさんの化学肥料を使うと、作物はよく育(そだ)つ。だけど、弱く病気になりやすい。そこで病気にならないように、たくさんの農薬を使うことになってしまうんだ。
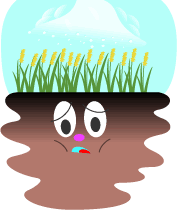
こんなことをくり返していたら、土はどうなってしまうだろう。土の中では植物が食べ残した化学肥料がたまって、微生物(びせいぶつ)が減(へ)ってしまい、土の環境(かんきょう)が変わってしまう。農薬の多くは分解(ぶんかい)されずに、土に残ってしまう。こうして土は、汚染(おせん)されてしまうんだ。
ほかにも、鉱山(こうざん)や工場から重金属(じゅうきんぞく)を流すと、雨水を通って土を汚していく。最近問題になっているのは、空き地(あきち)や谷などに捨(す)てられている廃棄物(はいきぶつ)だ。工場から出る廃棄物からは有害物質(ゆうがいぶっしつ)がしみ出して、土を通って地下水に流れこむ。汚れた土を通って、人が口にする水までが汚れてしまうよ。
土がよごれると私たちもあぶない?
土が汚(よご)れると、植物だけでなく動物や人間、生き物みんなが影響(えいきょう)を受けることになる。化学肥料(かがくひりょう)や農薬(のうやく)で土が汚れると、土の中にすむ生き物の世界もバランスがくずれてしまうんだ。カビやバクテリアなどの微生物(びせいぶつ)の種類や数が減(へ)って、特定の生物だけが増(ふ)えてしまう。作物の病気の原因(げんいん)になるものが増(ふ)えると、農薬を大量に使うことになり、ますます土の汚染(おせん)がすすむことになる。
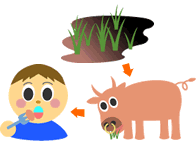
汚れた土で育った農作物には、農薬などの有害な物質(ぶっしつ)がふくまれているかもしれない。そんな農作物を牛やブタなどの家畜(かちく)が食べると、さらに汚染が広がっていく。汚染された牛やブタの肉を、人が食べる。汚染された野菜も、人が食べる。こうして人の体に、汚染物質がたまってしまう。長い時間をかけてゆっくりたまった汚染物質は、どんなふうに体に影響を及(およ)ぼしていくのだろう。わかっていないことも多いだけに、心配だ。
地球に砂漠(さばく)が広がっている?
世界では今、砂漠(さばく)が広がっている。砂漠は水が少なく、植物もほとんど生えていないところだ。どうして砂漠は、広がっているんだろう。雨が少なくなったり、地球温暖化(ちきゅうおんだんか)のために気温が上がったせいだったり、砂漠化にはいろんな原因(げんいん)がある。でも、その原因の多くは、人が作り出したものなんだ。

たくさん家畜(かちく)を放牧したせいで、エサとなる草を食べつくしてしまったことも原因のひとつ。作物を植え続けたために、養分の少ない乾(かわ)いた土地で、ますます養分が減(へ)ってしまったせいもある。木をたくさん切ってしまったために、植物から出る水分が減って、乾いた土が広がってしまったなど、いろいろ理由はある。
アジアでは熱帯林がたくさん切られて、土地が荒(あ)れてしまっている。アフリカではサハラ砂漠のまわりの村がどんどん砂漠にのみこまれ、飢(う)えや干(かん)ばつに苦しんでいる。植物も生えないような砂漠では、とても人はくらしていけない。なんとかしないと大変だ。
土を守るにはどうしたらいいの?
生き物の食べ物となって、命を支(ささ)えている植物。その植物を育てているのが、土だ。つまり土を守ることが、地球を守る土台といっていいかもしれないね。土を守るために、最近は有機農業が見直されている。有機農業とは化学肥料(かがくひりょう)や農薬を使わずに、たい肥(ひ)を入れた土のこと。たい肥は牛やニワトリなどのフンに、落ち葉などをまぜて腐(くさ)らせたものだ。農薬を使わないから虫がつくけれど、虫も喜んで食べるほど、安全でおいしい野菜ができるよ。

家で出る生ゴミを利用して、たい肥を作ることもできるよ。料理を作った時にできる野菜くずを、コンポストという容器(ようき)に入れておくんだ。するとミミズなどが分解(ぶんかい)して、肥料に変えてくれる。地面に穴(あな)を掘(ほ)って、生ゴミを入れて土をかぶせるだけでもできるし、生ゴミ処理機(しょりき)という機械もある。こうすれば肥料を作れるし、同時にゴミを減(へ)らすこともできるんだ。