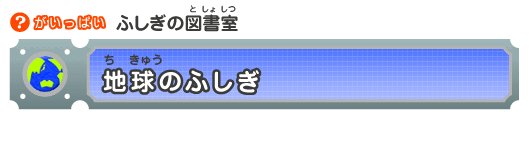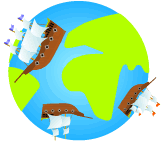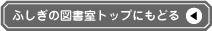サイト終了のお知らせ
パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
地球はいつ、どうやって生まれたの?
わたしたちがすんでいる地球はいつ、どうやってできたのかな?広い宇宙(うちゅう)の中にある地球。銀河系(ぎんがけい)という星の集団のはしに太陽系(たいようけい)があり、そこに地球はある。それでは、誕生(たんじょう)のひみつをさぐってみよう。
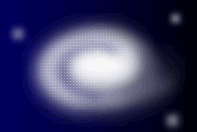
地球が生まれるきっかけは、およそ50億(おく)年前にさかのぼる。宇宙のどこかで、星の大爆発(だいばくはつ)が起こったんだ。この爆風によって、うすいガスやチリが大きな渦(うず)を作り始めた。渦の中心には物質(ぶっしつ)が集まってどんどん高温になり、やがて核融合反応(かくゆうごうはんのう)というものが起きた。こうして生まれたのが、太陽だよ。
一方、ぐるぐるまわっている渦の中では、ガスが冷えてこまかな粒子(りゅうし)ができた。粒子は集まって、やがて微惑星(びわくせい)と呼(よ)ばれる大きなかたまりになった。微惑星はおたがいに引力で引きつけあって、どんどん大きくなる。これが地球をはじめ、惑星の原型になったんだ。原始の地球は、およそ46億年前にできたと考えられているよ。
地球のなかまにはどんなものがあるの?
こまかいガスやチリの渦(うず)の中から、地球が誕生(たんじょう)したことはわかったかな。同じころ、ガスやチリが集まって、ほかの惑星(わくせい)も生まれていたんだよ。
太陽系(たいようけい)の惑星は、太陽に近い順に、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星と8つある。これら太陽系の惑星は、兄弟のようなものだね。でも、同じ太陽系の惑星でも、大きさなど特徴はそれぞれ違っているよ。太陽に近い水星、金星、地球、火星はどちらかというと小さく、岩石でできている。木星、土星、天王星などは大部分がガスでできていて、とても大きいんだ。
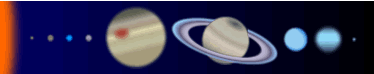
地球には豊(ゆた)かな空気と水があり、たくさんの生き物が生きている。地球は、太陽系の惑星にはない個性(こせい)を持った星といえるかもしれないね。
さいしょは地球に海はなかった?
できたばかりのころの地球って、どんな姿(すがた)をしていたと思う?初めのころの地球には、海も陸もなかった。岩石は1,200度以上の熱でどろどろとけて、熱いマグマの海になっていたんだって。そして微惑星(びわくせい)や隕石(いんせき)がつぎつぎと衝突(しょうとつ)していたんだ。上空の高いところでは、水蒸気(すいじょうき)が集まって雲を作っていたらしい。
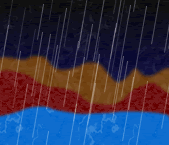
やがて微惑星や隕石の衝突が減(へ)ってくると、マグマの海はだんだん冷えていった。地球の気温が300度くらいまで下がった時、地表の近くに雲ができ、雨が降(ふ)り出した。そして雨は、熱い大地を急激(きゅうげき)に冷やしていったんだよ。
地表が冷えると、大気の中の水蒸気が冷やされて、また雨が降る。地表では雨の水がたまり、川や池や湖を作る。さらに大洪水(だいこうずい)をくり返し、たまった水がつながって、やがて海になったんだ。大雨は、なんと3,000年も降り続いたんだって。
ところで、海はどうしてしょっぱいのかな?
地球が水の惑星(わくせい)といわれるのはなぜ?
宇宙(うちゅう)から見た地球は、青く輝(かがや)いている。なぜなら地球の表面の10分の7が、水でおおわれているからだよ。だから、地球は「水の惑星(わくせい)」と呼(よ)ばれるんだよ。
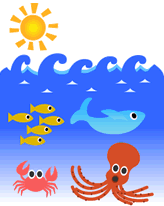
地球に海ができたことから、太陽系(たいようけい)の中ではただひとつ、生き物がたくさんすむ星になった。くわしいことはまだよくわかっていないけれど、最初の生き物は海から生まれたと考えられている。海水の中にとけこんだ酸素(さんそ)や炭素(たんそ)、水素(すいそ)や窒素(ちっそ)などが組み合わさって細胞(さいぼう)を作る。生き物のすべての祖先(そせん)となる生命は、海から生まれたってわけ。
そして海は、生命を作っただけでなく、それを守る役目も果たしていた。生命が生まれたのは約40億(おく)年前のこと。そのころ陸(りく)には太陽からの紫外線(しがいせん)が今の数倍もあり、生物が生きていくには危険(きけん)がたくさんあった。だから生き物は長い間、海の中で進化を続けてきたんだよ。海のことを「母なる海」と呼(よ)ぶのも、そんなところからだったんだね。
陸はどうやってできたの?
誕生(たんじょう)したばかりのころ、熱いマグマの海におおわれていた地球。やがて海ができてからは、地球表面のほとんどが海でおおわれるようになった。表面だけを見ると、まるで水の球みたいだったそうだ。
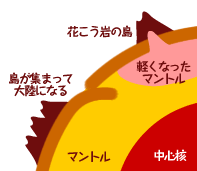
では、どうやって陸(りく)ができたのかな?海の底、地球の中をのぞいてみよう。海底はどうなっていたかというと、うすい岩の層(そう)でできた地殻(ちかく)でおおわれていた。そして、その下にはマントルという熱いかたまりの層があった。
地球が生まれて数億(すうおく)年たったころ、地球のまん中に「中心核(ちゅうしんかく)」と呼(よ)ばれるもっと熱い部分ができた。これがマントルをあたため、軽くなって浮(う)き上がってくると海底で冷やされてプレート、つまり岩盤(がんばん)になったんだ。プレートはマントルの流れに乗って動き、ほかのプレートとぶつかった。ぶつかり合ったプレートの境目(さかいめ)あたりには、つぎつぎと花こう岩という軽い岩の島が生まれた。そんな島がぶつかりながら集まって、やがて大陸ができたと考えられているよ。
大陸が動いているってほんと?
世界地図や地球儀(ちきゅうぎ)を、よく見てごらん。アメリカ大陸を動かして、アフリカ大陸にくっつけたら、ぴったり合うと思わないかな?およそ2億2,000万年前の地球は、今の大陸はみんなくっついていて、ひとつの巨大(きょだい)な大陸だったらしい。その大陸にわれ目ができ、ゆっくり動いて今の形に動いていったと考えられているよ。
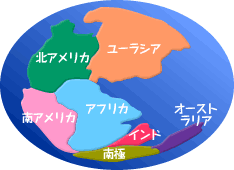
なぜ大陸が動いたかというと、地球の内部にあるマントルが関係している。地下ではマントルという熱いかたまりが動いていて、それに影響(えいきょう)を受けるからなんだ。
今、ヒマラヤ山脈があるところは、大昔は浅い海だった。ところが、インドの陸地が運ばれてアジアにぶつかり、強い力を受けてもりあがってヒマラヤ山脈になった。日本列島は、3億年くらい前までは海の底に沈(しず)んでいたんだって。約2億年前に海底から顔を出し、アジア大陸にくっついたままで、海から出たり沈んだりしていた。そして約10万年前まで、大陸と日本は陸続きだった。だから、陸をつたって人や生き物が日本にやってくることができたんだよ。
地球は今も活発に活動している?
地球が誕生(たんじょう)してから約46億(おく)年、たえず地球は活動している。火山の噴火(ふんか)や地殻(ちかく)の変動などによって、海や陸(りく)は今もさまざまな影響(えいきょう)を受けているんだよ。
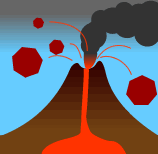
火山の噴火は、岩石が溶(と)けてマグマになり、地表をつき破(やぶ)ってふき出してくること。熱い溶岩(ようがん)が流れだし、火山灰(かざんばい)、水蒸気(すいじょうき)などをふき上げ、大きな災害(さいがい)をもたらすこともある。北海道の昭和新山(しょうわしんざん)のように、火山の噴火によって新しく山ができることだってあるんだよ。
大地をゆれ動かす地震(じしん)も、地球の活動だ。どうして地震が起こるのか、くわしいことはわかっていない。断層(だんそう)に沿(そ)った岩の中で、地殻(ちかく)やプレートが動くために起こる。岩が圧力(あつりょく)に反発してはじけると、そのショックが地面に伝わって揺(ゆ)らすんだ。地球って、まるで生きているみたいだね。
地球の中心はどうなっているの?
地球の中心は、いったいどうなっているのかな?地球の中身は、半熟(はんじゅく)たまごにたとえられる。地球の表面は、地殻(ちかく)というとてもうすい層(そう)におおわれている。私(わたし)たちは地下を掘(ほ)って石炭や石油など鉱物(こうぶつ)や燃料(ねんりょう)を採取(さいしゅ)しているけれど、この層は地球全体から見ると、とてもうすいたまごのカラみたいなものなんだね。
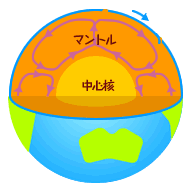
さらに地下の中心へ進んでいくと、マントルという層がある。マントルは、たまごにたとえると白身の部分にあたる。さらにその先には、黄身の部分にあたる中心核(ちゅうしんかく)がある。中心核は熱でどろどろに溶(と)けていて、6,000度もの熱があるといわれているよ。マントルは岩石からできていて、中心核の熱に温められて軽くなるとうき上がり、冷やされると重くなって沈(しず)む。これを対流と呼(よ)び、マントルはつねに動いている。マントルが動くと、それに引きずられるようにして、表面にある陸も少しずつ動いているんだよ。
地球はすごいスピードで動いている?
地球は、太陽のまわりをまわっている。これを公転といい、1年かけてひとまわりしているよ。地球は進む早さは、どのくらいだと思う?
なんと、1秒間におよそ30kmもの早さで進んでいるんだ。すごいスピードだよね。
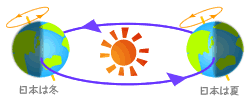
地球は、太陽のまわりをまわりながら、自分でもぐるぐるまわっているよ。これを自転といって、1日で1回転している。太陽に照らされているところが昼、反対側にある時は光がささない夜になる。1日に昼と夜があるのは、地球が自転しているからなんだ。
地球は23.4度傾(かたむ)いた状態(じょうたい)で自転しながら、太陽のまわりをまわっている。そうすると、地球から見た太陽の方向は、公転している間にどんどん変わっていくよ。これが地球に四季をもたらしているんだ。
どうして地球の気温は変化するの?
地球は23.4度傾(かたむ)いたままで、太陽のまわりをまわっていることはわかったね。そのため、太陽の光が地球表面にあたる角度が、1年のうちにつぎつぎ変わり、季節のうつりかわりが起きる。このしくみをもう少しくわしく説明しよう。
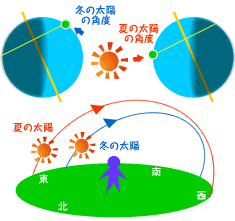
日の出(ひので)、日の入り(ひのいり)の場所と、太陽の高さは季節によって違(ちが)っている。秋分(しゅうぶん)と春分(しゅんぶん)では、太陽は真東から上がって真西に沈(しず)み、昼と夜の長さが同じだ。北半球では夏至(げし)になると、一番太陽が高く上がって昼が長くなり、暑い夏になる。反対に一番太陽が低い冬至(とうじ)は、昼が短くなり、寒い冬になる。
季節だけでなく、緯度(いど)によっても気温は変わってくるよ。赤道付近では、太陽が真上から照(て)りつけるから、気温が高くなる。緯度の高いところでは、太陽がななめから照るので、気温は低い。地球の緯度によって、熱帯・温帯・寒帯に分けることができるよ。
地球の水が減(へ)らないのはなぜ?
海の水はどうして減(へ)らないのかな?また反対に、海の水があふれてしまうことはないのかな?地球上では、水はずっと減ることもあふれることもなく、一定の量をたたえている。それは、水が姿(すがた)を変えていろんな場所で、ぐるぐるまわっているからだよ。
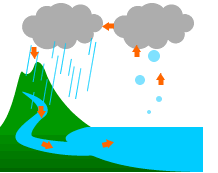
海の水が太陽の熱であたためられると、水蒸気(すいじょうき)になる。水蒸気は空気中で冷やされて、雲になる。そして雨や雪となって、地表に落ちる。その水は地表を流れ、川を通ってまた海に戻(もど)ってくるんだ。こんなふうにくりかえすことを、水の循環(じゅんかん)と呼(よ)んでいる。水は昔からずっと、空と陸(りく)と海を旅しているようなものだね。
地球は最後にどうなってしまうの?
地球にも一生があり、地球の寿命(じゅみょう)は太陽と深く関わっている。地球を照(て)らし続けている太陽は、永遠に輝(かがや)いているわけじゃないんだ。
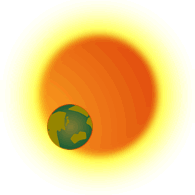
太陽の寿命はだいたい100億年といわれている。太陽は、1億年に1パーセントずつ明るくなってきている。5億年くらいたつと、地球は太陽の熱のために海水が蒸発(じょうはつ)してしまい、生き物がすめなくなってしまう。そしてあと50億年後くらいには、太陽が大きくふくらんで地球をのみこんでしまうといわれているよ。
徐々に膨らんだ太陽はその後、赤色になって、表面からガスを宇宙に放出していく。やがてガスがなくなると、最終的には白色の小さな星が中心に残り、とても長い時間をかけて冷え、暗くなっていくよ。