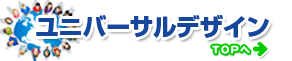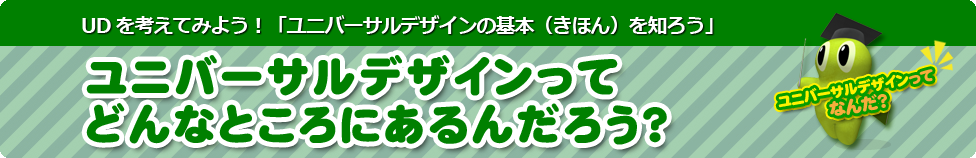
自動ドア、右利きの人も左利きの人も使えるハサミ・・・。
特定の人だけではない、みんながいっしょに使えるね。

7原則(げんそく)を知っても、ユニバーサルデザインってピンとこないって
人もいるよね。
じゃあ、身近にあるユニバーサルデザインといわれているものについて、
考えてみよう。
「自動ドアは、車いすを使用している人も、両手に荷物を持っている人も、もちろん
健康な人も、利用する人全員が特別あつかいされずに、
同じように便利に使えるね。」
これはユニバーサルデザイン。だれでも公平に使えるね。
「わたし、左利きなんだけど、家にあるお母さんのハサミは使いにくいのに、
学校にあるハサミは使いやすいのよ。」
昔のハサミは右利き用にできていたものが多いんだ。
学校のハサミは右利きの人にも左利きの人にも使いやすいように
作られているものなんだね。
だから、これも、ユニバーサルデザイン。これも、だれでも公平に、自由に使えるね。
「駅の改札が2階にあるんだけど、階段(かいだん)もエスカレータも
エレベータもあるから、ベビーカーをおしている人や、車いすを使用している人、
健康でも楽に移動(いどう)したい人は、エスカレータやエレベータを使えるよ。
急いでいる時は階段をかけ上がれるよ。」
これも、またまたユニバーサルデザイン。自由に選べるところがいいね。
すべての人が、使いやすいものを作るのはなかなかむずかしい。
だけど、困(こま)っている人だけのものを作るより、はじめからみんなが、
同じように使いやすいものを作ることは、弱い立場の人を特別視(し)しないことだよね。
それに、後で作り直したり何かを足したりすることがないから節約できるし、
作り直しに必要なエネルギー(電気やガソリン)が少なくて
環境(かんきょう)への負担(ふたん)もへることになるんだよ。

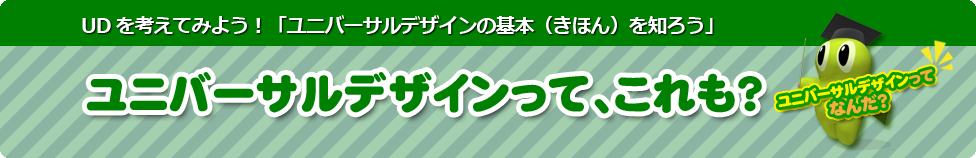
「しょうがいしゃ用トイレ」と「多目的トイレ」。
どちらが、ユニバーサルデザイン?
「しょうがいしゃ用トイレ」には、しょうがいのない人は入りにくい。
でも、「多目的トイレ」にしたら、みんなが、便利に使えるよ。
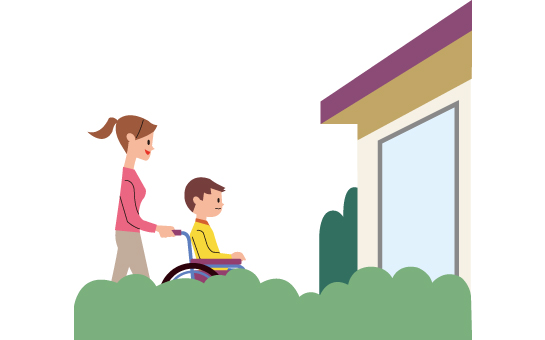
「公園のトイレに、車いすのマークがあって、しょうがい者用って書いてあるんだ。
小さな子どもを連れた人にも、広いトイレは便利だと思うんだけど。」
広いトイレは、小さな子どもを連れた人にも、荷物をいっぱい持っている人にも
使いやすいよね。
でも「しょうがい者用トイレ」と書いてあったら、しょうがいがある人しか使えない。
これでは、ユニバーサルデザインとはいえないよね。
バリアフリーでは、「しょうがいがあっても使いやすい」ものを作ること。
これは大切なことだけど、最初から特別な人だけのものを作るのではなく
最初からだれにでも使いやすいものを作ることが、ユニバーサルデザインなんだよ。
「しょうがい者用トイレ」「車いす用トイレ」と書くのをやめて、
「多目的トイレ」「だれでもトイレ」と書くだけで、バリアフリーだったトイレが
ユニバーサルデザインになるよね。

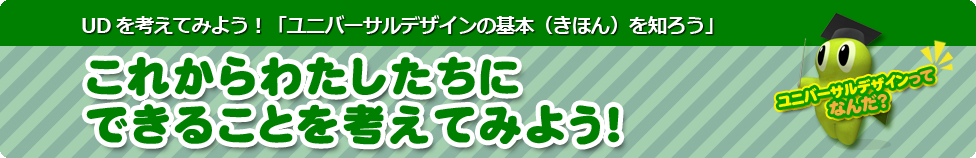
ユニバーサルデザインを学んで
自分に何ができるか、考えよう!
「しょうがいのある人でもふつうにくらせるべき」
「しょうがいがあることで特別あつかいされたくない」
そんな考えから方法が生まれ、家や学校や街に広まり、
進化しつつあるユニバーサルデザイン。
それに対してどう思い、自分に何ができるか、考えてみよう。
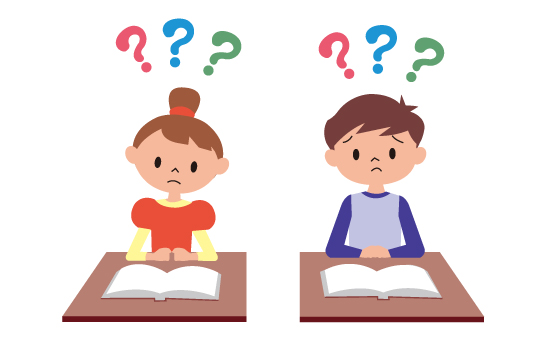
バンク・ミケルセンさんが感じた、「しょうがいのある人でもふつうにくらせるべき」
という考え方。
ロナルド・メイスさんがユニバーサルデザインを誕生(たんじょう)させた
きっかけである「しょうがいがあることで特別あつかいしてほしくない」という気持ち。
そして作られた7つの原則(げんそく)。
家や学校や街でいろいろなユニバーサルデザインが使われていること。
それについてどう思う?そして自分に何ができる?
たとえば街にあるスロ―プは、ユニバーサルデザインを学んだからこそ、
ベビーカーをおしている人や車いすを使用している人に
欠かせないものであることを知った人もいるんじゃないかな。
スロープに自転車とかを置きっぱなしにしない。
それも自分でできることのひとつだね。
いろいろな意見を聞いたり、みんなで話し合えたりするといいね!