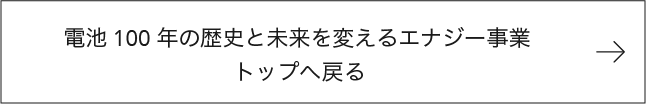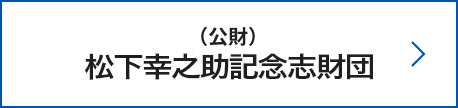先人たちの“やるしかない”エピソード
自転車用エキセルランプ(砲弾型電池式ランプ)の発売から4年後の1927年、松下幸之助は、手提げ用にも使えるコンパクトな角型ランプを開発します。
「国民の必需品に育てたい」との思いから「ナショナルランプ」と命名されたこのランプは、加速度的に販売を伸ばし、1930年には月産20万個を突破。乾電池の販売も急伸し、月50万個を超えるまでになりました。「ナショナルランプ」に用いる乾電池は、東京の岡田乾電池から仕入れていましたが、岡田1社ではまわらなくなり、幸之助は大阪の小森乾電池での委託生産を開始。そして、1931年には小森を買収し、いよいよ乾電池の自社生産を開始するのでした。
「ナショナルランプ」の販売はさらに増え、日本の津々浦々、山間僻地をくまなく照らす、文字通りの「国民のランプ」となります。そして乾電池についても、多くの人々が「電池といえばナショナルだ」と連想するまでになったのです。戦前の最高時、販売は月300万個に達したといいます。
ランプがけん引した乾電池の販売増は日本の乾電池産業の発展に貢献しました。1960年発行の『日本乾電池工業史』は、こう讃えました。
「屋井先蔵(1864~1927、乾電池の発明者)をわが国乾電池工業の始祖とするならば、松下幸之助を中興の祖と呼ぶ所以もここにある」
戦後復興が進む1950年代、日本の乾電池業界では欧米の技術を導入しようという動きが盛んになり、松下電器でも当時世界一と言われたアメリカメーカーとの提携話が進んでいました。
提携を押す声が大半を占めるなか、異を唱える人物がいました。それは他でもない、技術部門の総帥、中尾哲二郎でした。中尾はアメリカ出張中、街のスーパーでこのメーカーの乾電池を買い、滞在中のホテルで細かく切り刻み、徹底分析を試みました。その結果、「この程度なら、技術援助がなくてもできる」との確信を得たのです。
中尾は乾電池事業部の関係者にも意向を聞いてみました。すると「ぜひ独自の技術で新製品を開発したい」というではありませんか。わが意を得たり―中尾は彼らにこう告げました。
「君たちにそういう意気込みがあるなら必ず成功する。ぼくはだんぜん提携を断る意見を通す」結局、この提携話は、条件面で折り合いがつかずご破算となりますが、松下幸之助をはじめとする経営陣に取り止めを決意させたのは、「自信を持ってやります」という中尾のひと言でした。
こうして世界水準を見すえた新製品の開発が始まり、1954年、日本で初めての完全金属外装乾電池「ナショナルハイパー」が誕生したのです。
外装を紙筒から金属缶に変えることで液漏れを半減させ、貯蔵寿命も倍増となったこの製品が起点となり、松下電器の乾電池は「ナショナルハイトップ」(1963年)、「ナショナルネオ・ハイトップ」(1969年)へと飛躍的な成長を遂げていくのでした。



1957年、ある研究が三洋電機でスタートしました。それは、乾電池事業を担当していた井植薫(井植歳男の弟、後の三洋電機社長)が飛ばした檄、「次世代の電池に挑戦しよう」を受けた研究でした。
発奮した技術陣は、外国文献で見た、密閉したまま充電できる二次電池、密閉型ニッケルカドミウム電池(ニカド電池)に狙いを定め、「この電池を外国特許に頼ることなく開発しよう」という目標を立てます。
4年後の1961年、地道な研究が実り、三洋電機は独自方式によるニカド電池の開発に成功。1963年には、この電池を搭載した充電式トランジスタラジオを「カドニカラジオ」と称して発売。カドニカは新電池の愛称となりました。
弟、薫の檄から生まれたカドニカ電池。井植歳男はこの電池に大いなる夢を抱いていました。試作開始の頃から、研究所を訪ねては、「世界の人口30億、その10%の人にカドニカ電池のラジオを買ってもらおう」と、気宇壮大に語っていたといいます。
翌1964年、三洋電機は淡路島に洲本工場を開設すると、ここでカドニカ電池の量産を開始しました。
淡路は井植の故郷です。このことからも、カドニカ電池にかけた意気込みの強さが伝わってきます。
ラジオで始まったサンヨーカドニカは、シェーバーへ、懐中電灯へと、さらには非常灯や保安灯の分野へと、活躍の場を急速に広げていきます。登場当時の宣伝はこう謳いました。
「カドニカ製品を買ったら電池のことは忘れましょう」


1931年、松下電器はナショナルランプの大増販に向けて、乾電池の自社生産を開始しました。その後も電池の用途はランプや懐中電灯という時代が長く続いていました。
そうした中、乾電池事業部が需要拡大に向けて決起します。時に1955年、期待の新製品「ナショナルハイパー」が発売された翌年のことでした。
「需要を伸ばすには、まず電池を使ってもらえる“入れ物”を作らなければ。電池が生きる分野を“光”にとどめず、“熱”、“音”、“動力”にも広げよう!」こうした意気込みで応用製品の開発がスタートし、まず“熱”に着目した電池式ガスライターが誕生しました。当時のガスコンロはマッチで点火。台所仕事で濡れた手では、マッチが湿って火がつかない時もある。そんな不便を解消するこの製品は爆発的に売れ、1年半で200万世帯に普及しました。
松下電池工業で事業部長や営業本部長を務めた舟橋正雄は、こう振り返っています。
「ガスライターは2個の電池を使います。200万世帯ですから全部で400万個。毎日15回ガスライターを使うとして、電池は年4回取りかえないといけません。したがって年間では1,600万個になるでしょう。ランプと懐中電灯合わせて年間1億個の需要だったものが、ガスライターをつくっただけで、その1割6分もの需要が一気に出てくるわけです」
このガスライターを皮切りに、乾電池時計、自動ガスコンロ、110番ブザー、風呂ブザーなど、実に多くの応用製品が開発されていきました。これらが電池の需要増に大いに貢献したのです。
実際の展示の様子

乾電池応用製品
1955年頃まで、日本の乾電池はほとんど懐中電灯に使用されていました。しかし、懐中電灯における電池の需要は年間約1億個に過ぎません。そのため、電池産業発展のために、電池を使用する器具を開発し、電池の需要を刺激する必要がありました。まずはじめに、ガスライターが開発され、「光」の分野に「熱」の分野が加わりました。続いて、「音」(ブザーなど)、「力」(ごますり器など)の分野で積極的な商品開発が行われました。
合わせて、乾電池自体も、ハイトップ、ネオハイトップと高性能化し、電池関連機器と電池の需要は飛躍的な発展を遂げました。
1960年代、松下電器はアジアやラテンアメリカをはじめとする地域で、乾電池を先鋒として、次々と海外製造事業を展開していきました。1966年にペルーの首都リマに設立されたナショナル・ペルアーナもその一つ。責任者に抜擢されたのは、31歳の若き山田利郎でした。
ペルーに赴く山田に、当時の海外事業担当で、経営基本方針の伝道師と呼ばれた髙橋荒太郎副社長は、「経営基本方針に照らして、どうあるべきかを考えて物事を進めなさい。君がやる仕事はペルーのためになるのだ、それが会社のためになるのだと信じて、がんばってほしい」と説きました。
山田は工場用地に、「この会社はペルーの会社です。ペルーの発展に貢献します」と書いた看板を建て、ミッションを表明するとともに、既に工場建設を進めていた米国メーカーに遅れをとってはならぬと、思い切った方法に打って出ます。
リマではほとんど雨が降らない。屋根なしでもスタートできる。こう考えて屋根の据え付けを後回しにし、ライバルより1週間早く、電池を売り出すことに成功したのです。
さらに、能率的な稼働を妨げるペルーの労働法(夏4時間、冬3時間の昼休み)にも挑みました。
昼食の提供、夜学の学費補助など従業員の福祉向上を掲げつつ、当局に陳情を繰り返し、「昼休みは45分」の許可を得たのです。旧来の習慣を打ち破ったことに、従業員も謝意を表しました。一時帰国の度に、山田は松下幸之助と髙橋からこう問われたといいます。
「会社は国の役に立っているか?」「製品はペルーの人々に喜ばれているか?」「従業員は元気に働いているか?」