「違い」を乗り越えた先に共感がある。
日本留学で得た視野の広がりで見えた世界。
「違い」を乗り越えた先に共感がある。
日本留学で得た視野の広がりで見えた世界。
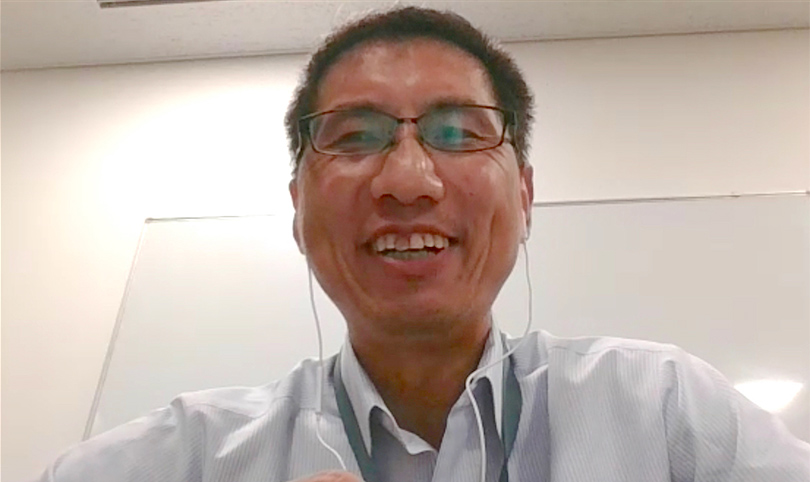
○杜 鹏(ト・ホウ)さん
1999年認定(海外採用)→東京大学入学(工学系研究科)→現在 中国の通信機器メーカー日本法人
○杜 鹏(ト・ホウ)さん
1999年認定(海外採用)→東京大学入学(工学系研究科)→現在 中国の通信機器メーカー日本法人
今回ご登場いただく、杜 鹏(ト・ホウ)さんは、パナソニック スカラシップが海外からの留学生を各国現地で募集・認定を開始した第1期の奨学生です。北京大学の卒業を目前に控えていた杜さんにとって日本への留学は想定外の人生の転機となりました。現在、日本で勤めながら、日中、そして中国と世界とをつなぐビジネスの現場で活躍。異なる背景を持つ人と人とを結び付ける自分の役割に、確かな手応えと未来への可能性を感じているそうです。異なる文化、多様なニーズ、複雑な国際コミュニケーションの現場でも、「心は通じ合える」「共感し合える」ことを確信。その原点は、パナソニック スカラシップにあったと言います。
今回ご登場いただく、杜 鹏(ト・ホウ)さんは、パナソニック スカラシップが海外からの留学生を各国現地で募集・認定を開始した第1期の奨学生です。北京大学の卒業を目前に控えていた杜さんにとって日本への留学は想定外の人生の転機となりました。現在、日本で勤めながら、日中、そして中国と世界とをつなぐビジネスの現場で活躍。異なる背景を持つ人と人とを結び付ける自分の役割に、確かな手応えと未来への可能性を感じているそうです。異なる文化、多様なニーズ、複雑な国際コミュニケーションの現場でも、「心は通じ合える」「共感し合える」ことを確信。その原点は、パナソニック スカラシップにあったと言います。
最初は進路の選択肢として選んだ日本留学
最初は進路の選択肢として選んだ日本留学
北京大学で電子工学を学んでいた杜さんは、大学卒業を前に修士への進路を決めその準備をしていました。そこに突然飛び込んできたのが、パナソニック スカラシップの情報でした。担任の先生から勧められるも、まったく想定していなかった選択肢に、当初は戸惑ったそうです。
杜さん:これは当時を振り返った上で、今の学生にも伝えたい私の反省点でもあるのですが、世界や将来を見通す視野が狭かった。日本への留学を可能性として捉えるよりも、悩んでしまったのです。そこで、先生や友人たちに相談しました。中国では修士課程は3年間あり、その間同じ環境で過ごすより、海外に出て、刺激を受け、見聞を広めるほうがいいと勧めてくれました。認定の面接では、パナソニック スカラシップの方も北京に来てくれましたし、認定後はパナソニックの現地法人の方が日本領事館の文化担当の方を紹介してくれるなど、多くの人に背中を押されて留学準備を一歩ずつ進めていきました。
大学の卒業は7月。日本への留学は翌年の4月。杜さんは、自らの進路を見据えるために留学先の大学院の情報を集め始めます。電子工学の学びをさらに進めたいと思っていた杜さんは、1999年当時、世界最先端ともいえた日本でのIT分野に関心を持っていました。
杜さん:当時の中国社会では、ITの社会実装はまだ進んでいませんでした。ところが、日本の大学院の情報を得ようとインターネットで検索すると、多くの大学院がウェブサイトを開設し、研究実績についても詳しい情報が公開されていました。しかも大学教授との連絡手段にはE-mailが活用されていました。私は、「ITの実用化」が進む日本に感心し、期待がふくらみました。
そうした準備を重ね、受け入れ先となった東京大学大学院の研究室に研究生として迎え入れられた杜さんは、東京都葛飾区で日本での生活をスタートさせます。
北京大学で電子工学を学んでいた杜さんは、大学卒業を前に修士への進路を決めその準備をしていました。そこに突然飛び込んできたのが、パナソニック スカラシップの情報でした。担任の先生から勧められるも、まったく想定していなかった選択肢に、当初は戸惑ったそうです。
杜さん:これは当時を振り返った上で、今の学生にも伝えたい私の反省点でもあるのですが、世界や将来を見通す視野が狭かった。日本への留学を可能性として捉えるよりも、悩んでしまったのです。そこで、先生や友人たちに相談しました。中国では修士課程は3年間あり、その間同じ環境で過ごすより、海外に出て、刺激を受け、見聞を広めるほうがいいと勧めてくれました。認定の面接では、パナソニック スカラシップの方も北京に来てくれましたし、認定後はパナソニックの現地法人の方が日本領事館の文化担当の方を紹介してくれるなど、多くの人に背中を押されて留学準備を一歩ずつ進めていきました。
大学の卒業は7月。日本への留学は翌年の4月。杜さんは、自らの進路を見据えるために留学先の大学院の情報を集め始めます。電子工学の学びをさらに進めたいと思っていた杜さんは、1999年当時、世界最先端ともいえた日本でのIT分野に関心を持っていました。
杜さん:当時の中国社会では、ITの社会実装はまだ進んでいませんでした。ところが、日本の大学院の情報を得ようとインターネットで検索すると、多くの大学院がウェブサイトを開設し、研究実績についても詳しい情報が公開されていました。しかも大学教授との連絡手段にはE-mailが活用されていました。私は、「ITの実用化」が進む日本に感心し、期待がふくらみました。
そうした準備を重ね、受け入れ先となった東京大学大学院の研究室に研究生として迎え入れられた杜さんは、東京都葛飾区で日本での生活をスタートさせます。
学業も生活も安心できる留学環境で視野を広げる
学業も生活も安心できる留学環境で視野を広げる
杜さん:パナソニック スカラシップの事務局による奨学生同士が交流するイベントやパナソニックへの会社訪問、社会体験の機会などを通じ、研究室や同じ国の出身者だけでなく、さまざまな国からの留学生とも交流を深めていくことができました。当初、留学生たちは日本語もほとんど話せませんでしたし、日本での生活に戸惑う人も多い。けれどもパナソニック スカラシップが、学費や生活費だけでなく、私たちの不安に寄り添ってくれたことで、安心して学び、プライベートの時間もリラックスした気分で過ごせる環境をつくってくれました。とても心強い制度だと感じました。
学業だけでなく、人と人とのコミュニケーションも自分を変えていく。当時を振り返ってそう考える杜さんは、留学の前と後とでは、自分に変化があったと言います。
杜さん:パナソニック スカラシップの事務局による奨学生同士が交流するイベントやパナソニックへの会社訪問、社会体験の機会などを通じ、研究室や同じ国の出身者だけでなく、さまざまな国からの留学生とも交流を深めていくことができました。当初、留学生たちは日本語もほとんど話せませんでしたし、日本での生活に戸惑う人も多い。けれどもパナソニック スカラシップが、学費や生活費だけでなく、私たちの不安に寄り添ってくれたことで、安心して学び、プライベートの時間もリラックスした気分で過ごせる環境をつくってくれました。とても心強い制度だと感じました。
学業だけでなく、人と人とのコミュニケーションも自分を変えていく。当時を振り返ってそう考える杜さんは、留学の前と後とでは、自分に変化があったと言います。

奨学生時代、さまざまな出身国の人たちとの交流が、杜さんの人生観を大きく変えたそうです。写真:杜さん提供
奨学生時代、さまざまな出身国の人たちとの交流が、杜さんの人生観を大きく変えたそうです。写真:杜さん提供
杜さん:私は、以前、「能力のある人」に注目し、そればかりを評価する“悪い習慣”を持っていたのだと思います。しかし、パナソニック スカラシップの交流の場では、それぞれが役割を担います。スタッフの方々もそれぞれの奨学生に色々な行動の機会を持たせるような配慮をしてくれました。出身国も年齢も日本語の能力もさまざまでしたが、そんなことは関係なく、同じ体験に同じような気持ちを持ち、共感し合うことができる。この頃の経験は、私にとってとても大きなものとなりました。
大学院では、将来のIT技術の研究に携わっていた杜さんでしたが、修士課程を終え、修了後の進路を考えたときに日本のIT企業を選択することにしました。研究に専念できる環境と企業の活動の両面を知ることができたパナソニック スカラシップの奨学生だから選んだ道だと言います。
杜さん:大阪のパナソニックの会社を訪問したり、「松下幸之助 歴史館」を見学したりする機会がありました。私たち留学生が驚いたのは、経営者個人だけでなく、企業としての理念があり、それが社員にも浸透していることです。さらに、その驚きを話し合う中で私たちは、「日本の企業は人を育てる」ということに気づきました。これは、私が将来を考えていた中国の企業風土とは違うものです。どちらが良いとか悪いとかということではなく、その「違い」は日本だから体験できるものだと、とても興味を持ちました。私は「日本の企業で学び自分を成長させたい」と決めたのです。3年前、「修士課程に進む」という進路の1つの道として日本留学を決めた時には、考えてもいなかった未来が私の前にありました。
杜さん:私は、以前、「能力のある人」に注目し、そればかりを評価する“悪い習慣”を持っていたのだと思います。しかし、パナソニック スカラシップの交流の場では、それぞれが役割を担います。スタッフの方々もそれぞれの奨学生に色々な行動の機会を持たせるような配慮をしてくれました。出身国も年齢も日本語の能力もさまざまでしたが、そんなことは関係なく、同じ体験に同じような気持ちを持ち、共感し合うことができる。この頃の経験は、私にとってとても大きなものとなりました。
大学院では、将来のIT技術の研究に携わっていた杜さんでしたが、修士課程を終え、修了後の進路を考えたときに日本のIT企業を選択することにしました。研究に専念できる環境と企業の活動の両面を知ることができたパナソニック スカラシップの奨学生だから選んだ道だと言います。
杜さん:大阪のパナソニックの会社を訪問したり、「松下幸之助 歴史館」を見学したりする機会がありました。私たち留学生が驚いたのは、経営者個人だけでなく、企業としての理念があり、それが社員にも浸透していることです。さらに、その驚きを話し合う中で私たちは、「日本の企業は人を育てる」ということに気づきました。これは、私が将来を考えていた中国の企業風土とは違うものです。どちらが良いとか悪いとかということではなく、その「違い」は日本だから体験できるものだと、とても興味を持ちました。私は「日本の企業で学び自分を成長させたい」と決めたのです。3年前、「修士課程に進む」という進路の1つの道として日本留学を決めた時には、考えてもいなかった未来が私の前にありました。
「違い」を「誤解」にしない「つなぎ役」になる
「違い」を「誤解」にしない「つなぎ役」になる
杜さんは、修了後、日本のIT関連企業に就職。そこでは日本の製品開発を中国の企業に依頼していました。そして現在は中国の通信機器メーカーの日本法人に勤め、中国製品を使ったソリューションを日本企業に提案する立場にいます。ITの発達、日中の産業構造が大きく変わる20年間を見てきた杜さんは、自分を「つなぎ役」だと言います。
杜さん:なぜ日本の製品に関わる営業職に、外国人である自分が必要なのか? 周囲の人の中にはそうした気持ちを持った人もいたでしょう。実は、私自身も大学で研究した道筋の上ではない所に立ち、自分の価値とは何かとあらためて考える機会となりました。
杜さんは、自分という人間の「背景」をふり返って見ると、パナソニック スカラシップで来日してから得た、日々の経験から得た考えの変化を実感しました。国と国、人と人の「違い」を知っているからこそ双方の立場を理解できる。その両者の橋渡しができることが、自分の価値だと気づいたそうです。
杜さん:私は中国人と日本人の「違い」について考えることがあります。日本の高品質でハイスペックな製品と海外のニーズ・価格帯の違い。日本企業の几帳面なスケジュール管理と海外の企業風土の違い。「違い」は、時に互いに誤解を生んでしまうことがあります。でも「違い」を説明し、コントロールできれば、ビジネスの現場で合意することはできます。その「つなぎ役」は私の使命だと思っています。
杜さんが見いだした自身の役割。それはパナソニック スカラシップによる日本留学をきっかけに広げた視野で知った「世界中の人と人は、違う部分よりも共通の部分のほうが多い」という実感に基づいています。
杜さん:同じ場で同じものを見たら、心に感じるものは同じです。どうしても最初は「国」のような大きな枠組みや先入観で互いを見てしまいますが、この人も必ず同じことを感じてくれる、共感してくれる、そう信じてビジネスにも携わっています。そうした先入観は、自分自身にも持ってしまうもの。同じ言語・文化・環境の中にいると、限られた視野と考え方しか持てません。私は、若い人は誰もが海外に出て、異なる環境や文化を経験するべきだと思います。「こんなふうにしてもいいんだ」と考えることができれば、自分の可能性を広げることもできます。
杜さんは、修了後、日本のIT関連企業に就職。そこでは日本の製品開発を中国の企業に依頼していました。そして現在は中国の通信機器メーカーの日本法人に勤め、中国製品を使ったソリューションを日本企業に提案する立場にいます。ITの発達、日中の産業構造が大きく変わる20年間を見てきた杜さんは、自分を「つなぎ役」だと言います。
杜さん:なぜ日本の製品に関わる営業職に、外国人である自分が必要なのか? 周囲の人の中にはそうした気持ちを持った人もいたでしょう。実は、私自身も大学で研究した道筋の上ではない所に立ち、自分の価値とは何かとあらためて考える機会となりました。
杜さんは、自分という人間の「背景」をふり返って見ると、パナソニック スカラシップで来日してから得た、日々の経験から得た考えの変化を実感しました。国と国、人と人の「違い」を知っているからこそ双方の立場を理解できる。その両者の橋渡しができることが、自分の価値だと気づいたそうです。
杜さん:私は中国人と日本人の「違い」について考えることがあります。日本の高品質でハイスペックな製品と海外のニーズ・価格帯の違い。日本企業の几帳面なスケジュール管理と海外の企業風土の違い。「違い」は、時に互いに誤解を生んでしまうことがあります。でも「違い」を説明し、コントロールできれば、ビジネスの現場で合意することはできます。その「つなぎ役」は私の使命だと思っています。
杜さんが見いだした自身の役割。それはパナソニック スカラシップによる日本留学をきっかけに広げた視野で知った「世界中の人と人は、違う部分よりも共通の部分のほうが多い」という実感に基づいています。
杜さん:同じ場で同じものを見たら、心に感じるものは同じです。どうしても最初は「国」のような大きな枠組みや先入観で互いを見てしまいますが、この人も必ず同じことを感じてくれる、共感してくれる、そう信じてビジネスにも携わっています。そうした先入観は、自分自身にも持ってしまうもの。同じ言語・文化・環境の中にいると、限られた視野と考え方しか持てません。私は、若い人は誰もが海外に出て、異なる環境や文化を経験するべきだと思います。「こんなふうにしてもいいんだ」と考えることができれば、自分の可能性を広げることもできます。

杜さんの近影。外の世界に飛び出し、視野を広げたいと考えています。写真:杜さん提供
杜さんの近影。外の世界に飛び出し、視野を広げたいと考えています。写真:杜さん提供


