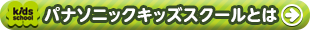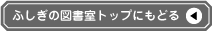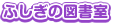
-
年を取ると、シワができるのはなぜ?
-
学校は昔から6さいで入るもの?
-
子どもの歯(は)はどうしてぬけるの?
-
七五三(しちごさん)は、どうして7才、5才、3才にするの?
-
大人と子どもで薬の量(りょう)がちがうのはなぜ
-
太陽は何さい?
-
年を取ると、こまることあるの?
-
年を取ると、かみが白くなるのはなぜ?
-
どうして人は死ぬの?
-
大人はどうしてひげが生える?
-
赤ちゃんのおしりにある青いあざは何?
-
「こどもの日」ってどういう日なの?
-
生まれたばかりの馬の赤ちゃんが歩けるのはなぜ?
-
干支(えと)ってなに?
-
人間は何歳(さい)まで生きていられるんですか?
-
なぜ爪(つめ)や髪(かみ)の毛が自然に生えるんですか?
-
髪の毛はいつまでも伸び続けるの?

学校は昔から6才で入るもの?
みんなが通っている学校、日本では元々(もともと)は寺子屋といって、ずっと昔、室町時代(むろまちじだい)にできたんだ。始めのころは、身分の高い家の子どもたちが通っていたんだけど、農民や町人の子どもも通うようになった。寺子屋には、みんなの教室にあるような黒板やいすはなくて、机(つくえ)だけで勉強していた。
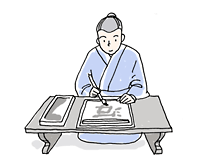
先生は、お坊(ぼう)さんや神主(かんぬし)さん、またはお侍(さむらい)さん。一つの寺子屋には7~13才までの子どもが20~30人集まって、読み書きのほかに、そろばん、手紙の書き方など、暮(く)らしに役立つことを学んでいた。これが学校の始まりだ。