Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs 国内助成 成果報告会
9団体による成果発表を聞き、
自団体の組織基盤強化を考える
2024年2月27日、パナソニックセンター東京(東京都江東区有明)で「Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs」国内助成の成果報告会を開催しました。対面での開催は今回が初めてとなります。成果報告会には、2022年度募集の組織診断や組織基盤強化に取り組んだ9団体のうち8団体の皆様、選考委員、事務局、これから組織基盤強化に取り組む団体の皆様などが参加しました。動画での発表も含めて9団体の成果発表の後には、質疑応答や選考委員からの講評の時間を設けました。それぞれの団体が抱える悩みや解決方法を自分たちの団体に置き換えながら、議論を通して、組織基盤強化に対する理解を深めることができました。
●開会挨拶
人には話しづらいことも共有し、仲間づくりの場に
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 企業市民活動推進部 部長 福田 里香
今年は年初から心の痛むことが起こり、私たちも何かできないかと、能登半島地震の状況を確認するために、スタッフが現地に入らせていただく予定です。また、風評被害に苦しむ福島の県産品を社員食堂で食べることで応援する「福島『復興』応援アクション」も続けております。パナソニックグループは、事業活動と企業市民活動を車の両輪のように進めてきましたが、その活動もNPOの力がなければ前には進みません。とはいえNPOも組織なので、いろいろな課題が出てきます。そこで、私たちは組織基盤の強化を支援させていただいていますが、応援してきた団体が組織を強化され、多方面で活躍されているのを伺うと本当にうれしく思います。一人の人間や一つの分野だけで解決できる課題は、ほとんどありません。今日は、人には話しづらい困難なことも悩ましいことも共有して、団体自身を強くするのと同時に、お互いにコミュニケーションを取り、仲間づくりもできるような場にできればと思っています。

●第1部 組織診断の成果報告
自転車操業状態の組織を立て直すために組織診断
一般社団法人 やまがた福わたし 代表理事 伊藤 智英さん
食のセーフティネットとして生命を守るために、フードドライブやフードバンク活動を行っています。コロナ禍で活動エリアが広がり、食品が10トン増え、経費も増大。助成金や寄付に頼らざるを得ない自転車操業の状態で、組織構築のために応募しました。まずは全員に助成事業の内容を説明。コンサルタントとのミーティングを重ね、寄付者へのアンケートや理事・ボランティア・寄付者へのヒアリングを実施しました。その結果、みんなが倉庫が狭いと感じていることがわかり、外部倉庫に一部を移動。准ファンドレイザーの資格を取り、寄付者の思いを知ったことは、今後のファンドレイジングに活かすことができます。さらに、県議5名にフードバンクの説明をしたところ、県にフードバンクの窓口ができることに。今後は運営資金を強化し、幅広い年齢層のボランティアを増やしていきたいです。

フルリモートから対面で組織の強みや課題を共有
特定非営利活動法人 多様な学びプロジェクト 理事 梅林 千香子さん
不登校の子どもや保護者、不登校の子どもの居場所の運営者に向けた事業を行っています。不登校の子どもは増加し、団体への期待は高まっていますが、メンバー全員がフルリモートで、ビジョン・ミッションのすり合わせが足りず、自律的な運営ができていなくて、財政基盤も脆弱でした。そこで、まずはメンバーへのアンケートに基づく組織診断を行い、ステークホルダーへのアンケートとその分析、2度の合宿を実施しました。メンバー全員が対面で話し合う時間をもてたことで、メンバー間の相互理解が深まり、団体の魅力や強み、課題を共有。不登校の当事者が自分の言葉で発信でき、支援される側から自立して活動主体となれる場を提供していることの価値を再確認できました。今後は、ビジョン・ミッションの再検討と動画研修サイトの新設、伴走支援プログラムの開発をしていきたいと思っています。

内部・外部の評価を知り、世代交代に一歩踏み出す
認定特定非営利活動法人 陽だまり 代表理事 市川 マヤさん
東広島で市民の助け合い活動、高齢者や障がい者の訪問介護、学童保育、コミュニティカフェなどを行っています。設立から20年ですが、慢性的な資金不足や中心メンバーの高齢化などが悩みで、団体の現在地と10年後の姿を明らかにしたいと考えました。まずは内部の役員・職員・ボランティア・会員、外部の利用者・寄付者・事業パートナーにアンケートとヒアリングを行い、コンサルタントとの組織診断で課題を明らかに。解決の方向性を見いだしました。団体への評価が予想外に高く、関係者のモチベーションが上がり、チームワークも強化されました。外部関係者とのパートナーシップも深まり、コラボ企画が進んでいます。世代交代を意識した採用活動をしたことで、3人の利用者がスタッフになりました。スケジュールが3ヵ月遅れ、2年目は採択されませんでしたが、自己資金で診断結果の分析からやり直そうと思っています。

●質疑
3団体からの発表後、会場からは、やまがた福わたしに対して「県議5名にアプローチをしたとのことですが、その方々とはどのようにつながったのですか?」との質問が出ました。やまがた福わたしの伊藤さんは、「すべての会派の議員さんに自分たちでアポイントを取り、資料を用意し、団体の活動状況を説明しにうかがいました。議員さんたちはフードバンクという名前は聞いたことがあるけど、どんな活動をしているかは知らなくて、何人かの議員さんが継続的に困り事はないか、連絡をくださるようになりました」と答えました。

●選考委員からの講評
関係者と専門家の意見を多角的に採り入れる
特定非営利活動法人 ワンファミリー仙台 理事長 立岡 学さん
私も4つほど団体を経営しているので、どうやって継続していくか常に考えています。組織基盤強化で皆さんが最初に取り組んだ組織診断で共通していたことは、関係者みんなの意見を聞くこと。そこから組織というものを考えていくというのが、この1年目の事業なのだと思います。それぞれが会って、多様な意見を聞く中で、自分たちの組織を見つめ直した、その成果を今日聞くことができました。どの団体も地域からなくなっては困る存在になっていて、いろいろな人の意見を吸い上げるところは吸い上げ、調整するところは調整することが大事なのだと思います。どうしても助成金頼みになってしまうのはわかりますが、委託事業も一定程度あったほうがいいし、自主事業も半分くらいはあったほうがいいでしょう。専門家にも入っていただいて、その視点を素直に受け入れると同時に、みんなで話し合い、そこで出た意見を多角的に採り入れながら、前に進めていくことが大事だと思います。

●第2部 組織基盤強化の成果報告
【基盤強化1年目】
円卓会議から千葉県最大のネットワークが誕生
特定非営利活動法人 多文化フリースクールちば 理事長 白谷 秀一さん
外国につながる学齢期を過ぎた子どもたちに日本語を教える活動を始めて10年目で、163人を高校に入学させました。代表の私と講師から成る団体ですが、コロナ禍で生徒が急増。事務局体制強化のために応募しました。教室として借りている会議室が大規模改修のため、新たな教室も探す必要がありました。助成1年目は東京や神奈川、茨城などの他団体を視察。土地の特徴をつかんだ資金集めを勉強させてもらいました。教育と福祉の一体化に向けて、行政や教育委員会を交えた円卓会議も2度開催しました。まだ半分しかできていませんが、10年史の編集も進めています。成果としては、福祉・教育団体が一体となった千葉県最大のネットワークを設立することができ、千葉県も日本語学習の就学指導を行う団体に助成金を出してくれることになり、24時間使える新しい教室を借りるめどが立ちました。

急拡大した組織の働き方や財政基盤を改革
特定非営利活動法人 サンカクシャ 代表理事 荒井 佑介さん
若者の居場所づくりや仕事・住まいの支援をしています。2019年に設立し、コロナ禍で相談が増え、年間20本くらいの単年度の助成金を中心に運営していて、自転車操業状態でした。まずは自分たちの事業を5つのステップに分けてモデル化。若者1人が自立するまでのコストを算出しました。中期ビジョン・中期計画を策定して、全員が兼業のスタッフの働き方改善や人事制度の整備をし、事業ごとに5人のリーダーを置いて、現場を託すことにしました。さらに、財政基盤強化のためにファンドレイジングチームを立ち上げ、法人寄付に力を入れていくために法人営業担当を採用。寄付の比率が20%くらいまで増えました。その過程で、自団体の活動を広げるだけでなく、全国に担い手を増やすことも必要だと気づきました。何より、代表である私自身の働き方が変わったことが1番の成果だったかもしれません。
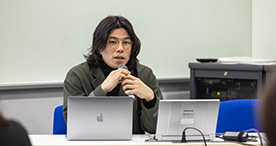
●質疑
2団体の発表を終えて、参加者からサンカクシャに、「兼業のスタッフが20数名いるとのことですが、なぜ兼業なのか教えてください」との質問がありました。これに対し、サンカクシャの荒井さんは、「お笑い芸人をしていたり、他のNPOの手伝いで認定ファンドレイザーをしていたり、活動を通して出会った地域の人から仕事をもらったりしているスタッフもいます。週5日も若者と関わっていると、いやになってしまうので息抜きのため、という意見もありますし、兼業することで他の視点を得たり、いろいろなつながりが活動に活かせたりするので、兼業を推奨しています」と回答しました。

●選考委員からの講評
見落とされがちな子ども・若者の支援に重要な役割
神奈川県立保健福祉大学 准教授 吉中 季子さん
多文化フリースクールちばは、文科省と厚労省のはざまにいる子どもたちを支援していて、教育と福祉のマッチングに苦労しているというお話が印象に残りました。そんな中で、両方の立場から、円卓会議に集まってもらったのは大きな成果です。自分たちがどんな哲学と理念をもって活動してきたか、実践の経緯と実績を10年史という形で残すのも本当に大事なことです。見落とされがちな子どもたちが増えてきた中で、非常に重要な活動だと思います。私も大学生と関わる中で、若者の支援が制度から漏れやすいことは日々実感していますが、サンカクシャは、考え方や視野を広げる意味で、兼業を肯定的にとらえているところが新しいと感じました。ただ、年間20本の助成金は本当に大変だと思います。こういう分野は職人的なことが評価されがちですが、この1年で代表の考え方が変わったとのことなので、人材を増やすためにも、しっかり休んで、労働環境を向上させていただきたいと思います。

【基盤強化2年目】
継続的な支援者を増やすために発信力を強化
特定非営利活動法人 名古屋難民支援室 理事/コーディネーター 羽田野 真帆さん
東海地域に暮らす難民・難民申請者への個別支援、地域の方たちへの理解促進、ネットワーク構築に取り組んでいます。ボランティア登録者は114人いますが活動参加率の向上には課題があり、収入の9割が助成金で、継続した支援を続けるには基盤強化が必要でした。1年目は事務局と理事で、優先して取り組みたいことと課題を確認し合い、個別支援の質を高めることを第一に考えていることがわかりました。そのためには組織基盤が重要だと話せる雰囲気になったことが1番の成果です。私たちの活動は専門性が必要なので、関われるメンバーが限られています。そこで2年目は、活動に共感して継続的に寄付してくれる人を増やすために、ウェブサイトをリニューアルしました。新たなスタッフも加わって、FacebookやXの発信力を強化しました。自己資金を増やすための寄付を募るランディングページも新設し、そのエッセンスをまとめたチラシを作成しました。今後はその効果を検証しながら、一般向けの発信をさらに強化していきます。

急成長する組織を支える応援団の情報を一元化
特定非営利活動法人 こどもソーシャルワークセンター
理事長 幸重 忠孝さん
ソーシャルワーカー 鳴橋 杏里さん
滋賀県大津市を中心に、環境によって本来の力を発揮できない子ども・若者を地域で支える活動をしています。コロナ禍以降の急成長に組織が追いつかず、業務整理のために組織診断をしました。その結果、事務専門の職員がいないため、ファンドレイジングが弱く、たくさんのボランティアや寄付者がいるのにデータベースが統一されていなくて、情報発信力も弱いという課題が見えてきました。そこでまずは、専門支援の質を高めるために電子カルテシステムを構築。セールスフォースを導入して、応援団の情報を一元化し、新データベースに移行しました。法人を知ってもらうためにホームページをリニューアルし、団体紹介の冊子をつくりました。新データベース導入後は急激に寄付が増えました。電子カルテでソーシャルワーカー間の情報が共有されたことで、個別支援の見通しも立てやすくなりました。広報ツール作成の過程で、法人が大事にしてきたものや成長も実感できました。次は中長期計画を作成したいと考えています。

●質疑
基盤強化2年目の2団体からの発表後、会場からは、こどもソーシャルワークセンターに、「どうしてそんなにたくさんの応援してくださる方に囲まれているのでしょうか?」との質問が出ました。この質問に対し、こどもソーシャルワークセンターの幸重さんは、「居場所を求めて来ている当事者性の高いボランティアもたくさんいるので、職員は最初に1時間くらいかけて話を聞き、適材適所の役割を当て込みます。また、その時々の困り事はその日のうちに振り返り、場合によっては役割を変え、ありがとうをちゃんと伝えるようにしています」と答えました。

●選考委員からの講評
情報基盤をつくるプロセスへの参加がスタッフの力をつける
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 理事長 山岡 義典さん
(※選考委員の代理として講評)
名古屋難民支援室と子どもソーシャルワークセンターは全然違う種類の活動でしたが、基礎的な情報を整備し、それによって広報を行うだけでなく、仲間内でも共有した点が共通していました。情報というのは外に出すだけでなく、仲間内で共有されることの意味が非常に大きく、情報をつくる過程で、その情報がもつ深みを組織が身につけていくことも重要なのだと教えられました。情報基盤をしっかりつくるというプロセスに参加したことで、スタッフにも、それなりの力がついたのではないでしょうか。一定の経験を積んだところで、今まで自分たちが取り組んできたことの実態は何だったのか、きちんと分析して公表する。その基礎的な作業の上に、2年目の事業が成立しているように感じました。組織診断を行い、基礎的な情報整備を行った上で次のステップへと進む。2団体の取り組みは、ヒューマンサービス分野の団体における組織基盤強化のモデル的な方法論を体現していたと実感しました。
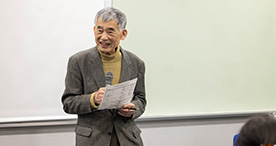
【基盤強化3年目】
メンバー間で目線を共有し、次の成長フェーズへ
認定特定非営利活動法人 PIECES 理事/事務局長 斎 典道さん
子ども・若者の孤立を防ぐために、子どもに関わる人の質の向上や市民性の醸成に取り組んでいます。設立から5年経ち、組織のフェーズが変化する中で中長期的な視点が必要になりました。コンサルタントが加わった組織診断では事業・組織・財務の課題が浮かび上がり、漠然とした不安が解消されて、メンバー間の目線が共有されました。2年目は、Citizenship for Childrenというコア事業の受講者へのヒアリングを通して、サービスモデルを再設計し、自分たちのよりどころとなるコアバリューを言語化。ファンドレイジングに力を入れるために、新しいスタッフも採用しました。3年目は、各地域の団体と協働で、コア事業のエッセンスを採り入れ、その地域に合わせた形で実施していけるように、コンソーシアム化に取り組みました。寄付に関しては、過去に支援実績のある企業とコミュニケーションを取ることで、単年で終わらない複数年の大口寄付につなげることができました。合宿などで対話を重ねたことで、ダイナミックな変化が起き、団体は次の成長フェーズに差し掛かっています。

相談体制の拡充に向け、相談員をレベルアップ
認定特定非営利活動法人 京都自死・自殺相談センター 理事 竹本 了悟さん
(※動画による発表)
死にたい気持ちを抱えた方や大切な人を自死で亡くされた方を対象にした電話相談・メール相談・対面での居場所づくりのほか、講演・研修の提供などを行っています。相談体制を拡充したい一方で、ボランティアの定着率の低さやスタッフ間の理念のずれといった課題を抱えていました。1年目はコンサルタントに入ってもらい、課題に優先順位をつけ、組織の3~5年後のイメージを共有して、解決の方向性を見いだしました。2年目はミーティングを重ね、団体内の文化や言葉を共有し、中期計画を策定。相談員の役割を再定義して、スタッフごとにまちまちだったトレーニングの頻度を上げたことで、感覚のずれを是正できました。3年目は理念継承のための組織体制をつくり、VR上での相談を見据えたチームビルディングやファンドレイジングキャンペーンに取り組みました。この3年間で中堅相談員のレベルアップを図れたので、次は、新規相談員の獲得につながる枠組みづくりとオンライン相談を模索していきたいと思います。

●質疑
基盤強化3年目の2団体による発表に続いて、参加者からPIECESに、「また新たな成長フェーズに差し掛かっているとのことですが、どんなフェーズを経て今に至ったのでしょうか?」との質問がありました。PIECESの斎さんは、「助成が始まるまでは、創業メンバーの思いでやってきて、でもどこかで行き詰まり感がありました。助成の間は、自分たちの目線を合わせ、散らかったものの整理が進みましたが、安定がもたらされたことで今度は新たなチャレンジへのエネルギーが生まれています。いい形の破壊と創造を経て、やっとここから次のPIECESが始まるという感覚が組織の中に広がっています」と回答しました。

●選考委員からの講評
実践で迷った時は理念やミッションに立ち戻る
神奈川県立保健福祉大学 准教授 吉中 季子さん
PIECESは、事業・組織・財務という3つの柱を3年間通して取り組んだことで、いろいろなものが見えてきたのではないかと思います。合宿では、さまざまな人が入り混じって、膝を突き合わせて話をされたということで、課題を整理することも大事ですが、いったん思いをさらけ出す場面も必要なのだと感じました。京都自死・自殺相談センターは、センシティブな問題に向き合う団体であるだけに、スタッフのケアやトレーニングが非常に重要です。相談と言うと、人と人がリアルに向き合うものを想像しがちですが、相談体制の拡充にあたっては、VR相談という新しい取り組みと従来の取り組みのいいところを取って、今後のスタイルとしていくのがいいのではないかと思いました。忙しいと、つい合理性や効率性に流されてしまいますが、皆さんの発表を聞いて、実践で迷った時に立ち戻る理念やミッションの重要さに気づかされました。皆さんの実践が広く知れ渡り、若い人がどんどん入ってくることを期待しています。

●選考委員長からの全体講評
組織を見つめ直す勇気と決断が大きな成果に
放送大学/千葉大学 名誉教授 宮本 みち子さん
選考委員長を仰せつかって5年になります。事業に対する助成と違って、組織基盤強化はやらなければいけないとわかっていながら、できれば避けたい。でも組織であれば避けられない。そんな取り組みです。この20年の間に、非営利組織の社会的位置づけは格段に高まりました。昨年4月に発足したこども家庭庁の準備段階に関わりましたが、審議会・委員会・部会には、以前にも増して非営利組織の方が入っていると聞いております。
組織には必ず立ち止まって、過去と未来を見つめ直さなければならない時期が来ます。今日発表された団体の皆さんは勇気をもって、その決断をし、取り組まれました。サポートファンドの助成では、外部からコンサルタントが入り、言われたくないことも言われます。その抵抗を打ち破って議論し、わかり合うプロセスが大きな成果につながったように思います。先日、日本の株価は史上最高値を更新しましたが、失われた30年が終わってほしいと願う一方で、貧困解消の活動が、そう簡単に必要なくなることはないとの思いもあります。孤独や生きづらさを抱えた人はコロナ禍によって、より顕在化しました。皆さんの活動が、ますます大事な時代になってくると思います。

●修了書贈呈
続いて、Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGsの国内助成で3年間の助成プログラムを修了したPIECESに、パナソニックの福田より、修了書を贈呈しました。

●参加団体からの感想
やまがた福わたし 伊藤 智英さん
「活動内容は少しずつ異なりますが、共通の課題があり、いろいろな取り組みの成果を聞くことができたので、いい部分を採り入れて、私たちも取り組んでいきたいと思います」
多様な学びプロジェクト 梅林 千香子さん
「2年目、3年目の先輩の団体のお話を聞いて、私から見ると出来上がっているイメージですが、次の成長の段階に入っているというお話もあり、自分たちの団体もまだまだ先があることを改めて自覚しました。2年目の事業を頑張っていきたいと思います」
陽だまり 石井 弥生さん
「皆さんの発表を聞いて、抱えている課題が共通していることを感じました。その中でも、団体内での情報共有・言語化・ファンドレイジングが大切なのだと改めて気づかされました」
多文化フリースクールちば 白谷 秀一さん
「代表自身の働き方が変わったというお話がありましたが、実は私もそうで、自分で全部運営することをやめたら、講師が自分たちで翌年の分担を決めてくれました。新しい教室が確保でき、千葉県も協力してくれることになり、これから本格的に進めていきたいと思います」
サンカクシャ 塚本 いづみさん
「創業メンバーは代表の荒井だけで、今ちょうどスタッフが急増中という状況で、スタッフを増やすのに重要になってくるのがコアバリューなのだと改めて思いました。いろいろな団体さんの実践がとても勉強になりました」
名古屋難民支援室 刈茅 豊さん
「ほかの団体さんも同じような悩みを抱えていて、安心したところが大きかったです。今、団体の中では、自己資金をどう増やすかということも話していますが、増やされている団体さんもたくさんいて、勉強させてもらいました」
こどもソーシャルワークセンター 鳴橋 杏里さん
「どこの団体さんも、思いや理念、言葉の共有ということを言われていたと思いますが、たぶん私たちの団体の現場の職員も同じ気持ちでいると思います。自分の団体に戻ったら、頑張って一緒につくり上げていきたいと思います」
PIECES 斎 典道さん
「一団体ですべてを完結させることの限界を感じていて、組織基盤強化のプロセスでも、ほかの団体さんとできることがあるのではないかと思いました。みんなの共通するところを重ね合わせて、この業界の基盤強化につながる取り組みができたらいいなと考えています」
●閉会の挨拶
リアルの会合で戻ってきたプログラム本来の力
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 理事長 山岡 義典さん
この3年間のコロナ禍による大波で、皆さんは大変な思いをされたのではないでしょうか。大きく発展した団体もある一方で、フィールド活動ができなくて、しぼんでいった団体があるかもしれません。私たち助成する事務局としては、リアルの会合をオンライン化したくらいで、特別なコロナ対応はしていませんが、今日のようなリアルの会合で交流を深め、仲間をたくさんつくって、お互いのエピソードを語り合うのが、このプログラムのいいところなので、本来の力がやっと戻ってきたという感じです。皆さんの中には、「組織基盤強化どころではないだろう」と言われながら、このプログラムに取り組んだ方もいたと思います。この3年間の貴重な経験を、ぜひ今後の活動に活かしてください。



