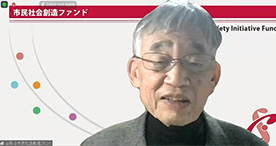Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs 国内助成 成果報告会
組織診断・組織基盤強化に取り組んだ
10団体が課題や成果を発表
2023年3月7日、オンラインで「Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs」国内助成の成果報告会を開催しました。成果報告会には、2022年に組織基盤強化に取り組んだ10団体の皆様と選考委員、事務局、2023年1月から組織基盤強化に取り組む団体の皆様など、35人の方々がご参加くださいました。10団体による成果発表の後には、選考委員からの講評や質疑応答の時間を設けました。コロナ禍での取り組みだったこともあり、つまずいたことや悩みなども共有しながら、今後の皆様の活動につなげていけるように、議論を深めることができました。
●開会挨拶
福島県産品を食べ、福島の復興を応援
フィランソロピー大賞に身の引き締まる思い
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 企業市民活動推進部 部長 福田 里香
コロナ禍やウクライナの戦争、トルコ・シリア大地震などで被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。パナソニックは福島県の風評被害に対し、県とパートナーシップを組み、福島県産品を食べることで応援する「福島『復興』応援アクション」を始めました。福島県産品を社員食堂で食べ、「ふくしまマルシェ」で買うことで、消費行動の変容を促しています。1918年に3人で創業したパナソニックは24万人の従業員を抱えるグローバル企業となり、事業活動と企業市民活動を車の両輪のように進めてきました。企業市民活動においてはSDGsの1番目に掲げられた「貧困」、「環境」と「人材育成(学び支援)」を重点テーマとして取り組んでいます。サポートファンドは組織基盤強化に取り組まれた団体や関係者の皆様のおかげで、企業フィランソロピー大賞を受賞することができ、改めて身の引き締まる思いがしています。
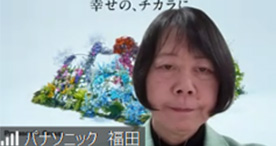
●第1部 【組織診断からはじめるコース】成果報告
継続的な運営に向けて優先課題を洗い出し計画立案
特定非営利活動法人 名古屋難民支援室 コーディネーター 中川 季紀さん
東海地域の難民や難民申請者が法的に保護され、安定して自立した暮らしを送れるように支援しています。コロナ禍で入国者数は減った一方で、生活や雇い止めに関する相談は増え、継続的な運営のために活動を見直すことにしました。週1回の外部コンサルタントとの打ち合わせと月1回の理事会での進捗報告を行いながら、課題点と解決方法の洗い出しワークショップや組織基盤に関する他団体へのヒアリング、広報活動の検討を実施し、単年度・中長期目標を立案しました。その結果、支援・団体運営・ファンドレイズ・広報が優先課題であるとわかり、組織基盤強化を見据えた計画を練ることができました。
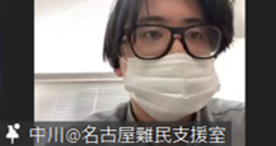
急拡大した組織の課題とファンドレイジングを見直す
特定非営利活動法人 こどもソーシャルワークセンター 理事長 幸重 忠孝さん
貧困や虐待など、家庭や学校の環境によって力を発揮できない子ども・若者に居場所を提供し、地域のボランティアがサポートしています。コロナ禍を機に組織が急拡大し、民間助成金によって財政規模も拡大しましたが、寄付集めには苦戦していました。コンサルタントが職員にヒアリングを行い、月1回のグループワークを通して、課題や優れている点をフィードバックすることで、職員は自信をつけていきました。子ども・若者のデータベースの電子カルテ化にも取り組みました。同時に、寄付者へのお礼が不十分で、顧客データの重みづけがされていないという課題も明らかになったので、今年もファンドレイジングに取り組んでいきます。
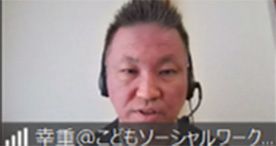
結束力と発信力を高め、外部とのつながりを強化
特定非営利活動法人 おかえり
事務局長 中川 陽介さん
評議員 並川 典子さん
里親家庭や児童養護施設等を巣立った子どもたちが気軽に戻ってこられる心のよりどころを目指して、支援をしています。すべてが理事長中心の組織体制で、事業も担当職員も重なり合っていました。そこで、月に1度、全体でのディスカッションを行うことで、課題を出していきました。その中で、業務分担の仕組みができていない、自主財源が少ない、効果的な発信ができていない、といった課題が出され、解決策を検討していきました。組織内でミッションや価値を共有したことで結束が強まり、外部とのコミュニケーションも円滑になりました。2月末にはHPのリニューアルを行い、今は業務分担の立て直しに取り組んでいる最中です。

●【組織診断からはじめるコース】講評
つらい意見も真摯に受け止める力が支援する力の源
神奈川県立保健福祉大学 准教授 吉中 季子さん
日本の難民認定は排除そのもののようなところがありますが、何にでも優先順位をつけたがる風潮の中で、置き去りにされがちな他国の人を支援する名古屋難民支援室の活動は、誰一人取り残さない支援の象徴だと思いました。事業の課題に関しては、詳細なシートを作成し、支援・運営・ファンドレイジングと具体的に分類して、他団体の取り組みをヒアリングし、2年目に向けて課題を抽出されていたのが、計画性があってよかったのではないかと感じました。

こどもソーシャルワークセンターは、コロナ禍で利用者が増加しているということで、業務の集中や権限の集中というところに課題を感じておられました。組織診断というと、ドラスティックな改革をしなければと思いがちですが、見過ごされそうな小さな仕事まで分析し、手元の仕事から見直して、改善していくことも重要なのだと気づかされました。ほかにも、寄付者への返礼として対話をしていくことで、団体を外部から支えてくれる方々の思いを汲み取る等、学びたいことの多い事例でした。
おかえりは、子どもから大人になっていく支援の薄れそうなところをアフターフォローされていて、常に子ども主体で、子どもたちが感じてきたスティグマも理解された上で、寄り添った支援をされていると思いました。ミーティングを重ねても、意見が割れることがなかったのは、職員同士のリスペクトがきちんとあったからでしょう。そして基本のミッションに立ち戻り、これを共有していくことで、コミュニケーションを強めていったのではないかと思います。
組織機基盤強化は試験をされているようで、つらい作業かもしれませんが、そういう意見を真摯に受け止める皆さんの力が、支援する力の源になっているのだと思います。
●第2部 【組織基盤強化コース1年目】成果報告
理念の浸透と多職種連携により人材を強化
一般社団法人 Burano 理事 秋山 政明さん
障がいの有無にかかわらず個性が輝く社会をつくるために、茨城・栃木・埼玉の障がい児や家族の支援、地域啓発などを行っています。医療的ケアには人が何よりも重要なので、法人運営の強化に加えて、採用基盤を整え、職員間の連携を強めたいと考えました。外部コンサルタントのサポートで、理事会・社員総会の権限を明確化し、採用の人材要件を可視化した結果、4名の採用に成功しました。理念浸透・多職種連携の研修も4回実施し、自己理解を深めることで、職種を超えた互いの理解を深めていきました。職員さん一人ひとりの声をもとに理念ブックをつくり、次は、その理念を日々の業務に落とし込んでいく展開を考えています。

スタッフインタビューをもとに労働環境の課題を分析
特定非営利活動法人 ぱっぷす 理事長 金尻 カズナさん
主に10~20代の性的搾取やデジタル性暴力に遭った方の総合的な支援をしています。コロナ禍による失業などの収入減で性的搾取に巻き込まれる人が増え、相談が急増。スタッフの労務管理やメンタルケア、教育に手が回らなくなりました。そこで、コンサルタントがスタッフ20人に個別インタビューを行い、課題を分析。待遇面での不安の声が多く聞かれました。月に1回、担当スタッフとコンサルタントがミーティングを重ね、寄付をどう集めるかについても検討しました。AV被害防止・救済法のロビー活動で中断することもありましたが、ビジョン・中長期目標・事業計画の一連の流れを可視化し、事業計画づくりにスタッフ全員が関わることが力を引き出すカギだとわかりました。

●【組織基盤強化コース1年目】講評
組織基盤強化は対象者と、そこで働いている人のため
認定特定非営利活動法人 抱樸 理事長 奥田 知志さん
組織基盤強化は何のためにするかというと、対象者とそこで働いている人のため。そこをいかに効率化するかと共に、一人の人をどう大事にするかという点で、Buranoの思いの可視化はいい取り組みだと思いました。一方で、身内の責任論や家族主義が強い社会では、家族支援と共に、家族の領域をどう広げて社会化し、地域で支えていくかがテーマになってくると思います。9割近くが自主事業で、今後はファンドレイズを強化したいとのことでしたので、事業の確実性とファンドレイズの自由さとの組み合わせにもチャレンジしていかれることを期待しています。
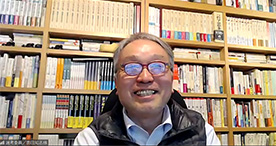
ぱっぷすは、ロビー活動に対する誹謗中傷で、大変な苦労をされたことと思いますが、性的搾取の問題に終止符を打つという姿勢はとても大事で、何があってもやり続けてほしいです。私も困窮者・ホームレス支援をしていますが、そうすると必ず反対運動が起きます。地域の反対運動は、昨日まで頑張ってと言っていた人から出て行けと言われるつらさがあります。その中で本当のミッションが問われ、本当に時代に合ったニーズなのかが問われる。そうやって、ブラッシュアップされていくのだと思います。これからも応援しています。
●【組織基盤強化コース2年目】成果報告
業務分担を見える化し、日々の活動の目的意識も向上
特定非営利活動法人 アダージョちくさ 理事長 榎本 美保子さん
名古屋市で精神障がい者への支援をしています。就労継続支援B型事業所と作業所型地域活動支援事業所を運営していますが、家族会からNPO法人化したため、理事会や事務局の機能・役割を明確にし、人材を育成する必要がありました。1年目は、行政書士による第三者組織評価と税理士による財務分析を実施し、クロスSWOT分析による戦略立案の方策を検討。グループワークで強みや課題を明らかにしました。2年目は、非常勤職員の資格手当の規定を改めるなどしてガバナンスを強化し、業務分担を見える化して指示命令系統と責任の所在を共有しました。

さらに、何をしていくべきか自分たちで判断していけるように、グループワークでミッションやクレドを策定し、評価モデルをつくりました。その結果、担当が分散して負担が軽減。日々の活動の目的意識と自身の行動評価意識も向上しました。
100回のチームミーティングが人材育成の機会に
一般社団法人 サステイナブル・サポート マネージャー 徳永 百合名さん
岐阜市で、主に精神障がい・発達障がいのある人や、さまざまな生きづらさを抱えた人の就労支援をしています。ここ数年で事業数・職員数が急増し、さまざまな課題が表出しました。1年目の組織診断では、中堅職員3名を主体とするタスクフォースメンバーの議論を全社ミーティングで共有し、ワークショップ形式で課題を整理しました。2年目は約30人の全職員をA~Cチームに分け、それぞれ「人を育てる仕組みづくり」「組織内コミュニケーションとやり甲斐の強化」「団体の強みの見える化とガバナンス強化」というテーマで課題解決に取り組み、代表理事とタスクフォースメンバーのみのDチームでは「団体の目標設定」に取り組みました。

4回の全社ミーティングと100回のチームミーティングを重ねながら計18個のアクションを遂行。それぞれの課題が解決に向かうと同時に、普段の業務では得られない中核的な人材育成の機会にもなり、スタッフの力量形成につながりました。助成終了後も、この実践を継続しています。
相談体制の拡充に向けて役割を明文化し、組織力アップ
認定特定非営利活動法人 京都自死・自殺相談センター 広報発信委員長 中川 結幾さん
2010年から、自死の苦悩を抱えた人の孤独をやわらげるために、電話やメールでの相談や、直接集まる居場所の提供をしています。年々相談のニーズは増えている一方で、チームとして理念の継承が図れていないことや、今の財政規模や体制では、長い目で団体を続けていくことが難しい点が課題でした。1年目の組織診断ではコンサルタントが入って、理事や運営メンバー、現場に長く関わる人、現場から離れた人にヒアリングを実施。運営メンバーや理事によるワークショップで思いや違和感を共有し、役割を明文化しました。

2年目は、団体内の文化や言葉の変遷を共有し、運営委員会の役割の違いを言語化。1年目のヒアリングをもとに、中長期計画を策定しました。その結果、理念継承の仕組みをつくることができ、相談員の役割の再定義も進みました。相談窓口をどう拡充していくかの方向性も定まったので、新規相談員の獲得やオンライン上での相談に向けて歩みを進めていきたいと思います。
小さな声まで聞くことで、慣習的運営から脱皮を目指す
認定特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター 事務局 上坂 紗絵子さん
安心してかかれる精神医療の実現に向けて、精神科病院に入院中の当事者の相談に乗り、大阪府内の全精神科病院を訪問しています。活動参加者も財政規模も拡大しましたが、助成収入の割合が大きいことが課題で、慣習的運営からの脱皮を目指し、組織診断に取り組みました。1年目は活動参加者へのアンケートや役員・運営会員・事務局へのヒアリングから強みと弱みが明らかになり、謝礼規定や就業規則を整理し、事務局の役割分担を進めました。2年目は、限られた人の声が反映されることの多かった理事会に、相談・政策提言・広報の3班から成る運営会議をつくり、各班長と事務局でリエゾン会議を開き、意見をまとめて理事会で検討しました。

さらに、活動参加者交流会で参加のきっかけを語り合い、経験交流会で入院中の当事者との面会における課題と解決方法を整理。優先順位をつけて2023年度の計画案に反映しました。それらの結果、これまで発言しなかった人も積極的に提案するようになりました。
団体のPRと連携の強化により自己資金を確保
特定非営利活動法人 NPOホットライン信州 事務局長 傳田 清さん
2011年から、誰もが「居場所・出番・自立・生活の改善」ができる地域社会を目指し、長野県で24時間365日の無料電話相談やフードバンク事業、子ども食堂の運営サポートを行っています。高齢の専務理事1名が全活動の管理を行い、収入の96%を助成に依存しているのが課題でした。1年目は私が新事務局長に就任して、スタッフの勉強会を開き、県と連携して、SDGs企業セミナーや子ども食堂セミナーを実施。飲料メーカーとのコラボで、子ども食堂自動販売機を84台設置しました。2年目はメディアに74回露出し、ホームページを更新。274万円の自己資金を確保できました。

6カ所だった活動拠点も10カ所に増え、80tだったフードバンクへの寄贈は200tに。90カ所だった子ども食堂も130カ所に増え、スタッフが自主的に運営にも関わるようになりました。社会福祉協議会と協働で、子どもの居場所づくりや、児童養護施設の子ども・若者のサポートも進めているところです。
●【組織基盤強化コース2年目】講評
人の重要性とミッションと情報共有が全体に共通するテーマ
神奈川県立保健福祉大学 准教授 吉中 季子さん
アダージョちくさは課題の分析が精巧で、緻密に考えられているように思いました。職員のワークショップでは模造紙を使ってクレドを策定していましたが、紙に書き出す作業は一見アナログで非効率に見えて、その作業自体が職員の間で時間や考えを共有し、確認し合うことになるので、参加者のつながりを得るにはもってこいなのだと教えられました。非常勤の方の労働環境を整備されたのも、財源的に厳しいNPOとしては思い切ったことで、働く意欲ややり甲斐につながりますし、他のスタッフにもいい影響を与えると思います。

サステイナブル・サポートの取り組みは、対象者をそれほど限定せず、ゆるやかに支援されていて、柔軟性が感じられました。ある時は保護猫カフェの運営をするなど、面白い取り組みだからこそ、制度のはざまにある人たちをカバーすることができるのだと思いました。100回ものミーティングを開き、18ものアクションを実践したところに本気度を感じました。そのエネルギーを維持することで、皆さんの間に共有意識が生まれたのだと思います。
全体に共通するテーマは、人の重要性とミッションと情報共有だと思いました。情報共有は私が関わっている団体でも課題が多く、一言で情報共有と言っても、日々の業務から職員の思い、個人情報まで、さまざまなレベルがあり、皆さんがそれぞれに工夫をこらしているのを感じました。
理解ある寄付者を育てることが社会の意識を変えていく
認定特定非営利活動法人 抱樸 理事長 奥田 知志さん
京都自死・自殺相談センターの孤独をやわらげるという活動は、エビデンスベースで議論が進んでいく世の中では、わかりにくい世界。だからこそ理念の共有化が大事になったのでしょう。ソーシャルワークの世界は解決型の支援に特化しすぎていますが、解決しなくてもつながっている伴走型支援のほうが意味のあることだと思っています。一方で、理念とは異なる時間軸の中長期計画も、組織としては立てないといけない。自死願望をもつ人の緊急対応やアウトプットのために、社会とどう連携していくかも課題になってくると思います。
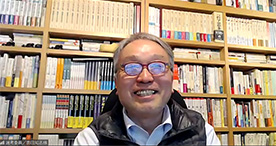
大阪精神医療人権センターは、中長期計画がまとまらなかったのも、それはそれでいいと思います。そもそも中長期計画は機が熟さないと出てこない。一方で、いろいろな声が届き始めて、解決案も出てきているようなので、次の段階では誰がするのかという問題にぶつかるでしょう。とは言え、プロジェクトも時と出会いこそが大事なのだと思います。なぜ精神の領域がこれほど嫌われるのかと考えた時に、そこには障がい者差別があると思うので、外部の声を聞く時は関係者だけでなく、少しだけ耳障りな声も入れたほうがいいかもしれません。
NPOホットライン信州は、フードバンクや子ども食堂に取り組まれていますが、これだけ市民権をもっているのに、資金提供も含めて、支える体制が全然整わない分野も珍しいと思います。悪く言う人はいないのに主体的な関わりが少なく、これをどうしていくか苦労されているようなので、そこをぜひ頑張っていただきたいと思います。
全体に言えるのは、寄付は経費が2割で、事業に使えるのは8割くらいと考えておいたほうがいいということです。ネットに広告を出せば、それだけでお金がかかります。そういう事業としての運営を理解できる寄付者をどう育てるかがNPОの生命線で、それ自体が社会の意識を変えていくことにつながるのだと思います。
●選考委員長による全体講評
相談員を確保し、質を担保する採用基盤の強化も重要
放送大学/千葉大学 名誉教授 宮本 みち子さん
成果報告をしていただいた10の団体は、厳しい状況に置かれている人に、草の根の一番大変な支援をしている団体ばかりでした。民間団体の地を這うような対人サービスで、今の日本はもっているのだと感じました。一方で、大事な活動を担い、力をつけなければならない団体ほど日々の活動に追われ、組織改革をする機会がないのも現状です。サポートファンドはそこに目をつけ、コンサルタントが団体と一緒に組織診断と組織基盤強化に取り組む活動です。どの団体も代表が、今組織改革に取り組まなければ組織はもたないと強く感じて本気になり、その決意が職員に伝わって、その気になることで成果を上げたことが伝わってきました。

深い悩みをもつ生身の人間に対する活動だけに、相談員の数を確保し、質を担保することも重要で、採用の基盤を強化することが組織基盤の強化にもつながるのだと思います。問題意識をしっかり受け止め、地道に丁寧に改革に取り組まれた皆さんに感服しました。
●修了書の贈呈
「組織基盤強化コース」に2年間取り組んだNPOホットライン信州には、パナソニックの福田より修了書を贈呈しました。

●閉会挨拶
発表に触発され、学び、成長していったプログラム
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 理事長 山岡 義典さん
今日ご報告いただいた10の団体は、いずれも重い命に向き合う活動で、ホットな日々の中で組織基盤強化という最もクールな活動に取り組み、別の世界を行ったり来たりされたのではないかと思います。そんな中で、ミッションを掲げて活動するNPOの運営とは何かという、さまざまな哲学を学ばせていただきました。今日は選考委員の先生方からも、皆さんの発表に触発された素晴らしいコメントをいただきました。この助成によって得た苦しかった経験、楽しかった経験は、今後のそれぞれの活動の底力になると思います。先日、パナソニックは企業フィランソロピー大賞を受賞しました。このプログラムは皆さんの発表に触発され、学びながら、成長していったのだと思います。皆さんに感謝いたします。