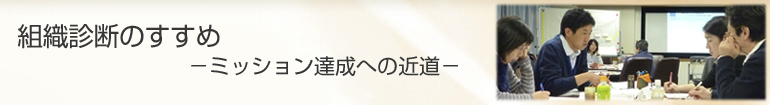
Panasonic NPOサポートファンドは、市民活動の持続的発展、社会課題の解決促進に貢献するため、NPO/NGOのキャパシティビルディング(組織基盤強化)を支援しています。10年にわたる経験をふまえ、キャパシティビルディングをより効果的に行うために、組織診断の手法を活用するプログラムに進化させました。集合研修型の組織診断プログラム「Panasonic NPOサポート マネジメント イノベーション プログラム」をパナソニックと協働で開発したNPO法人パブリックリソースセンターの田口由紀絵さんに「組織診断のすすめ」を寄稿いただきました。
組織基盤強化と組織診断
森の荒廃、耕作放棄地の増加、子どもが育つ環境の変化、虐待、在日外国人が直面する問題、被災地の生活再建。私たちが生きる社会には、たくさんの課題が存在します。その課題の解決のために、新しい発想と機動力で社会変革に取り組む組織体がNPOです。
社会課題の解決の担い手として期待を寄せられているNPOですが、限られた資源(資金、人材、ネットワークなど)を最大限に活用し、そのミッションやビジョンに基づいて十全に活動を行い、持続的に成長していくためには、自己変革による組織基盤強化が欠かせません。いい仕事をするためにはいい身体が必要で、病気があればそれを治し、体力が足りなければ体力づくりが必要でしょう。それと同じで、NPOがより効果的に社会の課題を解決していくためには、団体の運営上の課題を解決し基礎体力をつけること、すなわち組織基盤強化が必要なのです。
しかし、運営上の課題の根本原因がどこにあるのか、どのようなメニューで基礎体力をつけるのが効果的なのかを見極めるのは難しく、手間もかかります。そのため何か運営上の問題が持ち上がったとしても、一時的な解決ですませ、根本原因の解決は先送りしてしまいがちです。
人間ドックに入ったりスポーツジムで体力診断を受けたりすれば、病気の根本的な治療や効果的な体力強化に取り組むことができるのに、忙しさの中でつい対症療法でその場を乗り切ったり、いきなり走り込んで膝を痛めたりしてしまうのと同じです。
組織診断は、組織の課題の根本原因を突き止め、解決の方向性をみつけるために行います。
組織の課題は、ミッションやビジョンに基づくNPOの「ありたい姿」と、組織の現状との間にある差(=ギャップ)の中にあります。組織診断は、そのギャップを明らかにし、組織運営上の課題がどこにあるかを把握するためのひとつの手法です。組織診断で課題が明らかになっていれば、組織基盤強化への取り組みがより効果的に行えるようになるでしょう。
組織診断の方法
組織の課題の掘り下げ方は、団体の課題認識のレベルによって様々です。
例えば、組織課題に気づいていない場合。自分達は順調だと思っていても、実は目の前に山が迫っていることに気づかないまま飛行機を飛ばしていることもあり得ます。今自分達がどこにいてどういう状態なのか、課題を認識し、対策を講じることが必要です。第三者の客観的な視点を入れ、指摘を受けることも有効でしょう。
あるいは、表面上の課題は認識されているが根本原因には思い至っていない場合。やはり現状を把握し、できれば第三者の視点も活用しながら課題を掘り下げることが必要です。
あるいは、課題には気づいているけれども団体内で合意ができていない、という場合。客観的な事実をもとに、話し合いの場を持つことが重要となります。
組織診断の実際のステップについては、パブリックリソースセンターが行っている組織診断の方法論をもとにポイントをご紹介します。
組織診断の方法論 (1)「現在の姿(現状)」の把握
組織診断のプロセスは大きく2つに分けられます。前半は「現在の姿(現状)」を把握するための情報収集が中心です。後半は課題を抽出し、優先順位をつけ、解決の方向性について団体内で合意するための話し合いが中心です。
「現在の姿」を把握するための情報収集は、[1]NPOマネジメント診断シートを活用したマネジメントチェック、[2]外部の関係者の意見収集、[3]社会環境の変化の把握の、3つの方法で行います。
[1] NPOマネジメント診断シートの活用
組織のマネジメント上の強みや弱みがどこにあるのか、NPOマネジメント診断シートを使って各分野についてのチェックを行います。NPOマネジメント診断シートは、団体の「運動性」と「事業運営面の適切性」の2つの視点を盛り込みパブリックリソースセンターが作成しました。
この診断シートは、「マネジメント能力」、「人材」、「財務管理」、「プログラム(事業)」、「事業開発・計画・マーケティング能力」の5つの診断領域で構成されています。
例えばひとつめの「マネジメント能力」は、以下の診断項目にブレイクダウンされています。
- ミッション
- 社会的課題・ニーズの把握と組織の客観化
- 計画・評価
- リーダーシップ・ガバナンス
- 資金調達
- コミュニケーション、協働への取り組み、情報開示
- リスクマネジメント
各診断項目の中には具体的な設問が用意されており、例えば「ミッションは団体内で理解され、共有されている」「ミッションを実現するために必要な3年程度先を見越した中期目標・中期計画を立てている」といった設問に対して、各人が5段階で評価を行います。
理事・スタッフなど、団体内で組織運営を担う人にそれぞれ回答してもらい、集計結果を分析して、組織の強みや弱み、意見が分かれているところなどを把握します。
この診断シートの項目と設問は、よき組織運営のひとつの在り方を示しています。それと照らし合わせて組織の現状はどうなっているかを分析することで、課題をあぶりだします。
[2] 外部の関係者の視点
外部の関係者の視点を得るために、重要なステークホルダーからの意見収集を行います。団体のサービスの受益者や、会員、支援者に、インタビューやアンケートなどで、団体の強みや弱みはどこにあると思うか、今後団体になにを期待するか等を尋ねます。外から見た団体の姿を知ると同時に、団体の独自性や優位性を改めて認識する、貴重な機会です。
実際に外部意見の収集を行った団体からは、「こういう機会がないと外部の関係者に意見を聞きに行くことはしなかった。外部の方に団体を理解してもらうきっかけにもなった」「外部の関係者から予想外の意見を得ることができ、今後の団体運営に活かしていける」といったコメントがありました。
[3] 社会環境の変化の把握
社会環境の変化は、組織診断のためだけでなく、常に把握に務めるべきです。特に、事業分野の政治的動向や、世間の関心、同業者の動き、受益者の変化など、自分ではコントロールできない社会の変化に対して常にアンテナを立てておくことが必要です。そして変化に対応するだけでなく、団体にとって重要な社会の変化の先を読んで対応することで、チャンスを逃さず、脅威に備え、連携を作り出せる組織になるでしょう。
[4] コンサルタントの活用
日常業務に追われて組織診断が滞ってしまわないための強制力として、客観的な意見を提供する第三者として、話し合いを行う際のファシリテーター役として、コンサルタントを活用するのは効果的です。団体のミッションへの共感があるコンサルタントに入ってもらうのが良いでしょう。
(2)課題抽出および解決の方向性についての合意形成
パブリックリソースセンターが行う組織診断では、根本的な課題の見極めと同時に、団体内の合意形成も重視しています。組織診断の後半は、収集した情報をもとに、客観的な事実に基づき、課題抽出のための話し合いを行います。
話し合いは、組織の強み・弱み・チャンス・脅威を整理し、共有することから始めます。あまり認識していなかった団体の強みにあらためて価値を見出す一方で、団体の弱みがはっきりと突きつけられることもあります。組織運営を担ってきた人にとってはつらい部分かもしれません。
しかしこのプロセスをふむことで、団体が取り組むべき課題について合意形成がなされ、解決の方向性について納得して進むことができるようになります。
組織診断の効果
2011年度のPanasonic NPOサポートファンド グループコンサルティングコースで組織診断に取り組んだ8団体は、組織診断に取り組んだことで、今後取り組むべき優先課題や、解決の方向性が明らかになったと言っています。
例えばある団体の場合、組織診断に取り組む前は、「ミッション・ビジョンの再構築」「組織運営を担う人材の強化」「収益事業の開拓」が課題であるとしていました。しかし組織診断を進めるうちに、それまでひとりのリーダーシップに頼ってきた組織運営を、中・長期計画を策定して皆が意識統一しながら進めていくスタイルに変えていくべきだということが見えてきました。
他の団体からも「問題・課題の所在と、改善のための道のりを整理できた」というコメントがありました。組織診断を行うことで、課題が明確になり、解決の方向性が見えることは大きな効果といえます。
それと同時に、組織診断のプロセスそのものが、組織運営を担っていく人たちの運営力強化につながるという側面もあります。
団体からの組織診断についての感想の中には、
「あえて時間をとらないと日常業務では流されてしまうことについて考えを深められた」
「自分やスタッフが経営者的視点に立つことができた」
「成果志向で考えるクセがついた」
「診断シートに記入することで何人かのスタッフの意識が変わった」
といったものも多数ありました。
診断シートに答えたり話し合いの場で意見を言ったりすることで、団体運営にかかわるひとりひとりの関心やコミットメントが確実に高まり、コミュニケーション力や問題解決力の強化がはかられます。
そのほか、「目的・あるべき姿を明文化し、スタッフで共有できた」「組織全体で問題点や課題が共有され、『話し合える』土台が整った」など、団体内における共有が進み、同じ方向を向いて進んでいける基盤ができたという効果も生まれています。
組織診断を有効に行うために
組織基盤を強化したいと考えるなら、ぜひ組織診断に取り組んでいただきたいと思います。しかし団体の状態によっては、組織診断があまり有効にはたらかない場合があります。
たとえば団体が立ち上げの時期にあるとき、組織診断を行うのに適したタイミングとはいえません。組織診断で確認すべき「現在の姿(現状)」がまだ固まっていない段階なので、さまざまな情報収集が意味をなさなくなってしまうからです。診断より事業の立ち上げに注力するべきだといえるでしょう。
また、組織基盤の強化に取り組むことについて、代表者や理事会が納得していない場合は、組織診断の効果が得られにくくなります。もちろん組織診断のプロセスの中で、スタッフが経営的視点を持ったり、コミットメントを深めたりといった効果は期待できるでしょう。しかし理事会など意思決定を行う人たちが、組織診断の意義とプロセスを理解してリーダーシップを取らなければ、団体全体での合意形成がなされず、組織診断の結果がその後に活かされなくなります。
もしあなたが事務局のスタッフで、組織変革のために組織診断事業に取り組みたいと思っているとしたら、理事会の合意を得ることから始めるべきです。組織診断の必要性について理解が得られ、組織全体で優先的に取り組むことについて合意が得られたら、組織診断はうまくいったも同然です。その後の組織基盤強化の取り組みも効果を生むことになるでしょう。
日常業務を行いながら組織診断を行うのは、時間的にも精神的にも、なかなか大変です。しかし一度立ち止まって組織運営について考えるのは、ミッション達成への近道であることは間違いありません。社会課題の解決へのさらなる一歩を踏み出すために、ぜひ組織診断に取り組んでみてください。

