
Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs【海外助成】 成果報告会
8団体の事例を通して、
問題解決や新しいチャレンジのヒントを共有
2025年2月21日、官民共創HUB会議室(東京都港区虎ノ門)で「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs【海外助成】」の成果報告会を開催しました。会場には、2023年募集の「組織診断からはじめるコース」に取り組まれた2団体と「組織基盤強化コース」に取り組まれた6団体の皆様、選考委員、事務局関係者、参加のお申し込みをいただいた皆様など、42名の方々にお集まりいただきました。この日は、8団体の皆様から、組織診断・組織基盤強化の取り組みの概要と成果をご報告いただいたあと、選考委員より講評をいただき、ご参加の皆様と感想や気づきを共有しました。会の終了後には交流会の時間を設け、情報交換の場としてご活用いただきました。それぞれの事例から、問題解決や新しいチャレンジのヒントを得て、今後の活動をさらに深める貴重な機会となりました。
●開会挨拶
紛争や自然災害が頻発する世界、掲げる3つの重点テーマ
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 企業市民活動推進部 部長 堂本 晃代
現在、世界ではイスラエル・パレスチナの紛争やウクライナ情勢、自然災害の頻発が大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、報道は少なくなっているように感じられます。パナソニックでは従業員に向けて講演会を開催し、福利厚生のポイントを使った寄付を呼びかけてきましたが、引き続き支援活動を行ってまいります。創業から107年となるパナソニックは事業活動と企業市民活動の両方で、社会課題の解決と社会価値の創造に向けて取り組んできました。企業市民活動においては、SDGsの1番目の目標であり、創業からの変わらぬ思いでもある「貧困の解消」、事業でも最優先で取り組んでいる「環境」、社会課題の解決に取り組むために必要な「人材育成(学び支援)」を重点テーマとしています。2024年度は対面の活動も戻り、皆様の働き方や活動の進め方も選択肢が広がってきたことと思います。私たちも、NPO/NGOをはじめとする多様なステークホルダーの皆様から気づきやアドバイスをいただきながら、企業市民活動を進めていきたいと考えています。

堂本 晃代
●第1部 【組織診断からはじめるコース】成果報告
講演キャラバンで日本を縦断し、“らしさ”を模索
特定非営利活動法人 earth tree 副理事長 野中 秀憲さん
私たちはカンボジアを中心に、自然素材のものづくり・体験型の教育支援・農業による経済発展に取り組んでいます。その可能性を知ってもらい、つながりをつくる拠点として、働く場やレストラン、宿泊施設、学校が一体となったカンボジア最大規模の竹建築の複合施設を建築中です。しかし現地に20~30人の雇用を抱える一方で、財政の8割を寄付に頼り、マネジメントの体制に課題を抱えていました。そこで、コンサルタントにカンボジアまで来てもらい、職人やその家族、州の教育長、学校の先生にヒアリングを実施。昨年1年間、組織診断・現状分析、戦略の策定、その一部の試行に取り組みました。成果としては、キャンピングカーで日本を縦断する講演キャラバンを行い、クラウドファンディングで800万円を集めました。こうした動きをグラフィックレコーディングで図式化し、HPに掲載。短編映画の制作も進めています。クリエーターが多く所属する団体の強みである「関係性のデザイン」を軸に、“らしさ”あふれる新ビジョンを策定し、マネジメントも強化していきたいと考えています。

野中 秀憲さん
ケニアの事業拡大に向け、日本の支援者との交流を強化
特定非営利活動法人 ケニアの未来 事務局(事業副担当者) 甲斐田 真希さん
ケニア共和国で、社会的に困難な状況にある青年・子どもの保護と健全な育成を目指し、保護司制度の導入や、クラブ活動を通じた非行防止活動などをしてきました。やりたい事業はたくさんありますが、2014年の設立以来、ほとんど変わらない少人数の職員体制や助成金に依存した不安定な財政状況が課題でした。そこで、過去にイベントに参加した500人以上へのアンケートやヒアリングを試み、出てきた課題をもとに関係者と考えるワークショップの機会を設け、4つの基盤強化計画を策定。おろそかにしてきた支援者との双方向の交流や、オンラインスタディツアーのパイロット版を実施しました。そして理事への組織診断・振り返りワークショップでは、内部の帰属意識の希薄さという課題も見つかりました。コンサルタントに入ってもらったことで、今あるリソースを活かした基盤強化の方法がわかり、支援者ケアや収益事業の必要性を認識できました。オンラインスタディツアーでは、現地の住民と参加者との双方向の交流を図ることで、資金確保と支援者拡大による長期的な組織基盤強化の可能性が見えてきました。

甲斐田 真希さん
●【組織診断からはじめるコース】講評
“ワクワク”をつくる活動に、孤立や孤独を解決していく可能性
AVPN マネージャー
スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー・ジャパン 副編集長
Nピボ 共同代表理事 井川 定一さん
earth treeの発表を聞き、社会に“ワクワク”をつくってくれたことに感謝したい気持ちになりました。HPに掲載している報告と動画も感動的で、1年間やってきたことがストンと胸に落ちました。クリエーティブな技術面だけでなく、丁寧に公開していくカルチャーに関心をもちました。活動はオンリーワンなのにとがっていなくて、みんなが触れたくなる雰囲気があります。目指すものを言語化する努力に感心するのと同時に、それを実現させてくれる、この助成金の懐の深さも感じました。今、孤立や孤独、子どもたちの自尊心の低さが大きな社会問題となっていますが、earth treeの活動は、そこを解決していく重要な機能をもっているのではないかと感じました。

選考委員 井川 定一さん
組織を自分事化し、継続的に支援してもらう施策を考える
シャプラニール=市民による海外協力の会 代表理事 坂口 和隆さん
ケニアの未来が取り組む子ども・青年の居場所づくりは、どの国にも共通した課題で、伸びしろがあります。基盤強化の中で内部の帰属意識の希薄さがわかったのも、いい気づきだったのではないかと思います。昨今は一つの団体に深く関わらず、自分の興味関心の変遷に従って、お気に入りの団体を変えていく傾向が強く、支援者に継続的に支援してもらうための施策をみんなで考え、共有していくことが重要になってきました。設立から10年と言えば中堅どころでもあるので、外部からどう見られていくか、構築する必要があります。オンラインスタディツアーに関しては費用対効果を検証し、時には対面で現地を見てもらうことも、組織を自分事化してもらう一歩になると思います。

選考委員 坂口 和隆さん
●全体での感想共有
会場の参加者は、2団体の発表を聞いて感じたことをグループごとに話し合い、そこで出た感想を会場全体で共有しました。
「earth treeはデザイナーさんを中心とした団体で、メッセージがシンプルで、わかりやすいと思いました。帰属意識の希薄さの話も出ていましたが、組織が大きくなってくると、だんだんそうなっていく傾向があり、自分たちの団体にも当てはまる難しい問題だという意見も出ました」
「earth treeのコンサルタントとして現地に行ってきました。組織診断にはロジカルな部分が多いですが、現場に関わっている人たちの場合はイキイキ・ワクワクが先に来て、よくよく話を聞いてみると、実はこういう課題に対して、このような戦略を立てているという話が後からついてくる。活動の現場に身を置いて組織診断・組織基盤強化を行うことの可能性を強く感じました」
●第2部 【組織基盤強化コース(1)】成果報告
DAOを通じたコミュニティで新規支援者を拡大
特定非営利活動法人 エイズ孤児支援NGO・PLAS 代表理事 門田 瑠衣子さん
ケニアとウガンダで、貧困家庭など取り残された子どもたちが前向きに生きられる社会をつくる活動をしています。財源の約半分が寄付ですが、クラウドファンディングやマンスリーサポーターの募集を毎年行っても期待するようにはなかなか伸びず、新たな支援者を獲得するために、Web3の関心層に向け、DAOを通じた支援者のコミュニティをつくることにしました。「PLAS DAO」を開設し、SNSやイベント、プレスリリースで広報したところ、初年度は5500人が参加。プラットフォーム「FiNANCiE」でトークンを発行し、4000人から500円ずつ200万円の寄付をいただきました。支援者との双方向コミュニケーションも活発になり、1年間に6万件以上のコメントが寄せられました。DAOからオンラインイベントへの集客もできました。DAOをどう居心地のいい場所にして、継続的に運営し、資金調達や組織の成長につなげていけるかが未知数なので、リソースをどこまで投入すべきか議論を深め、DAOを中期計画の経営戦略にも組み込んでいきたいと考えています。
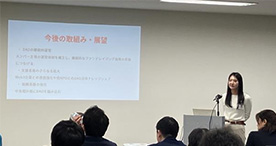
門田 瑠衣子さん
プロボノを活動に活かすプラットフォームを確立
特例認定特定非営利活動法人 ASHA 代表理事 任 喜史さん
ネパールの地方部で医療を提供する仕組みを構築する活動をしています。プロボノで運営していることが最大の特徴で、昨年度は、これをどう自走させていくかに取り組み、出てきた課題を分解して、今年度の取り組みを決めました。今年度の1つのテーマは「仕組み化」で、法務や財務・会計は専門家による仕組みの体系的な整備、人材面は新規加入者のオンボーディングやチームへのアサインの定型化、代表の権限のチームリーダーへの委譲、プロボノでは無理な業務は有償化するなどに取り組みました。次に、昨年定めた「Purpose/Dream」達成に向けたエンゲージメント向上の施策として、イントラネットを整備し、内部のコミュニケーションを活性化。メンバーの活動状況をアンケートによって可視化し、ASHAらしさのあるコンテンツとして社内報をつくり、ネパールのメンバーと共有しました。私たちの財源はほぼ助成金ですが、寄付財源やファンを増やしていくために、クラウドファンディングにも挑戦しています。この2年で何をすべきかが見え、形ができてきたので、これを定着させ、運用に落とし込んでいきたいと思っています。

任 喜史さん
BSCを使い、一丸となって取り組める基盤強化策を策定
認定特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会 理事 野村 政道さん
主にカンボジアやネパールで教育支援を行っています。創立30周年という節目を迎え、持続的な成長に向けて財政基盤と組織基盤の強化に取り組みました。基盤強化策の策定にあたっては、広く採用されているビジネスフレームワークのBSC(バランススコアカード)を採用し、1年目の組織診断で取り組んだSWOT分析の成果物である戦略マップをもとに、「財務・支援者・業務プロセス・学習と成長」の4つの視点から、戦略目標、重要成功要因を決めていきました。推進メンバーが全職員を巻き込んで取り組んだことで、BSCの理解も深まり、東京、プノンペン事務所が一丸となって、この事業を進めることができました。外部コンサルタントがカンボジアを訪問し、プノンペン事務所のスタッフにこの事業の意義を説明し、ローカルスタッフを含めた全員の理解と認識を高めました。またプノンペン事務所が取り組んでいる全事業の現場に立ち会ったことで、今後基盤強化に関する幅広いアドバイスを受けることが可能になりました。創立者が亡くなり、いろいろと不安のある中、メンバーの熱い想いを言語化し、策定した基盤強化策を実行して、これからの30年を力強く歩んでいきたいと思います。
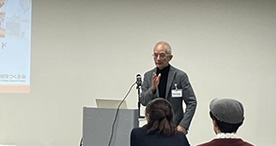
野村 政道さん
●【組織基盤強化コース(1)】講評
チャレンジするプロセス自体が社会を前に推し進める
AVPN マネージャー
スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー・ジャパン 副編集長
Nピボ 共同代表理事 井川 定一さん
NPO/NGOの一番の課題は一般の人たちとの接点のなさですが、エイズ孤児支援NGO・PLASのように、遠いところにいる5500人に一気にリーチするというチャレンジができるのも、助成金のいいところだと思いました。DAOは地方創生関連でも、数年前から聞くようになりました。今後のオフラインとの連携や既存の支援者さんとの関係づくり、メタバースとの融合も楽しみにしています。チャレンジする精神や新しいものをつくっていくカルチャーが団体の強みで、そこが経営戦略に表現されると、もっとしっくりくると思います。そして、そのプロセス自体が社会を前に推し進めている印象を受けました。

選考委員 井川 定一さん
存在感増すプロボノを活かした取り組みに高い先見性と先駆性
シャプラニール=市民による海外協力の会 代表理事 坂口 和隆さん
NPO/NGOの課題は人・物・金・情報に集約されますが、ASHAの取り組みには、ほとんどすべてが入っていました。プロボノでこれだけの活動をされて、課題意識から解決までつなげておられるのは特筆すべきことだと思いました。地域で活動していても、自分のスキルを活かしたプロボノという存在が、どんどん大きくなりつつあるのを感じます。プロボノのプラットフォームに焦点を当てた今回の取り組みには、高い先見性と先駆性があると思います。代表はまだお若いのに、事業継承についても絶えず考えていらっしゃるように見受けられました。現地の大学生にインターンをお願いして、出番をつくってみるのもいいかもしれません。
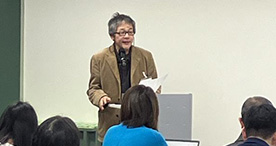
選考委員 坂口 和隆さん
難解だが、1度つくれば微調整して使い続けられるBSC
シャプラニール=市民による海外協力の会 代表理事 坂口 和隆さん
JHP・学校をつくる会は、難解なBSCに取り組まれ、ここまでしっかり細かく紙に落とし込まれたことに感心しました。1度つくれば微調整して、コンサルタントがいなくても使い続けていけるのがBSCのよさでもあります。今回、残念ながら代表がお亡くなりになって、今後は集団合議制でいくのか、新たなリーダーをつくるのか、かなり議論されてきたことと思います。団体のブランドをどう変えるのか、あるいは変えないのか、DNAを継承しつつ新たな団体にしていくのか、それとも今まで通りやっていくのか。いずれにしても、今回のことが団体を新たにつくり変える一つの機会になるのではないかと思います。
●全体での感想共有
会場の参加者は、3団体の発表を聞いて感じたことをグループごとに話し合い、そこで出た感想を会場全体で共有しました。
「私が所属している団体も理事や支援者が70~80代になって、ホームページもチラシもなく、どう続けていけばいいのか悩んでいましたが、3団体のお話をうかがって、新しいことを採り入れたり、プロボノの方に協力をお願いしたりする方法があることを知り、希望がもてました。今日勉強させていただいたことを活かし、この助成にも応募したいと思います」
「1団体目のDAO、2団体目のプロボノの活用、3団体目の代表の影響力。それぞれが私の団体の課題や今後の方向性にも直結するキーワードで、活用したいものがたくさんありました。DAOに関しては、活用することで新規の開拓はできそうですが、どんな方々が集まるのかまだわからず、どのように活用できそうか、グループ内でも話し合っていたところです」
●第3部 【組織基盤強化コース(2)】成果報告
事業承継を見据え、団体をリブランディング
認定特定非営利活動法人 アジア・コミュニティ・センター21 理事・事務局次長 辻本 紀子さん
私たちACC21は、アジアの人々や現地の団体とのつながりを大切にしながら、さまざまな活動を続けている団体で、今年の3月で20周年になります。設立から団体を引っ張ってきた代表理事が退任し、設立当初からの支援者の多くも高齢化。事業承継を考え、1年目は中長期計画を立案。それに合わせてビジョン・ミッションを変え、2年目は団体をリブランディングして、ロゴやウェブサイトも刷新しました。団体の理念や活動を知ってもらい、支援者を増やすために、毎月のオンラインイベント「月カフェ」と「若者チャレンジ100募金」を実施したところ、幅広い年代の参加があり、今年は昨年より多くの寄付が集まりました。資金調達の方法を増やすために、国内外の財団や企業にもアプローチし、ボランティアの受け入れ体制を構築するために、学生中心のイベントを試行しました。2024年6月に前代表理事を含め計3名の理事が退任し、理事体制も新しくなりました。そのタイミングで正会員、理事、事務局が今後について話し合う場を設け、今後に向けた前向きな議論を行い、信頼関係をさらに深めることができました。2年間この助成をいただいたおかげで大きな混乱も生じず、事業を続けることができました。
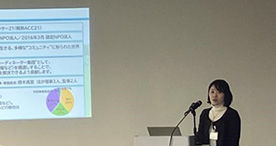
辻本 紀子さん
チャリティーディナーを体系化し、他地域に横展開
認定特定非営利活動法人 ホープ・インターナショナル開発機構
海外事業マネージャー 木下 香奈子さん
ファンドレイジングマネージャー 松浦 史典さん
私たちは1975年にカナダ、2001年に日本で設立された団体で、カンボジア・フィリピン・エチオピアで水供給事業を中心に行ってきました。2019年に、代表が創設者から新事務局長へと変わった4カ月後に、コロナ禍で、設立当初から寄付と並んで主要な収入源だったチャリティーディナーが開催できなくなり、新体制を構築するために3年間の助成を受けました。チャリティーディナーは食事をしながら、サイレント・オークションなどで寄付を募る欧米型のファンドレイジングです。コンサルタントに入ってもらい、組織診断を行った結果、団体の強みであるチャリティーディナーを適正規模で体系化し、これまでに実施していない地域で横展開していくことになりました。まずは広島のNPOセンターの協力で、中国地方のNPOに広めることができました。チャリティーディナーは十数人のボランティアに支えられていて、特に他地域での展開ではキーサポーターが重要になります。今後は、チャリティーディナーの伴走支援や企業との連携も考えていきたいと思っています。

木下 香奈子さん、松浦 史典さん
年間予算1億円を目指し、経営課題を明確化
特定非営利活動法人 Piece of Syria
事務局長 鈴木 のどかさん
ファンドレイジングマネージャー 島 彰宏さん
私たちは「シリアをまた行きたい国へ」というビジョンを掲げ、シリア国内での初等教育支援、トルコのシリア難民向け補習教育支援、日本国内での講座・情報発信を行っています。助成1年目は任意団体で、NPO運営のいろはからサポートしていただき、2年目は合宿を経て、組織・財政基盤強化に向けた計画を策定し、共有。3年目は経営・ファンドレイジング・海外事業の3チームに分かれ、それぞれ目標を設定し、専門のコンサルタントに伴走支援してもらいました。経営においては年間予算1億円を目指し、経営者訪問をオンラインで実施。コミュニケーションとリーダーシップに問題があることが明確化しました。ファンドレイジングにおいては代表に集約されていた業務や役割を分散し、昨年の秋には1000万円を超える資金を獲得できました。海外事業においては、シリア人のNPO職員の協力で現地モニタリングを実施し、プロジェクトの改善を図ることができました。課題が浮き彫りになりましたが、認識をすり合わせ、ポジティブな解決策を見出すことができました。その一つとして、代表が現場に専念し、共同代表制にするという案も出てきました。

鈴木 のどかさん、島 彰宏さん
●【組織基盤強化コース(2)】講評
若いアクターを採り入れ、組織を活性化
シャプラニール=市民による海外協力の会 代表理事 坂口 和隆さん
2年間の取り組みで、ビジョン・ミッションを変えられたのは大きなことだったと思います。ACC21と言うと、大人の方々が粛々と仕事をしている玄人集団という印象がありましたが、「若者チャレンジ100募金」や学生ボランティア受け入れの模索などで、若いアクターを採り入れていくことが組織の活性化や血の入れ替えにつながる気がしています。最近は高校生も地域の活動に活発に参加しているので、この方向性は間違っていないと思います。おそらくオンラインのサードプレイスみたいな位置づけの「月カフェ」も、そのうちソーシャルワーク的な音頭を取る人が必要になってくるかもしれませんが、いい取り組みだと思います。

選考委員 坂口 和隆さん
NPO/NGOの新しい財源になり得るチャリティーディナー
AVPN マネージャー
スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー・ジャパン 副編集長
Nピボ 共同代表理事 井川 定一さん
ホープ・インターナショナル開発機構はミッション・ビジョンを見つめ直し、何を収益としていくかに向き合った3年間だったのではないかと思います。クラウドファンディングやマンスリーサポーターに代わる新しい財源として、チャリティ―ディナーはポテンシャルが高いと思います。日本でも、たとえば経営者などはソーシャルマインドをもち、NPOへの関心も高いので、たとえ小規模でも、チャリティーディナーを開催するカルチャーが浸透すれば、NPO/NGOの新しい財源となって、寄付者が増えていくのではないでしょうか。

選考委員 井川 定一さん
新しい団体に浮上する問題は急成長に伴う成長痛
AVPN マネージャー
スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー・ジャパン 副編集長
Nピボ 共同代表理事 井川 定一さん
NPO/NGO業界も高齢化が進み、なかなか新しい団体が出てこない中で、Piece of Syriaのような新しい団体が生まれてきてくれたことをうれしく思います。設立から数年で急成長し、まったく違うレベルの組織になった印象を受けますが、まだ任意団体の段階で助成を決めたサポートファンドも素晴らしいと思います。経営やファンドレイジング、海外事業の強化や代表の負担の分散といった問題は、どこの団体でも起こり得ることですが、おそらく成長が早すぎるがゆえに、成長痛のような痛みを伴っているのではないでしょうか。
この3年間の取り組みを今後の活動に活かし、更なる発展につながることを期待しています。
●選考委員長による全体講評
組織・基盤・強化、3つの視点で見る組織基盤強化
多摩大学 経営情報学部 教授
NPOサポートセンター 代表理事 松本 祐一さん
NPO/NGOの事例をじっくり共有できる機会はあまりないので、非常に有意義な時間でした。せっかくなので、「組織基盤強化」という言葉に含まれる3つの要素・視点から見てみたいと思います。まずは「組織」です。NPO/NGOは組織の境界があいまいで、関わり方の強弱もある。どこまでの範囲を自分たちの「組織」として意識的にコントロールできるかがカギになってきます。2つ目が「基盤」です。今日のお話にも、“自分たちらしさ”という言葉が何度も出てきましたが、まさに「基盤」となるビジョン・ミッションも創設の思いを見つめ直し、時代に合った言葉にしていくことが大事で、そのためには、外の視点で自分たちの組織を見る癖をつけることが必要です。3つ目は「強化」です。組織診断等のプロセスの中で、見たくないものと向き合わなければいけない瞬間があったと思いますが、そこから逃げたら、「強化」という次の投資にたどり着きません。この助成が、NPO/NGOにとっての投資とは何かを考えるきっかけになれば幸いです。
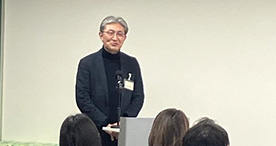
選考委員長 松本 祐一さん
●修了書の贈呈
今年度で、「Panasonic NPO/NGO サポートファンド for SDGs【海外助成】」の助成プログラムを修了されたアジア・コミュニティ・センター21、ホープ・インターナショナル開発機構、Piece of Syriaの皆様に、パナソニックの堂本部長より、修了書を授与しました。

アジア・コミュニティ・センター21、Piece of Syria、ホープインターナショナル開発機構への修了書贈呈の様子
●閉会挨拶
新しいチャレンジがセクター全体を活性化
特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC) 事務局長 水澤 恵さん
激戦を経て選ばれた8団体の皆さんがNPO/NGOを牽引してくださることを願って、私たちも助成のお手伝いをさせていただきました。時には、団体の弱みを突きつけられるようで、痛みや葛藤を抱えることもあったのではないでしょうか。若い団体さんから設立30周年の団体さんまで幅広く、この助成を活用していただけたことをうれしく思います。DAOやチャリティーディナーのような、他の団体の参考になる新しいチャレンジがたくさん出てきたことで、このセクター全体が活性化されていくことを願っています。JANICとしても、この学びを皆さんがいろいろな場面で発信できるようサポートし、来年度からは、皆さんに伴走するコンサルタントのサポートや育成にも取り組んでいきたいと考えています。

協働事務局 水澤 恵さん