未来を目指せる場所に立っている。
その道のりの起点となった日本への留学。
未来を目指せる場所に立っている。
その道のりの起点となった日本への留学。

姉妹揃ってリモート取材に応じてくれたサイリンさん(右)とサイセンさん
姉妹揃ってリモート取材に応じてくれたサイリンさん(右)とサイセンさん
○周采霖(シュウ・サイリン)さん
2005年認定→東京大学入学(工学系研究科 精密機械工学)→現在 パナソニック インダストリー株式会社
○周采霖(シュウ・サイリン)さん
2005年認定→東京大学入学(工学系研究科 精密機械工学)→現在 パナソニック インダストリー株式会社
○周采璇(シュウ・サイセン)さん
2009年認定→東京大学入学(工学系研究科 システム創成学)→一般消費財メーカーの日本法人
○周采璇(シュウ・サイセン)さん
2009年認定→東京大学入学(工学系研究科 システム創成学)→一般消費財メーカーの日本法人
第1回にご登場いただくのは、台湾出身の姉妹、姉の周采霖(シュウ・サイリン)さん、妹の周采璇(シュウ・サイセン)さんです。パナソニック スカラシップは、奨学生として認定されると来日後1年間は研究生として学びながら、希望する大学院への入試準備を進めることになります。合格後の2年間と併せて、計3年間の学習面・生活面の資金がサポートされます。「来日直後から生活面でも安定し、集中できる学習環境が得られたことが、今、社会人としてやりたいことに取り組める起点になっています」と声を揃えるお二人に、パナソニック スカラシップへの参加の意義をうかがいました。
第1回にご登場いただくのは、台湾出身の姉妹、姉の周采霖(シュウ・サイリン)さん、妹の周采璇(シュウ・サイセン)さんです。パナソニック スカラシップは、奨学生として認定されると来日後1年間は研究生として学びながら、希望する大学院への入試準備を進めることになります。合格後の2年間と併せて、計3年間の学習面・生活面の資金がサポートされます。「来日直後から生活面でも安定し、集中できる学習環境が得られたことが、今、社会人としてやりたいことに取り組める起点になっています」と声を揃えるお二人に、パナソニック スカラシップへの参加の意義をうかがいました。
学費だけではない、「学ぶ意欲」を見守るサポート
学費だけではない、「学ぶ意欲」を見守るサポート
台湾大学で機械分野の制御システムの研究をしていたサイリンさんは、より実践的に社会課題に取り組める研究をしたいとパナソニック スカラシップ選抜試験に挑戦。来日初年度の研究生の頃から世界的に著名な研究者の間近で学べたことが印象的だったと振り返ります。
台湾大学で機械分野の制御システムの研究をしていたサイリンさんは、より実践的に社会課題に取り組める研究をしたいとパナソニック スカラシップ選抜試験に挑戦。来日初年度の研究生の頃から世界的に著名な研究者の間近で学べたことが印象的だったと振り返ります。
サイリンさん:さらに驚いたことは、大学の先生方も「パナソニック スカラシップの奨学生は積極的に受け入れたい」と迎えてくれたことです。諸先輩の奨学生たちの実績もあってのことですが、この制度は、3年間の学費に加え生活費も給付されますが、返済やその後の就労の義務や条件が生じません。奨学生は生活費のためにアルバイトをすることもなく、学習や研究に集中できる点が評価されていました。
サイリンさん:さらに驚いたことは、大学の先生方も「パナソニック スカラシップの奨学生は積極的に受け入れたい」と迎えてくれたことです。諸先輩の奨学生たちの実績もあってのことですが、この制度は、3年間の学費に加え生活費も給付されますが、返済やその後の就労の義務や条件が生じません。奨学生は生活費のためにアルバイトをすることもなく、学習や研究に集中できる点が評価されていました。
奨学生側からは、資金面にとどまらず、安心感も得られるサポートだったとサイリンさんは言います。パナソニック スカラシップの 事務局のスタッフが、生活面のことも小まめに相談に乗ってくれたことが大きな支えになったそうです。
奨学生側からは、資金面にとどまらず、安心感も得られるサポートだったとサイリンさんは言います。パナソニック スカラシップの 事務局のスタッフが、生活面のことも小まめに相談に乗ってくれたことが大きな支えになったそうです。
サイリンさん:台湾ではずっと実家で暮らしていたので、海外生活はもちろん、一人暮らしも初めてでした。日本語も習い始めたばかりで不安は大きかったのですが、事務局の方々は、私を娘や妹のように気にかけてくださり、まるで家族に見守られているかのような安心感を得られました。実は、研究生として学んでいた大学の秋の大学院受験に失敗してしまったのです。院に進めないと次年度からの認定がされなくなります。受験結果を事務局に報告するときには、かなり落ち込んでいました。すると当時の事務局次長が、親身に受け止めてくれた上に、多くの奨学生を見守ってきた経験から次の受験に向けたアドバイスをしてくれたのです。日本語の勉強の進み具合も「どうですか」とさりげなく、そして小まめに声を掛けていただき、学ぶことへの意欲を刺激し続けてくださいました。そのおかげもあり、東京大学の大学院に無事合格することができました。
サイリンさん:台湾ではずっと実家で暮らしていたので、海外生活はもちろん、一人暮らしも初めてでした。日本語も習い始めたばかりで不安は大きかったのですが、事務局の方々は、私を娘や妹のように気にかけてくださり、まるで家族に見守られているかのような安心感を得られました。実は、研究生として学んでいた大学の秋の大学院受験に失敗してしまったのです。院に進めないと次年度からの認定がされなくなります。受験結果を事務局に報告するときには、かなり落ち込んでいました。すると当時の事務局次長が、親身に受け止めてくれた上に、多くの奨学生を見守ってきた経験から次の受験に向けたアドバイスをしてくれたのです。日本語の勉強の進み具合も「どうですか」とさりげなく、そして小まめに声を掛けていただき、学ぶことへの意欲を刺激し続けてくださいました。そのおかげもあり、東京大学の大学院に無事合格することができました。
生まれ故郷と日本、さらに世界とのつながりを得る機会
生まれ故郷と日本、さらに世界とのつながりを得る機会
サイリンさんの日本留学は、妹のサイセンさんの未来にも新たな視点を与えました。当時、サイセンさんは、北米の大学院へ進学するための共通試験であるGRE (Graduate Record Examination=主に米国やカナダの大学院への入学に求められる統一試験)の受験準備を進めていました。台湾の大学では心理学を学んでいたサイセンさんが、日本への留学を視野に入れたのは、その学問分野での先進性への期待でした。
サイリンさんの日本留学は、妹のサイセンさんの未来にも新たな視点を与えました。当時、サイセンさんは、北米の大学院へ進学するための共通試験であるGRE (Graduate Record Examination=主に米国やカナダの大学院への入学に求められる統一試験)の受験準備を進めていました。台湾の大学では心理学を学んでいたサイセンさんが、日本への留学を視野に入れたのは、その学問分野での先進性への期待でした。
サイセンさん:私が学んだ心理学は、台湾では理系の分野に属します。その延長線上でもう少し心理学を学びたいと考えていました。東京大学にシステム創成学という専攻があり、まさにその分野で世界先進の研究が行われていたのです。私も姉も小さい頃から日本のポップカルチャーに強く憧れていました。その日本に留学中の姉から、勉強も生活も充実している様子を聞いて、留学先の候補としての期待と、うらやましさも相まって、母に相談しました。
サイセンさん:私が学んだ心理学は、台湾では理系の分野に属します。その延長線上でもう少し心理学を学びたいと考えていました。東京大学にシステム創成学という専攻があり、まさにその分野で世界先進の研究が行われていたのです。私も姉も小さい頃から日本のポップカルチャーに強く憧れていました。その日本に留学中の姉から、勉強も生活も充実している様子を聞いて、留学先の候補としての期待と、うらやましさも相まって、母に相談しました。
「パナソニック スカラシップだけはなんとか受けさせてください。チャンスに挑戦して、万が一ダメだったら日本への留学は諦めます」と自分の決意を話したと言います。
「パナソニック スカラシップだけはなんとか受けさせてください。チャンスに挑戦して、万が一ダメだったら日本への留学は諦めます」と自分の決意を話したと言います。

家族はご両親と弟さんの5人家族。写真は台湾料理のお店で。写真:サイリンさん提供
家族はご両親と弟さんの5人家族。写真は台湾料理のお店で。写真:サイリンさん提供
サイセンさんは、そのチャンスを活かし、見事に日本留学を手に入れ、希望の学びだけでなく、予想外の視野の広がりを日本での生活で得たと言います。そのスタートは、パナソニック スカラシップの認定式でのことでした。
サイセンさんは、そのチャンスを活かし、見事に日本留学を手に入れ、希望の学びだけでなく、予想外の視野の広がりを日本での生活で得たと言います。そのスタートは、パナソニック スカラシップの認定式でのことでした。
サイセンさん:研究生として大学に入学する前に、大阪で行われた認定式に参加しました。そこで、アジア各国からの同期の奨学生たちと初めて会ったのですが、台湾から日本という海外へ飛び出すステップが、国際交流という大きなジャンプにつながりました。その日に出会った中国からの奨学生とは、それからの十数年間、互いの人生を支え合うこととなり、今でも大親友です。
サイセンさん:研究生として大学に入学する前に、大阪で行われた認定式に参加しました。そこで、アジア各国からの同期の奨学生たちと初めて会ったのですが、台湾から日本という海外へ飛び出すステップが、国際交流という大きなジャンプにつながりました。その日に出会った中国からの奨学生とは、それからの十数年間、互いの人生を支え合うこととなり、今でも大親友です。
今そして未来に向けてやりたいことは、
スタート地点からつながっていた
今そして未来に向けてやりたいことは、
スタート地点からつながっていた
お二人は、いずれも大学院修了後に日本で就職しました。パナソニックのグループ会社に勤めるサイリンさんは、入社の動機に奨学生としての経験が大きく影響していると言います。
お二人は、いずれも大学院修了後に日本で就職しました。パナソニックのグループ会社に勤めるサイリンさんは、入社の動機に奨学生としての経験が大きく影響していると言います。
サイリンさん:事務局の方々とは、日々の相談に加え、夏季には全国の奨学生が集まるイベントなどでも交流する機会が多くありました。そこでは日本人の働く姿勢というものを間近で見ることができました。国際的な奨学金制度をつくり人材育成に取り組む企業姿勢はもちろんですが、その運営に携わる人びとの「真面目さ」が、若かった私にはとても印象的でした。当時はまだ、将来の自分を夢見たときに、見た目やかっこよさばかり追いかけてしまう年頃でしたが、「本当の芯のある生き方」こそが実はとても大切なこと、価値のあることなのだと学びました。
サイリンさん:事務局の方々とは、日々の相談に加え、夏季には全国の奨学生が集まるイベントなどでも交流する機会が多くありました。そこでは日本人の働く姿勢というものを間近で見ることができました。国際的な奨学金制度をつくり人材育成に取り組む企業姿勢はもちろんですが、その運営に携わる人びとの「真面目さ」が、若かった私にはとても印象的でした。当時はまだ、将来の自分を夢見たときに、見た目やかっこよさばかり追いかけてしまう年頃でしたが、「本当の芯のある生き方」こそが実はとても大切なこと、価値のあることなのだと学びました。
サイリンさんは、会社では企業のESG(環境・社会・ガバナンス)推進活動を担当しています。まだ担当して間もない仕事だそうですが、はっきりとしたやりがいを感じていると言います。
サイリンさんは、会社では企業のESG(環境・社会・ガバナンス)推進活動を担当しています。まだ担当して間もない仕事だそうですが、はっきりとしたやりがいを感じていると言います。
サイリンさん:弊社はB to Bのデバイス機器を取り扱っており、一般消費者になじみのない製品が多いです。しかし、デバイス機器だからこそ、内側から世の中に変化をもたらせると信じています。。私生活では二人のまだ小さな子どもの将来がより良い社会にあることを願う母親として暮らしています。新たな仕事を任されたとき、パナソニック スカラシップは、まさに企業のESG活動の先駆けだと思ったのです。そこからスタートした私が、今、ESG推進活動を担当している。子どもたちの未来にも少し関わることができるかもしれない。そうしたつながりを実感しています。
サイリンさん:弊社はB to Bのデバイス機器を取り扱っており、一般消費者になじみのない製品が多いです。しかし、デバイス機器だからこそ、内側から世の中に変化をもたらせると信じています。。私生活では二人のまだ小さな子どもの将来がより良い社会にあることを願う母親として暮らしています。新たな仕事を任されたとき、パナソニック スカラシップは、まさに企業のESG活動の先駆けだと思ったのです。そこからスタートした私が、今、ESG推進活動を担当している。子どもたちの未来にも少し関わることができるかもしれない。そうしたつながりを実感しています。
一方、サイセンさんは、消費財メーカーの日本法人に勤めています。自分がやりたいことと、自分の仕事とを結びつけるものは、やはりこの奨学生制度によって機会を得た学びのチャンスからつながっていると実感しているそうです。
一方、サイセンさんは、消費財メーカーの日本法人に勤めています。自分がやりたいことと、自分の仕事とを結びつけるものは、やはりこの奨学生制度によって機会を得た学びのチャンスからつながっていると実感しているそうです。
サイセンさん:私自身は、数年前から「サステナビリティ」に強い関心を持っています。現在の仕事、取り扱っている製品にはプラスチックも使われていますが、そうした現状、製法や原材料も含め、「サステナビリティ」の視点で取り組むことで向上させていける部分がたくさんあると思います。そこに心理学の学びから得た視点で、人と物とを結び合わせるストーリーをつくることができないか。そうした展望を持っています。「サステナビリティ」という世界の潮流に乗って、日本の消費者や市場により良いものを提供する仕事に大きなやりがいを感じています。
サイセンさん:私自身は、数年前から「サステナビリティ」に強い関心を持っています。現在の仕事、取り扱っている製品にはプラスチックも使われていますが、そうした現状、製法や原材料も含め、「サステナビリティ」の視点で取り組むことで向上させていける部分がたくさんあると思います。そこに心理学の学びから得た視点で、人と物とを結び合わせるストーリーをつくることができないか。そうした展望を持っています。「サステナビリティ」という世界の潮流に乗って、日本の消費者や市場により良いものを提供する仕事に大きなやりがいを感じています。
サイリンさん、サイセンさんの姉妹は、同じパナソニック スカラシップによって、日本で学ぶ機会を得ました。その後も、日本で働いているお二人ですが、それぞれの「やりたいこと」に足場を置き未来を見つめています。「振り返ればその道筋にすべて意味がある」と声を揃えるお二人は、その起点となった「学びたい」の第一歩を、社会のサポートによって安心して踏み出せたことが大きかったと言います。
サイリンさん、サイセンさんの姉妹は、同じパナソニック スカラシップによって、日本で学ぶ機会を得ました。その後も、日本で働いているお二人ですが、それぞれの「やりたいこと」に足場を置き未来を見つめています。「振り返ればその道筋にすべて意味がある」と声を揃えるお二人は、その起点となった「学びたい」の第一歩を、社会のサポートによって安心して踏み出せたことが大きかったと言います。
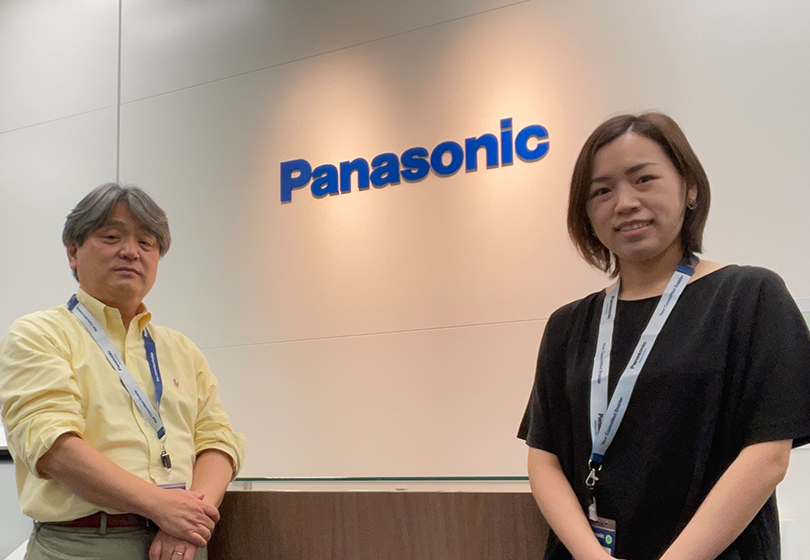
サイリンさんは現在パナソニックのグループ会社に勤務。留学時代に得た経験がとても役立っていると言います。
写真左は現在の上司。写真:サイリンさん提供
サイリンさんは現在パナソニックのグループ会社に勤務。留学時代に得た経験がとても役立っていると言います。
写真左は現在の上司。写真:サイリンさん提供


