
2024年1月25日、「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」の贈呈式に続いて、日本NPOセンターとの共催により、組織基盤強化フォーラムを開催しました。会場には、贈呈式に参加された助成先の皆様と、参加のお申し込みをいただいた一般の方々、合わせて約100名の皆様にお集まりいただきました。ビジョン/ミッションについての基調講演や、ビジョン/ミッションの再構築と組織基盤強化に取り組んだ団体の実践事例の紹介、パネルディスカッションと意見交換を通して、ビジョン/ミッションの意味と、その再構築の必要性について掘り下げていきました。
●開会挨拶
グローバルな課題と創業者の理念から生まれた3つの重点テーマ
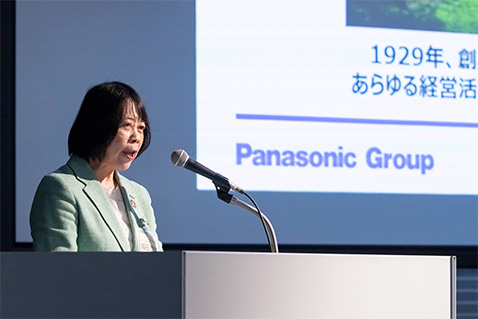
パナソニック ホールディングス株式会社
CSR・企業市民活動担当室 室長 福田 里香
松下幸之助が106年前に3人で創業したパナソニックグループは、23万人強の従業員を抱えるグローバル企業となりました。一企業市民としても社会のお役に立てないかと、私どもは企業市民活動と事業活動を車の両輪のように進めてきました。創業100周年に向けて、活動の軸となるグローバルな課題を検討していた2015年に国連でSDGsが採択されたことから、1番目の開発目標であり、創業者も掲げていた「貧困の解消」を軸と定めました。その間、新しい社長を迎え、21世紀の最優先課題を検討した結果、これまでも取り組んできた環境問題を取り上げ直すこととなり、そのベースとなる人材育成を加えた「貧困の解消、環境、人材育成(学び支援)」の3つを重点テーマとしました。サポートファンドは「貧困の解消」の取り組みの一つです。どの活動を取っても、パナソニックだけではできません。現場で活動されているNPO/NGOの皆さんをはじめ、様々なステークホルダーの皆様とパートナーシップを組みながら、進めてまいりたいと思います。
●基調講演
あらためて「ビジョン/ミッション」とは? その再構築とは?

特定非営利活動法人 ホールアース自然学校
代表理事 山崎 宏さん
静岡県富士宮市で、ホールアース自然学校という環境教育のNPOの代表をしています。子どもの頃から野鳥が好きで、生息地を守りたくてNPOの活動に足を踏み入れ、団体を1982年に立ち上げた創設者から引き継ぐ形で、2014年に代表者となりました。組織を維持するためにサポートファンドで3年間、組織基盤強化の助成を受けた後、選考委員を務めました。そこで、組織基盤強化のプロセスもやり方も団体の数だけあることを知りました。
ビジョンは方向性、あるべき姿、将来像、ミッションは組織の使命、自分たちは何をするために存在しているのか、と言い換えることができます。日本NPOセンター顧問の山岡義典先生はNPOの組織基盤を船、事業を積み荷にたとえます。だとすれば、ビジョン/ミッションの再構築とは船の進行方向や速度の見直し、目的地の再設定をすることだと言えます。
再構築のタイミングは世代交代や定期的な見直しの際、活動の成果を検証した結果、社会情勢が大きく変わった時、ステークホルダーとの関係の中で、といった時期が考えられます。社会の変化が激しい時代にどこまでコストをかけるか、判断はそれぞれだと思います。 再構築のプロセスで大切にしたい「在り方」は組織ごと、あるいはメンバー間でも違っていて、拡大路線に引っ張られると、大事な組織の風土が崩れてしまうこともあります。再構築の向こうにある組織基盤強化とはどういう状態を指すのか、肝はどこにあるのか、常に意識しておく必要があります。
●ビジョン/ミッションの再構築と組織基盤強化の事例発表
やってみて見直すサイクル回し、ビジョン/ミッションを定義

認定特定非営利活動法人 D×P
理事・ディレクター 入谷 佐知さん
不登校、中退、家庭内不和、経済的困難、いじめ、虐待などによって安心できる居場所を失った10代の孤立に対し、定時制・通信制高校での居場所づくり、10・20代のLINE相談「ユキサキチャット」、大阪ミナミのユースセンター事業などに取り組んでいます。
共同代表の退職を機にサポートファンドに応募し、2017・18年度に組織基盤強化の助成を受けました。コンサルタントを依頼し、組織診断としてキャパシティ・アセスメントを実施。課題に経営陣で点数をつけ、対話を重ねた結果、ミッション/ビジョンの不明確さが論点として浮上しました。そこで合宿を開催し、課題の優先順位を話し合いました。まずはやってみて見直すというモニタリングの体制をつくり、それから、ビジョン/ミッションを見直すことになりました。
ビジョンは「目指す社会像」と定義した上で「ひとりひとりの若者が自分の未来に希望を持てる社会」、ミッションは「成すこと」と定義した上で「ひとりひとりの若者がつながりを得られる状態をつくる」としました。
2020年からのコロナ禍の中では困窮している10、20代からの声がたくさん届き、LINE相談事業の拡大や食料支援、現金給付を始めました。これを受けて、ミッションを「ユース世代に、セーフティネットと機会提供を」と再定義しました。取り組みの成果なのか、スタッフの離職率が低くなりました。時代の変化に応じて、ミッションはコロコロ変わりますが、やってみて見直すサイクルを回し続けることが私たちには大事だったのだと思っています。
共通の価値観に向かって進む大きなワンチームを構築

認定特定非営利活動法人 日本ハビタット協会
事務局長 篠原 大作さん
日本ハビタット協会は国連ハビタット(国連人間居住計画)の広報及び募金活動を行う団体として、2001年に設立されました。2010年頃からは自主事業として、東日本大震災等の復興支援、ケニアにおけるトイレの建設による衛生環境改善事業、ラオスにおける環境教育基盤づくりによる環境保全事業を行ってきました。設立から20年近く経った頃、世界情勢も変わり、NGOが果たす役割について思い悩み、組織診断と組織基盤強化に取り組みました。
専門家(伴走支援者)を交えた外部及び内部環境分析、3C/4P分析を踏まえて、ミッション/ビジョン/バリューを再設定し、中長期計画に落とし込み、共通の価値観に向かって進む大きなワンチームを構築して、さらなる共感を生むための対外発信を強化しました。
団体運営を客観的に振り返り、存在意義を見直す機会となり、団体内のコミュニケーションが促進されて、風通しのいい団体に成長しました。ボランティアにも目指す姿を見せることができ、継続して参加してくれる人が増えました。広報やファンドレイジングにも、意見を出し合って取り組むようになりました。組織基盤強化に取り組む前には、団体内で同意を得ていたほうがいいと思います。ミッション/ビジョンの見直しは団体の存在意義に関わるので、血が流れます。外部専門家が入るとてもいい機会なので、客観的かつ論理的な視点や思考を柔軟に受け入れて、目先ではなく将来の団体の発展を考えることをお勧めします。
●パネルディスカッション
【コーディネーター】
ホールアース自然学校 山崎 宏さん
【登壇者】
D×P 入谷 佐知さん
日本ハビタット協会 篠原 大作さん
外部のコンサルタントが入ることの難しさ
篠原さん 私たちの団体は役員が20人、うち主要理事が5~7人もいて、中には外部専門家が入ることに違和感を覚えている理事もいましたが、私たちになかった視点で団体運営を見てくださることを丁寧に説明しました。月1回の事務局会議には主要理事も参加し、常日頃からコミュニケーションは取れていたので、ご理解いただくことができました。
ビジョン/ミッションを決めていったプロセス
入谷さん 組織診断を踏まえての合宿は経営メンバー3人で行いました。ビジョン/ミッションはある程度の案がある状態から、トップダウンで決めていきましたが、スタッフには会議の場だけでなく、常日頃のチャットや立ち話、食事の席でも意見を聞いたので、自分の意見が反映されていなくても、話を聞いてもらえたという感覚はもっていると思います。
ビジョン/ミッションを再構築した成果
篠原さん 団体を動かしていくのは人だと思っているので、私たちが何のためにやっているかが明確になって、職員や支援者、寄付者、会員、ボランティアなど、さまざまな人のベクトルを目指すべき方向にもっていけたことがよかったと思います。
入谷さん 私たちは日々、子ども支援をしている団体や弁護士さん、婦人科の先生、依存症の先生、自治体のソーシャルワーカーさんと連携しています。私たちが何を大切にしているか改めて見直したことで、何かしら共通したものを見ながら、一緒に次のステップに進んでいけるようになりました。
山崎さん ビジョン/ミッションの再構築と、その向こうにある組織基盤強化をやってみると、自分たちだけではできない道筋も見えてきます。だけど、その部分を隣にいる団体がやってくれたらうれしい。共通言語を掲げる団体を増やし、どんどん化学反応を起こしていかないと社会課題の多様さや変化の激しさには追いつけません。組織基盤強化のプロセスの成果を隣の団体との連携にもつなげていくことが大事なのだと思います。とはいえ、ステップを一つ踏んだら、また新しい課題が出てきて、改めて組織基盤強化のプロセスを回さないといけなくなる。組織がある限り、組織基盤強化は続きます。

パネルディスカッションの様子
●意見交換
自組織のビジョン/ミッションの共有と再構築の必要性について
パネルディスカッションのあと、会場の参加者は4人で一つのグループになって、この日学んだことを分かち合い、それぞれの組織のビジョン/ミッションを紹介し、意見を交換しました。25分間のディスカッションを経て、最後に全体で質疑応答の時間を設けました。

意見交換の様子
組織基盤強化のためのコミュニケーションや対話の時間をどう創出すればいい?
篠原さん たとえば、サポートファンドの組織基盤強化の助成を受けるとか、何か強引なきっかけをつくらないと、忙しいからと後回しになってしまいます。やらなきゃいけない状況に追い込まれ、そこから「やってよかった」と思えて初めて、コミュニケーションは必要だから、そういう時間を設けていこうという方向に変わっていくのではないかと思います。
入谷さん その時間の給与や業務委託費、交通費を出し、できれば交流会費も無料にすることが大事だと思います。そこにちゃんとお金を出すということは、その組織の意思を示すことにもなるからです。まずは声をかけやすいスタッフから始めて、時間を取ってくれなさそうなスタッフへと波紋を広げていくといいのではないでしょうか。
ビジョン/ミッションとは別に、存在意義を意味するパーパスの設定はしている?
山崎さん サポートファンドの組織基盤強化のプログラムの中では、パーパスという言葉はあまり議論されず、パーパスについては考えていない団体も多いのではないかと思いますが、パーパス経営というキーワードがこれだけ社会に広がってきているので、「NPOにとってのパーパス」というのは、とてもいい新たな問いかけになるのではないかと思います。
