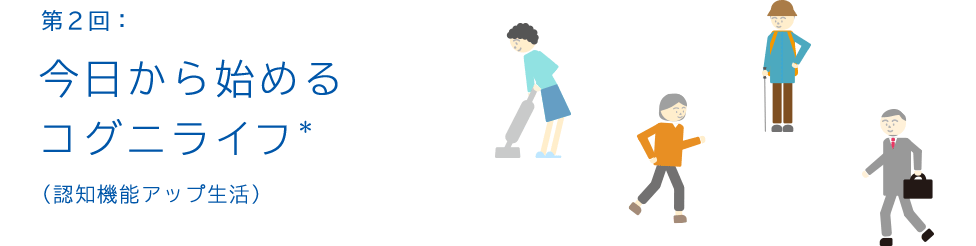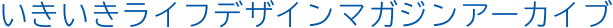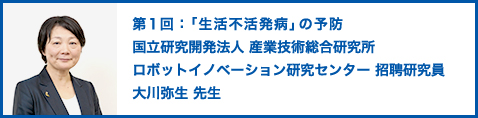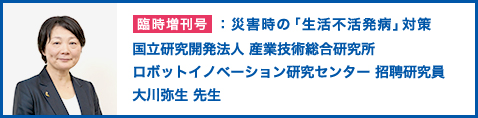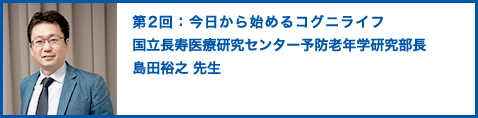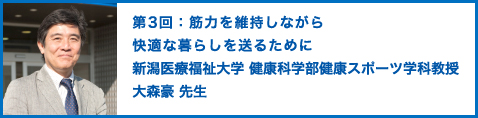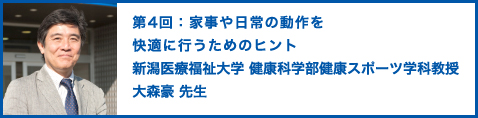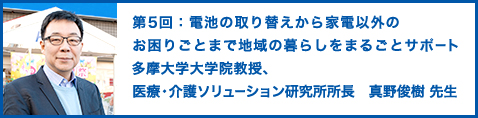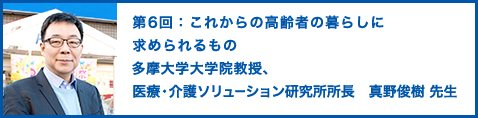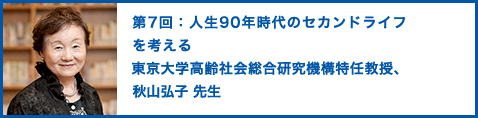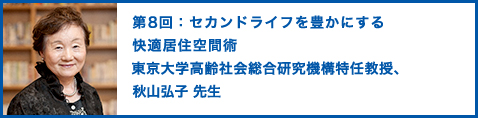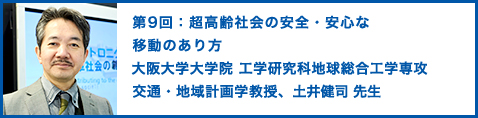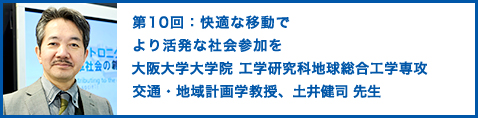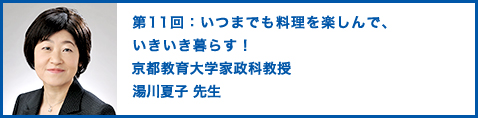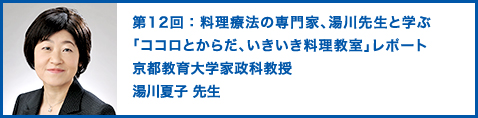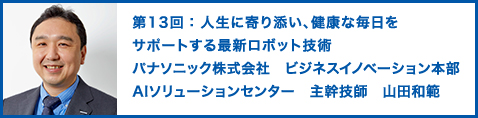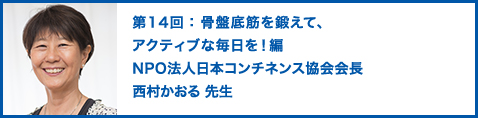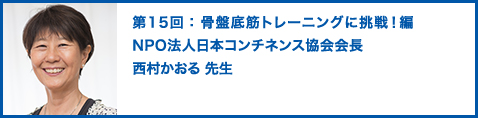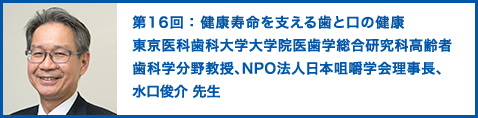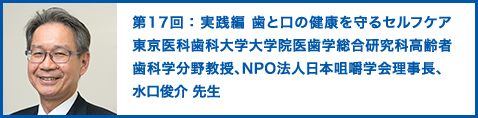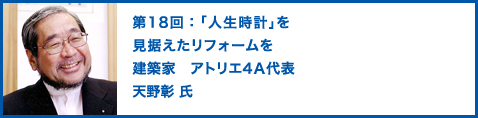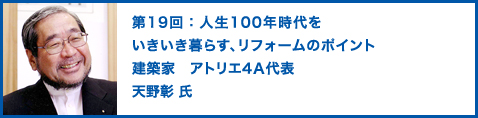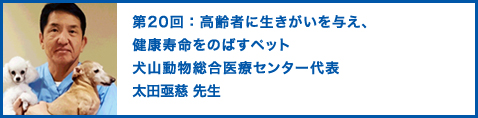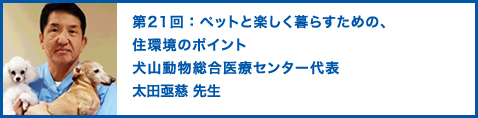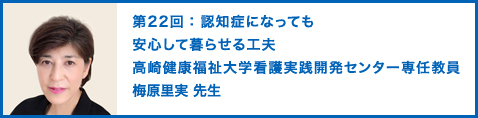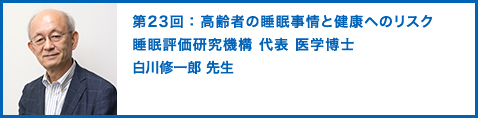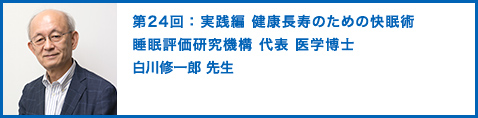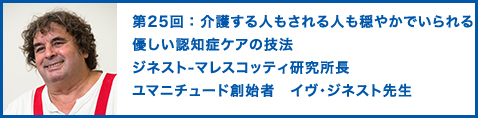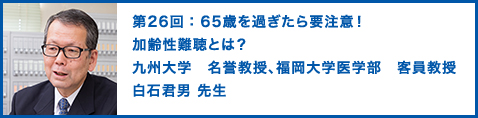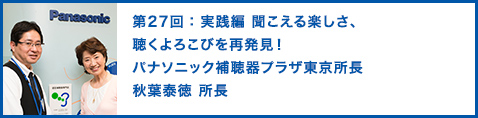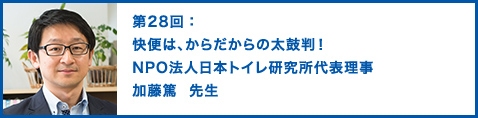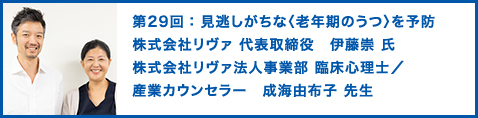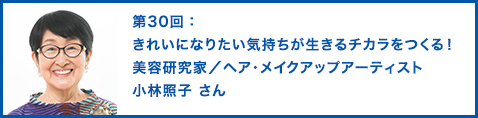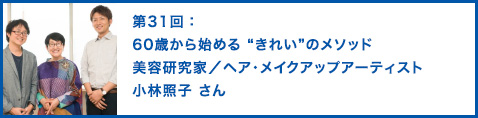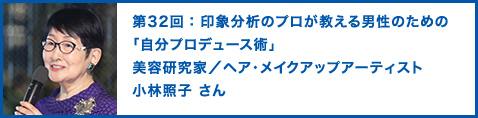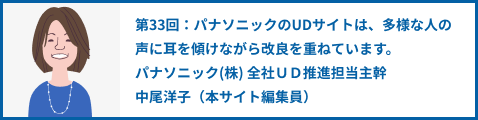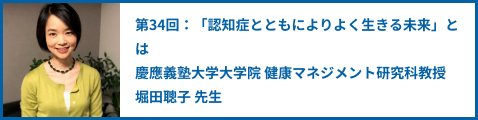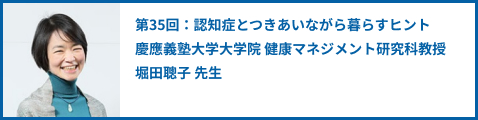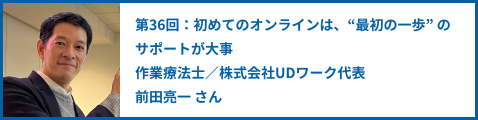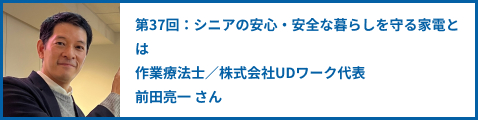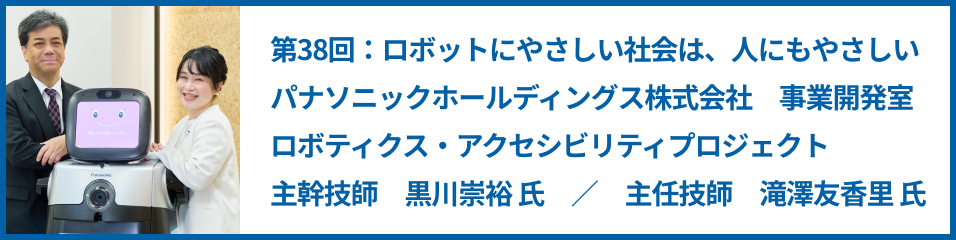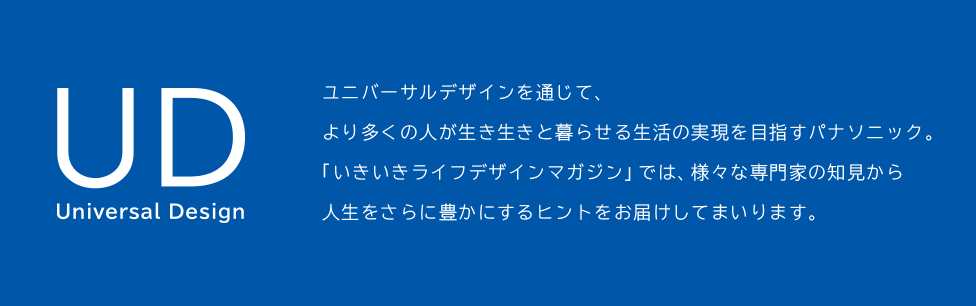
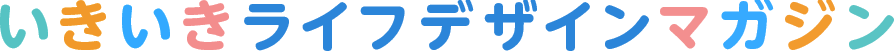
国立長寿医療研究センター予防老年学研究部長
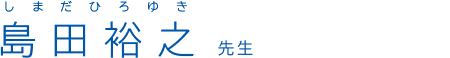
生き生きとした高齢社会実現のために、認知症の予防が大きな課題となっています。
年齢を重ねると認知機能がだんだん衰えてきますが、最新の研究では、活動的な毎日を送ることが認知機能を高め、認知症の予防になりそうだということがわかってきました。
認知症予防に詳しく、著書も数多く執筆されている国立長寿医療研究センター予防老年学研究部長の島田裕之先生に、日常生活の中で認知機能を高めるポイントをうかがいました。


先生がご所属されている国立長寿医療研究センター
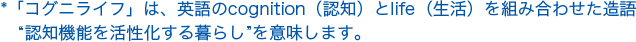
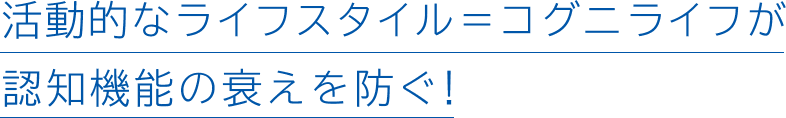
たとえば注射を1本打てば、絶対に認知症にならない。そんな特効薬があればいいのですが、残念ながらまだ見つかっていません。ただ、認知症になる前に必ず認知機能が落ちてきます。これをMCI(軽度認知障害)と呼びますが、この段階でも、認知機能を向上させたり、認知症の発症を遅らせたりすることができそうだということがわかってきました。
認知症の中でも一番多いアルツハイマー病は、脳の中にβアミロイドと呼ばれる物質が蓄積して脳細胞がダメージを受けて発症する、という経緯があります。このβアミロイドの蓄積は、じつは発症の20年前から始まっています。80歳でアルツハイマー病を発症する場合は、60歳からβアミロイドの蓄積が始まっていることになります。
ですから、理想を言えば、認知症予防の取り組みは早ければ早いほどいい。でも、何歳だから遅いということはありません。気になり始めたとき、自分でやろうと思ったときが始めどき。大切なことは、長く続けることです。
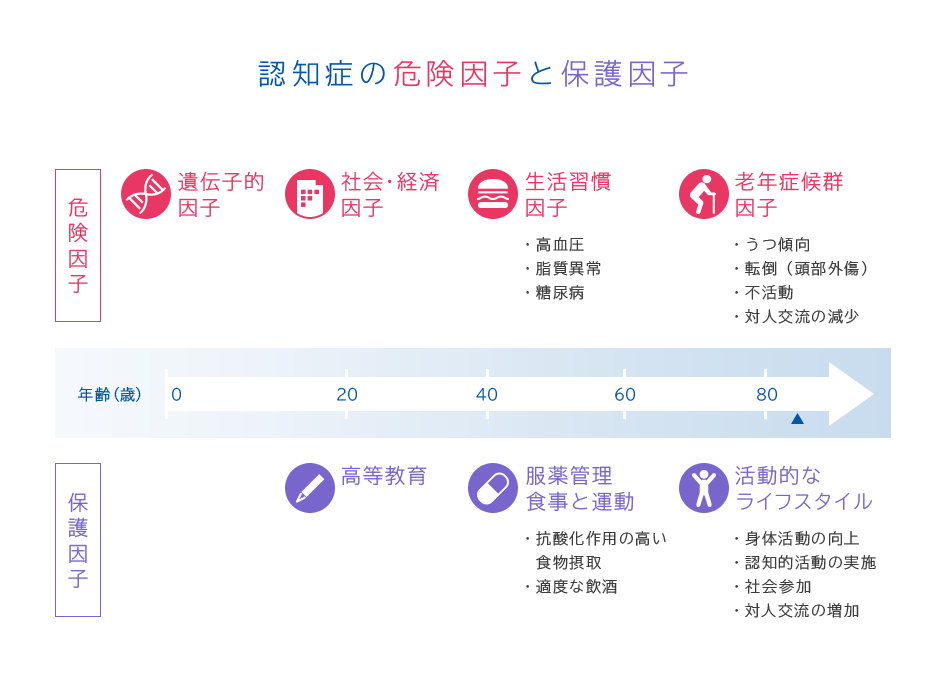
引用:島田裕之編(2015)『運動による脳の制御:認知症予防のための運動』杏林書院,p.13
まず、認知症のリスク要因である生活習慣病の治療をすること。そして、からだを動かす、いろいろな人と交流する、地域でつながりを持つなど、認知活動の活性化が、認知症発症の抑制に役立ちそうだということが最近わかってきました。認知活動には、身体的な活動、精神的な活動、社会的活動などがあります。ひと言で言うとしたら、活動的なライフスタイルをいかに持続させるかが、認知症予防には最も大事なのです。
認知活動を活性化するライフスタイルのことを、私は「コグニライフ」*と名付けました。次に、コグニライフのポイントをご説明しましょう。
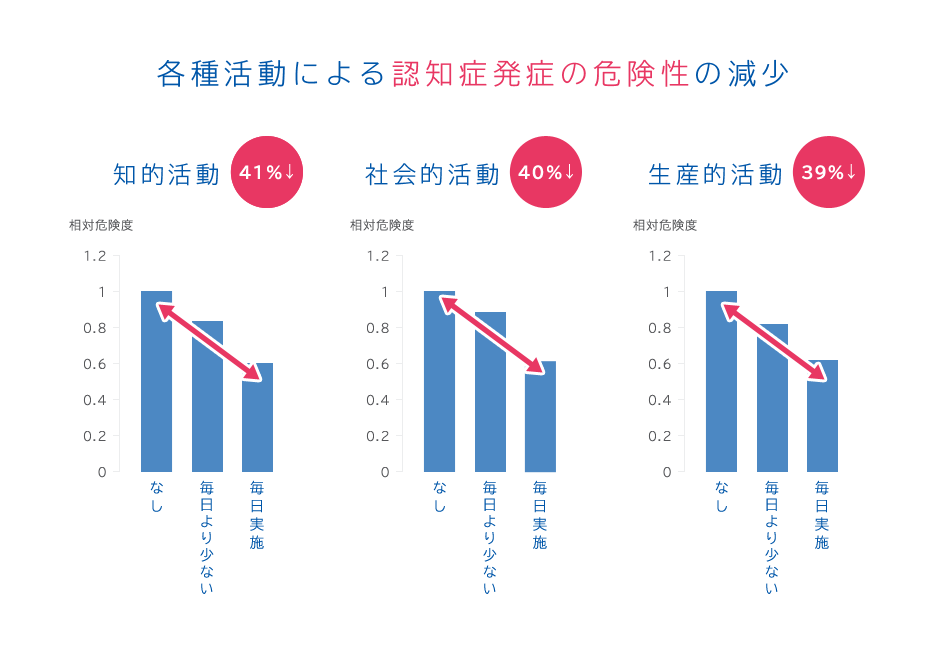
出展:Hui-Xin Wang, Anita Karp, Bengt Winblad, and Laura Fratiglioni. Late-Life Engagement in Social and Leisure Activities Is Associated with a Decreased Risk of Dementia: A Longitudinal Study from the Kungsholmen Project. Am J Epidemiol. 2002 Jun 15;155(12):1081-7.

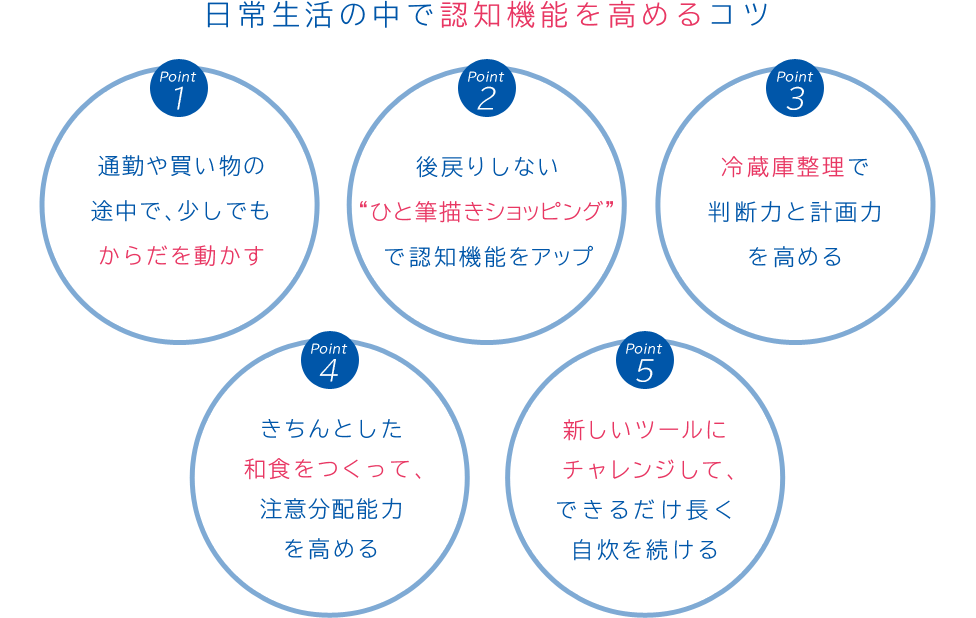
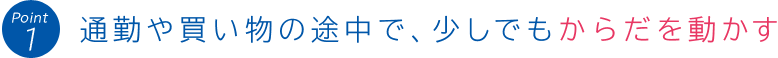
認知機能アップには有酸素運動がいいと言われていますが、筋トレで認知機能が改善するという報告もあります。有酸素運動と筋トレをバランスよく組み合わせるといいですね。
ふだん運動の時間がとれない人は、日常生活の中でからだを動かすことが大切です。たとえば、駅のエスカレーターを使わずに階段を使う。バスや地下鉄のひと駅分を歩く。スーパーに買い物に行くとき、血眼になって入り口の近くの駐車スペースを探していませんか?そんなときは、むしろ遠くに停めれば、ちょっとした運動ができます。
今はなんでも自動化されて、運動するチャンスが失われています。その結果、生活習慣病が増え、認知症のリスクが増えてきました。認知機能の低下が気になり始めたら、これまでの価値観を少し切り替えて、便利さを求めるよりも、「身体を動かすよいきっかけになった」と思うようにして、日常の中で少しでも多くからだを動かす機会を見つけるようにしましょう。
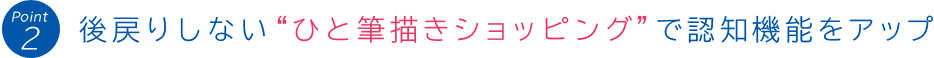
みなさんは、スーパーに行く前に献立を決めますか?それとも、お店に行ってから何にしようかと決めますか?
コグニライフの観点から言えば、前者が正解です。
買い物もやり方によっては、認知機能アップに最適なトレーニングになります。以下の手順で買い物をしてみてください。脳にちょっとしたストレスをかけることで、計画力や記憶力を高めます。日々の買い物にあえて意識してゲーム感覚を取り入れることで、楽しみながら認知機能をトレーニングしましょう。
① 冷蔵庫の中に何があるかを考え、まず献立を決める。
② 足りないものを頭の中のメモ帳に書き込んで買い物へ。
③ 効率よく買う順番を考え、一度も引き返さずに済むようにひとまわりで買い物を済ませる。

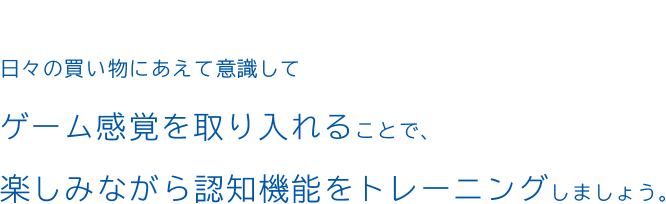

冷蔵庫の中にいつ買ったかわからない食べ物がぎっしり詰め込まれているのは、認知症の初期によく見られる例です。これは、取捨選択能力が落ちているからです。
その意味で、冷蔵庫の中をきれいに整頓して食材をきちんと管理しておくことは、認知機能を向上させる良いトレーニングになります。最近の冷蔵庫はドアポケットがたくさんついていて、整理しやすくなっているのがいいですね。
また、最近の冷蔵庫には瞬間冷凍機能やチルド冷蔵など、いろいろな機能がありますが、これらを上手に活用している人は少ないはず。まず冷蔵庫の機能を知ってしっかり活用することは、計画力を鍛えるトレーニングにもなります。

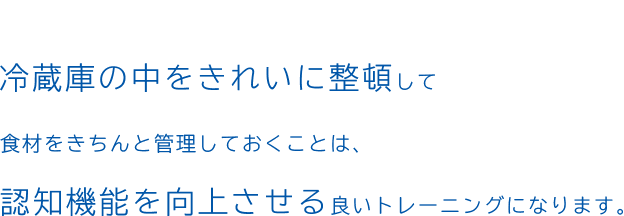
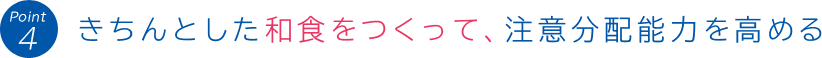
加齢と共に落ちやすい能力のひとつに、注意分配能力があります。何かをしながら別のことを行うことがだんだんできなくなってくる。たとえば料理をするには、野菜を切る、魚を焼くなど複数の課題を同時並行で行うので、注意力をうまく分配する必要があります。ですから、料理をすることは注意分配能力のトレーニングになるのです。
さらに、コグニライフ、いや、コグニクッキングを意識するなら、ふだん30分かかる料理を25分で作ってみる。そうすると、“時計を気にする”という課題が増えます。さらに、お皿の数を増やす。ますます課題が増え、食材の多様性が増すので、栄養のバランスもよくなります。コグニクッキングの観点からすると、一汁三菜を目安にお皿をたくさん並べる和食は、理想の食事形態と言えます。
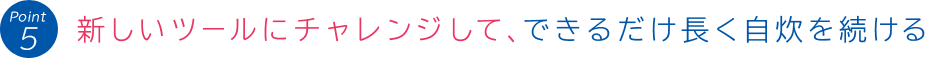
自炊をすることは、いろいろな意味で健康づくりのベースになります。まず献立を考え、食材を管理することで、判断力や計画力が鍛えられます。調理をすることで、注意分配能力が鍛えられます。栄養バランスもとりやすい。皿洗いにも段取りや計画性が必要です。
高齢のひとり暮らしになると火の始末が心配になるかもしれませんが、IHや電子レンジなどの調理家電を活用することで、安全に自炊を続けられるかもしれません。
今はさまざまな種類の調理家電があり、電子レンジひとつとっても、ただ温めるだけではなく、さまざまな機能を持っています。
60代、70代前半で、今まで使ったことのない新しい家電や道具に挑戦する。その意欲自体が「コグニライフ的」と言えそうです。また、それらの機能を知ってうまく使いこなすことで、料理の幅が広がり、生活の質が上がる可能性があります。とはいえ、使い方のわからない家電を分厚い取り扱い説明書を見ながら使うのは大変ですから、それらを見なくても操作ができるようなものを選ぶといいかもしれません。安全で便利な道具を活用しながら、できるだけ長く自炊を続けることが、コグニライフを維持する秘訣と言えそうです。
また、面倒がらずに自炊を続けるためには、達成感が必要です。時間を計って、ゲーム感覚で楽しくつくる。新しいレパートリーに挑戦する。家族や友人にほめてもらう。男性であれば、つくるだけでもほめられるかもしれませんね。

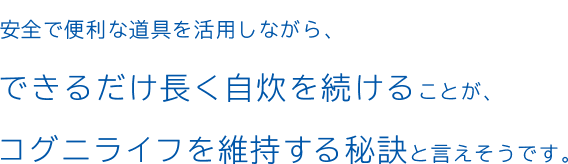

1971年生まれ。理学療法士を経て北里大学医学部大学院に入学。
卒業後、東京都老人総合研究所、プリンス・オブ・ウエールズ・メディカルリサーチ・インスティチュート客員研究員を経て、2010年国立長寿医療研究センター自立支援システム開発室室長。2012年より予防老年学研究部長。
専門領域は、老年学、神経科学、リハビリテーション医学。
主な著書:「認知症予防運動プログラム コグニサイズ®入門」
「ボケたくなければ歩きなさい」
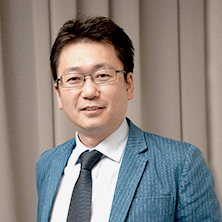

中尾洋子 パナソニック(株) デザイン戦略室 課長 / 全社UD担当
認知機能を向上させたり、認知症の発症を遅らせることができるというのは心強いお話でした。
私は買い物の際、よく後戻りしてしまうので、一筆書きショッピングをしないといけないなら大変だな、と思いましたら、先生から「いつもじゃなくて良いんですよ。やってみようと思う時に挑戦してみて下さい。」と言って頂いてほっとしました。続けるためにも、無理せず、楽しんで取り組んでみて下さいね。
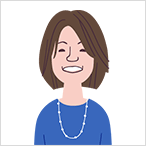
※このUDサイトは、より多くの方へのアクセシビリティを高めるために、様々な方のご意見をお聞きして改善を行なっております。
※障害の漢字表記に関して:スムーズな読み上げを実現するために、障害という単語を漢字で表記しています。