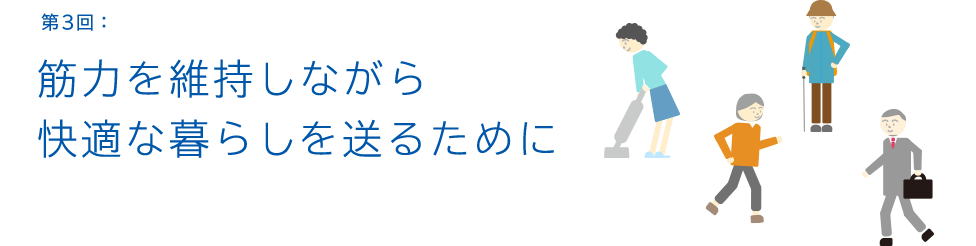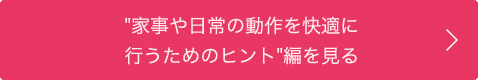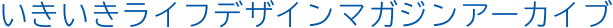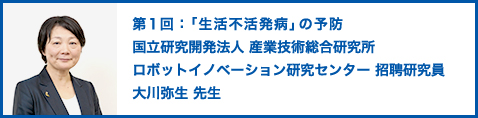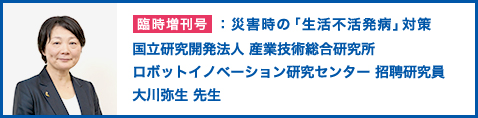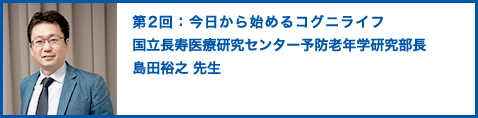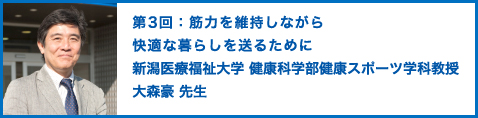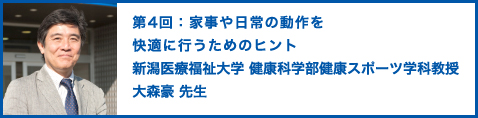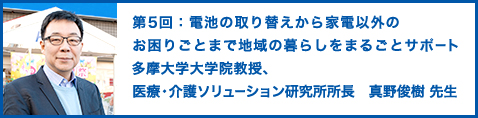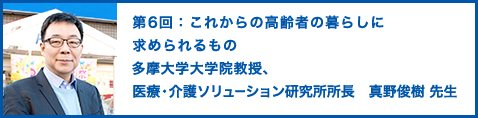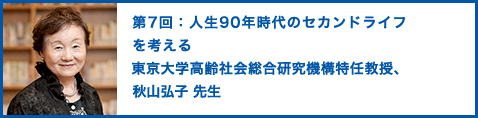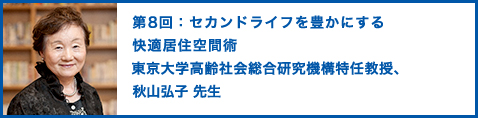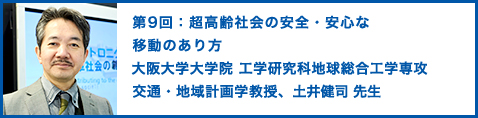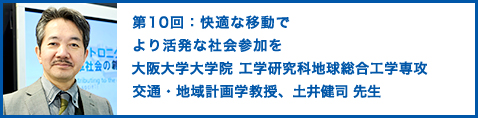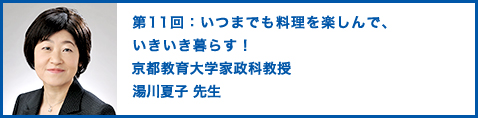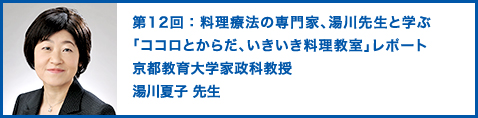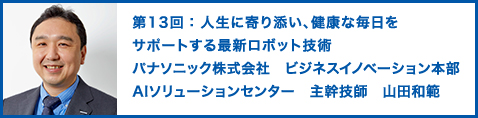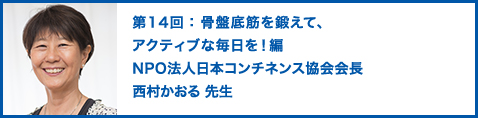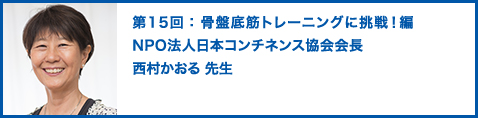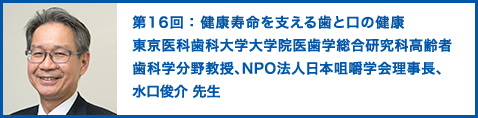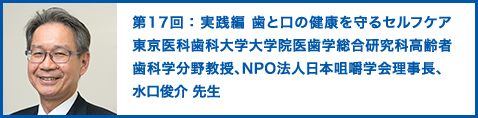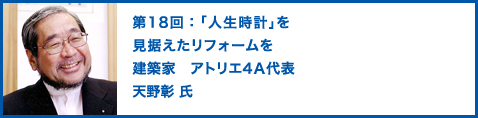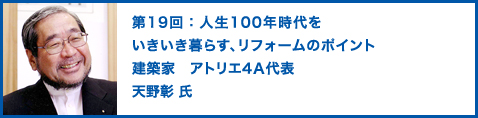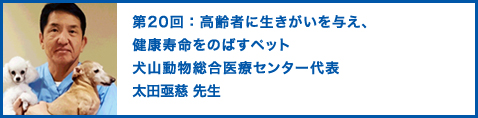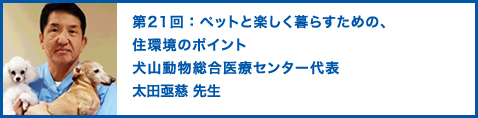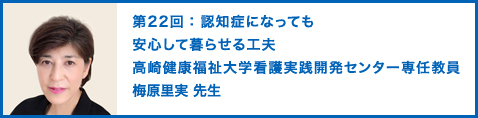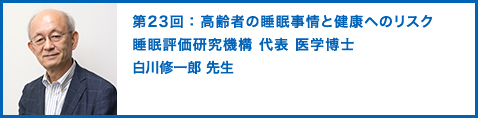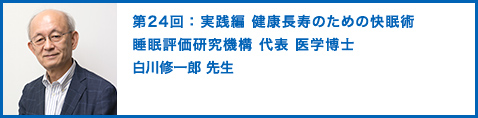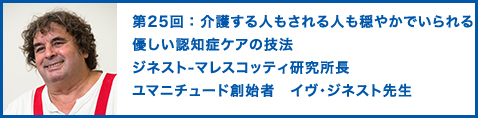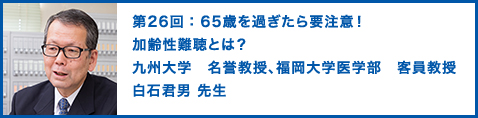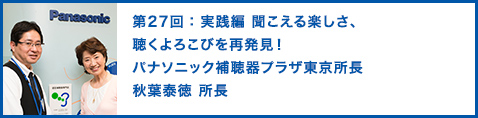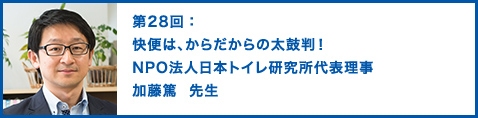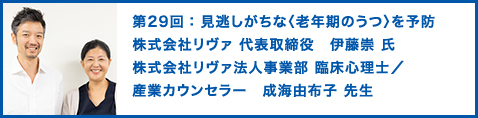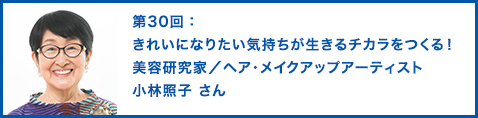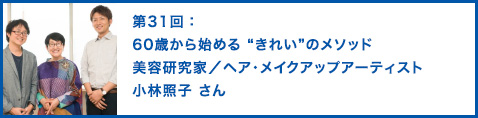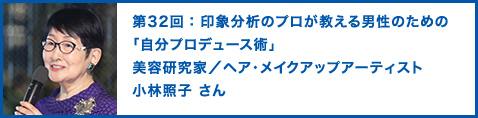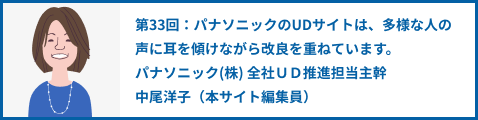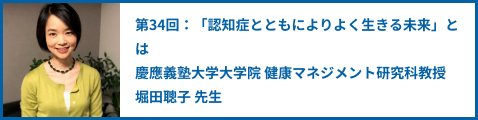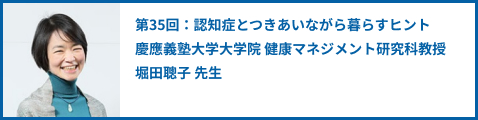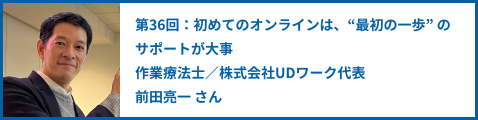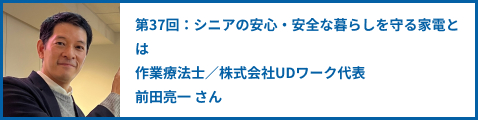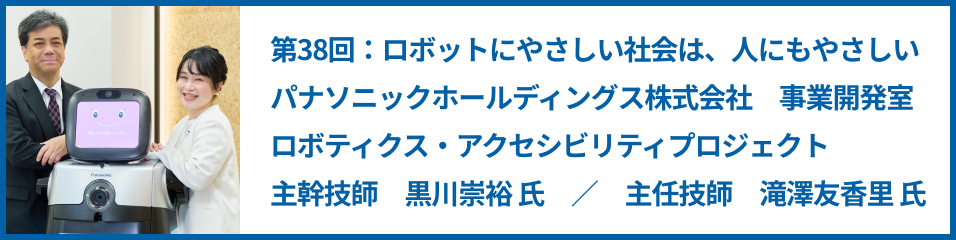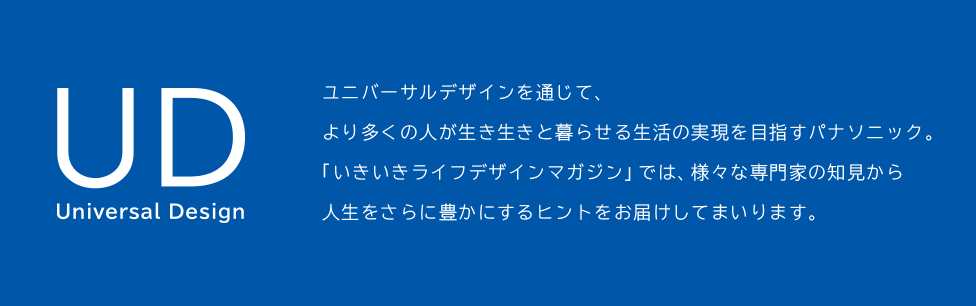
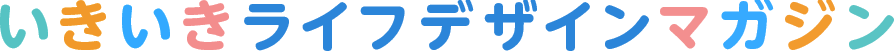
新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科教授
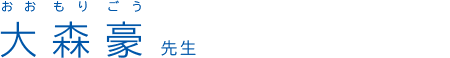
介護予防の観点から見ると、メタボよりも実は怖いと言われているのが、運動機能の衰えです。特に歩いたり体を支えたりする運動機能の衰えは、日常生活に支障をきたしてしまいます。いくつになっても元気に自立した暮らしを送るためには、年齢と共に少しずつ衰えていく筋力を意識して鍛え、運動機能の衰えを防ぐことが重要です。
整形外科医として長年介護予防に取り組んでこられ、『中高年の「ひざ」の痛み』の著者でもある大森豪先生(新潟医療福祉大学 健康科学部教授)に、日常生活の中で筋力を維持するコツと快適な暮らしのヒントを伺いました。

お話をお伺いした「パナソニック
リビングショウルーム 高崎」にて
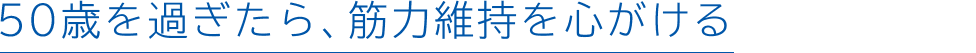
私たちが自由に体を動かすことができるのは、骨や関節や筋肉などで構成される「運動器」の働きによるものです。運動器には体を支えたり動かしたりする機能がありますが、年齢を重ねていくと、運動器本来の機能が衰え、日常生活の中で困ることが増えてきます。
たとえば、骨がもろくなる骨粗鬆症になると、骨折しやすくなります。
骨と骨をつないでいる関節の機能が低下すると、体を支えられず、歩きにくくなります。
筋肉は関節を動かす力の源なので、筋肉が衰えると、運動器全体の機能が衰えてしまいます。
一般的に、全身の筋力を反映するのは握力だと言われていて、握力は20代をピークに年齢と共に少しずつ落ちていきます(図1)。

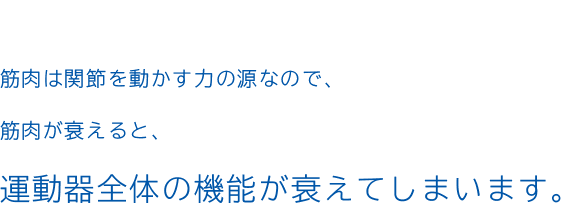
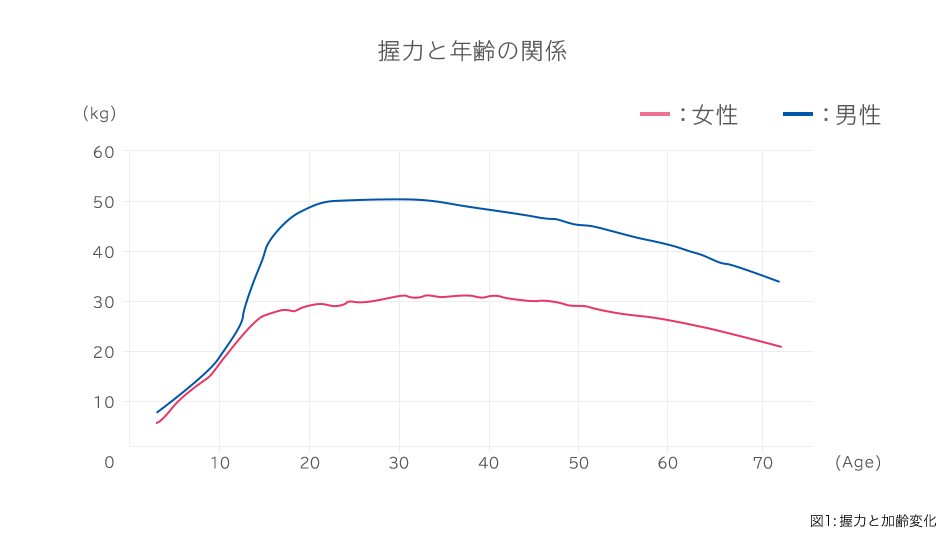
出展:東京都立大学体力標準値研究会(2000) 『新・日本人の体力平均値』
ところが最近、膝を支える太ももの筋肉(大腿四頭筋)は50歳までそれほど変わらず、50歳を過ぎるとだんだん落ちてくることがわかりました(図2)。ですから、50歳を過ぎたら、立ったり歩いたりするときに使う筋肉を維持するように気にかける必要があります。意識的に筋肉を動かすことで、骨に刺激が加わって骨の丈夫さを保つことができますし、体を支える関節の機能を維持出来る可能性が高くなります。
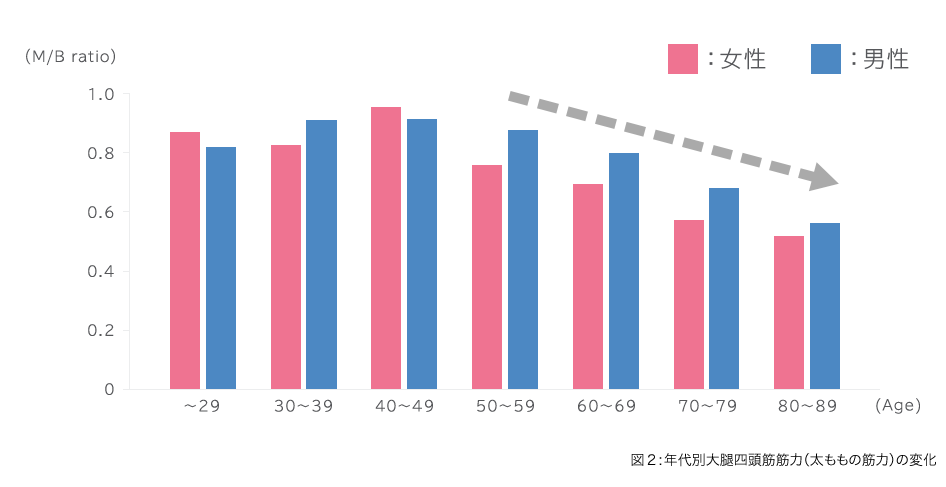
出展:Omori G. J Orthop Sci (2013)
日本整形外科学会では、骨、関節、筋肉などの機能が衰えて、そのまま進行すると介護が必要になるリスクが高い状態を「ロコモ(運動器症候群/ロコモティブ・シンドローム(locomotive syndrome)」と定義し、健康長寿の実現のためにロコモ予防を呼びかけています。このロコモ予防に最も効果があるのは、意識的に筋肉を動かし、筋力を維持することなのです。

(日本整形外科学会公認ロコモティブシンドローム予防啓発サイトより)
7つの項目はすべて、骨や関節、筋肉などの運動器が衰えているサインです。
ひとつでも該当する場合はロコモの心配があります。お近くの整形外科医に相談しましょう。
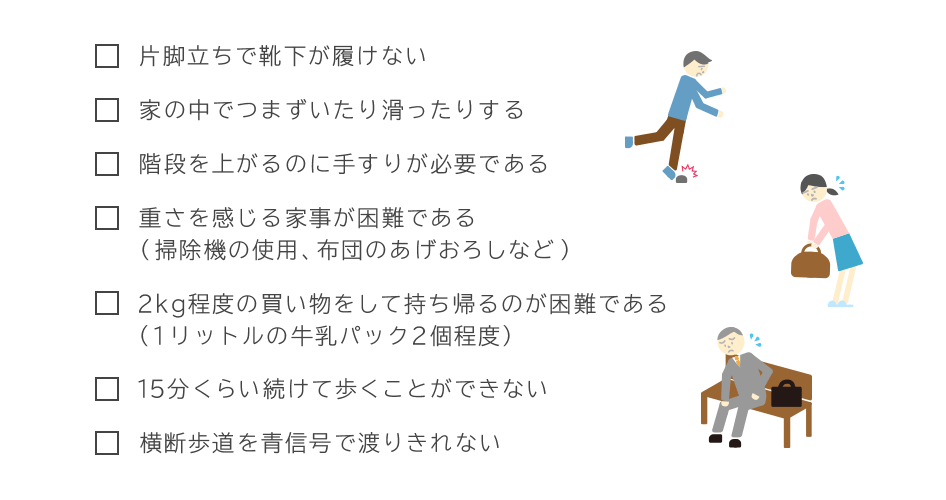
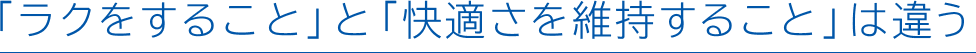
朝起きたとき、「関節が硬くて、体が動かしづらい」「肩や腰の痛みが悪化している」と感じたことはありませんか。これは、寝ている間は寝返りなどを打ったとしても、起きているときに比べると動きが格段に少ないため、関節や筋肉がこわばった状態となっているからです。だから、朝は痛くても、少し動いていると、関節や筋肉がだんだん温まってきて、動かせるようになります。痛いからと動かさないでいると、痛みはさらに悪化するので、無理のない範囲で動かすことが大事です。
そもそも、年齢に関わらず、体にとって一番良くないのは、“同じ姿勢を続ける”ことです。
タクシーやトラックの運転手さんに腰痛が多いのも、長時間座ったままだからです。座っているのは立っているよりラクに見えるかもしれませんが、同じ姿勢をとりつづけることは、関節に負担を与えます。人間の体は本来動かし続けるようにできているのです。
ですから、リビングのソファに座ったまま何でもリモコンで操作するような生活は、体にとっていいことではありません。「ラクをすること」と「快適さを維持すること」は根本的に違うのです。大切なのは、いくつになっても快適に動けるように、日常生活の中で無理せず筋力を維持していくことだと思います。

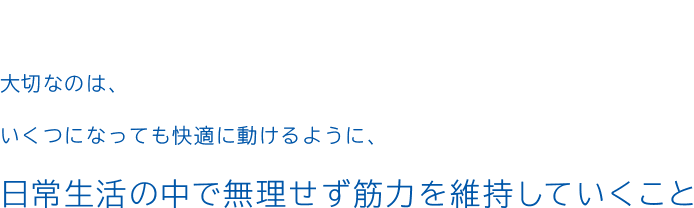
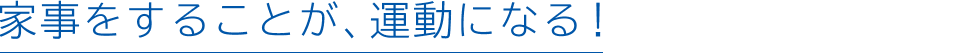
筋力を鍛えるというと、何か特別な運動を連想するかもしれませんが、ジムに行って走ったりマシンを使ったりすることだけが運動ではありません。家事の消費エネルギーはみなさんが想像するより大きく、ちょっとしたウォーキングに匹敵するほどです(図3)。天候に左右されるウォーキングとはちがって、家事なら毎日続けられます。家の中で家事をすることも立派な運動なのです。
ただ、筋力が弱っていたり、筋肉の柔軟性が低下したりしていると、なんでもない動作で五十肩やギックリ腰を起こしてしまうこともありますから、負担なく家事を行うためには工夫や注意が必要です。サッカーをするなら土よりも芝生の方がいいように、家の中も家事という運動が快適にできるように整えてあげることが大切です。
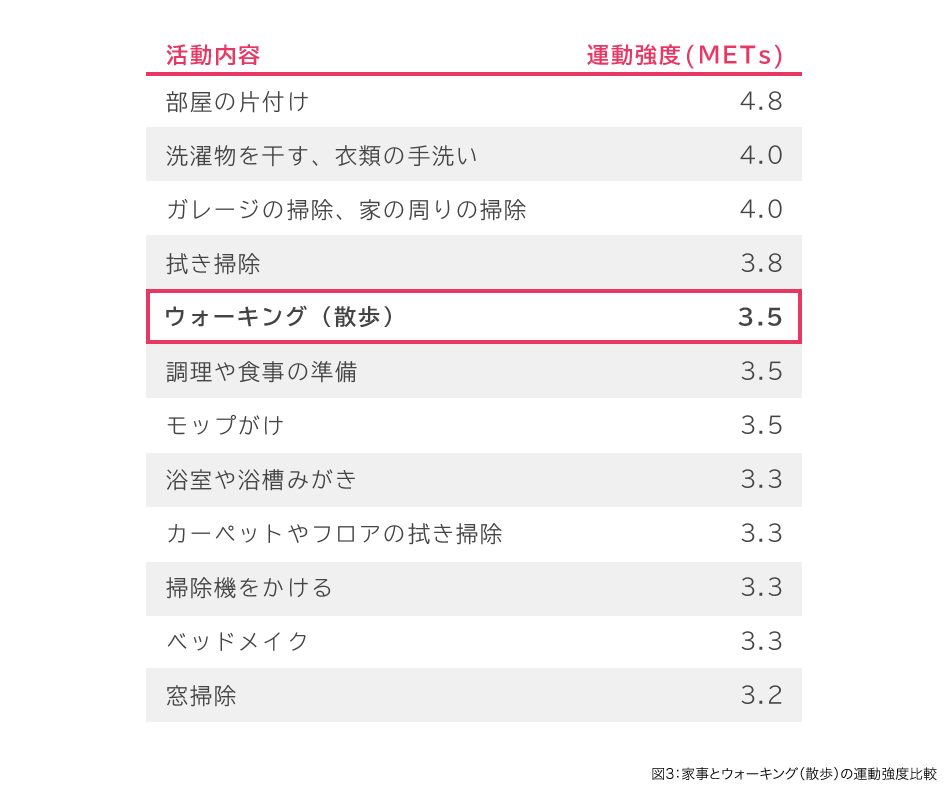
改訂版「身体活動のメッツ(METs)表」(国立健康・栄養研究所)より抜粋
※METsとは運動強度の単位で安静時を1METsとして定めたものです。
次回は、家事や日常の動作を快適に行うためのヒントについてお話しします。
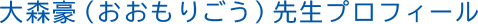
1958年生まれ。1985年新潟大学医学部卒業。
新潟大学助教授を経て2004年より新潟大学超域研究機構教授に就任。
2013年より新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科教授。
アルビレックス新潟FCチームドクター。
専門領域は整形外科、スポーツ医学、生体工学。
著書:『図解 中高年の「ひざ」の痛み―変形性膝関節症の予防と治療』


中尾洋子 パナソニック(株) デザイン戦略室 課長 / 全社UD担当
「ラクをすること」と「快適さを維持すること」は根本的に違うというお話は、今の暮らしを見つめ直すきっかけになりそうです。そんな中、家事をすることがちょっとしたウォーキングに匹敵する運動になるというのは、忙しくて特別な運動をする時間が取れないと思っている私にとって、うれしい情報でした。
次回は、日常生活の中でからだに負担をかけないコツについてお話し頂く予定ですのでご期待下さい。
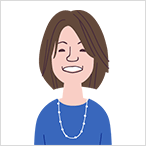
※このUDサイトは、より多くの方へのアクセシビリティを高めるために、様々な方のご意見をお聞きして改善を行なっております。
※障害の漢字表記に関して:スムーズな読み上げを実現するために、障害という単語を漢字で表記しています。